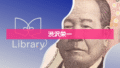「株ってニュースでよく聞くけど、いったい何のこと?」
「株価が上がった!下がった!」とアナウンサーが言っていても、よくわからない…という人は多いのではないでしょうか。
でも実は、株は私たちの生活とも深いつながりがあります。スーパーやゲーム会社、お菓子メーカーも「株式会社」。つまり、身近なあの会社も株と関係しているんです。
この記事では、小中学生でもわかるように「株」「株式会社」「株価」のしくみをやさしく解説します。途中にクイズもあるので、ゲーム感覚で挑戦してみましょう!
株ってなに?【小学生・中学生にもわかる株式の意味】
株(かぶ)とは、会社の「持ち主である証(あかし)」のことです。
もう少しやさしくいうと、「会社の権利を分けた小さなチケット」 のようなものだと考えるとイメージしやすいです。
たとえば友達とお店をつくると…
あなたと友達2人で「クレープ屋さんをひらこう!」となったとします。
- あなたは1万円を出して材料を買う
- Aくんは1万円を出して屋台をつくる
- Bさんは1万円を出してチラシを配る
3人がそれぞれ同じ金額を出したので、3人は「お店の持ち主」といえます。
でも「だれがどれだけお金を出したか」をはっきりさせる必要がありますよね。
ここで登場するのが 株 です。
3人が出したお金を「株」という形で分けて、それぞれに「あなたはこのお店の3分の1を持っていますよ」と証明するわけです。
この「持ち主の証」が株なのです。
株主ってなに?
株を持っている人を 株主(かぶぬし) といいます。
株主は「会社の一部を持っている仲間」なので、会社が利益を出したらその分け前をもらえたり、会社の方針を決める会議に参加できたりします。
つまり、株を持つ=会社に参加する仲間になることなのです。
👉 クイズ①
株を持っている人のことを何と呼ぶでしょう?
- 社員
- 株主
- 投資家
正解は **2. 株主** です。
このように、株はただのお金の紙切れではなく、「会社の一部を持っている証」 なんですね。
株式会社とは?【会社とお金の仕組みをやさしく解説】
会社は、お菓子を作ったりゲームを開発したり、新しいお店をひらいたりするときに、たくさんのお金が必要になります。
でも、ひとりの社長さんや家族だけでは、そのお金を用意するのは大変です。
そこで登場するのが 株式会社(かぶしきがいしゃ) というしくみです。
株式会社のしくみをイメージしよう
- お金を集めたい会社
新しい商品を作るには、10億円くらい必要!でも自分のお金だけじゃ足りない…。 - お金を出してくれる人(株主)を募集
「株を買ってくれたら、その分あなたもこの会社の仲間です」と呼びかけます。 - 株を買った人=会社のオーナーの一部
たくさんの人から少しずつお金を集めることで、大きな資金があつまります。
こうしてできたのが株式会社。
つまり「みんなでお金を出し合って、みんなで会社を育てる」仕組みなのです。
たとえばケーキ屋さんだったら…
- ケーキを作るオーブンが欲しいけど100万円足りない!
- 「株」を100枚にわけて1枚1万円で売る
- 100人が1万円ずつ出してくれれば、100万円が集まる
- ケーキ屋さんは新しいオーブンを買えて、株主は「このお店の一部を持っている人」になる
このように、株式会社は大きなプロジェクトを実現するための「仲間集めの仕組み」といえます。
銀行から借りるのと何がちがう?
- 銀行から借りる → 必ず返さないといけない
- 株を売る → 返さなくてもいいけど、株主と利益を分けたり意見を聞いたりする必要がある
だから株式会社は「借金ではなく、協力してもらう形」で成り立っているのです。
👉 クイズ②
会社が株を売るのは何のためでしょう?
- 社員をふやすため
- お金を集めるため
- ライバルをこわすため
正解は **2. お金を集めるため** です。
こう考えると「株式会社」は、社長ひとりのものではなく、たくさんの人に支えられて動く仕組み だとわかりますね。
株を持つとどうなる?【配当・株主総会・会社への参加】
株を持つことは、ただの紙切れやデータを持つことではありません。
実は「会社の仲間」として、いろいろな権利やメリットをもらえる立場になるのです。
① 利益の一部をもらえる(配当)
会社が一年間の仕事で大きな利益を出したとします。
するとその一部を、株を持っている人に分けてくれることがあります。これを 配当(はいとう) といいます。
- ケーキ屋さんに例えると…
お店が1年間で10万円もうかったとします。
株を持っている人に「ありがとう!」の気持ちをこめて、その一部を渡すイメージです。 - だから株を持っていると「応援してよかった!」という実感がわきます。
② 株主総会に参加できる
会社では、1年に1回「株主総会(かぶぬしそうかい)」という大きな会議が開かれます。
そこでは次のようなことが話し合われます。
- 会社がどんな活動をして、どれくらいもうかったか
- 来年はどんな方針で進むのか
- 社長や役員をどうするのか
株主は、この会議に出席して意見を言うことができます。
もちろん大企業では数万人の株主がいるので、実際に大きな決定をするのは社長や役員ですが、「株主の意見」も大切にされる のです。
③ 株主優待をもらえることもある
すべての会社ではありませんが、株を持っている人に「特典」をプレゼントする会社もあります。これを 株主優待(かぶぬしゆうたい) といいます。
- お菓子会社なら「自社製品のお菓子セット」
- 鉄道会社なら「電車の割引券」
- レストランチェーンなら「お食事券」
「株を持つ=応援してくれてありがとう!」という気持ちを形にしたプレゼントですね。
株を持つ=会社の一部に参加すること
まとめると、株を持つと
- 利益の一部(配当)をもらえる
- 会社の会議(株主総会)に参加できる
- 株主優待などで特典がもらえることがある
つまり株主は、ただのお客さんではなく、会社を一緒に育てる仲間 という立場になるのです。
👉 クイズ③
株主が集まって会社のことを話し合う会を何というでしょう?
- 株主総会
- 社員会議
- 取締役会
正解は **1. 株主総会** です。
株価とは?【株の値段が決まる仕組みを子ども向けに解説】
株には、野菜やお菓子と同じように「値段」があります。
その値段を 株価(かぶか) といいます。
でも、じゃがいもやジュースの値段はスーパーが決めますよね。
では株価はだれが決めるのでしょうか?
株価は「買いたい人」と「売りたい人」で決まる
株価は 政府や社長が勝手に決めるものではありません。
株を「買いたい人」と「売りたい人」の気持ちのバランスで変わるのです。
- 「この会社はこれから大きく成長しそうだ!」と思う人が多いと、株を買いたい人が増える → 値段(株価)が上がる
- 「この会社はちょっと心配だな」と思う人が多いと、株を売りたい人が増える → 値段(株価)が下がる
つまり株価は、みんなの「人気投票」のようなものなんです。
ゲームソフトやカードと同じ?
たとえば、人気ゲームの新作が発売されると、みんなが欲しがって値段が高くなります。
逆に人気が落ちると、中古ショップで安く売られてしまいますよね。
株もそれと同じ。「欲しい!」と思う人が多ければ値段は上がり、少なければ下がる。
とてもシンプルな仕組みです。
株価はニュースでもよく出てくる
テレビや新聞で「今日の日経平均株価は…」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。
これは「日本の大きな会社の株価の平均値」を表していて、日本の経済の元気さを知る目安になっています。
つまり株価は、ただのお金の数字ではなく、「みんながその会社をどれくらい信じているか」 を表しているのです。
👉 クイズ④
株価はどうやって決まるでしょう?
- 政府が決める
- 会社が勝手に決める
- 買いたい人と売りたい人のバランスで決まる
正解は **3. 買いたい人と売りたい人のバランスで決まる** です。
株と私たちの生活【身近な会社と株式のつながり】
「株」と聞くと、ニュースや大人の話でしか出てこない難しいもののように思えますよね。
でも実は、私たちが毎日のように使っているサービスや買っている商品も、たくさん「株」とつながっています。
スーパーで売っているお菓子や飲み物
- カルビー(ポテトチップスで有名)
- 明治(チョコレートやヨーグルト)
- 森永製菓(キャラメルやアイス)
これらの会社はすべて「株式会社」です。株を発行して、会社を大きくしてきました。
ゲームやアニメも「株式会社」から生まれている
- 任天堂(スイッチやポケモン)
- ソニーグループ(プレイステーション)
- バンダイナムコ(ガンダムやドラゴンボールのゲーム)
みんなが大好きなゲームやアニメも、実は「株」を通じて支えられているのです。
交通や暮らしのインフラも株で成り立っている
- 電車を走らせる JRや私鉄
- ガスを供給する 東京ガス・大阪ガス
- 電気を送る 東京電力・関西電力
私たちが安全に暮らすためのサービスも、多くは株式会社によって運営されています。
株は「生活の中にある」
こうしてみると、「株ってお金持ちの人だけが関係しているもの」ではないことがわかります。
スーパーで買うお菓子、家で遊ぶゲーム、通学で使う電車、家庭に届く電気やガス…
どれも「株式会社」があって、株によって支えられているのです。
だから、株は実はとても身近で、私たちの生活を支えるしくみなんですね。
株の自由研究・調べ学習アイデア【小学生・中学生向け】
株はちょっと難しそうに見えますが、調べ方を工夫すれば 自由研究や調べ学習の絶好のテーマ になります。
ここでは、小学生・中学生がすぐに取り組めるアイデアを紹介します。
① 好きな会社の歴史を調べてみよう
- 自分がよく利用している会社を1つ選ぶ(例:任天堂、カルビー、JRなど)
- 「いつ設立された?」「どうして株式会社になった?」を調べる
- 会社の公式サイトに「沿革(えんかく)」ページがあるので、そこから年表をつくれる
👉 発展:創業者の考え や「どんな社会の役に立ちたかったのか」まで調べると、歴史と社会をつなげられる。
② 株価を調べてグラフにしてみよう
- 新聞やインターネットで「株価」を調べる
- 1週間や1か月の株価を記録して、折れ線グラフをつくる
- 上がった日・下がった日を調べて「なぜ?」を考える
👉 発展:「会社のニュースが株価に影響する」という気づきが得られる。
例:新商品を発表した → 株価が上がった。事故や不祥事があった → 株価が下がった。
③ 株主優待を調べてまとめてみよう
- 「株主優待とは?」を説明できるようにする
- 有名な優待例を調べてリスト化
- カルビー → 自社のお菓子詰め合わせ
- イオン → お買い物の割引券
- 鉄道会社 → 乗車割引券
👉 発展:なぜ会社は株主優待をするのか? → 「株主に応援してもらうため」「会社のファンを増やすため」という答えにたどり着ける。
④ 株式会社と公共サービスのちがいを比べよう
- 株式会社のサービス(例:コンビニ、ゲーム、電車)
- 公共サービス(例:市営バス、公立図書館、小学校)
👉 「利益を目的にしているかどうか」という観点で整理すると、社会のしくみがよくわかる。
⑤ 株のニュースを子ども目線で解説してみよう
- 新聞やテレビで「株価が上がった」「日経平均が下がった」というニュースを1つ選ぶ
- そのニュースを自分なりに要約し、クラスや家庭で説明してみる
👉 難しいニュースを自分の言葉に置きかえる練習になり、社会科や国語の勉強にもつながる。
自由研究としてまとめるポイント
- 調べる → まとめる → 発表する の3ステップを意識する
- 年表・グラフ・写真を入れると見やすくなる
- 「なぜそうなるのか?」という自分なりの考察を入れると先生から高評価
👉 これで「株」がただのニュース用語ではなく、調べて深掘りできる身近なテーマ に変わります。
株のおさらいクイズ【3択で復習しよう】
記事の最後に、これまで学んだ内容をふり返るクイズです。3択にチャレンジして、どれくらい理解できたか確認してみましょう!
クイズ①
株を持っている人はなんと呼ばれるでしょう?
- 社員
- 株主
- 社長
正解は **2. 株主** です。 株主は「会社の一部を持っている人」であり、会社に参加する仲間という立場です。
クイズ②
会社が株を売るのは何のためでしょう?
- 社員をふやすため
- お金を集めるため
- 宣伝するため
正解は **2. お金を集めるため** です。 会社は新しい商品やお店のために大きなお金が必要です。その資金を株を売ることで集めます。
クイズ③
株主が集まって会社のことを話し合う会はなんでしょう?
- 株主総会
- 部活動
- 授業参観
正解は **1. 株主総会** です。 株主総会では「会社がどんな活動をしたか」「これからどう進むか」などが話し合われます。
クイズ④
株価はどうやって決まるでしょう?
- 政府が決める
- 人気で変わる
- サイコロで決める
正解は **2. 人気で変わる** です。 正確には「買いたい人と売りたい人のバランス」で決まります。人気のある会社は株価が上がり、不安がある会社は下がります。
4問すべて正解できましたか?
間違えても大丈夫!もう一度記事を読み返してみれば、株のしくみがもっとよくわかるはずです。
このクイズをきっかけに、自由研究や授業で「株と会社」について調べてみるとさらに理解が深まりますよ。
まとめ|株とは会社とお金をつなぐ大切な仕組み
- 株=会社の一部を持つ証
- 会社は株を発行してお金を集める
- 株主は配当や意見をもらえる立場
- 株価はみんなの人気度で変わる
- 株は自由研究にも使えるテーマ
この記事を書いた人
西田 俊章(MOANAVIスクールディレクター/STEAM教育デザイナー)
公立小学校で20年以上、先生として子どもたちを指導し、教科書の執筆も担当しました。
現在はMOANAVIを運営し、子どもたちが「科学・言語・人間・創造」をテーマに学ぶ場をデザインしています。