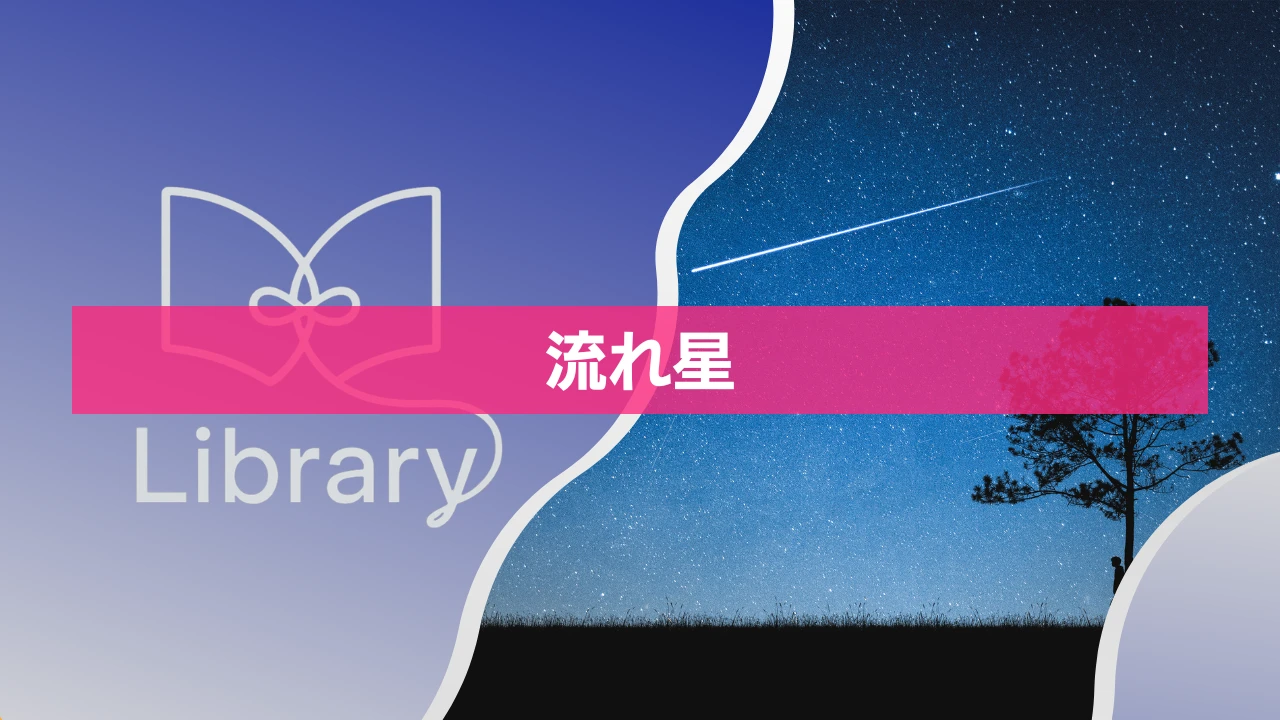
夜空を見上げて、スーッと光が流れるのを見たことはありますか?
それが「流れ星」です。あっという間に消えてしまうので、「お願いごとをすると叶う」とも言われています。
でも…「どうして光るの?」「本当に星が落ちてきているの?」と考えたことはありませんか?
この記事では、流れ星の正体や光る理由、隕石との違い、流星群のひみつまでを、小学生にもわかる言葉でやさしく解説します。途中にクイズもあるので、挑戦しながら楽しく学んでみましょう!
流れ星とは?【小学生にもわかる流れ星の正体と意味】
夜空を見上げると、まるで星が空から落ちてきたように光がスーッと流れることがあります。
でも実は、流れ星は星が落ちてきているわけではありません。
その正体は、宇宙にただよっている 小さなチリや石のかけら です。
大きさは砂つぶくらいのものから、ビー玉くらいまでさまざま。ほとんどはとても小さいのに、空でピカッと光るのです。
🌍 地球と宇宙の関係
地球は太陽のまわりをぐるぐる回る大きなボールのような存在です。
その道のりには、昔に通った彗星(ほうき星)がまき散らしたチリや小石がたくさん残されています。
ちょうど自転車で走っているときに虫にぶつかるみたいに、地球も宇宙のチリにぶつかります。
そのとき、小さなかけらが空に飛び込み、一瞬だけ強く光るのです。
✨ どうして「星」と呼ばれるの?
本当は星ではなく「宇宙のチリ」なのに、なぜ「流れ星」と呼ばれるのでしょう?
それは、夜空でキラッと光ってスーッと流れる姿が、まるで星が走っているように見えるからです。
昔の人も「空から星が落ちてきた!」と思って、そう呼ぶようになったのです。
👉 クイズ①
流れ星の正体は何でしょう?
- 星が爆発したかけら
- 宇宙のチリや石のかけら
- 地球の火山のかけら
正解は **2. 宇宙のチリや石のかけら** です。
流れ星はなぜ光るの?【空気との摩擦で光る仕組み】
宇宙からやってくるチリや小石は、ものすごいスピードで地球に飛び込んできます。
その速さはなんと 秒速20〜70km。1秒で東京から横浜どころか、東京から富士山のふもとまで一気に行けるくらいのスピードです。
そんなスピードで空気にぶつかるとどうなるでしょう?
手をこすり合わせるとだんだん温かくなりますよね。あれと同じで、ものすごい摩擦(こすれる力) が生まれ、かけらは一瞬で真っ赤に熱くなります。
その温度はなんと 数千度。鉄を溶かすくらいの高温です。
だから小さなチリや石のかけらでも、燃えながら空で光を放つのです。
🔥 身近な例えで考えてみよう
- 流れ星 → マッチをすったときの火花が空で起きているようなもの
- 空気との摩擦 → 自転車で手を前に出したら風で痛くなるような感じ
- 光る瞬間 → 小さな石が「燃える」ほどの速さで空を走り抜ける
だから私たちの目には、夜空をすべるように光って消える姿が見えるのです。
👉 クイズ②
流れ星が光るのはなぜでしょう?
- 星が電気を出しているから
- 空気との摩擦で高温になり光るから
- 地球がライトで照らしているから
正解は **2. 空気との摩擦で高温になり光るから** です。
流れ星と隕石の違い【燃え尽きるか地上に落ちるか】
流れ星はほとんどが空の途中で燃え尽きてしまいます。
大きさが砂つぶや小石くらいなので、地球の空気とぶつかったときに一瞬で燃えて消えてしまうのです。
でも、なかには少し大きなかけらが地球にやってくることがあります。
この場合、燃え尽きずに地上まで落ちてくることがあり、それを 隕石(いんせき) と呼びます。
🌌 流れ星と隕石のちがいを整理すると…
- 空でピカッと光って消える → 流れ星
- 燃え尽きずに地上に落ちてくる → 隕石
つまり「見える現象」が流れ星で、「落ちてきたもの」が隕石なんですね。
🌍 実際に落ちてくることもある
世界では、実際に隕石が人の家や車に落ちた記録があります。
たとえばアメリカでは、家の屋根を突き破ってリビングに落ちた隕石がニュースになったこともあります。
日本でも「岡山県津山」や「長野県佐久」など、過去に隕石が見つかった場所があります。
博物館に展示されているものもあるので、実際に見に行くと「これが宇宙から来たのか!」と実感できますよ。
👉 クイズ③
燃え尽きずに地上まで落ちたものを何と呼ぶでしょう?
- 流星群
- 隕石
- 火山石
正解は **2. 隕石** です。
流星群とは?【たくさんの流れ星が見える理由】
夜空を見ていると、まれに「今日は流れ星がいっぱい見えるよ!」とニュースで伝えられることがあります。
それが 流星群(りゅうせいぐん) です。
🌌 流星群のしくみ
宇宙を通る彗星(ほうき星)は、通り道にチリや小石をたくさん残していきます。
地球がその「チリの道」を毎年通過すると、一気にたくさんのかけらが地球の空に飛び込みます。
だから夜空に次々と流れ星が流れるのです。
つまり、流星群は「流れ星のシャワー」。
いつもは1時間に1個か2個見られるくらいですが、流星群のときは1時間に数十個以上も見えることがあります。
🌟 有名な流星群
- ペルセウス座流星群(8月ごろ) → 夏休みの自由研究にぴったり
- ふたご座流星群(12月ごろ) → 冬の澄んだ空にたくさんの流れ星
- しぶんぎ座流星群(1月ごろ) → 新年の夜空をにぎやかにする流星群
これらは毎年同じ時期に見られるので、**「星空のイベント」**として世界中で楽しまれています。
📓 自由研究のアイデア
流星群を観察するときは、
- 見えた時間
- どの方向に流れたか
- 何個見えたか
をメモしておくと、立派な調べ学習になります。
写真やスケッチを添えればポスター発表にもできますよ。
👉 クイズ④
流星群が毎年同じ時期に見られるのはなぜでしょう?
- 彗星のチリの道を地球が毎年通るから
- 星が同じ日に爆発するから
- 人工的に花火を打ち上げているから
正解は **1. 彗星のチリの道を地球が毎年通るから** です。
流れ星は願い事と関係あるの?【言い伝えの理由】
「流れ星にお願いごとをすると叶う」という話を聞いたことがありますか?
これは科学の説明ではなく、昔から伝わる 言い伝えや文化 なんです。
🌌 昔の人にとっての流れ星
今のように電気や街灯がなかった時代、夜空は真っ暗で、星の光はとてもはっきり見えました。
そんな中で突然スーッと強い光が走ると、「神さまからのしるし」や「天からのメッセージ」だと思われていたのです。
「一瞬で消えてしまう光だから、すぐに願いを言えば神さまに届く」
そんな考えから、「願いごとをすると叶う」と言われるようになりました。
🌍 世界にもある流れ星の言い伝え
実は「流れ星と願い事」の話は、日本だけではありません。
- ヨーロッパ → 流れ星は天使が地上をのぞいたサイン
- ギリシャ神話 → 神さまが人間の願いを聞く合図
- 南アメリカ → 流れ星は祖先の魂が空を渡る姿
どの国でも「流れ星は特別な存在」とされていたのですね。
🙋 今でも残る願い事の習慣
現代でも、流れ星を見つけるとつい願い事をしたくなります。
科学的に「願いがかなう」ことが証明されているわけではありません。
でも、「大切なお願いごとをすぐに言葉にする」こと自体が、夢や目標に近づく一歩になるのかもしれません。
👉 例えば…
- 「テストで100点とりたい!」
- 「友だちと仲良くしたい!」
- 「サッカーがうまくなりたい!」
流れ星を見ながら願うと、なんだかワクワクして頑張れる気がしますよね。
流れ星は突然現れて一瞬で消えてしまいます。
そんな瞬間に願い事ができるくらい、いつも心に強く願って頑張っているからこそ、願いが叶うのかもしれませんね。
自由研究・調べ学習におすすめ!流れ星をテーマにする方法
流れ星は「見るだけ」でも楽しいですが、自由研究や調べ学習のテーマにするともっと面白くなります。
ここでは小学生でもチャレンジできる方法を紹介します。
① 流れ星と隕石のちがいを図にまとめる
- 「流れ星」→空で光って消える現象
- 「隕石」→地上まで落ちてきたもの
絵やイラストを使って、2つのちがいを比べるとわかりやすいです。
👉 模造紙に「流れ星」「隕石」とタイトルをつけてまとめれば、理科の発表にもピッタリ!
② 流星群を観察して記録する
夏休みや冬休みは流星群を観察するチャンスです。
- 見えた時間
- 方角(北・南・東・西)
- 流れた数
をノートに書き、グラフにすると立派な研究になります。
👉 家族や友だちと一緒に観察会をすると、安全で楽しく記録が取れます。
③ 世界の「流れ星と願い事」の言い伝えを調べる
日本だけでなく、世界の文化や神話を調べてみましょう。
「ヨーロッパでは天使のサイン」「南アメリカでは祖先の魂」などを紹介すると、社会科や国語の学習にもつながります。
👉 地図と一緒にまとめると「世界の流れ星マップ」が完成します!
④ 星座や宇宙との関係を調べる
「どの星座の近くで流れることが多いのか?」を調べて、星座早見盤やアプリと一緒にまとめるのもおすすめです。
👉 自分で描いた星座のイラストを入れると、作品にオリジナル感が出ます。
⑤ 流れ星の科学をもっと掘り下げる
- なぜ秒速20〜70kmも出せるのか?
- どんな物質が燃えているのか?
- 隕石には鉄やニッケルが多いって本当?
図鑑やインターネットで調べると、科学的な自由研究に発展します。
👉 実際に「隕石展示」をしている科学館に行ってレポートすると、さらに本格的になります。
📌 ポイントは、「調べる・まとめる・発表する」を意識すること。
流れ星の不思議を調べると、理科・社会・国語の力を同時にのばせる自由研究になります。
流れ星のおさらいクイズ【3択で楽しく復習】
これまで学んだ内容をクイズでふりかえりましょう。家族や友だちと一緒に答えてみても楽しいですよ!
クイズ① 流れ星の正体は?
- 星が爆発したかけら
- 宇宙のチリや石のかけら
- 地球の火山のかけら
正解は **2. 宇宙のチリや石のかけら** です。
クイズ② 流れ星が光るのはなぜ?
- 星が電気を出しているから
- 空気との摩擦で高温になり光るから
- 地球がライトを当てているから
正解は **2. 空気との摩擦で高温になり光るから** です。
クイズ③ 隕石とはどんなもの?
- 流れ星が燃え尽きて消えたもの
- 燃え尽きずに地上まで落ちたもの
- 星の光が特別に強くなったもの
正解は **2. 燃え尽きずに地上まで落ちたもの** です。
クイズ④ 流星群が毎年同じ時期に見られる理由は?
- 彗星のチリの道を地球が通るから
- 星が毎年同じ日に爆発するから
- 人工的に花火を打ち上げているから
正解は **1. 彗星のチリの道を地球が通るから** です。
まとめ|流れ星の科学とロマンを学ぼう
- 流れ星の正体は、宇宙からやってきた小さなチリや石のかけら。
- 光る理由は、ものすごいスピードで地球に入り、空気との摩擦で燃えるから。
- 燃え尽きずに地上に落ちてきたものは「隕石」と呼ばれる。
- 流星群は、地球が彗星のチリの道を通るときにたくさんの流れ星が見える現象。
- 願い事の言い伝えは科学的な理由ではないけれど、世界中で「特別な光」として大切にされてきた。
流れ星は「科学のしくみ」と「人々のロマン」がまじわった不思議な現象です。
夜空を見上げたとき、ただ「きれいだな」と思うだけでなく、「どうして光るのか?」「昔の人はどう考えたのか?」と考えると、宇宙や歴史への興味がどんどん広がります。
もし流れ星を見つけたら、ぜひ願い事をしてみましょう。
科学的な理由はなくても、「夢に一歩近づける力」を自分に与えてくれるかもしれませんよ。
📚 学びの本棚から、次の1冊を
このテーマに関連する教材・読み物を、本棚を眺めるように探せます。
→ MOANAVI Library をひらく
この記事を書いた人
西田 俊章(MOANAVIスクールディレクター/STEAM教育デザイナー)
公立小学校で20年以上、先生として子どもたちを指導し、教科書の執筆も担当しました。
現在はMOANAVIを運営し、子どもたちが「科学・言語・人間・創造」をテーマに学ぶ場をデザインしています。


