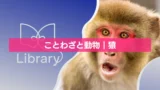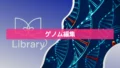動物のことわざとは?|昔の人の観察と知恵から生まれた言葉
「猿も木から落ちる」「猫に小判」「馬の耳に念仏」……
みなさんも、こんな“動物が出てくることわざ”を聞いたことがあるかもしれません。
ことわざは、昔の人が生活の中で感じたこと・気づいたことを短い言葉にまとめたものです。
その中には、人の行動や気持ちを、動物の特徴にたとえて表したものがたくさんあります。
🐾 動物が登場することわざが多い理由
昔の人にとって、動物はとても身近な存在でした。
農作業を手伝う牛や馬、家を守る犬、ねずみをとる猫など、
人間といっしょに暮らす動物がたくさんいたのです。
また、野山で見かけるサルやキツネ、鳥などの行動を観察し、
そこから人間の生き方や考え方を学ぼうとしたのです。
たとえば——
- サルは木登りが上手 → 「得意でも失敗することがある(猿も木から落ちる)」
- 猫は気まぐれで自由 → 「人の言うことを聞かない(猫に小判)」
- 馬は力が強い → 「聞く気がない人には何を言ってもむだ(馬の耳に念仏)」
このように、動物のしぐさや性格を人間に重ね合わせたのが、動物のことわざなのです。
🌏 ことわざは“昔の観察記録”でもある
今でこそ動物の行動は科学的に研究されていますが、
昔の人は道具もカメラもありません。
それでも、長い時間をかけて動物を観察し、特徴を見抜いてことわざを作りました。
つまり、ことわざは「言葉の形をした観察ノート」。
動物のことわざを学ぶことは、昔の人の「科学する心」にふれることでもあります。
🐕 動物ことわざからわかる人の考え方
動物のことわざを見ていくと、昔の人が
「まじめに働く」「失敗を恐れない」「欲ばらない」
といった生き方を大切にしていたことが伝わってきます。
ことわざはただの古い言葉ではなく、今の私たちにも役立つ知恵がたくさんつまっているのです。
📚 学びの本棚から、次の1冊を
このテーマに関連する教材・読み物を、本棚を眺めるように探せます。
→ MOANAVI Library をひらく
この記事を書いた人
西田 俊章(MOANAVIスクールディレクター/STEAM教育デザイナー)
公立小学校で20年以上、先生として子どもたちを指導し、教科書の執筆も担当しました。
現在はMOANAVIを運営し、子どもたちが「科学・言語・人間・創造」をテーマに学ぶ場をデザインしています。