教育・学びのコラム
 教育・学びのコラム
教育・学びのコラム  教育・学びのコラム
教育・学びのコラム 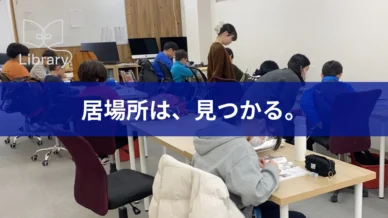 不登校・オルタナティブ教育
不登校・オルタナティブ教育 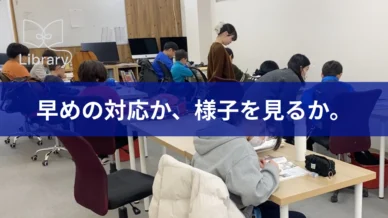 不登校・オルタナティブ教育
不登校・オルタナティブ教育 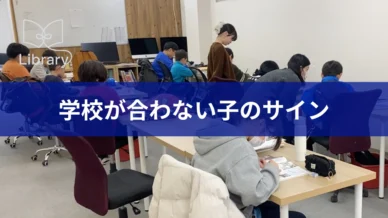 不登校・オルタナティブ教育
不登校・オルタナティブ教育 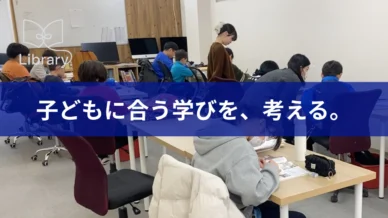 不登校・オルタナティブ教育
不登校・オルタナティブ教育 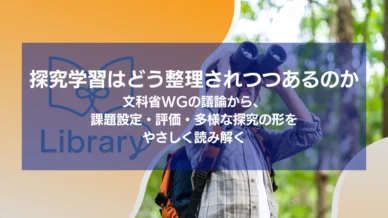 学校教育・制度
学校教育・制度  不登校・オルタナティブ教育
不登校・オルタナティブ教育  学校教育・制度
学校教育・制度  不登校・オルタナティブ教育
不登校・オルタナティブ教育  家庭学習・子育て
家庭学習・子育て  学校教育・制度
学校教育・制度  学校教育・制度
学校教育・制度  不登校・オルタナティブ教育
不登校・オルタナティブ教育  学校教育・制度
学校教育・制度  家庭学習・子育て
家庭学習・子育て  家庭学習・子育て
家庭学習・子育て  家庭学習・子育て
家庭学習・子育て  家庭学習・子育て
家庭学習・子育て  家庭学習・子育て
家庭学習・子育て  家庭学習・子育て
家庭学習・子育て  不登校・オルタナティブ教育
不登校・オルタナティブ教育  家庭学習・子育て
家庭学習・子育て  家庭学習・子育て
家庭学習・子育て  家庭学習・子育て
家庭学習・子育て  STEAM教育
STEAM教育  家庭学習・子育て
家庭学習・子育て  学校教育・制度
学校教育・制度  家庭学習・子育て
家庭学習・子育て  学校教育・制度
学校教育・制度  学校教育・制度
学校教育・制度  家庭学習・子育て
家庭学習・子育て  学校教育・制度
学校教育・制度  STEAM教育
STEAM教育  manabloom
manabloom  家庭学習・子育て
家庭学習・子育て  不登校・オルタナティブ教育
不登校・オルタナティブ教育  MOANAVIのイベント情報
MOANAVIのイベント情報  不登校・オルタナティブ教育
不登校・オルタナティブ教育  不登校・オルタナティブ教育
不登校・オルタナティブ教育  不登校・オルタナティブ教育
不登校・オルタナティブ教育  不登校・オルタナティブ教育
不登校・オルタナティブ教育  不登校・オルタナティブ教育
不登校・オルタナティブ教育  家庭学習・子育て
家庭学習・子育て  家庭学習・子育て
家庭学習・子育て  不登校・オルタナティブ教育
不登校・オルタナティブ教育  学校教育・制度
学校教育・制度  家庭学習・子育て
家庭学習・子育て  家庭学習・子育て
家庭学習・子育て 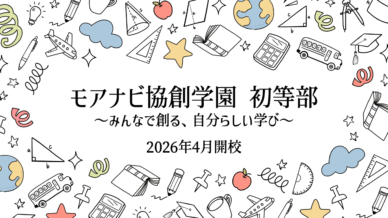 不登校・オルタナティブ教育
不登校・オルタナティブ教育  教育・学びのコラム
教育・学びのコラム  家庭学習・子育て
家庭学習・子育て  学校教育・制度
学校教育・制度  不登校・オルタナティブ教育
不登校・オルタナティブ教育  不登校・オルタナティブ教育
不登校・オルタナティブ教育  不登校・オルタナティブ教育
不登校・オルタナティブ教育  STEAM教育
STEAM教育  家庭学習・子育て
家庭学習・子育て  学校教育・制度
学校教育・制度  学校教育・制度
学校教育・制度  学校教育・制度
学校教育・制度  家庭学習・子育て
家庭学習・子育て  不登校・オルタナティブ教育
不登校・オルタナティブ教育  STEAM教育
STEAM教育  家庭学習・子育て
家庭学習・子育て  不登校・オルタナティブ教育
不登校・オルタナティブ教育  不登校・オルタナティブ教育
不登校・オルタナティブ教育  不登校・オルタナティブ教育
不登校・オルタナティブ教育  不登校・オルタナティブ教育
不登校・オルタナティブ教育  家庭学習・子育て
家庭学習・子育て  家庭学習・子育て
家庭学習・子育て  STEAM教育
STEAM教育  STEAM教育
STEAM教育  不登校・オルタナティブ教育
不登校・オルタナティブ教育 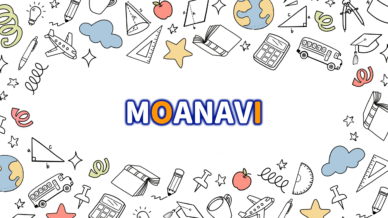 MOANAVIのお知らせ・イベント情報
MOANAVIのお知らせ・イベント情報  MOANAVIのお知らせ・イベント情報
MOANAVIのお知らせ・イベント情報  STEAM教育
STEAM教育 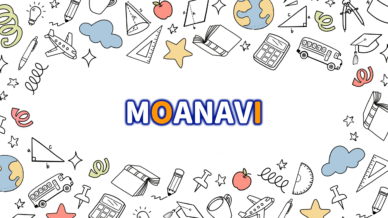 MOANAVIのお知らせ・イベント情報
MOANAVIのお知らせ・イベント情報  家庭学習・子育て
家庭学習・子育て 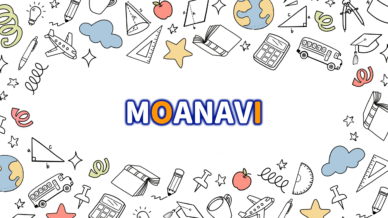 MOANAVIのイベント情報
MOANAVIのイベント情報  MOANAVIのお知らせ・イベント情報
MOANAVIのお知らせ・イベント情報  教育・学びのコラム
教育・学びのコラム  教育・学びのコラム
教育・学びのコラム  教育・学びのコラム
教育・学びのコラム  学校教育・制度
学校教育・制度 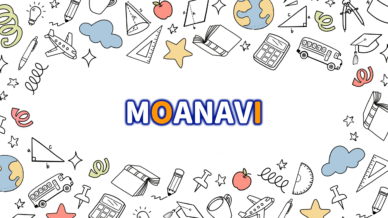 MOANAVIのニュース・活動報告
MOANAVIのニュース・活動報告 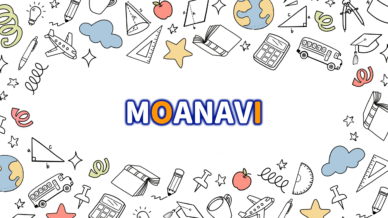 MOANAVIのイベント情報
MOANAVIのイベント情報 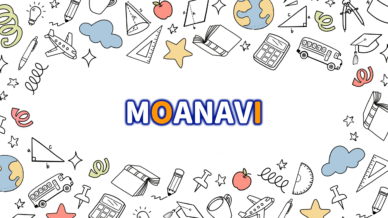 MOANAVIのイベント情報
MOANAVIのイベント情報 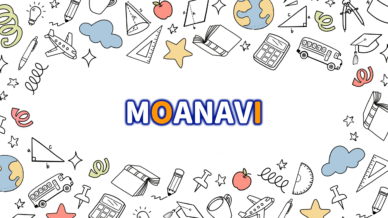 STEAM教育
STEAM教育  MOANAVIのお知らせ・イベント情報
MOANAVIのお知らせ・イベント情報 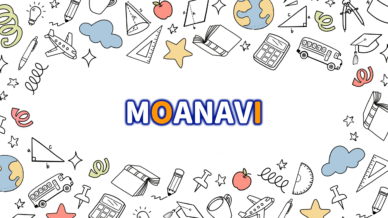 MOANAVIのお知らせ・イベント情報
MOANAVIのお知らせ・イベント情報  家庭学習・子育て
家庭学習・子育て  家庭学習・子育て
家庭学習・子育て 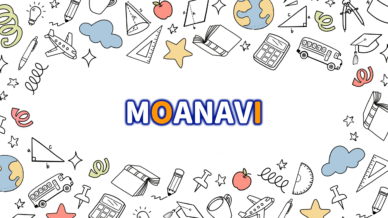 MOANAVIのお知らせ・イベント情報
MOANAVIのお知らせ・イベント情報  不登校・オルタナティブ教育
不登校・オルタナティブ教育 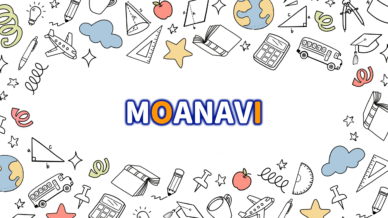 MOANAVIのお知らせ・イベント情報
MOANAVIのお知らせ・イベント情報  学校教育・制度
学校教育・制度 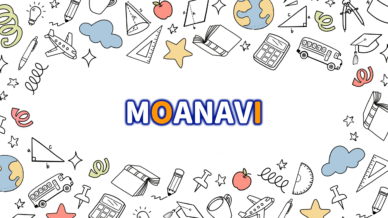 教育・学びのコラム
教育・学びのコラム  家庭学習・子育て
家庭学習・子育て  STEAM教育
STEAM教育  不登校・オルタナティブ教育
不登校・オルタナティブ教育