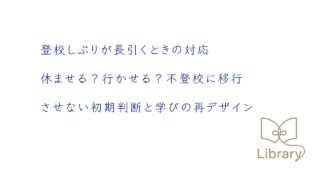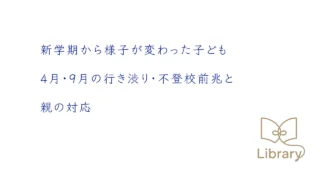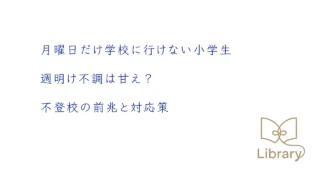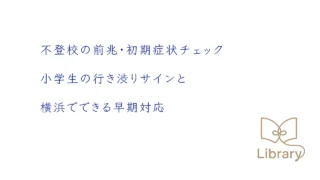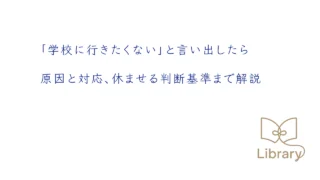理科教育が変わる!
中教審・理科ワーキンググループが示す探究学習と新しい学びの方向性
保護者が知っておきたい改革のポイント
いま、文部科学省の中央教育審議会(中教審)では、
理科教育の大きな見直しが始まっています。
2025年秋に立ち上がった「理科ワーキンググループ(理科WG)」では、
“知識を覚える理科”から“考える理科”へ――という方向転換が議論されています。
キーワードは「探究学習」。
子どもたちが自分で問いを立て、観察・実験を通して答えを導く学び方が、これからの理科の主流になります。
この動きの背景には、AI・情報化社会の進展と、
科学的な判断力を育てる教育への転換があります。
主査の古村孝志教授(東京大学地震研究所)は、
「日本の子どもは知識はあるが、判断する力が弱い」と指摘し、
“科学的に考える力”を重視する方向性を示しています。
この記事では、
中教審・理科WGで議論されている理科教育改革の内容をわかりやすく解説し、
これからの理科がどう変わるのか、そして家庭で何ができるのかを整理します。
保護者が知っておきたい「新しい理科の学び」のポイントを、丁寧に読み解いていきましょう。
理科教育が変わる理由|中教審で進む「探究重視」への転換
いま、文部科学省の中央教育審議会(中教審)では、次の学習指導要領の改訂に向けて、理科教育の大きな見直しが始まっています。
背景にあるのは、子どもたちの理科離れや理系進学率の低下、そして急速に進むAI・デジタル社会への対応です。
これまでの理科は「正しい答えを覚える教科」として扱われることが多く、知識中心の学びになりがちでした。
しかし、現代社会では、科学的な知識を持つだけでなく、情報を正しく判断し、根拠をもって考える力が求められています。
中教審では、「理科教育を探究的に見直すこと」が、未来の教育に欠かせないテーマとして位置づけられています。
その中核を担うのが、今回設置された**理科ワーキンググループ(理科WG)**です。
理科ワーキンググループとは|中教審が設置した専門チームの役割
理科ワーキンググループは、中教審の「教育課程部会」に設置された専門組織で、理科教育の現状と課題を分析し、改訂の方向性を提言する役割を持っています。
このWGには、大学研究者、教育現場の教員、教育委員会関係者など、幅広い専門家が参加。
主査(まとめ役)は、東京大学地震研究所の古村孝志教授です。
古村氏は地震学の研究者として知られていますが、近年は「科学的リテラシーをどう育てるか」という教育分野にも強い関心を持ち、理科教育改革をリードする存在です。
第1回会合は2025年10月6日に開催され、今後数回にわたって議論を重ね、2026年度中に最終報告(答申)をまとめる予定です。
この議論が、次の学習指導要領や教科書の内容に直接反映されていきます。
理科教育の新しい方向性|理科WGで議論された5つの柱
理科ワーキンググループ(WG)では、これまでの理科教育を「知識を教える教科」から「考える力を育てる教科」へと変えていくために、いくつかの重要な視点が話し合われています。
その中心となるのが、次の5つの柱です。いずれも、子どもたちの“理科との向き合い方”を根本から変えていくものです。
① 探究活動の充実|「自分で問いを立てて考える」学びへ
WGで最も強調されているのが、「探究的な学びの充実」です。
これまでの理科では、授業で先生が教える内容をそのまま覚えるスタイルが主流でした。
しかしWGでは、子どもが自分で「なぜだろう?」と問いを見つけ、その疑問を自分の力で調べるというプロセスを重視しています。
たとえば、「なぜ台風の進路は毎年ちがうの?」「なぜ光は反射するの?」といった身近な疑問を出発点に、観察・実験・調査・発表を行い、答えを導くような授業へ。
その中で、データの扱い方や結果のまとめ方、論理的に説明する力を育てることがねらいです。
この「問い→調べ→考える→伝える」という一連の流れが、次期学習指導要領でも理科教育の中心軸となります。
つまり、理科は「答えを教わる教科」ではなく、「答えを見つけ出す教科」に変わっていくのです。
② 観察・実験の環境整備|“探究できる理科室”をつくる
探究的な理科教育を進めるうえで課題となるのが、「実験や観察の環境整備」です。
理科WGでは、全国の学校で実験器具の老朽化や、先生の準備負担が大きいことが問題視されています。
たとえば、実験道具の更新が進まず、古い器具を使っている学校も多くあります。
また、安全面の懸念や、時間不足によって「観察・実験の省略」が起きている現実も指摘されています。
WGではこうした課題を受けて、
- ICTやセンサーなどのデジタル機器を活用した観察・実験
- クラウド上でデータを共有できる**“オンライン実験ノート”の導入**
- 一人一台端末を活かしたデータ解析・比較活動
など、現代的な環境整備を進める方向性が議論されています。
実験が「時間を取る負担」ではなく、発見の楽しさを実感できる体験へと変わるような支援策が求められています。
③ 知識偏重からの脱却|「なぜそうなるのか」を理解する授業へ
理科は“暗記教科”という印象を持つ人も多いですが、WGではこの考え方を根本から見直す方針です。
知識を丸暗記しても、それを活用して考えられなければ意味がありません。
たとえば「植物は光合成をする」という事実を覚えるだけでなく、
「なぜ光が必要なのか」「環境によってどう変わるのか」「地球全体のエネルギー循環とどうつながるのか」といった背景の理解と応用を重視するようになります。
この変化は、単なる知識量の削減ではなく、思考の深さを重視する方向転換です。
“詰め込み”から“深掘り”へ——これが、今回の理科改革の核心とも言えます。
④ 教科書と授業内容の見直し|「量」よりも「質」へ
WGでは、教科書の内容が過剰になっている現状にも着目しています。
学習指導要領の改訂や教材の充実により、1単元あたりの情報量が増えすぎ、
「授業時間内に終わらない」「実験まで手が回らない」といった声が現場から多数あがっています。
そのため、次の改訂では、内容を精選(せいせん)し、“考える時間”を確保する方向での見直しが進む見通しです。
つまり、今後の教科書は「すべてを詰め込む総まとめ型」ではなく、**「深く学ぶための道しるべ」**になることを目指しています。
また、デジタル教科書との併用によって、動画やシミュレーションなどを活用し、
紙だけでは伝わりにくい現象を“体感的に理解する”流れも検討されています。
⑤ 女子の理系進路支援|「理科は自分に関係ない」を変える
WGの議論では、「女子の理系進学率の低さ」も重要なテーマの一つです。
OECD諸国の比較でも、日本は理系進学・理数系職種への女性比率が依然として低い水準にあります。
背景には、「理科は難しい」「女性には向かない」といった無意識の固定観念が、社会や家庭の中に根強く残っていることがあります。
理科WGでは、
- 女子生徒が興味を持てる教材・テーマの開発
- 女性研究者・技術者の講話や出張授業
- 保護者・教師の意識改革研修
といった取り組みを進めるべきだという意見が出されています。
特に、古村主査は「子どもよりも、まず大人の意識を変えることが大切」と指摘しています。
理科教育を通して、“性別に関係なく科学を楽しむ文化”を広げることが、次の時代の教育の土台となりそうです。
これらの5つの柱は、単に授業内容の見直しにとどまらず、
「理科の学び方そのものを変える」教育改革です。
子どもたちが「なぜ」「どうして」と自分から問いを立てられるようになれば、理科はより身近で、生きた学びになります。
「探究的な学び」とは?理科の授業がどのように変わるのか
理科ワーキンググループでの議論の中心テーマとなっているのが、**「探究的な学び」**です。
この言葉は近年よく耳にしますが、保護者の方にとっては少し抽象的に感じられるかもしれません。
一言で言えば、探究的な学びとは――
**「自分で問いを見つけ、自分の力で考え、調べ、答えを導き出す学び」**です。
これまでの理科は、教師が説明し、生徒がそれを覚えるという「受け身の授業」が中心でした。
しかしこれからの理科では、子どもが自分で考え、行動し、学びを組み立てることが求められます。
「知識をもらう」から「問いを立てる」へ
たとえば、これまでは「水が沸騰する温度は100℃です」と教わって終わりでした。
しかし探究的な学びでは、
「なぜ水は100℃で沸騰するのか?」「お湯に塩を入れると温度はどう変わる?」
といった問いを子ども自身が出し、その答えを実験や資料から導き出します。
教師は答えを与える“解説者”ではなく、学びの設計者・伴走者へと役割を変えていきます。
授業は一方的な講義ではなく、子どもたちの意見や気づきを中心に進んでいくようになります。
実験・観察に「考察」と「説明」が加わる
探究的な授業では、単に実験を行って結果を記録するだけでは終わりません。
「なぜその結果になったのか」「他の条件ならどうなるか」といった**考察(かんさつ+思考)**を重視します。
また、他の生徒や先生に対して、自分の考えをデータや根拠をもとに説明する「表現」の場も設けられます。
つまり、理科の授業が「結果を書いて終わり」ではなく、
考える・伝える・振り返るまでのプロセスを一体として扱うように変わります。
こうした流れは、単なる理科の知識を超えて、「論理的に話す力」「相手に伝える力」「チームで考える力」など、社会で必要とされるスキルの育成にもつながります。
教科横断型のテーマが増える
理科の探究は、もはや理科だけの話ではありません。
地球温暖化、再生可能エネルギー、AI技術、食と環境、防災など――。
これらは理科的な知識だけでなく、社会・情報・国語・道徳など、他の教科の視点と重なり合うテーマです。
理科WGでも、「教科横断的な学びを通して、現実社会の課題を科学的に考える力を育てるべき」との意見が多く出ています。
たとえば、
- 「気候変動を止めるには、科学的に何ができるのか?」
- 「AIは自然科学の理解をどう変えるのか?」
- 「防災・減災に科学技術はどう貢献できるのか?」
こうしたテーマに取り組むことで、子どもたちは「理科=身近な社会を支える学問」として捉えられるようになります。
デジタル時代の「探究」をどう進めるか
探究活動の中では、ICTの活用も進んでいきます。
タブレットを使ったデータ収集、オンラインでの共同調査、シミュレーション実験など、
紙のノートや黒板だけではできなかった**“実験の再現性と共有”**が可能になります。
たとえば、実験結果をクラウド上で比較したり、動画で記録して振り返ったりすることで、
子どもたちが自分の仮説を客観的に見直す経験を積めるようになります。
理科WGでは、こうした**「デジタル×探究」**の取り組みを全国的に支援する仕組みづくりも検討されています。
評価も「正答」から「プロセス」へ
このように学び方が変わると、当然、評価の基準も変わります。
従来のように「答えが合っているかどうか」だけではなく、
- どんな疑問を立てたか
- どのように調べ、考えたか
- 結果をどう説明したか
といった**学びのプロセス(過程)**が評価対象になります。
これにより、「暗記が得意な子だけが評価される」状況から、
「考える力や表現力のある子が伸びる」学びへと変化していきます。
探究的な学びは、短期間で成果が見えるものではありません。
しかし、こうした経験の積み重ねが、将来の「問題解決力」や「科学的思考力」につながります。
理科WGの議論がめざすのは、
“理科を学ぶ”から“理科で考える”へ――
子どもたちの学びをそのように変えていくことです。
主査・古村孝志氏の発言に学ぶ|理科教育で育てたい「判断力」と「思考力」
古村孝志主査は、第1回会合で次のような趣旨の発言をしています。
「日本の子どもたちは理科の知識レベルは高いが、SNSなどで誤った科学情報に影響されることも多い。
知識だけでなく、情報を判断する力を育てることが重要だ。」
この言葉は、まさに現代社会の課題を象徴しています。
インターネット上には、科学的根拠のない情報も多く存在します。
理科教育は、正しい知識を伝えるだけでなく、「情報を見極め、科学的に考える力」を育てる場であるべきだという考え方です。
また、古村氏は「理科教育を通じて、社会課題に向き合う思考力を育てたい」とも語っています。
理科の学びを“社会のリアルな問題解決”につなげることが、今後の教育の大きなテーマになるでしょう。
2025年度以降のスケジュール|学習指導要領改訂と理科教育の今後
理科WGの議論は、2025年度いっぱいまで継続される見込みです。
その後、教育課程部会・特別部会を経て、2026年度中に新しい学習指導要領が告示される予定です。
実際の学校現場での教科書改訂や授業変更は、2027年度以降に段階的に導入される見通しです。
つまり、今の小学生が中学生になるころには、新しい理科教育が本格的にスタートする可能性があります。
同時に、探究活動を支える教員研修・教材開発・設備整備も進められる計画です。
これにより、学校現場の指導体制が「探究型授業」に対応できるようになります。
保護者ができるサポート|家庭で育てる「探究する力」
理科教育の改革は、学校の中だけで完結するものではありません。
「探究的な学び」は、子どもたちが日常の中で疑問を持ち、考え、調べることから始まります。
その最初のきっかけをつくるのが、実は家庭なのです。
「なぜ?」と聞く力を育てる
子どもの探究心の芽は、何気ない日常の中にあります。
たとえば、
- 「雨が降る前に空が暗くなるのはなぜ?」
- 「冷蔵庫に入れるとどうして氷ができるの?」
- 「どうして夏になるとセミが鳴くの?」
こうした素朴な疑問に対して、大人が「それはね…」とすぐに答えてしまうと、子どもの思考がそこで止まってしまいます。
大切なのは、答えを教えることではなく、考えるきっかけを渡すことです。
たとえば、
「どうしてだと思う?」「それを確かめるにはどうしたらいいかな?」
と問い返してみる。
この一言で、子どもは“自分で調べてみよう”というモードに切り替わります。
家庭での会話の中に、こうした「考える余白」を意識的につくることが、探究的な学びの第一歩になります。
「一緒に考える時間」を大切にする
探究学習で求められるのは、子どもが自分の考えを持ち、相手と共有する力です。
家庭では、親が“先生”のように教えるのではなく、学びのパートナーとして一緒に考える姿勢を見せることが大切です。
たとえば、テレビのニュースや科学番組を見ながら、
「どうしてこういうことが起きたんだろうね?」
「自分だったらどうする?」
と話してみるだけでも、立派な探究の時間になります。
親子で“正解を探す”のではなく、“考えを交換する”という体験が、
子どもにとって「意見をもつことの面白さ」や「考える楽しさ」を実感するきっかけになります。
「調べる」「試す」を家庭でも
学校での探究活動とつなげるように、家庭でも簡単にできる科学的な体験を取り入れてみましょう。
特別な教材がなくても、身近なもので十分です。
- 冷蔵庫の中で氷ができるスピードを温度で比べる
- 洗濯物の乾き方を、日向と日陰で観察してみる
- ペットボトルで空気砲を作ってみる
- 夜空を見て、星の動きを毎晩スケッチする
こうした小さな体験が、子どもにとっては**「理科=自分の生活の中にあるもの」**という実感につながります。
重要なのは結果ではなく、「どうしてそうなったかを話す」時間を取ることです。
「結果」よりも「考え方」を認める
子どもが自由研究や実験をしたとき、結果がうまくいかないこともあります。
でも、探究的な学びでは「正解」よりも「考え方」や「過程」が大切です。
「思ったようにならなかったけど、どうしてそうなったと思う?」
「次にやるとしたら、どんな工夫ができそう?」
こうした声かけが、子どもの思考を深めます。
「うまくいかなかった=失敗」ではなく、「次の発見につながるステップ」として受け止める習慣を、家庭から育てていきましょう。
「理科嫌い」を生まない家庭の関わり方
理科が苦手になる原因の多くは、「難しそう」「自分には関係ない」と感じることにあります。
でも、理科WGがめざしているのは、「すべての子どもにとって理科が身近で楽しい教科」になることです。
そのためには、家庭でのちょっとした声かけが大きな支えになります。
- 失敗を笑わず、一緒に考える
- 興味を持ったテーマを尊重する
- 結果ではなく過程を褒める
- 理科の話題をポジティブに扱う
こうした小さな積み重ねが、子どもの「科学への信頼感」を育てます。
“理科は苦手”ではなく、“理科は面白い”と感じること。
それが探究的な学びの出発点です。
家庭と学校をつなぐ“学びの橋渡し”に
学校での理科の授業と、家庭での体験がつながると、学びは格段に深まります。
たとえば、授業で学んだ内容を家庭で話題にしたり、自由研究のテーマを一緒に考えたりするだけでも、子どもにとっては学びの再体験になります。
MOANAVIのように、家庭でも実践できるSTEAM教育や探究教材を提供する場を活用するのも有効です。
「家庭が探究の入り口になる」ことで、理科教育の改革はより実りあるものになります。
これからの理科教育は、学校と家庭が協力して“学ぶ力”を育てる時代へ。
保護者の関わり方が、子どもの未来の学び方を変えていきます。
まとめ|理科は「覚える」から「考える」教科へ
中教審・理科ワーキンググループでの議論は、理科教育のあり方を根本から問い直す重要な動きです。
これからの理科は、単に知識を覚えるだけではなく、判断力・思考力・表現力を育てる教科へと進化していきます。
保護者にとって大切なのは、この変化を“テスト対策”ではなく“未来への準備”として受け止めること。
子どもたちが自ら問いを立て、考え、学び続ける姿勢を家庭でも支えることが、これからの理科教育の鍵になります。
MOANAVIでは、こうした教育改革の動きをわかりやすく発信し、家庭や地域で実践できる「探究型の学び」を応援していきます。
理科教育の改革が進む今、子どもたちに求められているのは「自分で問いを立て、考え、学ぶ力」です。
MOANAVI(モアナビ)では、こうした探究的な学びを日常の中で育てるために、
科学・言語・人間・創造の4テーマを軸にしたSTEAM教育やプロジェクト型学習に取り組んでいます。
実験や創作を通して、理科や社会の知識を“使って考える力”を育てる――
そんな学びの場を、子どもたち一人ひとりに。
記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)
STEAM教育デザイナー / MOANAVIスクールディレクター
理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。
📚 経歴・資格
✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者
✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)
✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)
✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演
✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説