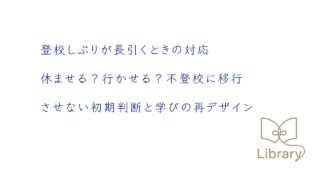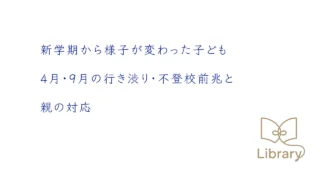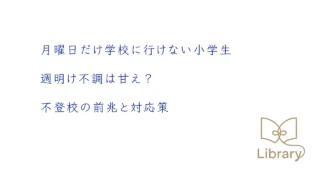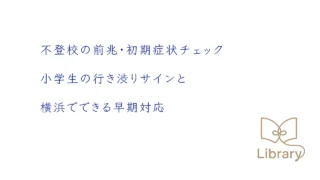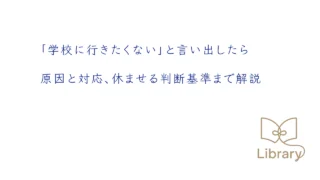子どもが学校に行きたくない…どうすればいい?
不登校の始まりと親ができる最初の対応
子どもが「学校に行きたくない」と悩んでいる保護者の方へ。この記事では、不登校になりかけの子どもに対して 親が最初にすべきこと・してはいけないこと を解説します。焦らず、子どもの気持ちに寄り添い、親ができる対応方法をわかりやすくご紹介します。学校へ行かないことが必ずしも悪いことではなく、適切なサポートがあれば新たな学びの道を切り開くことができます。最初の一歩を踏み出すためのヒントが見つかりますよ。
1. はじめに
「最近、うちの子が学校に行きたくない」と感じている保護者の方へ。お子さんが学校に行きたくない理由が何かあるのでしょうが、それに気づくことは容易ではありません。特に、最初に学校へ行かない理由を話してくれない場合、親としてどう接するべきか悩んでしまいますよね。
でも、不登校になりかけた場合でも焦る必要はありません。まずは 子どもの気持ちを理解すること が大切です。この段階では、親がどんな対応をするかが子どもの心の回復に大きく影響します。無理に学校に行かせるのではなく、まずは子どもの話に耳を傾け、どんなサポートが必要なのかを見極めましょう。
この記事では、不登校の始まりにある保護者が知っておくべき、最初に取るべき行動と避けるべき対応を紹介します。
2. 「不登校のはじまり」によくある親の戸惑い
子どもが学校に行きたくないと言い始めた時、保護者は次のような思いを抱くことが多いです。
- 「これはただの甘えじゃないか?」
- 「このままだと、どうなってしまうんだろう?」
- 「他の子どもたちは普通に行っているのに、うちの子だけ…」
- 「学校に行かないことで、将来困るのでは?」
親としては、学校に行かないことに対して不安が募り、何とか解決しなければという焦りが生まれます。しかし、このような感情が強くなりすぎると、子どもは「理解されていない」と感じ、さらに心を閉ざしてしまうことがあります。
まず大切なのは、「不登校」とは一概に悪いことではない ということです。子どもが学校に行かない理由は多岐にわたり、心の問題、環境の問題、友達関係など、いろいろな背景があります。それを理解し、焦らずに子どもの気持ちを受け止めていきましょう。
3. 親が最初にすべき3つのこと
子どもが学校に行きたくないと言い始めたとき、親としてはどのように接するべきでしょうか?以下の3つの対応が大切です。
① 子どもの話をじっくり聞く
子どもが学校に行きたくない理由をしっかりと聞くことが最初のステップです。
ただし、「どうして学校に行きたくないの?」と無理に問い詰めるのは避けましょう。子どもは答えることがプレッシャーに感じる場合があります。
代わりに、「最近学校はどうだった?」や「何か困っていることがあった?」と、自然に話せるような雰囲気を作りましょう。
子どもが安心して話せる環境を整えることが、最も大切です。
もし話すことが難しければ、手紙やメモで気持ちを伝えてもらう方法も効果的です。子どもは言葉にしにくい気持ちを文字にすることで、少しずつ整理できることがあります。
② 安心できる環境を作る
子どもが学校に行かないことで焦ってしまう親の気持ちはわかりますが、「学校に行かない=悪いこと」 という考え方を改めることが重要です。
「今日はゆっくりしていいよ」「無理に行かなくても大丈夫だよ」というメッセージを伝えることで、子どもは安心感を感じ、気持ちが楽になります。
この時間を使って、子どもがどんなことに悩んでいるのか、どうして学校に行きたくないのかをじっくりと聞いてあげましょう。
また、家で過ごす時間を心地よく過ごせるように、安心できる環境作りを意識しましょう。穏やかな空間で過ごすことが、気持ちを整理する手助けとなります。
③ 親自身が落ち着く
親が不安や焦りを感じていると、それが子どもに伝わります。子どもは敏感にその雰囲気を感じ取りますので、親が冷静でいることがとても大切です。
もし自分自身が心配でどうしていいか分からなくなった場合は、他の保護者や専門家に相談してみるのも良い方法です。
冷静に、かつ穏やかな気持ちで子どもと向き合い、支えていきましょう。
4. やってはいけない対応
親が不安になりすぎて取るべきでない対応もあります。以下のような対応は避けましょう。
- 「行けない理由を聞いても納得できない」と責める
- 「みんな行ってるのに、あなただけはどうして?」と他の子と比較する
- 「このままだと将来困るよ」と脅す
- 塾や習い事を無理に増やす
これらの言葉や行動は、子どもを 「理解されていない」「ダメな子だ」と感じさせる 可能性が高いです。子どもが抱えている問題に焦点を当て、前向きに解決策を考えることが必要です。
5. 「このままで大丈夫?」不安を感じたら
もし「このままで本当に大丈夫なのか?」と感じる場合、親は学校に行かせることだけが正解ではないことを知っておくことが大切です。
不登校を経験することが、必ずしも将来に悪影響を及ぼすわけではありません。
フリースクールや家庭学習、オンライン学習など、学びの方法はたくさんあります。
親は、情報を集めて子どもに合った方法を選び、子どもが自信を持てる環境を整えていくことが求められます。
6. MOANAVIという選択肢

MOANAVIでは、「対話と体験」を大切にした学習 を提供しています。
子どもが学校に行きたくない理由は様々ですが、MOANAVIでは、子どものペースに合わせて、学びの場を提供します。
学校に通わないことで、学びのチャンスを失うことはありません。MOANAVIは、お子さんが自分のペースで成長できる環境を整え、安心して学べる場を提供します。
もし不安を感じたら、ぜひMOANAVIを選択肢としてご検討ください。
7. まとめ
不登校になることは決して悪いことではありません。まずは、子どもがどうして学校に行きたくないのか、その理由を理解すること が重要です。焦らず、子どものペースで支えていきましょう。親の対応が子どもの心を癒し、新しい学びの道を切り開くことができます。MOANAVIのような支援を受けることで、安心して学び続けることができます。
子どもにとって最適な学びの環境を一緒に見つけて、前に進んでいきましょう。
記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)
STEAM教育デザイナー / 株式会社MOANAVI代表取締役
理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。
📚 経歴・資格
✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者
✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)
✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)
✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演
✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説