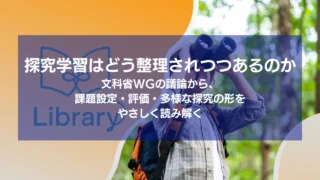オルタナティブスクールとは?
教育の新しい選択肢とMOANAVIの取り組み
今、注目を集めている「オルタナティブスクール」。
不登校や学校に馴染みにくい子どもたちの受け皿として、全国的にニーズが高まっています。この記事では、「オルタナティブスクールとは何か?」という基本から、主な特徴や教育理念、最新の統計データまでを分かりやすく解説。
さらに、横浜市内でSTEAM教育と自己調整学習を融合した独自の取り組みを行うMOANAVIの事例を紹介し、どんな家庭や子どもに向いているのかを具体的に解説します。
はじめに:オルタナティブスクールとは何か?
近年、「オルタナティブスクール」が注目されています。文部科学省の調査によると、不登校の児童生徒数は2024年度で約20万人に上り、その受け皿として多様な学びの場が求められています。
オルタナティブスクールとは、公立・私立の従来型の学校とは異なる教育理念や学びのスタイルを持ち、多様な学習ニーズに対応する学校の総称です。子ども一人ひとりの個性やペースを尊重し、自由な学びや子ども主体の教育を実践。特に不登校や学校に馴染みにくい子どもたちにとって重要な居場所となっています。
オルタナティブスクールの特徴とメリット
教育改革の流れの中で、文科省も「多様な学びの場」の推進を掲げ、オルタナティブスクールの役割が拡大しています。
主な特徴は次の通りです。
- 個性尊重と自由な学び
2023年の調査では、約65%のオルタナティブスクールが子どもの興味やペースに合わせたカリキュラムを採用しています。 - 子ども主体の教育
教師主導ではなく、子どもが主体的に学習テーマや活動を選べることが多く、主体性の育成に効果的です。 - 多様な教育理念
シュタイナー、サドベリー、STEAM教育など、さまざまな教育哲学が存在します。2024年の業界レポートでは、STEAM教育を取り入れるスクールが前年比15%増加しています。 - 不登校支援の役割
不登校児童生徒の約30%がオルタナティブスクールやフリースクールなど多様な教育機関を利用しており、そのニーズは今後も増加傾向です。
MOANAVIのオルタナティブスクールとしての取り組み
MOANAVIは横浜市西区に拠点を持ち、STEAM教育と自己調整学習を融合させた独自の教育システムを展開しています。
- プロジェクト型学習
子どもが自分の興味を追求しながら学ぶことで、21世紀に求められる問題解決力や創造力を育成。 - 自己調整学習とSTUDY POINT制度
自分に合った学習ペースを選び、取り組みの質を高める仕組みとして評価されています。 - 不登校支援
先生たちが子どもの”今”に寄り添うことで、子どもたちが安心して通える居場所。
MOANAVIは、こうした特色を持つオルタナティブスクールとして地域の多様なニーズに応えています。
オルタナティブスクールの選び方のポイント
教育環境の多様化が進む中で、最適なスクール選びが重要です。
- 教育理念や学習スタイルが子どもの性格や興味に合うか
- 通いやすい場所か、送迎やオンライン対応の可否
- 不登校支援やサポート体制が充実しているか
- 費用の透明性と家庭の負担に見合っているか
2025年の最新調査によれば、親の約70%が「サポート体制の充実」を最重要視しています。
まとめ
不登校や多様な学びのニーズが増加する中、オルタナティブスクールは重要な選択肢として社会的役割を果たしています。
MOANAVIは、最新の教育理論と実践を融合し、子どもたち一人ひとりに寄り添った学びの場を提供。地域の多様なニーズに応え続けています。
横浜でオルタナティブスクールをお探しの方は、ぜひ一度MOANAVIの公式サイトをご覧ください。
記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)
STEAM教育デザイナー / 株式会社MOANAVI代表取締役
理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。
📚 経歴・資格
✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者
✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)
✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)
✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演
✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説