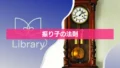橋や鉄塔、そして東京タワーやスカイツリー――。
どれも「トラス構造」という三角形の仕組みで支えられています。
トラス構造とは、三角形の形を組み合わせて、力を分け合いながら支えるデザインのこと。
この形は、建築や機械だけでなく、ヒンメリのような北欧アートや日本の木造建築にも生かされています。
この記事では、
トラス構造のしくみや種類、日本の建築との共通点、
東京タワーやスカイツリーの構造、ヒンメリのデザイン、
さらに家でできる自由研究アイデアまでを、やさしく解説します。
「強さ」と「美しさ」をつなぐ三角形の科学とデザインの世界へ――
いっしょにのぞいてみましょう。
トラス構造とは|三角形が生み出す強さと美しさのひみつ
橋や鉄塔、体育館の屋根などを見上げると、三角形の骨組みがたくさん並んでいるのを見たことがありませんか?
それが「トラス構造(Truss Structure)」です。
トラス構造とは、細い棒や柱を三角形につないで組み合わせることで、大きな力を効率よく支える構造のことをいいます。
一見すると軽そうに見えますが、実はとても丈夫で安定しています。
この「軽くて強い」デザインこそが、トラス構造の魅力です。
🔺 三角形はなぜ強いの?
四角形の枠を作って押したり引いたりすると、形がくずれてしまいます。
しかし、三角形はどこを押しても形が変わりません。
これは、力が3つの辺に分散されて流れるためです。
三角形の頂点を押すと、力は「引っぱられる辺」と「押される辺」に分かれ、
お互いを支え合うようにバランスが取れます。
この性質を使うと、少ない材料で大きなものを支えられるのです。
⚙️ 力の流れをデザインする
トラス構造では、「引張力(ひっぱる力)」と「圧縮力(おす力)」の2つを上手に分けて使います。
たとえば、橋の上を車が通るとき、重さがかかる部分には引張力が働き、
上側の部材には圧縮力がかかります。
この2つの力を三角形の中でうまく分けることで、
全体として安定し、ゆがみにくくなるのです。
建物や橋は、「力の流れ」を考えて設計されています。
つまり、**トラス構造は“見えない力のデザイン”**でもあるのです。
🌿 自然界にもあるトラス構造
実は、自然の中にもトラスのような形がたくさんあります。
ハチの巣の六角形、トンボの羽の細かい網目、木の枝の分かれ方――。
これらはすべて、力を分け合って安定する「構造の知恵」です。
自然が生み出した形と人間のデザインが、ここでつながります。
クイズ①
次のうち、「三角形の形が強い」理由として正しいものはどれでしょう?
- 三角形は面積が広いから
- 三角形は力が分散されて形がくずれにくいから
- 三角形は見た目がシンプルだから
正解は 2 です。
👉 三角形は、力を3つの辺に分けて支えるため、押されても形が変わりません。
トラス構造の仕組みと種類|力を分けて支える三角形のデザイン
トラス構造のいちばんの特徴は、「形で力を支える」という点です。
鉄や木のような材料の強さだけでなく、どのようにつなぐかという“形の設計”が強度を決めます。
ここでは、トラスの基本的な仕組みと、代表的な種類を見ていきましょう。
⚙️ 力を伝えるしくみ
トラス構造では、細い棒(部材)が「節点」と呼ばれる交点でつながっています。
それぞれの部材には、押される「圧縮力」か、引っぱられる「引張力」がはたらきます。
この2種類の力がうまく釣り合うことで、全体が安定するのです。
四角形では角が動いて形がくずれてしまいますが、
三角形に組むと、力の流れが三方向に分かれて“逃げ道”をつくります。
この仕組みが、トラス構造を支える大きな秘密です。
🏗 トラスの主な種類
トラス構造には、使う場所や目的に合わせていくつかの種類があります。
- ワーレントラス(Warren Truss):
もっとも一般的な形。三角形を交互に並べたデザインで、橋や屋根に多く使われます。 - プラットトラス(Pratt Truss):
下向きの力に強い構造。引張と圧縮をバランスよく分けられるため、長い橋に適しています。 - ハウトラス(Howe Truss):
プラットとは逆に、上向きの力に強い構造。木造の屋根などに多く使われます。 - 平行弦トラス(Parallel Chord Truss):
上下の線が平行で、体育館の天井やホールの梁などに使われます。
どの形も「三角形の組み合わせ」であることに変わりはありません。
三角の連なりが、力を全体へ分けて逃がしているのです。
🧱 材料によって変わるデザイン
トラスは「材料」によっても形が変わります。
鉄やアルミは引張力に強く、木材は圧縮力に強い素材です。
そのため、鉄骨トラスでは細い部材でも十分な強さが得られ、
木造トラスでは太めの材を使って“あたたかみのあるデザイン”が可能になります。
どちらも、**「最小の材料で最大の強度を生み出す」**という考え方に基づいています。
これは、自然界にも通じる“効率の美しさ”です。
クイズ②
次のうち、「プラットトラス」が得意とする力の方向として正しいのはどれでしょう?
- 横からの風の力
- 下からの浮き上がる力
- 上からの重力による力
正解は 3 です。
👉 プラットトラスは上からの重さ(重力)を効率よく支えるように設計されており、橋などに多く使われます。
日本の木造建築とトラス構造の共通点|軸組と筋交に見る伝統の強さ
日本の家やお寺、神社などの木造建築には、トラス構造と同じ原理がかくれています。
「軸組(じくぐみ)構造」や「筋交(すじかい)」と呼ばれる部分が、建物を支える三角形の役割を果たしているのです。
🪵 木造軸組構造とは?
日本の多くの木造住宅は「木造軸組構造」という方法で作られています。
柱・梁(はり)・土台を「軸」として組み立て、建物の“骨格”をつくるやり方です。
ただし、これだけでは四角い枠がゆがみやすく、地震や風の力で倒れてしまうおそれがあります。
そこで、柱と柱のあいだに斜めに入れる「筋交(すじかい)」が登場します。
この筋交が入ることで、四角形の枠が三角形の構造に変わり、強度がぐんと上がるのです。
つまり、筋交とは木造建築における「トラスの一本」なのです。
🏯 寺社建築にも見る三角の知恵
昔の寺や神社を見上げると、屋根の下に複雑な木組みが並んでいます。
これは「斗栱(ときょう)」や「小屋組」と呼ばれる部分で、
三角形の組み合わせによって屋根の重さを分散させる構造です。
鉄やボルトを使わずに木だけで強度を出す――
この“組む”技術は、まさにトラス構造の考え方と同じです。
日本の大工は、長い年月をかけて「力の流れ」を読む技術を磨いてきました。
その知恵が、現代の建築デザインにも受け継がれています。
🧩 木造トラスの進化と現代の建築
最近では、**「木造トラス」**と呼ばれる新しい建築技術も広がっています。
鉄骨トラスのようなデザインを木で再現し、温かみのある空間をつくる手法です。
たとえば、体育館や公共ホールなどでは、
木の梁を三角形につないで天井を支える「木造トラス屋根」が使われています。
これにより、広い空間を柱なしで支えることができるのです。
木のぬくもりと構造美を両立させたこの技術は、
まさに「伝統×現代」のトラスデザインといえるでしょう。
クイズ③
木造建築で「筋交(すじかい)」を入れる目的として、正しいものはどれでしょう?
- 柱の数を減らして風通しをよくするため
- 建物の見た目を美しくするため
- 四角い枠を三角形にして強度を高めるため
正解は 3 です。
👉 筋交を入れることで建物の枠が三角形の構造となり、ゆがみにくくなります。
東京タワー・スカイツリーに見るトラス構造の進化と美しさ
日本のまちを見上げると、空へ向かって立つ2つの象徴――
東京タワーと東京スカイツリー。
この2つの塔は、まったく異なる時代に建てられましたが、
どちらも「トラス構造の力」によって支えられています。
🗼 東京タワーのトラス構造
1958年に完成した東京タワーは、高さ333メートル。
完成当時は世界で最も高い自立式鉄塔でした。
その秘密は、格子(トラス)状の骨組みにあります。
細い鉄の部材を三角形につなぎ合わせることで、
風を通しながらも強風や地震に耐えられる軽くて丈夫な構造になっています。
実際、東京タワーに使われた鉄の総量はおよそ4,000トン。
見た目以上に“空気を抱きしめる”ような構造で、
材料の量を減らしながら、驚くほどの強度を実現しているのです。
🌆 スカイツリーの三角断面構造
一方、2012年に完成した東京スカイツリー(高さ634メートル)は、
東京タワーの約2倍の高さを誇ります。
スカイツリーでは、塔の下部が三角形の断面になっており、
上にいくほど円形へと変化していく「ねじれ防止」のデザインが採用されています。
この形は「トラス構造+筒状構造(チューブ構造)」のハイブリッド。
中心には「心柱(しんばしら)」と呼ばれる太い柱があり、
地震のときには逆方向に揺れて振動を打ち消すという、
日本ならではの耐震設計が使われています。
古代の五重塔の構造をヒントにした、伝統と最先端の融合です。
🧩 構造の美しさはデザインの一部
東京タワーもスカイツリーも、
その形自体が“機能の結果として生まれたデザイン”です。
どちらも、ただ高くするのではなく、美しく・安全に立つための形。
「強さ」と「美しさ」を両立させるという点で、
トラス構造はまさに建築とアートの境界線に立つ存在です。
だからこそ、これらの塔は“日本のシンボル”になったのです。
クイズ④
スカイツリーが三角形の断面をしている理由として、正しいものはどれでしょう?
- 風の抵抗を大きくするため
- 揺れを防ぎ、ねじれを抑えるため
- 見た目を東京タワーに似せるため
正解は 2 です。
👉 スカイツリーは三角形から円形に変化する断面構造で、揺れやねじれを防ぐ設計になっています。
ヒンメリとトラス構造|北欧デザインに見る美しい三角形の秘密
日本の建築や橋の中にある三角形の構造――それとよく似た形を、
遠く離れた北欧の国フィンランドでも見ることができます。
それが「ヒンメリ(Himmeli)」です。
🌾 ヒンメリとは?
ヒンメリは、もともと麦わら(ストロー)を使って作られる立体モビールです。
「幸せを呼ぶ飾り」として、フィンランドではクリスマスやお祭りの時期に天井から吊るして飾ります。
このヒンメリ、実はよく見ると三角形と四角形を組み合わせた幾何学的な構造になっています。
細い麦わらをひもでつなぎ、軽くて丈夫な形を作る――
つまり、アートの中にトラス構造の原理が生きているのです。
🔺 美しさと強さを両立するデザイン
ヒンメリが美しい理由は、形のバランスと対称性にあります。
重力に対してすべての面が均等に力を分け合っているため、
少しの風が吹いても安定してゆらめくのです。
これはまさに、建築における「トラス構造」と同じ考え方。
建物を支える強度を、形の中に“デザインとして組み込む”発想です。
北欧の人々は、自然の中にある形を観察し、
それを生活の中に取り入れる文化を大切にしてきました。
ヒンメリはその象徴的な存在といえるでしょう。
🎨 科学とアートをつなぐトラスの発想
トラス構造は「力を分ける仕組み」ですが、
同時に「形を生み出すデザインの原理」でもあります。
三角形の安定性は、建築や工学だけでなく、
アート、インテリア、さらにはプロダクトデザインにも応用されています。
身近なものでは、観覧車の骨組みやテントのフレーム、
ドーム型の天井などにもトラスの思想が使われています。
このように、科学の原理が美しさを生み出すのが、トラス構造の面白さです。
クイズ⑤
ヒンメリの形が安定している理由として、正しいものはどれでしょう?
- 軽くて柔らかい材料を使っているから
- すべての辺が同じ長さで力が分散されているから
- 針金で固定されて動かないようにしているから
正解は 2 です。
👉 ヒンメリは対称的な三角形と四角形の組み合わせで、重力のバランスがとれているため安定します。
トラス構造を使った自由研究アイデア集|身近な材料で体験できる構造のふしぎ
トラス構造は、「強い」「軽い」「美しい」という3つの特長をもつ構造です。
その性質を身近な材料で実際に確かめることで、
科学・技術・デザインを同時に学べるのが魅力です。
ここでは、小学生から中学生まで挑戦できる
トラス構造をテーマにした自由研究アイデアを紹介します。
🏗 アイデア①:ストローブリッジ実験
テーマ:三角形の数と橋の強さの関係を調べよう
・材料:ストロー、テープ、定規、重り(おもちゃ・ペットボトルなど)
・作り方:三角形を少なくした橋と、多くした橋を作る
・実験方法:同じ重りを少しずつのせて、どちらが先に壊れるかを記録
・考察ポイント:三角形の数が多いと力が分散して強くなる
👉 理科×図工×算数の複合テーマにおすすめです。
🪵 アイデア②:筋交(すじかい)の有無で家の強さを比べよう
テーマ:筋交を入れるとどれだけ強くなる?
・材料:割りばし、紙、ボンドまたはグルーガン
・作り方:四角い家の枠を2つ作り、片方だけ斜めに筋交を入れる
・実験方法:横から押したり揺らしたりして、どちらがくずれにくいか比較
・考察ポイント:筋交を入れると四角形が三角形になり、強度が上がる
👉 社会科や防災学習にもつなげられる研究テーマです。
🌉 アイデア③:橋の形と強さを比べよう(アーチ・トラス・板)
テーマ:橋の構造によって強さがどう変わるか
・材料:厚紙、ストロー、セロテープ、重り
・作り方:①平らな板の橋、②アーチ型の橋、③トラス型の橋を作る
・実験方法:それぞれに重りをのせ、どの橋がいちばん多く支えられるかを測定
・考察ポイント:力の流れの違い(トラス=分散、アーチ=伝達、板=集中)
👉 グラフにまとめると、データ整理の練習にもなります。
🧩 アイデア④:ヒンメリ型のトラスをデザインしてみよう
テーマ:美しくて安定した三角形の立体を作ろう
・材料:ストロー、たこ糸、ハサミ
・作り方:立方体・三角すい・八面体などを組み合わせてデザイン
・観察方法:風を当てたり、吊るしてバランスを見たりする
・考察ポイント:力が均等に分散するほど、形が安定する
👉 芸術×科学のSTEAM自由研究として最適です。
🏠 アイデア⑤:木と鉄でトラスを作って素材の違いを比べよう
テーマ:素材によってトラスの強さは変わる?
・材料:竹ひご(木材)、アルミワイヤー(鉄の代用)、おもり
・作り方:同じ形のトラスを2種類の素材で作る
・実験方法:どちらが多くの重さに耐えられるかを測定
・考察ポイント:素材によって「引張力」「圧縮力」の強さが違う
👉 高学年〜中学生におすすめの発展型テーマです。
🧮 アイデア⑥:三角形の角度と強さの関係を調べよう
テーマ:どんな三角形がいちばん安定している?
・材料:ストロー、定規、分度器、テープ
・作り方:二等辺三角形・正三角形・鋭角三角形・鈍角三角形のフレームを作成
・実験方法:上から押して、どの角度の三角形が壊れにくいか比較
・考察ポイント:角度の違いが力の分散にどう影響するかを分析
👉 数学的な探究要素を加えたい人におすすめです。
🌏 アイデア⑦:自然界のトラスを探そう!
テーマ:自然の中にある“強い形”を見つけよう
・観察対象:ハチの巣、木の枝、葉脈、貝がら、昆虫の羽など
・調べ方:写真を撮って、どんな形がトラス構造に似ているかをまとめる
・考察ポイント:自然と人間のデザインに共通する法則を探る
👉 理科・図工・総合学習をつなぐ観察型自由研究です。
これらの自由研究テーマは、
どれも**「形の中に力を見つける」**という共通テーマを持っています。
身のまわりの材料で挑戦できるので、
夏休みの自由研究にも、STEAM型の学びにもぴったりです。
おさらいクイズ|トラス構造の原理・建築・デザインを総チェック
これまで学んできたトラス構造の知識をクイズでふりかえってみましょう!
三角形の強さ、日本の建築の知恵、東京タワーやヒンメリなど、
科学と創造をつなぐ“形のひみつ”を思い出しながら考えてみてください。
クイズ①
トラス構造で、三角形が強い理由として正しいのはどれでしょう?
- 力を3つの辺に分けて分散できるから
- 四角形よりも面積が広いから
- 厚みがあるから
正解は 1 です。
👉 三角形は力を3方向に分けることで、押されても形がくずれにくくなります。
クイズ②
木造建築で筋交(すじかい)を入れる目的として正しいのはどれ?
- 屋根の重さを軽くするため
- 四角い枠を三角形にして強度を高めるため
- 柱を減らしてデザインをすっきりさせるため
正解は 2 です。
👉 筋交を入れることで建物のゆがみを防ぎ、地震にも強い構造になります。
クイズ③
東京スカイツリーの下部が三角形の断面になっている理由は?
- 揺れを防ぎ、ねじれを抑えるため
- 見た目を東京タワーに似せるため
- 建築費を安くするため
正解は 1 です。
👉 三角形の断面はねじれに強く、建物全体のバランスを保つ働きをしています。
クイズ④
ヒンメリの形が安定している理由として正しいのはどれ?
- 針金でしっかり固定しているから
- すべての辺が同じ長さで、力が分散しているから
- 材料が重くて動きにくいから
正解は 2 です。
👉 ヒンメリは均等な三角形と四角形でできており、重力のバランスが保たれています。
クイズ⑤
トラス構造で使われる「引張力」と「圧縮力」について正しい説明はどれ?
- 引張力は押す力、圧縮力は引っぱる力
- どちらも力を弱める方向に働く
- 引張力は引っぱる力、圧縮力は押す力
正解は 3 です。
👉 この2つの力が釣り合うことで、トラス構造は安定して形を保つことができます。
クイズ⑥
次のうち、トラス構造の特徴として正しいものはどれ?
- 重くて動きにくい構造
- 軽くても強く、力を分散できる構造
- 柔らかく変形しやすい構造
正解は 2 です。
👉 トラス構造は、軽くても大きな力を支えられる効率的な構造です。
まとめ|トラス構造は“強さと美しさ”をつなぐ創造の科学
トラス構造は、力を分け合い、形で支えるという、シンプルでありながら深い仕組みです。
三角形の組み合わせによって軽くて丈夫な構造をつくり出すこの考え方は、
橋や建物だけでなく、自然やアート、デザインの世界にも生きています。
🔺 「形」が生み出す強さ
トラス構造の根本にあるのは、三角形の安定性です。
四角形ではゆがんでしまう力も、三角形にすれば均等に分散され、形を保つことができます。
これは物理の法則であると同時に、「形の知恵」といえるでしょう。
木造建築の筋交(すじかい)も、鉄骨トラスも、ヒンメリも――
どれも“強さ”を形の中に組み込んだデザインです。
🏗 科学と伝統の融合
日本の建築には、昔からトラス構造と同じ考え方がありました。
寺院や神社の屋根、町家の柱の組み方、地震に強い木造住宅の筋交……。
これらは「力の流れ」を読むという職人の知恵の結晶です。
現代の建築では、その知恵が鉄骨やコンクリートの技術と結びつき、
東京タワーやスカイツリーといった構造の美しさを生み出しました。
🎨 美しさと機能の両立
トラス構造は、ただ強いだけではありません。
「必要な部分だけに力を通す」ことで、無駄のない洗練された形になります。
その機能的な美しさこそ、デザインの原点。
北欧のヒンメリが見せる対称的な美も、
構造の中にある“バランスの芸術”といえるでしょう。
つまり、美しさとは、自然と力の調和のかたちなのです。
🌱 未来のトラスへ
トラス構造の考え方は、これからの時代にも広がっていきます。
木と鉄を組み合わせたハイブリッド建築、3Dプリンタで作る軽量構造、
宇宙ステーションやロボットアームにも、同じ発想が使われています。
「どうすれば少ない材料で大きな力を支えられるか?」
それを考えることは、未来をつくる創造の第一歩です。
💡 最後に
三角形の中には、科学の法則とデザインの心が共に息づいています。
トラス構造は、強さ・美しさ・効率をひとつにした、人類の知恵のかたち。
もし次に橋や建物を見上げたとき、
その中にある三角形を探してみてください。
きっと、あなたの目の前にも「創造の科学」が隠れています。
📚 学びの本棚から、次の1冊を
このテーマに関連する教材・読み物を、本棚を眺めるように探せます。
→ MOANAVI Library をひらく
この記事を書いた人
西田 俊章(MOANAVIスクールディレクター/STEAM教育デザイナー)
公立小学校で20年以上、先生として子どもたちを指導し、教科書の執筆も担当しました。
現在はMOANAVIを運営し、子どもたちが「科学・言語・人間・創造」をテーマに学ぶ場をデザインしています。