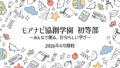これからの時代、通知表は本当に必要?
これからの時代に求められる新しい評価のかたち
これまでの通知表は、子どもの学力を一括して数字で示す「総括的評価(エバリュエーション)」が中心でした。しかし、子どもたちの学びのあり方が多様化する中で、これだけでは個々の成長を十分に捉えきれなくなっています。今、注目されているのが「形成的アセスメント」です。これは、学びの過程に寄り添い、子ども自身が成長を実感できる評価のあり方です。本記事では、通知表の役割を見直しつつ、MOANAVIが実践する新しい評価方法についても紹介します。
通知表とは?これまでの役割
学校で渡される通知表は、子どもの学期ごとの成果をまとめた成績表です。これは「総括的評価」と呼ばれ、学習の成果を定量的に把握する手段として使われてきました。内申点や進路選択に関わることも多く、保護者の関心も高い項目です。
ただし、通知表は「何ができたか」という結果に焦点を当てており、学びの途中でのつまずきや努力、伸びしろまでは十分に見えづらいという課題もあります。
通知表だけでは見えない「学びの力」
実は、成績の良し悪しよりも大切なことがあります。それは、子どもがどのように学び、何を感じ、どんなふうに成長しているかという「学びのプロセス」です。
教育評価の研究者であるブラックとウィリアム(1998)は、「形成的アセスメント」が学力の向上に最も効果的であることを示しました。これは、学習の途中で子どもの理解を確認し、必要に応じてフィードバックを与える評価方法です。
点数をつけるのではなく、学びの質を高めるための“支援”としての評価なのです。
これからの時代に求められる「形成的アセスメント」
このような「形成的アセスメント」は、単に正誤を判断するだけでなく、子どもの思考や学習行動に注目し、対話を通じて支援を行うものです。
発達心理学者ヴィゴツキーの「発達の最近接領域(ZPD)」の考え方では、子どもが少し背伸びすれば届くところを周囲が支援することで、次の成長が引き出されるとされます。まさに形成的アセスメントはこの“今まさに伸びようとしている”瞬間を捉えることを目的としています。
なぜ通知表に頼らないほうがいいのか?
通知表が子どもの成長を完全に見取ることは難しく、数字や評価によってやる気を失ったり、自信をなくす子どもも少なくありません。
特に、失敗やつまずきも大切な学びであるという視点が評価に反映されないと、学ぶこと自体が「評価されるための行為」になってしまう危険性があります。
一方で、形成的アセスメントは、子どもが「どう考えて取り組んだのか」「どんな工夫をしたのか」など、学習のプロセスを大切にします。これにより、子ども自身が“自分は学べる存在だ”と実感し、学びに対する前向きな態度を育てることができます。
MOANAVI(モアナビ)が実践する、子どもに寄り添う評価のかたち
MOANAVI(モアナビ)では、通知表に代わるものとして「STUDY POINT(スタディ・ポイント)」システムを導入しています。ただし、これは単なる点数の記録ではありません。
先生たちが子どもの隣でリアルタイムに対話を通じて行う、形成的アセスメントの一つなのです。
子どもが課題に取り組んでいるとき、先生はそっと近づき、
「どこから始めたの?今はどこまで進んだ?」
「この方法、どうして選んだの?」
「ちょっと行き詰まってる?じゃあ一緒に考えてみようか」
といったように、子ども自身が自分の考えや学習方法を言葉にできるよう、問いかけを重ねていきます。
こうした対話を通じて、先生はその子の思考過程や困難のポイントを丁寧に見取り、「いま、どの段階にいるのか」「どんな支援が有効か」を判断します。必要であれば、その場でアドバイスをしたり、一緒に立ち止まったりします。
さらに、子どもが自分の行動を振り返り、「今日はどんな工夫ができた?」「どこが前よりもできるようになった?」と自己評価するプロセスも取り入れられています。これこそが、自分の学びに主体的になる力=自己調整学習につながるのです。
このように、STUDY POINTは数字ではなく、対話とふり返りを通じて学びを可視化する仕組みであり、通知表の代替ではなく、学びの“現在地”をともに見つめる道しるべなのです。
まとめ
これからの時代、子どもたちには「正解を覚える力」以上に、「自分で問いを立て、学び続ける力」が求められます。その力を育てるには、結果を示すだけの通知表ではなく、学びのプロセスに伴走する形成的アセスメントが重要です。
MOANAVIが大切にしているのは、子どもたちが「学ぶって楽しい」「わかるってうれしい」と感じ、自信を持って歩んでいけるような評価のあり方です。
保護者の皆さんも、ぜひ「点数」ではなく、子どもがどんなふうに考え、悩み、挑戦しているかに注目してみてください。
子どもたちは、評価されるためではなく、自分の未来をつくるために学んでいるのですから。
記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)
STEAM教育デザイナー / 株式会社MOANAVI代表取締役
理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。
📚 経歴・資格
✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者
✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)
✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)
✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演
✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説