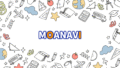アートもAIができる時代、
だからこそ「人間を学ぶ」STEAM教育が必要です。
AI(人工知能)がますます私たちの生活の中に入り込んできています。
数年前までは「AIが絵を描く?音楽を作る?」と驚いていたことが、今では日常的に行われるようになりました。
画像生成AIや自動作曲ツールなど、かつて“人間らしさの象徴”とされた創造的な行為でさえ、AIがこなせるようになった時代に、私たち人間は「何を学ぶべきか」を改めて考える必要があります。
MOANAVI(モアナビ)では、STEAM教育を中心に据えながらも、あえて「人間を学ぶ」というテーマを重視しています。
この記事では、MOANAVIの実践を通して、これからの教育においてなぜ「人間中心の学び」が大切なのかを、やさしくわかりやすくお伝えします。
STEAM教育って何?そして、何のために?
STEAMとは、以下の5つの頭文字をとった教育のことです:
- S:Science(科学)
- T:Technology(技術)
- E:Engineering(工学)
- A:Art(芸術・創造)
- M:Mathematics(数学)
最近では、ただ知識を覚えるだけでなく、横断的に考える力や、実社会に応用できる力を育てる教育として注目を集めています。
MOANAVIでもこの考え方をベースに、次のような4つの領域を軸に学びをデザインしています。
- 科学
- 言語
- 人間
- 創造
この中でも、「人間」というテーマを学びの柱に据えていることがMOANAVIの特徴のひとつです。
アートもAIができるようになった今、私たちは何を学ぶのか?
AIは、すでにイラストや音楽、文章の生成をこなすようになりました。
これは一見、未来的でワクワクする進歩のように見えますが、同時にこうした技術革新は、“人間とは何か”という問いを浮かび上がらせる契機にもなっています。
たとえば、
- 誰かの気持ちに寄り添って描いた絵
- 誰かを励ますために書いた詩
- 誰かの喜ぶ顔を思い浮かべて作るワークショップ
こうした「人のことを思って生まれる表現」は、人間にしかできない“意味を込める行為”です。
つまり、創造「らしきこと」はAIにできても、「人のために生み出す」という文脈や動機は人間だけが持ち得るのです。
MOANAVIの実践:人のために、社会の中で学ぶ
MOANAVIの子どもたちは、たとえば「お祭りプロジェクト」や「未来の街をデザインするワークショップ」など、社会とつながるリアルなプロジェクト学習に取り組んでいます。
たとえば、お祭りプロジェクトでは、
- 誰を対象にするか?
- 喜んでもらうには何をすればいいか?
- 費用はどうするか?
- 収益はどう使えば社会のためになるか?
といった問いに向き合いながら、自分たちで企画・準備・運営までを行います。
ここには、学校で教科ごとに分かれて学ぶのとはまったく異なる「つながりの中で育つ学び」があります。
それは単なる職業体験でも、子ども向けのイベントでもありません。
「誰かの役に立つ喜び」「自分も社会に貢献できるんだという実感」を持てる学びです。
デザイン思考:人からはじまり、人に届ける学びの力
MOANAVIの学びの中には、「デザイン思考」というアプローチも自然に取り入れられています。
これは、ものづくりや問題解決の際に、
- 人の困りごとや願いに耳を傾ける(共感)
- アイデアを考える(発想)
- 形にしてみる(試作)
- 実際に試してみて改善する(テストと改善)
というプロセスを通じて、「人のために考え、工夫する力」を育てる方法です。
たとえば、「スタンプでつくるオリジナルアイテム」のワークショップでは、
年齢や興味に合わせて選べるアイテムを用意したり、やさしいデザインに工夫したりすることで、「自分ではない誰か」の視点を大切にしています。
これこそ、AIにはできない「人間らしさの設計」なのです。
子どもたちの未来に必要な「人間力」
私たちは、これからの社会で本当に求められる力とは、次のような“人間力”だと考えています。
- 意味をつくる力:「何のためにやるのか?」を自分で考えられる力
- 共感的想像力:「あの人だったらどう感じるかな?」と想像する力
- 倫理的判断力:「正しそうなこと」と「本当に正しいこと」を見極める力
これらは、教科書やAIには教えられない、“生きた人間”と関わる中でしか育まれないものです。
人間を学ぶことは、未来を生きる力を育てること
MOANAVIのSTEAM教育は、単にスキルや知識を育てるのではなく、
人とのつながりの中で、自分の力をどう活かすかを考える教育です。
「人間を学ぶ」とは、自分のことを深く知ることでもあり、誰かの存在に想いを馳せることでもあります。
AI時代のいまだからこそ、子どもたちが人間として育つこと、そして他者のために行動できる力を身につけることは、ますます大切になってくるのではないでしょうか。
MOANAVIの実践が、同じように子どもたちの育ちを大切にされているご家庭や教育関係の方々にとって、何かヒントになれば幸いです。
記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)
STEAM教育デザイナー / 株式会社MOANAVI代表取締役
理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。
📚 経歴・資格
✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者
✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)
✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)
✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演
✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説