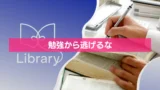【子どものやる気はどう育てる?】
やる気は“出る”ものではなく、“出す・作る”もの
「子どもがやる気を出さない」「すぐにあきらめてしまう」「続かない」
そんな悩みを抱える保護者の方は多いのではないでしょうか。
子どもが自主的に机に向かい、楽しく学び続けてくれたら…。親としては、そんな理想を描きたくなりますよね。でも、実は「やる気」とは、自然に出てくるものではない、ということをご存じでしょうか?
最新の学習科学では、「やる気は出るのを待つものではなく、自分で出すもの、作るもの」であることが明らかになっています。そして、親の関わり方次第で、子どもは“自分でやる気を作り出せる”力を育んでいくことができるのです。
この記事では、「やる気」の科学的な仕組みと、家庭でできる実践的なサポート方法をご紹介します。
やる気は“自分で作る”もの:学習科学の基本
心理学では、やる気には大きく分けて2つの種類があります。
- 内発的動機づけ:自分が好きだから、楽しいから取り組む動機
- 外発的動機づけ:ご褒美や賞罰など、外から与えられる動機
例えば、子どもが絵を描くとき、「描くことが楽しい!」と感じているなら、それは内発的動機です。一方で、「描いたらお菓子をもらえる」という理由で取り組んでいるなら、外発的動機です。
学習科学の研究では、この内発的動機づけのほうが学びを継続する力につながることがわかっています(Ryan & Deci, 2000)。
しかし、重要なのは「やる気は必ずしも最初から湧いてくるわけではない」という点です。
子どもも大人も、「興味はあるけれど、めんどう」「ちょっとやりたくない」と感じることはよくあります。
ここで大切なのが、動き出すことで、やる気が後からついてくるという考え方です。
作業興奮:動くことでやる気が生まれる
「やる気が出たらやる」のではなく、「やっているうちにやる気が出てくる」という現象を、心理学では作業興奮と呼びます。
この概念は、ドイツの心理学者エミール・クレペリンが提唱したもので、作業を始めると脳が徐々に活性化し、集中しやすくなることを指しています。
実際に、東京大学の研究チームが行ったfMRI(脳の活動を可視化する検査)の実験では、作業開始後、前頭前皮質の活動が顕著に高まることが確認されています(坂本・山本, 2006)。
また、脳内の側坐核という部分が、作業開始から15分程度で活発になり、やる気や快感に関係するドーパミンが分泌されることも報告されています。
つまり、やる気は動き始めてから生まれるものであり、まず「手を動かす」ことが最初の一歩になるのです。
続けることが力になる:自己調整学習の重要性
行動することでやる気が高まるといっても、一時的な“作業興奮”だけでは長続きしません。
ここで注目されているのが、自己調整学習(Self-Regulated Learning)という考え方です。
自己調整学習とは、
- 目標を立てる
- 自分の行動を観察する
- 結果を振り返る
- 必要に応じてやり方を調整する
というサイクルを自分で回せる力のこと。
この力が身につくと、子どもは自分で学びを進め、自分でやる気を引き出せるようになります。
そして、自己調整学習を支えるのが、自己決定理論(Self-Determination Theory:SDT)で示されている3つの基本的欲求です。
- 自律性(自分で決めたいという気持ち)
- 有能感(できた!と実感できること)
- 関係性(誰かとつながっていると感じられること)
この3つが満たされると、子どもはやる気を「外から与えられるもの」ではなく、「自分の内側から作り出すもの」として感じることができるのです。
親ができる!家庭でのやる気サポート実践法
「やる気は作るもの」とはいっても、家庭でどのようにサポートすればよいのでしょうか?
保護者が今日からできる具体的な支援方法を4つご紹介します。
① まずは「5分だけやってみよう」と伝える
作業興奮は「やり始めること」で生まれます。
「今すぐ全部やろう」ではなく、「まず5分だけやってみよう」と声をかけることで、心理的ハードルが下がり、行動のスイッチが入りやすくなります。
子どもが嫌がっても、「ちょっとだけならやってみよう」と小さな第一歩を提案してみましょう。
② 自分で決めさせる(自律性のサポート)
やる気を引き出すためには、親が「やりなさい」と指示し続けるより、子どもに選ぶ権利を渡すことが効果的です。
「いつ宿題をやる?」「どの問題からやる?」と、選択肢を用意し、自分で決めさせましょう。
自分で決めたことは、途中で諦めにくくなります。
③ 「できた!」の積み重ね(有能感のサポート)
努力の結果をしっかり認め、「頑張ったね」「工夫したね」と、具体的に声をかけてあげましょう。
点数や成績よりも、「続けた」「試した」「間違いを直した」といった行動に注目することが大切です。
できたことの小さな成功体験が、次のやる気につながります。
④ 一緒に関わる(関係性のサポート)
子どもが取り組むことに、親が少しでも関心を持ち、一緒に話したり、見守ったりするだけで、「自分は応援されている」と感じられます。
親がそばにいるだけでも、子どもは安心して学びに向かいやすくなります。
継続する力を育むために
やる気は「出るのを待つもの」ではなく、「出すもの」「作るもの」。
これは、子どもにとっても、保護者にとっても、すぐに実感できる小さな習慣の積み重ねで育てていけるものです。
大切なのは、「子どもがやる気を出さないこと」を責めるのではなく、どうやって動き出すきっかけを作るか、どうやって続けられる仕組みを支えるかという視点に立つこと。
「まずやってみる」→「できた!」→「もっとやってみたい」と、小さなサイクルを一緒に回していきましょう。
MOANAVIの学び場では

私たちMOANAVI(モアナビ)では、子どもたちが自分のペースで学びを楽しみ、やる気を自ら作り出せる力を育てることを大切にしています。
MOANAVIでは、算数や国語などの基礎学習と、STEAM教育を組み合わせたテーマ学習を行っています。子どもたちは、ただ知識を学ぶだけでなく、自分で選び、挑戦し、失敗を乗り越える経験を重ねています。
私たちが目指しているのは、「自分で考えて、自分で決めて、自分で学ぶ」ことができる人間に育てることです。
やる気を引き出したい、続ける力を育てたいと願う保護者の方は、ぜひ一度MOANAVIの活動を覗いてみてください。
記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)
STEAM教育デザイナー / 株式会社MOANAVI代表取締役
理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。
📚 経歴・資格
✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者
✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)
✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)
✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演
✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説