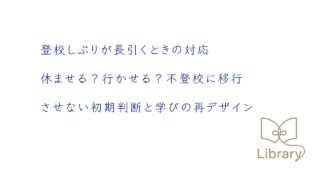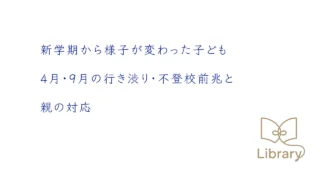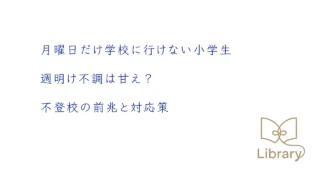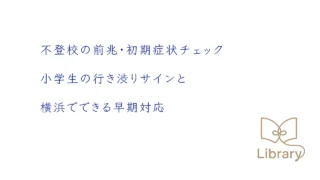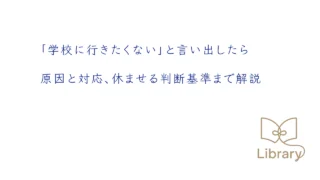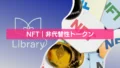不登校の子どもを支える新制度「特別の教育課程」とは?
文部科学省の方針を保護者・先生向けにやさしく解説
【2025最新】
不登校の子どもをもつ保護者や、学校現場で支援にあたる先生にとって、
「これから不登校の子どもの学びはどう保障されるのか?」は大きな関心事ではないでしょうか。
文部科学省は2025年10月、「不登校児童生徒に係る特別の教育課程ワーキンググループ」を立ち上げ、
「学校に行けなくても学びを保障する」ための新しい制度づくりを進めています。
この制度が実現すれば、家庭での学びや地域での活動、オンライン学習なども
学校教育の一部として正式に認められる可能性があります。
この記事では、10月7日に行われた第1回会合の内容や制度改訂の見通しを中心に、
不登校の子どもを支える家庭での実践のヒント、そしてMOANAVIが地域で行う
“自由進度・個別最適な学び”の取り組みを紹介します。
- 不登校の子どもを支える「特別の教育課程」とは?文部科学省が進める新しい学びの仕組みを徹底解説
- 【10月7日】中教審「不登校ワーキンググループ」で議論された内容まとめ|第1回会合で見えた方向性
- 不登校の教育課程は2025年にどう変わる?制度化のスケジュールと今後の見通しをわかりやすく解説
- 不登校の子どもを支えるために保護者が今できること|家庭での学びを“教育課程”につなげる3つの視点
- 家庭でできる不登校支援と学びの実践|親子でできるSTEAM・オンライン学習・探究活動のすすめ
- 「居場所」から「学びの場」へ──これからの不登校支援がめざす方向
- 不登校の教育課程改訂で何が変わる?家庭・学校・地域が協力して子どもを支える時代へ
- 学びをあきらめない子どもたちへ|MOANAVIが地域で実現する“自由進度・個別最適な学び”
- 記事を書いた人
- 新着記事
不登校の子どもを支える「特別の教育課程」とは?文部科学省が進める新しい学びの仕組みを徹底解説
いま、日本の不登校児童生徒は約40万人。過去最多を更新し続けています。
文部科学省はこの状況を受けて、単に「学校に行かせる」だけではなく、「行かなくても学びを保障する」仕組みづくりを進めています。
その中心にあるのが、「不登校児童生徒に係る特別の教育課程」という新しい制度の検討です。
この「特別の教育課程」は、これまでのように「出席扱い」「在宅学習の補助」という位置づけではなく、
子ども一人ひとりの状況に応じて柔軟に教育課程(カリキュラム)を組むことを正式に認めようとする仕組みです。
つまり、「学校に行けない=学べない」ではなく、家庭や地域、オンラインなど多様な場所での学びも“学校の学び”として認める方向に進んでいます。
なぜ文部科学省は「特別の教育課程」を検討するのか
文部科学省がこの制度を立ち上げた背景には、次のような課題があります。
- 不登校の長期化・多様化
学校に行けなくなる理由が「いじめ」や「学業不振」だけでなく、発達特性、心身の不調、環境要因など多岐にわたっている。
全国的に“戻す支援”だけでは限界が見えてきています。 - 地域・学校ごとの対応格差
適応指導教室や教育支援センター、フリースクールなどの支援がある地域もあれば、十分に整っていない地域もある。
制度として学びの機会を保障する仕組みが必要になっています。 - 「居場所」はあっても「学びの保障」が不十分
居場所づくりは進んできた一方で、学力や探究活動など“学びの継続”が評価に結びつきにくい現状がありました。
結果として、子どもの自信や将来へのつながりが途切れてしまうケースも少なくありません。
こうした課題を受けて、文科省は「学びを止めない社会へ」という方針のもと、
学校の外でも学びが保障されるよう、教育課程そのものを柔軟に運用できる制度設計に踏み切りました。
「学びの保障」とは何を意味するのか
「学びの保障(Learning Guarantee)」という言葉には、次の2つの意味があります。
- 教育を受ける権利を切らさない:どんな環境にあっても、子どもが学ぶ権利を守ること。
- 個に応じた学び方を認める:教室にいなくても、自分に合ったペース・方法で学ぶことを認めること。
これまでの学校制度では、「授業を受ける=出席」「試験を受ける=評価」という形が前提でした。
しかし、不登校の子どもたちにとっては、“学校に通えない時間”こそが学びの空白になりやすいという現実があります。
そこで文科省は、学校外でも教育課程に位置づけられる学びを制度として認め、
「家庭での学習」「地域活動」「オンライン学習」「フリースクール等の活動」などを
正式な学びの一部として扱う方向を打ち出しました。
不登校特例校・学びの多様化学校との違い
保護者の方からよくある質問が、
「不登校特例校や“学びの多様化学校”と何が違うの?」
という点です。
簡単に言えば、これらの制度はすでに“特別な学校の枠”で運営されています。
| 学校種 | 目的・特徴 |
|---|---|
| 不登校特例校 | 不登校児童生徒専用の学校。柔軟な教育課程をもとに学び直しを支援。 |
| 学びの多様化学校 | 不登校以外の子も含め、個別最適・協働的な学びを推進。地域に開かれた学校。 |
| 特別の教育課程(検討中) | 通常の学校(在籍校)でも、個々の子どもに合わせた教育課程を編成できるようにする制度。 |
つまり「特別の教育課程」は、**すべての学校で柔軟な学びの設計ができるようにする“仕組み”**です。
不登校特例校のような専用校を増やすのではなく、在籍校・家庭・地域が協力して“学びの多様化”を実現する方向へ進んでいます。
「行かせる」から「支える」へ──社会の視点が変わり始めている
この制度が実現すれば、保護者の役割も「学校に戻す」ではなく、
「子どもが学びを続けられるよう支える」方向へシフトしていきます。
文科省が目指すのは、出席日数やテスト結果では測れない「学びの継続力」「探究心」「自己調整力」を評価できる社会。
不登校の子どもたちが、
- 家庭で植物を育てて理科とつながる、
- 好きな本から文章を書く練習をする、
- オンラインで世界の人と英語で交流する、
そんな活動を、学校教育の一部として正式に認めていく――。
それが「特別の教育課程」が目指す未来像です。
【10月7日】中教審「不登校ワーキンググループ」で議論された内容まとめ|第1回会合で見えた方向性
2025年10月7日、文部科学省の中央教育審議会(中教審)で「不登校児童生徒に係る特別の教育課程ワーキンググループ(WG)」の第1回会合が開かれました。
これは、今後の教育制度の中で不登校の子どもたちの学びをどう保障するかを話し合うための、初めての専門チームです。
会合の目的と出席メンバー
この会合は、教育課程部会の下に設けられた小規模な検討チームで、
教育学の専門家、現場の校長・教員、不登校支援に関わるNPO代表などがメンバーに入っています。
主査(座長)は神戸女子大学の伊藤美奈子教授。
「学校に行かなくても学びを続ける子どもをどう支えるか」をテーマに、複数回にわたって議論が進められる予定です。
文部科学省側は、「居場所支援」から「学びの保障」へと政策をシフトする方針を改めて示しました。
このWGでは、そのための**制度的な裏付け(教育課程の新ルール)**を整えることが使命とされています。
議論された主なテーマ
第1回会合では、特に以下の4つの論点が重点的に取り上げられました。
- 対象児童生徒をどう定義するか
「どんな子どもが“特別の教育課程”の対象になるのか」という点です。
欠席日数や在籍の有無だけでなく、「長期的に登校が難しい」「心理的な不安が強い」など、
子どもの状況に応じて柔軟に対象を判断できるようにするという方向が示されました。 - 教育課程の編成と学習内容
通常の学級の時間割にとらわれず、子どもの状態に合わせた「別の時間割」を組むことができるようにする案が出されました。
たとえば、家庭学習・体験学習・オンライン学習を組み合わせる形です。
「どこで、どのように学ぶか」を学校と保護者が相談して決めることを想定しています。 - 出席扱い・評価・成績の扱い
「特別の教育課程」での学びを、在籍校での出席や成績評価にどう反映させるかが重要な論点になりました。
現在は地域や学校によって判断が異なり、子どもによって評価のされ方が不公平になる問題があります。
WGでは、全国共通の基準づくりを目指す方針が確認されました。 - 保護者の関与と学校の判断のバランス
一部の保護者からは「家庭で学ばせたい」という要望がありますが、文科省は
> 「保護者の要望によって自動的に学校が義務を負う仕組みにはしない」
と明言しました。
つまり、学校が子どもの状況を見て判断する仕組みにとどめるという立場です。
これにより、学校現場の負担を増やさずに制度を運用する狙いがあります。
文部科学省の姿勢:「枠を決めすぎない柔軟性」
主査の伊藤教授は会合で次のように述べています。
「制度の枠を硬く決めすぎると、子どもや先生がかえって動きにくくなる。
子どもが“学びたい”と思ったときに動き出せる柔軟な仕組みを目指したい。」
この発言は、WG全体の方向性を象徴しています。
つまり、「制度のために子どもを合わせる」のではなく、子どもに合わせて制度を調整するという考え方です。
この柔軟性こそが、これまでの学校制度と大きく異なる点です。
「居場所」+「学びの場」という新しい発想
もう一つ大きなポイントは、文科省が「居場所」と「学び」を別々に考えない方向に動き出したことです。
これまでの支援は、「心の安定=居場所づくり」「学力保障=学校での指導」と分けて考えられてきました。
しかしWGでは、
「安心できる環境の中でこそ学びが生まれる」
という考え方が共有されました。
つまり、安心と学びを一体で支える仕組みを制度として整えることが目標です。
この方針は、不登校特例校や学びの多様化学校、フリースクールにも共通する理念です。
現場・保護者にとっての影響
この議論が進むことで、保護者にとっては次のような変化が期待されます。
- 家庭での学びやオンライン活動が「正式な教育課程」として認められる可能性
- 学校と家庭が連携して「個別の学習計画」を作ることが当たり前になる
- 子どもが「行けない時間」にも学びの記録や評価が残る
一方で、学校現場の負担や判断責任が増える懸念もあります。
そのため、文科省はガイドラインや事例集の整備を行い、現場の混乱を防ぐ方針を示しました。
第1回会合のまとめ:方向性は「制度の柔軟化」と「現場の自立支援」
まとめると、第1回の議論で明確になったのは次の2点です。
- 不登校の子どもを“制度の外”に置かない
→ 学校外の学びを教育課程に含める方向へ。 - 現場に合わせて制度を設計する
→ 全国一律ではなく、地域や学校に裁量を持たせる。
この考え方は、まさに「子ども中心の教育制度」への転換点と言えるでしょう。
文部科学省は年内に第2回・第3回会合を開き、対象範囲や評価の基準などをより具体的に検討する予定です。
不登校の教育課程は2025年にどう変わる?制度化のスケジュールと今後の見通しをわかりやすく解説
「特別の教育課程」は、まだ正式な制度として始まったわけではありません。
しかし、2025年10月7日のワーキンググループ(WG)第1回会合をきっかけに、
文部科学省はこの仕組みを2026年度の中間まとめ→2027年度の答申・制度化に向けて動かし始めました。
つまり、今まさに「制度の設計図」を描いている段階です。
制度化までのスケジュール:2025〜2027年の流れ
文科省が示した「参考資料5 今後のスケジュール(案)」によると、
不登校WGは月1回程度のペースで会合を重ね、以下のような流れで検討が進みます。
| 時期 | 主な内容 | 検討テーマ |
|---|---|---|
| 2025年10月 | 第1回会合(実施済) | 現状と課題、検討事項の整理 |
| 2025年11月 | 第2回会合 | 対象児童生徒の範囲、制度の基本設計 |
| 2025年12月 | 第3回会合 | 教育課程の設計・評価方法・出席扱い |
| 2026年春〜夏 | 中間まとめ(報告書案) | 制度骨子の策定、公表 |
| 2027年度 | 教育課程部会・中教審本体で答申 | 制度化(法改正・告示改訂を含む) |
文科省の内部スケジュールでは、次期**学習指導要領改訂(2030年度施行予定)**と並行して、
この不登校支援制度も“教育課程の柔軟化パッケージ”として位置づけられる見通しです。
つまり、「特別の教育課程」は一過性の不登校対策ではなく、今後の教育の根幹に関わる制度改正になる可能性があります。
制度化の目的:学びの「場所」ではなく「仕組み」を変える
これまでの不登校支援は、「居場所をつくる」「相談にのる」といった**“サポート中心”**の政策でした。
しかし今回の議論は、そこから一歩進んで、教育課程そのものを柔軟にするという方向に踏み出しています。
文科省は次の3つの柱を掲げています。
- どこで学んでも“学校の学び”として認める仕組みを整える
→ 在籍校で出席扱いにできるよう、教育課程の中に家庭・地域・オンラインでの学びを組み込む。 - 学校が子どもに合わせて教育課程を編成できるようにする
→ 校内に「特別の教育課程」を設け、通常の時間割とは異なる個別カリキュラムを作成可能にする。 - 地域や民間団体との協働を制度として支える
→ フリースクールや適応指導教室などを「教育課程の一部」として認める方向を検討。
つまり、学びの「場所」ではなく、学びの“仕組み”そのものを再設計しようとしているのです。
2026年度に見込まれる具体的な変化
もしWGでの議論が順調に進めば、2026年度中には次のような変化が見えてくると考えられます。
- ガイドライン・指針の公表
→ 不登校児童生徒への教育課程編成・評価の具体的手順を示す文書が文科省から出される見込み。 - 先行実施モデル地域の指定
→ 学びの多様化学校や不登校特例校を中心に、モデル校・モデル地域として先行運用が始まる可能性。 - 校外学習・地域活動の単位化
→ 体験学習・探究活動・ボランティア活動などが「正式な学習」として評価される方向。 - オンライン授業・ICT学習の活用拡大
→ 在宅での学びを支える教材・配信環境の整備を国が推進。
こうした仕組みが整えば、「学校に行かない時間」が「学びが止まる時間」ではなくなり、
子どもが自分のペースで学びを続けられる社会へと近づいていきます。
保護者が今のうちに知っておくべきポイント
この制度の変化は、学校や行政だけでなく、家庭の関わり方にも影響を与えます。
特に保護者が意識しておきたいのは次の3点です。
- “家庭での学び”が教育課程に入る可能性がある
→ 家での探究活動やオンライン学習も「正式な学び」として認められるようになるかもしれません。 - 在籍校との連携がより重要になる
→ 学校側は個別カリキュラムを作るため、保護者との情報共有や相談がこれまで以上に求められます。 - 地域・民間との協働が前提の時代へ
→ これからは「家庭×学校×地域」が一体で子どもを支える仕組みが主流になります。
この変化は一朝一夕ではありませんが、制度が整う前に「家庭でどう支えるか」を考えておくことで、
子どもの学びの選択肢を広げる準備ができます。
制度改正のカギを握る「教育課程の柔軟化」
文部科学省はこの「特別の教育課程」を、
2030年度施行予定の新しい学習指導要領に向けた**“柔軟化の試金石”**と位置づけています。
つまり、不登校支援だけでなく、将来的にはすべての子どもに関わる「学びの多様化」を見据えているのです。
この流れは、不登校の子どもを特別扱いするのではなく、
「どんな子も、自分のペースで学ぶことができる社会をつくる」
という教育の根本的な方向転換でもあります。
まとめ:不登校の教育課程改訂は、家庭にとっての「新しいチャンス」
制度の変化というと難しく聞こえますが、実際には次のような明るい可能性が広がっています。
- 学校に行けなくても、学びを続けるルートが増える
- 家庭の学びが“正式な教育”として認められる可能性
- 子どもが自分の得意・関心をもとに進学や将来を考えられるようになる
「特別の教育課程」は、不登校の子どもたちのためだけではなく、
すべての子どもの学び方をアップデートする制度です。
その第一歩が、いままさに始まっています。
不登校の子どもを支えるために保護者が今できること|家庭での学びを“教育課程”につなげる3つの視点
文部科学省が進める「特別の教育課程」の制度化によって、
これからは**“家庭での学び”や“地域での体験”が正式な教育課程の一部として扱われる時代**が近づいています。
しかし、この仕組みがすぐに全国で動き出すわけではありません。
では、制度が整う前の今、保護者として何ができるのでしょうか。
ここでは、子どもの「学びの芽」を家庭の中で育て、将来の教育課程につなげていくための3つの視点を紹介します。
❶ 家庭での学びを「見える化」することから始める
不登校の子どもたちは、学校の授業に出ていないだけで、決して“学びをやめている”わけではありません。
むしろ、家庭の中や日常生活の中で、本人の関心から自然に学びが生まれていることが多いのです。
- 動物が好きで図鑑を読み込む
- 好きなYouTubeチャンネルから理科の知識を広げる
- 家事を通じて計算や段取りを学んでいる
こうした日常の学びは、将来的に「特別の教育課程」で評価される可能性があります。
まずは保護者がその学びを「見える化」することが第一歩です。
たとえば、
- 毎日の活動や興味をノートに記録する
- 写真や動画で成果を残す
- 子ども自身に「今日はどんなことを学んだ?」と振り返らせる
こうした記録は、後に学校との面談や個別カリキュラム作成の際にとても役立ちます。
“評価のための記録”ではなく、“成長を一緒に見守る記録”という気持ちで始めてみましょう。
❷ 「学び=教科」ではなく「興味から始まる体験」と捉える
不登校の子どもたちは、学校的な「教科の枠」にしばられると意欲を失いやすい傾向があります。
一方で、「やってみたい」「気になる」という気持ちが動くと、驚くほど集中し、継続して取り組めることも多いです。
たとえば、
- 好きなゲームからプログラミングを学ぶ
- 飼っているペットの観察を通して生物学に興味を持つ
- 家族旅行の計画を立てる中で地理や算数の要素に触れる
こうした学びは、まさに文科省が進める「個別最適な学び」「探究的な学び」に直結します。
学校に行かなくても、家庭の中で十分に「学びの循環」をつくることができます。
保護者が意識すべきは、「教科を教える」のではなく、
「子どもが何をおもしろいと感じているか」
を見つけ、それを伸ばしてあげることです。
それが、今後の教育課程改革で最も重視される“主体的・対話的で深い学び”につながります。
❸ 学校や地域と“ゆるやかにつながり続ける”
制度が進むにつれて、今後は在籍校が保護者と協力して**個別カリキュラム(個別の教育課程)**を作ることが一般的になります。
そのためにも、「つながりを切らさない」ことがとても大切です。
不登校になると、どうしても学校との連絡を避けたくなる時期があります。
しかし、完全に関係を断ってしまうと、将来「特別の教育課程」が始まったときに、
在籍校と家庭が学びの記録や評価を共有しづらくなってしまいます。
つながり続けるといっても、無理に登校させる必要はありません。
- 月に一度でも先生と近況をメールで共有する
- 教育支援センターや地域の学び場のイベント情報を受け取る
- 学校行事の案内を“見るだけ”でも関係を保つ
こうした「ゆるやかな関係維持」が、制度改正後のスムーズな連携につながります。
保護者が学校との“橋渡し役”になれると、子どもの選択肢は確実に広がります。
まとめ:家庭は「学びの最前線」
これからの不登校支援は、「学校が主、家庭が補助」という構図ではなくなります。
むしろ、家庭こそが学びの出発点であり、学校がそれを認め、社会が支える時代へ。
「学びの保障」という言葉は、政策用語に聞こえるかもしれません。
けれど、その本質は「どんな子も、自分のペースで成長できる権利を持っている」というシンプルな考えです。
保護者ができることは、制度を待つことではなく、
“今日のわが子の学びを見つけること”
から始まります。
その小さな積み重ねが、次の教育制度を支える力になっていくのです。
家庭でできる不登校支援と学びの実践|親子でできるSTEAM・オンライン学習・探究活動のすすめ
不登校の子どもにとって、家庭は「休む場所」であると同時に、「もう一つの学びの場」でもあります。
文部科学省が目指す「学びの保障」は、まさにその発想の延長線上にあります。
子どもが安心できる環境で、自分のペースで興味を広げていくこと――それが“学びの再スタート”の第一歩です。
ここでは、今日から家庭でできる実践例を紹介します。
❶ 安心できる生活リズムを整えることが、すべての学びの土台
学び以前に大切なのは、「安心できる生活リズム」です。
不登校の時期は、昼夜逆転や食欲・睡眠リズムの乱れが起こりやすく、
それが「何もやる気が出ない」という悪循環につながることがあります。
保護者が意識すべきは、“学校の時間割”ではなく、“生活のリズム”を取り戻すことです。
たとえば:
- 朝にカーテンを開けて自然光を入れる
- 起きた時間を一緒に記録する
- 午前中に軽い活動(朝食づくり・散歩・ペットの世話など)を入れる
これだけで、脳が「今日も一日が始まる」と感じ、生活のテンポが整っていきます。
“勉強を再開する”よりも先に、“生活を整える”ことこそが、学びの再スタートの第一歩です。
❷ 興味や得意を出発点にした「家庭STEAM学習」
STEAM(スティーム)とは、Science(科学)・Technology(技術)・Engineering(工学)・Arts(芸術)・Mathematics(数学)の頭文字を取った、
今注目されている教科横断型の学び方です。
文部科学省も新しい学習指導要領の中で、STEAM的な探究活動を重視しています。
家庭でも、STEAMの考え方は簡単に取り入れられます。
たとえば――
- 【Science】植物や天気を観察し、写真やメモでまとめる
- 【Technology】パソコンで自分の好きなテーマを調べてプレゼンを作る
- 【Engineering】ブロックや工作で「動くもの」をつくる
- 【Arts】絵・音楽・動画などで自分の表現を楽しむ
- 【Mathematics】買い物の合計や料理の分量を一緒に計算する
こうした活動は、「遊びながら学ぶ」ことを通して“自分で考える力”を育てることにつながります。
特に不登校の子どもは、教科書的な学びよりも「実感のある体験」からの方が吸収が早いことが多いのです。
❸ オンライン教材やデジタル学習の力を上手に借りる
近年、オンラインで学べる教材・動画・プログラミング教材が急速に充実しています。
不登校の子どもたちにとって、**自分のペースで学べるオンライン環境は“第2の教室”**になります。
おすすめの使い方の一例:
- YouTubeで「自由研究」「科学実験」など興味を刺激する動画を見る
- 小・中学生向けのオンライン教材(NHK for School、スタディサプリ、アオイゼミなど)を一緒に体験してみる
- プログラミングアプリ(Scratchなど)で「動く作品」を親子で作る
大切なのは、「やらせる」ではなく、「一緒にやってみよう」と声をかけること。
親子で画面を共有しながら、「これ面白いね」「こんなふうに考えるんだね」と話すだけでも、
子どもは“誰かとつながって学んでいる”という安心感を得られます。
❹ 家庭でもできる探究活動のヒント
探究的な学びとは、「自分で問いを立て、考え、まとめる」プロセスです。
家庭で始めるなら、難しいテーマでなくても構いません。
たとえば:
- 「なぜ空は青いの?」を調べてまとめてみる
- 「家の電気はどこから来るの?」を図にしてみる
- 「家族のごはんの材料はどこで作られている?」を地図で調べる
こうした小さな探究活動は、子どもが“知る喜び”を思い出すきっかけになります。
また、保護者が「教える人」ではなく「一緒に調べる人」になることで、
家庭の中が自然と「学びのチーム」に変わっていきます。
❺ 「できたこと」を言葉にして認める
不登校の時期は、どうしても「できていないこと」に目が向きがちです。
けれど、子どもにとって一番の励ましは、「今日できたこと」を認めてもらうことです。
- 朝起きられた
- 好きな動画を見て学べた
- 工作に没頭できた
- 自分から話しかけてきた
そうした小さな積み重ねを「学びの成果」として捉え、
「今日の〇〇、すごかったね」と具体的に言葉にして伝えましょう。
それが、子どもの次の行動につながる“自己効力感(できる感覚)”を育てます。
まとめ:家庭は「安心+学び」のハイブリッドな空間へ
不登校は「止まっている時間」ではなく、
「子どもが自分を取り戻し、次の学び方を探している時間」です。
文部科学省の制度改革は、その時間を“教育の一部”として正式に認めようとしています。
だからこそ、保護者が家庭でできる支援には大きな意味があります。
安心できるリズムの中で、好きなことをきっかけに学びを広げ、
親子で「できた」を共有する――。
それだけで、子どもの学びは確実に前に進んでいます。
「居場所」から「学びの場」へ──これからの不登校支援がめざす方向
これまでの不登校支援の中心は、「安心できる居場所づくり」でした。
学校に行けない子どもが、心を落ち着かせたり、友達と過ごしたりできる空間を整えること。
これはとても大切なことですが、「安心の次」にある“学びの保障” が、いま新たなテーマとして浮かび上がっています。
文部科学省のワーキンググループでは、
「居場所と学びを分けず、どちらも子どもの成長に必要な環境として一体的に考える」
という方向性が打ち出されました。
これは、不登校支援の考え方が**“心のケア中心”から“学びと成長の支援”へ**と変わることを意味しています。
❶ 「安心」があってこそ「学び」が生まれる
まず前提として、安心は学びの出発点です。
子どもが緊張や不安の中にいると、脳は「守ること」にエネルギーを使ってしまい、
新しい情報を吸収する余裕がなくなってしまいます。
だからこそ、不登校支援の第一歩は「安心して過ごせる場所」を整えること。
その上で、少しずつ「何かをやってみたい」という気持ちを引き出していくことが重要です。
文科省のWGでは、このプロセスを「安心から学びへ、連続した支援」と呼んでいます。
“休むこと”と“学ぶこと”を分けずに、両方を子どものペースで行き来できるようにする考え方です。
❷ 「居場所=学びの場」となる新しい支援のかたち
今後の制度設計では、校外の居場所や民間のフリースクール、地域の学び場などが
正式に「教育課程の一部」として位置づけられる可能性があります。
たとえば――
- 教育支援センター(適応指導教室)での活動が「出席扱い」になる
- フリースクールでの学びが在籍校の成績に反映される
- 地域の科学館・図書館・アート活動なども学びの記録として認められる
このように、“学びの場”は学校だけではないという考え方が、国の方針として動き始めています。
これは単に不登校のための特例ではなく、
「どんな場所でも子どもが成長できるなら、それを教育の一部として認める」
という、教育の根本的な考え方の転換です。
❸ 「学びの多様化学校」や地域の取り組みとの連携
「居場所から学びへ」という流れは、すでに一部の地域で始まっています。
たとえば、
- 公立学校の中に“学びの多様化教室”を設け、子どもが登校せずに校内で個別に学べる仕組み
- 教員と地域スタッフが連携して、週数回だけ登校したり、オンラインでやりとりする「ハイブリッド登校」
- 地域のフリースクール・民間教室と教育委員会が協定を結び、子どもの学びを共有する仕組み
こうした取り組みは、制度上の「特別の教育課程」と地続きです。
文科省は、これらの実践をモデルにして全国的な制度に発展させようとしています。
つまり今後は、学校・地域・民間が**「つながりのネットワーク」として学びを支える時代**になります。
❹ 保護者ができる“つなぎ役”としての関わり
この流れの中で、保護者の存在はますます重要になります。
なぜなら、学校・家庭・地域を「つなぐハブ」となるのは、子どもに最も近い保護者だからです。
保護者ができることは、制度や仕組みをすべて理解することではありません。
- 学校の先生と連絡をとり、子どもの状況を共有する
- 地域で使えそうな学びの場を調べ、つなぐ
- 子どもの意見を代弁し、学び方の希望を伝える
こうした小さな働きかけが、制度の実践を支える大きな力になります。
不登校の支援は、もう「専門家だけが行うもの」ではなく、家庭と地域が一緒に育てていく文化になりつつあります。
❺ 未来の方向性:学びをあきらめない社会へ
この改革の根底にあるのは、「すべての子どもに学ぶ権利を保障する」という理念です。
不登校の子どもたちは、社会の中で“学びの多様化”を先取りしている存在とも言えます。
なぜなら、彼らの姿が「どこでも学べる」「どう学んでもいい」という新しい教育の形を教えてくれているからです。
文部科学省が目指すのは、
「学校に戻す支援」から「学びを保障する支援」への転換。
居場所はゴールではなく、学びが再び動き出すスタートラインです。
そしてその“学び”は、子どもたちが社会と再びつながるための大切な橋になります。
まとめ:支援のかたちは変わっても、子どもを信じる気持ちは同じ
制度がどう変わっても、最も大切なのは「子どもを信じる」という親の姿勢です。
行動できない時期があっても、それは怠けではなく、次の学びに向かう“充電期間”。
安心して過ごせる時間が増えれば、必ず学びの意欲は戻ってきます。
不登校支援は、「居場所づくり」で終わらせない。
その先にある「学びの再発見」こそが、子どもの未来を照らす光です。
不登校の教育課程改訂で何が変わる?家庭・学校・地域が協力して子どもを支える時代へ
2025年から始まった「特別の教育課程」に関する議論は、
単なる“不登校対策”にとどまらず、日本の教育そのものを変えていく大きな転換点になろうとしています。
これまでは「学校に通うこと」が教育の前提でした。
しかし、社会の変化や子どもの多様化によって、
「学校に行かなくても学び続ける」
「学校以外でも成長できる」
という考え方が広がっています。
教育課程の改訂によって、私たちの身の回りの“当たり前”が少しずつ変わり始めています。
❶ 学校の役割が「管理」から「伴走」へ変わる
これまでの学校は、出席や授業進度を「管理」する側の立場でした。
しかし、特別の教育課程の導入によって、
学校は**「子どもと一緒に学びの形をつくる伴走者」**へと役割が変わります。
具体的には、
- 子どもの状況に合わせて「個別の教育課程」を学校が編成できる
- 教室以外の学び(家庭・地域・オンラインなど)を教育課程に組み込める
- 担任や支援担当が「学びの記録」を共有し、子どもの成長をチームで支える
つまり、「学校に行けるかどうか」ではなく、**「どう学びを続けているか」**が重視される時代になります。
この変化は、学校現場の負担を増やす側面もありますが、
同時に、教師にとっても「子ども一人ひとりと向き合う教育」の実現につながります。
❷ 家庭の学びが“正式な教育”として認められる方向に
これまで、家庭での学びやフリースクールでの活動は「参考」として扱われることが多く、
出席扱いや評価に直接反映されないケースも多くありました。
しかし、文科省の方針転換によって、今後は以下のような変化が想定されています。
- 家庭での探究学習・オンライン学習・体験活動を「特別の教育課程」に組み込める
- 在籍校と家庭が協働して学習計画を立てる仕組みが整備される
- 学校が家庭の記録(学びのポートフォリオ)を評価資料として活用できる
これにより、**「家庭の学び=学校教育の一部」**という新しい時代が始まります。
つまり、保護者のサポートが、これまで以上に子どもの未来を左右するようになります。
❸ 地域や民間の学び場が正式に“教育のパートナー”へ
教育の現場は、もはや学校だけでは完結しません。
今回の改革では、地域や民間の学び場が「教育のパートナー」として明確に位置づけられる方向です。
たとえば:
- フリースクールやNPOが学校と情報を共有し、学習計画を共同で作成する
- 地域の企業や大学と連携した探究活動が、正式な単位として認められる
- 公設民営の「学びの多様化学校」が全国に広がる
これによって、子どもたちは「地域の中で学ぶ」「社会の中で学ぶ」という新しい学び方を選べるようになります。
不登校支援の枠を越えて、教育と社会の境界が溶けていく流れが加速していくのです。
❹ 「学力」から「学びの力」へ評価の基準が変わる
教育課程の改訂では、「どれだけ覚えたか」よりも「どう学んだか」に焦点が移ります。
つまり、テストの点数や出席日数だけでなく、
- 自分で課題を見つける力
- 継続して取り組む姿勢
- 他者と協働する力
- 自分を客観的に振り返る力
といった「学び方」そのものが評価の中心になります。
これは、不登校の子どもたちがこれまで積み重ねてきた
**“自分で考え、試し、成長してきたプロセス”**を社会が正式に認めるということでもあります。
学びの多様性が、そのまま評価の多様性へとつながっていくのです。
❺ 保護者・学校・地域が「三位一体」で子どもを支える時代へ
教育課程改訂のキーワードは、「連携」と「共創」です。
これからの教育は、学校だけが主役ではなく、
家庭・学校・地域がそれぞれの強みを持ち寄って支え合う時代に入ります。
- 家庭:子どもの興味を見つけ、安心の基盤をつくる
- 学校:学びを整理し、評価・指導の橋渡しを担う
- 地域:体験・人との出会い・社会とのつながりを提供する
この三者がつながることで、子どもの「学びの地図」はより豊かに広がっていきます。
まとめ:教育課程の改訂は「制度改革」ではなく「文化の変化」
今回の不登校WGで進む教育課程の改訂は、法律や制度の話だけではありません。
それは、社会全体が
「子どもたちの学び方を信じる文化」
へと変わっていく第一歩です。
学校に通うことがゴールではなく、
どこにいても・どんな形でも学びを続けられる社会へ。
その実現には、家庭・学校・地域が互いを信頼し、学びを共有していく姿勢が欠かせません。
この流れの中で、不登校の子どもたちは「問題」ではなく、
**“未来の教育を先取りしている存在”**として見直されつつあります。
学びをあきらめない子どもたちへ|MOANAVIが地域で実現する“自由進度・個別最適な学び”
どんな子どもにも、自分のペースで学び続ける力があります。
たとえ学校に行けない日があっても、興味や関心から学びは生まれます。
MOANAVIでは、不登校や登校しぶりのある子どもたちが、
「自分に合ったスピードと方法」で学びを続けられる環境を整えています。
点数よりも“学びの過程”を大切にし、行動や工夫を評価する「STUDY POINT」など、
子どもが自分の成長を実感できる仕組みを取り入れています。
学びは、教室の中だけで生まれるものではありません。
家庭でも、地域でも、どこにいても、学びはつながっていきます。
MOANAVIは、その“学びをつなぐ”取り組みを地域から広げています。
制度の動きや実践の詳細は、別の記事でくわしく紹介します。
記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)
STEAM教育デザイナー / MOANAVIスクールディレクター
理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。
📚 経歴・資格
✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者
✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)
✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)
✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演
✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説