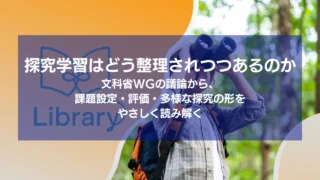「新学期が始まったのに、うちの子ちょっと元気がない…」
小学生の“行きしぶり”に気づいたら考えたいこと
新学期が始まり、子どもたちの生活が新しいリズムに変わっていく中、「朝起きられない」「学校に行きたくない」といった“ちいさな変化”に気づいた保護者も多いのではないでしょうか。
文部科学省の調査によると、子どもが不登校になるきっかけとして最も多いのは「4月・5月」と「9月」。つまり、新しい学期のスタートは、子どもにとって大きなストレスを感じやすい時期でもあるのです。
この記事では、小学生の“行きしぶり”や不安定な様子の背景をひも解きながら、保護者ができる対応と、「学校だけじゃない学びの場」としてのMOANAVIの取り組みをご紹介します。
「ちょっとした変化」に気づいたら
「朝になるとお腹が痛くなる」
「なんだか機嫌が悪い」
「学校から帰るとぐったりしている」
──そんな子どもの様子に、心当たりがある保護者も多いのではないでしょうか。
春休みや夏休み明けの時期は、新しい学年、担任、友達、学習内容など、変化がいっぺんに訪れるタイミングです。大人でも環境の変化にはストレスを感じるもの。子どもにとってはなおさらです。
こうした変化の中で、本人も気づかないうちに不安や緊張をためこんでしまい、それが「行きしぶり」や「体調不良」として表れることがあります。
データで見る「新学期の行きしぶり・不登校」
文部科学省「令和4年度児童生徒の問題行動・不登校調査」より
不登校が始まるきっかけとして多い月は、
- 4月(新学年スタート)
- 5月(GW明け)
- 9月(夏休み明け)
特に「9月1日」は、自殺の発生件数が年間で最も多い日としても知られており、子どもたちにとって新学期が大きな負荷となる時期であることは明白です。
ベネッセ「保護者の新学期に関する意識調査」(2021)
- 約60%の保護者が「新学期、子どもが不安を感じているようだった」と回答
- 最も多かった理由は「新しいクラスや先生への不安」
つまり、「なんとなく元気がない」は、決して特別なことではありません。多くの子どもが、毎年この時期にがんばりすぎたり、心をすり減らしている可能性があるのです。
保護者ができる3つの対応
① 話すことを急がせない
「どうしたの?」「何があったの?」と聞きたくなる気持ちは当然です。
でも、子どもは「自分でもよくわからないけど、つらい」状態であることも少なくありません。
話したがらないときは、「いつでも話してくれていいよ」と、安心できる空気をつくることが第一歩です。
② 「どうして?」より「どんな気持ち?」
「なんで学校に行きたくないの?」という問いは、無意識に責められているように感じさせてしまいます。
代わりに、「今、どんな気持ち?」と気持ちに寄り添う声かけを心がけることで、子ども自身が自分の感情に気づくきっかけになります。
③ 「学校に行く=正解」という思い込みを手放す
保護者にとって「学校に戻れたら」という希望は自然なものです。
でも、「安心できる場所で過ごすこと」こそが、子どもにとって最も大切な土台になります。
発達特性・HSCの子どもは、特にストレスを感じやすい
近年では、「HSC(Highly Sensitive Child)」と呼ばれる、感受性の強い子どもたちや、ASD/ADHDなど発達特性を持つ子の割合が高まってきています。
こうした子どもたちは、
- 音やにおい、まわりの雰囲気に過敏に反応する
- 新しい環境に慣れるまでに時間がかかる
- 頑張っているのに「怠けている」と誤解されやすい
…といった傾向があります。
つまり、「新学期」という環境変化は、定型発達の子以上にしんどいということを、大人が理解しておく必要があります。
よくある保護者の誤解と対応ミス
「一日休ませたら、ずっと行かなくなるのでは?」
「甘やかしになるのでは?」
「心を鬼にしてでも行かせるべき?」
こうした声もよく耳にします。でも実際には──
無理に行かせて「心が折れる」より、安心できる場所で回復した方が、結果的にスムーズに学校に戻れるケースも多いのです。
必要なのは、「頑張らせる」ことではなく、「安心できる居場所」を確保すること。そのうえで、回復とともに子どもが自ら動き出すタイミングを見守ることです。
学校内の支援との違い:保健室登校・通級など
学校には、保健室登校や通級指導教室など、様々な配慮の仕組みがあります。
でも、こうした支援は
- 学校という空間そのものがストレスになっている場合
- 教室に戻ることを前提としている場合
には、効果が十分に発揮されないこともあります。
MOANAVIという「第三の学び場」
MOANAVI(モアナビ)は、「学校でも家庭でもない、安心して学べる場所」です。
- 進度や学習内容を自分で選べる「自由進度学習」
- 子どもの気持ちを尊重し、無理に勉強させない
- 少人数だからこそできる個別の関わり
- 自己調整学習やSTEAM型のプロジェクト学習など、学校とは異なる学びの体験
私自身、MOANAVIを運営する中で、学校には行けないけれど「ここには来られる」という子どもたちにたくさん出会ってきました。
「行けるかどうか」ではなく「安心して過ごせるかどうか」を軸に学びが続けられる──
それが結果的に、子どもたちの自信につながっていくのだと感じています。
よくあるご質問
- Q学校に戻れなくなりませんか?
- A
無理に「戻す」ことをやめたことで、安心感が育ち、結果的に自分の意思で学校に行けるようになるケースも多いです。
- Q塾や放課後デイとはどう違いますか?
- A
MOANAVIは「勉強の補習」や「発達支援」ではなく、子どもが自己調整的に学ぶことを重視した“第3の学び場”です。
- Q見学はできますか?
- A
もちろんです。お子さんと一緒のご相談や体験も可能です。
最後に:保護者の不安も、当たり前です
「このままで大丈夫かな」
「休ませすぎている気がする」
「学校に行けない子を育ててしまったのかも」
そんな風に悩む保護者は、あなただけではありません。
でも、だからこそ「一人で抱え込まないこと」「誰かに話してみること」が大切です。
MOANAVIでは見学・相談を受け付けています
「子どもがちょっと不安定かも」「学校に行きしぶっている」
そんな時は、ぜひお気軽にご相談ください。
記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)
STEAM教育デザイナー / 株式会社MOANAVI代表取締役
理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。
📚 経歴・資格
✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者
✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)
✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)
✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演
✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説