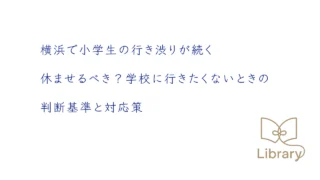不登校の子どもが笑顔を取り戻す方法
学校復帰と戻らない選択肢・横浜市の支援
不登校の子どもの笑顔を取り戻すためにできること
学校に戻る?戻らない?保護者が知っておきたい選択肢と横浜市の支援
お子さんが「学校に行きたくない」と言い出したとき、親としてどうすればいいのか悩む方は多いでしょう。
本記事では、不登校の背景や保護者の気持ちに寄り添いながら、横浜市の不登校支援の現状、学校に戻るためのサポート、そして「学校に戻らない選択肢」について詳しく解説します。
はじめに:不登校は「終わり」ではなく新しいスタート
文部科学省の調査によると、2024年度の不登校児童生徒数は34万人を超えました。
不登校はもはや珍しいことではなく、どの家庭でも起こりうる現象です。
大切なのは「無理に学校に戻すこと」だけをゴールにしないこと。
お子さんが安心して学べる環境を見つけることが、笑顔を取り戻す第一歩となります。
不登校の子どもと保護者の悩み
保護者の悩み
- 学校に戻らないと将来は大丈夫なのか
- 周囲から「親の責任」と思われていないか不安
- 学校や担任との関わり方が分からない
特に大きいのは「このままでいいのか」という焦りです。
ですが、その気持ちの背景には「子どもを守りたい」「自分も楽になりたい」という親自身の痛みがあることも少なくありません。
子どもの悩み
- 学校に行くのがつらい(勉強・友人関係・先生との相性など)
- 「怠けている」と思われるのが怖い
- 将来が不安
- 自分を責めてしまう自己否定感
子どもは「行かない」ことではなく、「行けない」ことに悩んでいます。その苦しさを理解することが出発点です。
不登校になる背景
不登校の理由は一つではありません。
人間関係・学業のプレッシャー・学校の環境・心身の不調・家庭の変化など、複数の要因が絡み合っている場合がほとんどです。
横浜市における不登校支援と制度
横浜市では、不登校児童生徒を支えるために以下のような制度が整えられています。
- 教育支援センター(適応指導教室)
学校に通えない子どもが安心して学び直せる場。個別学習やグループ活動を通して社会性を育みます。 - ハートフルルーム/ハートフルスペース
学校に代わる安心できる居場所を提供。子どもが落ち着いて過ごせるようサポートします。 - スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー
専門家が子どもや保護者に寄り添い、心理的・社会的支援を行います。 - 学びの多様化学校(文科省制度)
学校復帰を前提とせず、子どもが自分に合った形で学べることを重視する新しい仕組み。横浜市でも導入が進んでいます。
学校に戻る?戻らない?2つの選択肢を丁寧に考える
1. 学校に戻る選択肢
学校復帰を目指す場合は、段階的な方法があります。
- 適応指導教室を利用し、少しずつ登校感覚を取り戻す
- 保健室や特別教室で過ごす「別室登校」から始める
- 学校全体での理解が深まり、安心して戻れる雰囲気を整える
👉 学校に戻る道は「一気に元通り」ではなく、小さなステップを積み重ねていくものです。
2. 学校に戻らない選択肢
一方で、学校に戻らなくても子どもが笑顔を取り戻せる道もあります。
- フリースクールやオルタナティブスクールに通う
- 自宅やオンラインで自分のペースで学ぶ
- 趣味やプロジェクトを通じて学びや自信を育てる
👉 戻らない選択は「逃げ」ではなく、「自分らしい学び方を選ぶ」前向きな道です。
保護者の「戻ってほしい」という気持ちの背景
保護者が「戻ってほしい」と願うのは自然なことです。
ただ、その理由には以下のような「親自身の痛み」が含まれることもあります。
- 将来への不安(進学・就職への影響が心配)
- 周囲の目(「不登校=親の責任」と見られる不安)
- 親自身が苦しい(登校しない子どもを見続けるつらさ)
実は、その痛みは「学校に戻る」こと以外でも解消できます。
例えば、子どもが安心できる学びの場を見つけて笑顔を取り戻せば、保護者も安心できます。
戻らなくても笑顔になれる学びの場 ― モアナビ協創学園
MOANAVI協創学園は、「戻らない選択肢」を尊重するオルタナティブスクールです。
- 一人ひとりのペースに合わせた個別最適な学び
- STEAM教育を通じて探究心や創造力を育成
- 対話と体験を大切にし、安心できる仲間と学べる
- 在籍校との連携により出席認定に対応
「学校に戻れない=未来が閉ざされる」わけではありません。
戻らなくても、自分らしい学びの中で未来を拓くことができます。
まとめ:子どもの未来は一つじゃない
- 不登校は珍しいことではない
- 学校に戻る道も、戻らない道もある
- 横浜市には制度や支援が整っている
- 大切なのは「子どもと親が安心できる選択肢を見つけること」
焦らず、まずはお子さんの声に耳を傾けましょう。
笑顔を取り戻すための道は、学校の外にも広がっています。
記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)
STEAM教育デザイナー / MOANAVIスクールディレクター
理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。
📚 経歴・資格
✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者
✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)
✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)
✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演
✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説