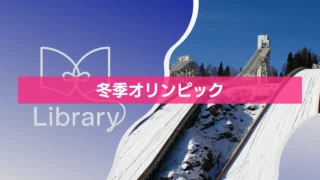ご褒美でやる気アップ!? 効果的な方法とは
「テストで100点取ったら100円あげるよ!」——この方法、本当に効果がある?
子どもが勉強をなかなかやらないとき、ご褒美を使ってやる気を引き出そうとしたことはありませんか?
確かに「〇〇をやったらご褒美がもらえる」と思うと、子どもは一時的に頑張るかもしれません。しかし、やり方を間違えると「勉強=ご褒美のためのもの」となり、子ども自身が学ぶ楽しさを感じられなくなることも……。
では、どうすれば子どもが自ら学ぶ力を伸ばせるのでしょうか?
この記事では、やる気の種類やご褒美の効果的な使い方を解説し、子どもが自然と学習習慣を身につける方法をお伝えします!
やる気には2種類ある
「やる気」とひとことで言っても、大きく分けて 「内発的動機付け」 と 「外発的動機付け」 の2種類があります。
🔹 内発的動機付け
→ 「新しいことを知るのが楽しい!」「できるようになると嬉しい!」 というように、本人が興味や楽しさを感じることで生まれるやる気。
💡 例:
✅ 「このクイズ、面白い!もっと解いてみたい!」
✅ 「この漢字、かっこいい!書けるようになりたい!」
🔹 外発的動機付け
→ 「100点取ったらご褒美がもらえる!」 のように、外からの報酬や評価がきっかけになるやる気。
💡 例:
✅ 「ご褒美がもらえるから頑張る!」
✅ 「先生に褒められたいから宿題をやる!」
理想は 「内発的動機付け」 ですが、子どもが最初から「勉強が楽しい!」と思うのは難しいもの。
そこで、ご褒美を活用した「外発的動機付け」が役立つこともあります。
しかし、注意しなければならないのは 「ご褒美の与え方」 です。
「100点取ったら100円」はNG? その落とし穴とは?
「テストで100点取ったら100円あげるよ!」——この方法、一見するとやる気を引き出せそうですが、実はあまり効果的ではありません。
なぜなら……
❌ 勉強の目的が「お金」になってしまう
「勉強すること自体が楽しい!」という気持ちにつながらず、「ご褒美がなければやらない」となりやすい。
❌ 結果にご褒美をつけると、やる気が続かない
100点を取ること自体が難しく、「もらえないならやらない」となる可能性も……。
❌ 運の要素が絡む
たまたま簡単な問題が出て100点を取れた場合、努力とは関係なく報酬がもらえることに。逆に頑張っても難しい問題が出れば報われないことも……。
では、どうすれば ご褒美を上手に活用できる のでしょうか?
ご褒美は「行動」に対してあげよう!
ご褒美を活用するなら、「結果」ではなく 「行動」に対して与える のがポイントです!
例えば、100円を10円ずつに分けて……
✅ 「音読をハキハキ読めたら10円」
✅ 「漢字を5回ずつ丁寧に書いたら10円」
✅ 「ノートをきれいにまとめ直したら10円」
✅ 「九九を全部言えたら10円」
✅ 「宿題を最後までやりきったら10円」
✅ 「授業中にノートをきちんと書いたら10円」
こうして小さな行動を積み重ねることで、やがて 「学習の習慣」 につながります!
褒めることもご褒美のひとつ!
「子どもを褒めて伸ばしたい!」と思っても、結果ばかりを見ていると褒める機会が少なくなってしまいます。
でも、「行動」を褒めるならどうでしょう?
💡 「宿題を最後までやりきったね、頑張ったね!」
💡 「音読の声がハキハキしていてよかったよ!」
💡 「漢字をいつもより丁寧に書いていてすごいね!」
このように、「行動」を褒めることで子どものやる気はぐんぐん伸びていきます!
学校でも、お金のご褒美は使えませんが、シールやスタンプ、先生のサインなどで子どもたちのやる気を引き出すことができます。
また、「頑張ったね!」のひと言だけでも、子どもにとっては大きな励みになりますよ!
MOANAVIでは「学習行動」を見逃しません!

MOANAVIでは、子どもたちの「学習行動」に注目し、適切なタイミングでアセスメント(評価)を行うことで、一人ひとりのやる気を引き出します。
✅ 「理解できた!」を増やす学習サポート
✅ 「行動」を見守り、学習習慣を定着させる仕組み
✅ 子どもが「勉強が楽しい!」と思える環境づくり
ただ結果を評価するのではなく、「頑張るプロセス」 を大切にすることで、子どもたちが 自分から学ぶ力 を育めるようサポートしています!
学力だけでなく、学習習慣も身につくMOANAVIの指導をぜひ体験してみませんか?
まとめ
✅ 「100点取ったら100円」よりも、「勉強する行動」にご褒美を!
✅ 小さな成功を積み重ねることで学習習慣が身につく!
✅ 「頑張ったね!」のひと言が、一番のご褒美になることも!
お子さんが「勉強が楽しい!」と感じられるように、今日からご褒美の使い方を見直してみませんか?お子さんが「勉強が楽しい!」と思えるように、ご褒美の使い方を工夫してみましょう!
記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)
STEAM教育デザイナー / 株式会社MOANAVI代表取締役
理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。
📚 経歴・資格
✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者
✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)
✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)
✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演
✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説