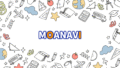「勉強しなさい!」を言わなくても大丈夫。
子どもの家庭学習を自然に促す方法とは?
家庭学習や宿題をめぐって子どもとバトルが絶えない…そんな保護者の悩みに応えるのが、”動機づけ”の学習理論と、子どもの行動を促す実践的な仕組みです。本記事では、学びへのやる気を引き出す「外発的動機づけ」と「内発的動機づけ」の活用法、MOANAVIの取り組み事例を紹介しながら、家庭でできる学習サポートのヒントをお届けします。
「やる気が出ない」は当たり前?──学びに必要なのは“動機づけ”
「うちの子、全然宿題やらないんです」
「勉強しなさいって言いたくないけど、放っておくと何もしない」
こうした声は、多くの保護者が経験しているものです。でも、それは決して“うちの子だけ”ではありません。子どもたちにとって、勉強は“やらされるもの”になりがち。だからこそ、勉強に取りかかるには「動機づけ」が必要です。
学習の動機づけには、大きく分けて2つのタイプがあります。
- 外発的動機づけ:報酬やご褒美、ほめられること、点数など、外側から与えられる理由で行動する
- 内発的動機づけ:新しいことを知る楽しさ、自分の成長の実感など、自分の内側から湧き出るやる気
「どうせご褒美がないと勉強しないんでしょ?」と思われがちですが、実は外発的動機づけから始めることは、内発的動機づけへつなげる第一歩でもあるのです。
外発的動機づけから始めてOK!MOANAVIの「STUDY POINT」システム
神奈川県横浜市で活動するMOANAVIでは、子どもたちの学習への取り組みをサポートする仕組みとして、「STUDY POINT」という独自のポイント制度を導入しています。
このシステムでは、「勉強ができたか」ではなく、「自分に合った学習を選んで取り組んだか」という“行動”そのものにポイントがつくのが特徴です。
しかも、そのポイントはおやつや軽食などと交換できるというシンプルなご褒美つき。ご褒美はその場ですぐにもらえるものもあれば、ポイントを計画的に貯めて選べるものもあり、子どもたち自身が「どれにしようかな」と自分で考える楽しさも味わえます。ポイントでもらったおやつを食べながら、さらに勉強を続けられるというメリットもあります。
行動の変化が学びの質を変える
こうした取り組みを続けていく中で、子どもたちの行動に変化が現れてきました。
- 教室に着いたらすぐに学習を始める子が増えた
- 学習時間を過ぎても「もうちょっとやりたい」と取り組む子が増えた
- 「プリントがどんどん溜まっていくのがうれしい」
- 「この問題、前はできなかったのに、今できるようになった」
最初はご褒美が目当ての外発的動機から始まっても、だんだんと「わかるようになる楽しさ」「できたという達成感」=内発的動機づけへとシフトしていく子どもたちが多く見られるようになったのです。
小さな成功体験で脳がやる気に!──「作業興奮」の活用法
「最初の一歩が踏み出せない」
「やり始めれば集中するのに…」
そんな子には、“作業興奮”を活用したアプローチがおすすめです。
作業興奮とは、何かに取りかかって手を動かし始めることで、脳が刺激されてやる気が高まる現象のこと。つまり、「やる気があるから始める」のではなく、「始めたらやる気が出てくる」んです。
MOANAVIでは、取りかかりやすい「64マス計算(かけ算)」などのタイムアタック系課題を導入。答えがわかっていて、1分程度で終わるような“負荷が低い課題”からスタートし、その後の学習へスムーズに入れるように工夫しています。
自分に合った学びを“自分で選ぶ”──学習の質を高める仕組み
MOANAVIのSTUDY POINTでは、子どもが自分で課題を選び、ポイントを獲得します。課題の難易度やチャレンジ度合いによって、次のようにポイントが分かれています。
- 1 point:やさしい・すぐに終わる課題
- 2 point:今の自分に合っている・やるべき課題
- 3 point:新しい学び・チャレンジ・作業量が多くて大変な課題
このように「どの課題をやるか」を自分で決めることで、自己調整学習の力が育まれます。自分にとってちょうどいいレベルの学びを、自分の力で選びとる習慣が、将来の“学び続ける力”へとつながるのです。
家庭でできるサポートとは?──「親は一緒に学ぶ人」になる
家庭でも、MOANAVIのような仕組みをまねして取り入れることは可能です。大切なのは、親が「見守る」存在になること。
たとえば──
- そばで一緒に読書したり、親も勉強してみる
- ご飯を作りながらでも「いるよ」と伝えられる距離感でいる
- 「今日は何をやろうか?」「終わったらどうする?」と、声かけだけでも◎
逆に、やる気をそぐ行動として注意したいのが、親がテレビやスマホを見ている姿を見せてしまうこと。
「子どもには勉強させてるのに、自分は遊んでいる」という状態は、子どものやる気を削いでしまいます。
子どもを“誰かと”比べない。「学びの質」で見守る姿勢を
家庭学習でありがちなのが、「○○ちゃんはもっとやってるよ」といった他の子との比較。
でも、学びは人それぞれです。量やスピードで評価するのではなく、
- 自分から取り組もうとしていたか
- 集中していたか
- わからないときに相談できたか
といった“学びの質”に目を向けることが、子どもの自己肯定感や学びのモチベーションにつながります。
まとめ:子どもの学びは“応援する姿勢”で変わる
勉強に向かう姿勢は、最初は外発的なご褒美や評価でも大丈夫。
大切なのは、「自分で選べる」「できた実感がある」という仕組みや声かけを通して、内発的なやる気へとつなげていくことです。
そして何より、家庭では「親も学びの仲間である」という姿勢を持つことが、子どもの背中を押す最も効果的なサポートになります。
MOANAVIでは、学びの習慣化に取り組む親子を応援しています
MOANAVIでは、日々の取り組みやイベント情報をSNSやブログで紹介しています。興味のある方は、お気軽に体験参加やお問い合わせをどうぞ。
記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)
STEAM教育デザイナー / 株式会社MOANAVI代表取締役
理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。
📚 経歴・資格
✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者
✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)
✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)
✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演
✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説