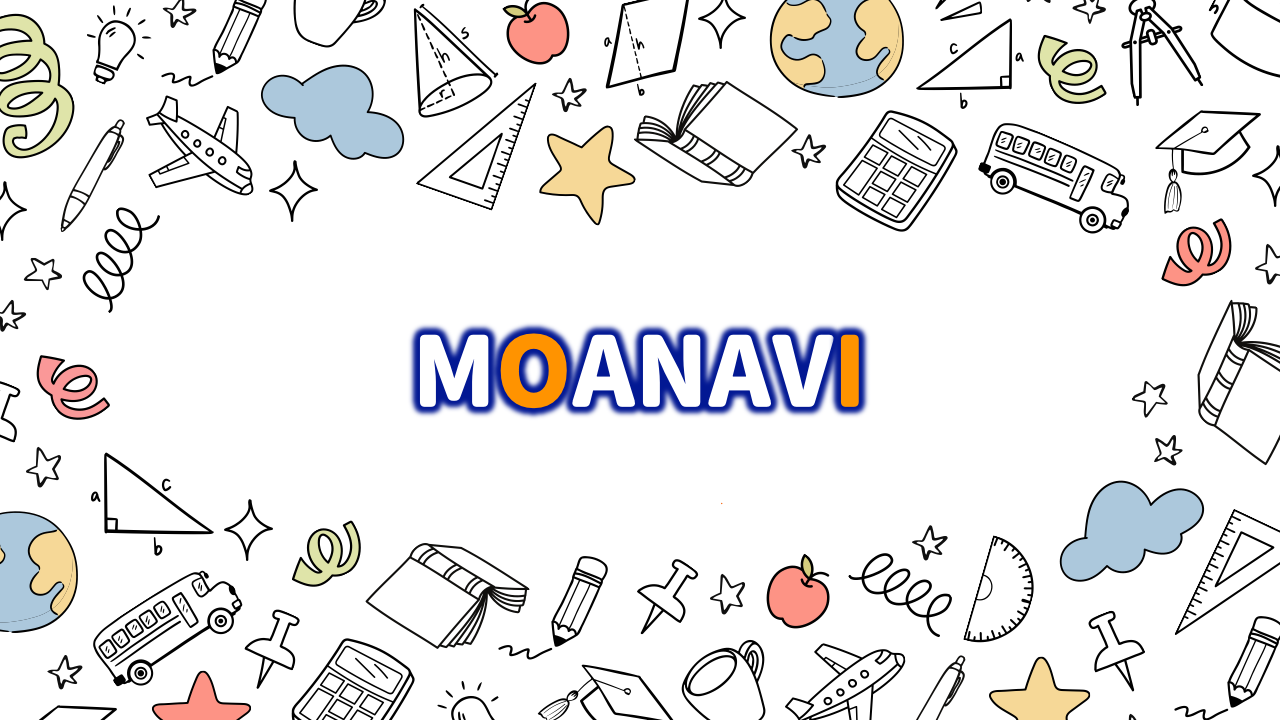未来の街を子どもたちがデザインする!?
MOANAVIのフリーオープンデー開催決定!
私たちは、横浜市を拠点に、子どもたちの「未来を創る力」を育てる学び場として活動しています。
日々の学びはもちろんのこと、地域の方々とのつながりを大切にしながら、子どもたちが自分らしく成長できる機会を広げています。
その一環として、MOANAVIでは【フリーオープンデー】というイベントを定期的に開催しています。
フリーオープンデーは、MOANAVIに通っていないお子さんや保護者の方も自由にご参加いただけるオープンな日。学びの一端に触れていただきながら、地域とつながるひとときを過ごせるようにと企画しています。
今回のオープンデーでは、初めてSTEAMのテーマ学習を取り入れたプログラムにチャレンジします!
テーマは「スマートシティ」!?
今回のメインプログラムは、子どもたちがグループで話し合いながら「未来の街」を自由に想像し、デザインしていくというもの。
その名も――
「スマートシティをデザインしよう! 君のアイデアでワクワクするような未来の街をつくろう!」
スマートシティとは、IT技術やAI、再生可能エネルギーなどを活用して、より便利で快適、安全で持続可能な社会を目指す都市のこと。
近年では、世界各地でこの「未来の都市づくり」が進んでいますが、実はその根っこには、「人がどんなふうに生きたいか」「どんな暮らしをしたいか」という問いがあるのです。
子どもたちの自由な発想は、大人では思いつかないような面白くて新しいアイデアに満ちています。
私たちは、そんな子どもたちの声を大切にしたいと考え、このテーマを選びました。
プログラム内容とスケジュール
当日のスケジュールはこちらです
🕚 11:00~12:30(満席・キャンセル待ち受付中)
- 子どもの遊び場(屋内外のフリータイムスペース)
- いっしょにランチ(持ち込みOK)
この時間帯は毎回人気で、すでに満席となっています。
キャンセル待ちでの受付を行っていますが、ご希望の方は早めにお申し込みください。
🕐 13:00~14:00(にしとも広場にて開催・若干名受付中)
- スマートシティをデザインしよう!ワクワクするような未来の街を作ろう!
西区役所1階にある「にしとも広場」で開催されるこのワークショップが、今回の目玉です!
にしとも広場についてはこちら
どんなことをするの?プログラム詳細をご紹介!
ステップ1:インスピレーションタイム(約10分)
まずは、未来の街ってどんなところ?を知る時間からスタート。
プロジェクターを使って、世界のスマートシティの写真や、短い映像をみんなで見ます。
たとえば、ドバイの空飛ぶタクシー、シンガポールの垂直農場、北欧のサステナブルな街づくりなどを紹介します。
「こんなところに住んでみたい?」「ちょっと変わってるけど面白そう!」――そんなリアクションが飛び交いながら、子どもたちの想像力を広げていきます。
また、日本の国土の特徴にも少し触れ、「地震が多い日本ならではの街の工夫」などについても話題にすることで、現実とのつながりも意識します。
ステップ2:グループで街をつくろう!(約15分)
ここからはグループワーク!
3~4人のグループに分かれて、「自分たちの理想の未来の街」を自由に考えます。
「こんな電車があったらいいな」
「空からご飯が降ってきたら楽しいかも!」
「おじいちゃんおばあちゃんが住みやすい街にしたい」
「みんなが仲良くなれる場所があるといいね」
ワークシートや白紙の地図のような用紙に、ペンやシールを使ってアイデアをどんどん書き込んでいきます。
今回は特に、小学校3〜6年生の子どもたちを想定しているため、難しい言葉や概念は使わず、楽しく・自由に表現できるよう工夫しています。
ステップ3:みんなに発表!(約15分)
完成したアイデアは、グループごとに発表します。
発表者はグループで決めてOK。得意な子が前に立って話してもいいし、恥ずかしい子は友だちと一緒でも大丈夫。
この時間では、他のグループのアイデアに対して質問や「それいいね!」の声かけも行い、アイデア同士がつながる楽しさも味わえます。
「人と協力して何かを創る」「自分の考えを伝える」という体験が、子どもたちの中で自信や表現力へとつながっていくのです。
ステップ4:ふりかえりと探究へのヒント(約10分)
最後に、全体のまとめとふりかえりを行います。
「どの街にも“やさしさ”があったね」
「お年寄りのために工夫してる街が多かったね」
「自然とテクノロジーをどう共存させるかが面白いね」
そんなふうに、共通点や視点の違いを共有しながら、今回の学びを次の探究へとつなげていきます。
自由研究のヒントになったり、家に帰ってから続きを描きたくなったり――ワークショップ後にも続く「学びの種まき」の時間です。
MOANAVIの想い:学びはもっと自由でいい
私たちMOANAVIは、「学習=知識を覚えること」だけではないと考えています。
自分の考えを持ち、人と関わりながら表現していくプロセスこそが、これからの時代に求められる「学ぶ力」だと信じています。
今回のワークショップでは、STEAMの5つの領域(Science, Technology, Engineering, Art, Math)を意識しながらも、子どもたちの感性や好奇心を第一にプログラムを設計しました。
テーマ学習の入り口として、たくさんの「楽しい!」が見つかる時間になることを願っています。
参加申し込みについて
「スマートシティをデザインしよう!」ワークショップのご参加は、事前申込みをおすすめします!
🔗 お申し込みはこちらから:
https://forms.gle/auDRjjPx9FUnFo9Y9
※当日参加も可能ですが、満席の場合はご参加をお断りする場合があります。
確実にご参加いただくために、事前のご予約をお願いいたします。
開催場所: にしとも広場(横浜市西区役所1階)
日時: 2025年4月20日(日)13:00~14:00
対象: 小学校3~6年生と(保護者の見学も可)
参加費: 無料
持ち物: 筆記用具(必要な材料はこちらで用意します)
未来を創る力を、地域とともに
MOANAVIは、地域に根ざした小さな学びの場として、不登校支援や自己調整学習、STEAM教育に取り組んでいます。
私たちは「未来を創る力」を、学びの中で子どもたち自身が発見していけるような体験を届けていきたいと願っています。
今回のフリーオープンデーが、そんな学びの入り口となり、たくさんの子どもたちと地域のつながりが生まれる1日になりますように。
スタッフ一同、みなさんのご参加を心よりお待ちしております
記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)
STEAM教育デザイナー / 株式会社MOANAVI代表取締役
理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。
📚 経歴・資格
✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者
✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)
✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)
✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演
✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説