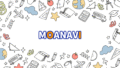【外遊びレポート】毎日が冒険!
MOANAVI流「宝獲り合戦」で育つチーム力とひらめき力
MOANAVIでは毎日の外遊びを通じて、子どもたちが主体的に動き、仲間と協力しながら学びを深めています。今日は、オリジナルの「宝獲り合戦」というゲームで大盛り上がり!この遊びには、自然と戦略的思考・協働・運動能力といった多くの力が育まれる要素が詰まっています。日々の遊びが、未来を創る力につながるMOANAVIの実践をご紹介します。
雨が降らなければ、今日も公園へ!
MOANAVIでは、天気が良い日は毎日外に出て、公園遊びをしています。午前中の学習や創作の時間を終えた後、自然の中で思いきり体を動かす時間は、子どもたちにとって何よりのリフレッシュタイム。
MOANAVIの拠点のまわりには、緑豊かで広々とした公園がいくつもあります。どこに行くかは、その日の子どもたちのじゃんけんで決めるのが習慣。小さなことのように思えますが、「自分たちで選ぶ・決める」ことができる環境は、子どもたちにとってとても大切な経験のひとつです。
「今日はどこにする?」
「○○公園の遊具、昨日の続きやりたいな」
「でもあっちは広いから、かくれんぼやるなら△△公園かな~」
そんなやりとりの中にも、自分の希望を言葉にしたり、相手の意見を聞いて譲ったり、日々の学びが詰まっています。
外遊びのレパートリー、どんどん増えてます!
公園に着いたら、遊びのスタイルはその日の気分次第。MOANAVIの子どもたちは、遊びの達人です。
- 定番の鬼ごっこやかくれんぼ
- 公園の地形を活かした探検ゲーム
- ボールを使ったドッジボールもどきやドッヂビー(フリスビー版ドッジボール)
- 長縄跳びを使った昔遊び
- チームで協力して得点を競うワンバウンドバレーテニス(テニス+卓球+バレーボール的な遊び)
ルールはみんなでその場で決めることも多く、「今日はこんな風にしてみようよ」と、柔軟に工夫する姿が見られます。
「その遊びはやりたくない!」などの小さな衝突が起きることももちろんありますが、それもまた学びの時間。どうすればみんなが楽しく遊べるかを考えて、解決する力も少しずつ身についていきます。
今日のハイライトは「宝獲り合戦」!
さて、そんな中で今日はひときわ盛り上がった遊びが登場。その名も仮称「宝獲り合戦」!
もともとは「鬼ごっこのちょっと発展版」としてスタートしたこの遊びですが、子どもたちのアイデアや工夫でどんどん進化し、今では立派な“チーム戦略型ゲーム”に成長しました。
【宝獲り合戦ルール(MOANAVIオリジナルver.)】
- 2チームに分かれる
- 公園の中央に線を引き、「自陣」と「敵陣」を決める
- 敵陣の奥にある“宝”(今日は長縄)を、自陣に持ち帰れば勝ち!
- 敵陣に入ったプレイヤーは、タッチされたら自陣まで戻る
- 宝を持っていても、途中でタッチされたらその場に置いて退場
- 自陣に戻ったら、すぐにプレーに復帰できる
【勝利のコツ】
- チームで話し合い、攻め・守り・おとりの役割分担をする
- 味方と声を掛け合って連携プレー
- 守りをかいくぐるために、敵を引き付ける作戦を練る
- 敵の動きに気づいたら、すぐ味方に知らせる
ゲームが始まると、子どもたちの集中力とテンションはMAX!
「そっち行ったよ!」「今だ、チャンス!」という声があちこちから飛び交い、全員がそれぞれの役割に夢中になっていました。
遊びが育む「未来を創る力」
この遊び、見た目には「ただの鬼ごっこ」かもしれません。でもその中には、子どもたちが生きる力を育む要素がぎっしり詰まっています。
✨自然に身につく“4Cスキル”
- Collaboration(協働):チームで役割を分担し、協力してゴールを目指す
- Communication(対話力):状況に応じて声を掛け合い、意思を伝え合う
- Critical Thinking(思考力):相手の動きを読みながら、どこを攻めるか判断する
- Creativity(創造力):毎回ルールや作戦を考えてゲームを進化させる
こうしたスキルは、教科書だけではなかなか育ちません。遊びの中だからこそ、夢中になりながら自然と体験できます。
💪 体力&運動技能もフル活用!
- 息が切れるくらい走る→持久力&瞬発力
- 相手の動きを予測する→空間認知&判断力
- タイミングよく動く→敏捷性
そして何より大事なのが、「楽しい!」という気持ち。
遊びが学びになるとき、それは子どもたちの“楽しい”が入り口なのだと、改めて感じます。
名前はまだない?でも、それもまた学びの時間
「宝獲り合戦」という名前は仮のもの。実は、正式な名前はまだ決まっていません。
でもこれもまた、MOANAVIらしい「子どもたちと一緒に作っていく」プロセス。
「もっとかっこいい名前にしようよ!」
「〇〇大作戦はどう?」
「ロゴとか旗も作ってみたい!」
こんな風に、ひとつの遊びから新しいアイデアがどんどん広がっていく様子を見ていると、大人が“与える”だけでは得られない学びの深さを実感します。
遊び=学び=生きる力
外遊びは、ただ体を動かすだけの時間ではありません。子どもたちが自分で考え、仲間と協力し、挑戦と失敗を重ねながら、社会で生きていくための土台を築く大切な時間。
MOANAVIでは、こうした遊びを「日課」にすることで、日々の小さな成長の積み重ねを大切にしています。
「なんとなく遊ぶ」ではなく、
「思いっきり楽しむ」ことで育つ力。
そして、子どもたち自身が「こんなことができるようになった」と感じられる経験。
これからもMOANAVIの外遊びは、子どもたちと一緒に進化していきます!
まとめ
「今日も楽しかった!」と汗だくになって帰ってくる子どもたちの顔を見るたびに、遊びの力を感じます。
次はどんな遊びが生まれるのでしょうか?名前が決まったら、またブログでご紹介します。どうぞお楽しみに!
記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)
STEAM教育デザイナー / 株式会社MOANAVI代表取締役
理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。
📚 経歴・資格
✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者
✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)
✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)
✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演
✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説