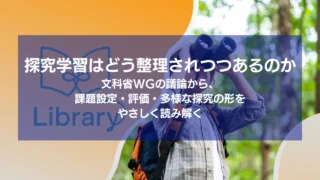小学生の自由研究におすすめ!サイコロ確率実験
出やすい目・組み合わせ表・大数の法則を徹底解説
サイコロを振ると「どの数字が一番出やすいの?」と気になったことはありませんか?
この記事では、小学生にもわかりやすく サイコロの確率実験 を紹介します。
✅ サイコロの目と仕組み
✅ 2個のサイコロを使った確率表(36通りの組み合わせ)
✅ 一番出やすい数字はどれか
✅ 大数の法則と試行回数の関係
を詳しく解説し、自由研究や親子での家庭学習にも活用できる内容にしました。ぜひ一緒にサイコロを転がして、確率の不思議を体験してみましょう!
サイコロの確率とは?【小学生にもわかる基礎解説】
サイコロは立方体(六面体)で、1〜6の数字が1つずつ書かれています。
実はサイコロには「反対の目を足すと7になる」というルールがあり、以下のように配置されています。
- 1の反対は6
- 2の反対は5
- 3の反対は4
この仕組みを知ると、サイコロの数字の並び方に興味が湧きますね。
サイコロ確率の実験方法|親子でできる自由研究におすすめ
サイコロを使った確率実験は、家庭でも簡単にできます。準備するものは次の通りです。
- サイコロ2個(市販のものでもOK)
- 記録用紙とペン
実験手順
- サイコロを2個同時に振る
- 出た目の合計を記録する
- これを36回以上繰り返す
- どの数字が一番多いか調べる
親子で一緒に表を作りながら記録していくと、自由研究にもそのまま使えます。
サイコロ2個の確率表と組み合わせ一覧【合計2〜12】
サイコロ2個を振ると、合計は「2〜12」になります。全部で36通りの組み合わせがあり、それぞれの回数は以下の通りです。
| 合計 | 出る組み合わせ例 | 出る回数 |
|---|---|---|
| 2 | (1,1) | 1回 |
| 3 | (1,2),(2,1) | 2回 |
| 4 | (1,3),(2,2),(3,1) | 3回 |
| 5 | (1,4),(2,3),(3,2),(4,1) | 4回 |
| 6 | (1,5),(2,4),(3,3),(4,2),(5,1) | 5回 |
| 7 | (1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1) | 6回 |
| 8 | (2,6),(3,5),(4,4),(5,3),(6,2) | 5回 |
| 9 | (3,6),(4,5),(5,4),(6,3) | 4回 |
| 10 | (4,6),(5,5),(6,4) | 3回 |
| 11 | (5,6),(6,5) | 2回 |
| 12 | (6,6) | 1回 |
サイコロで一番出やすい目は?7が最多の理由を解説
表からわかるように、合計が7になる確率が最も高いです。36通りのうち6通りが「7」になるため、確率は 6/36=1/6(約16.7%)。
次に出やすいのは「6」と「8」で、それぞれ5通りです。
「サイコロを振ると7が出やすい」と知っていると、ゲームの戦略にも役立つかもしれませんね。
サイコロ確率と大数の法則|試行回数を増やすとどうなる?
サイコロを36回振っただけでは、必ずしも7が一番多いとは限りません。
しかし、回数を増やすと結果は理論通りに近づいていきます。これを 大数の法則 といいます。
- 36回:偏りが出やすい
- 360回:確率通りに近づく
- 3600回:ほぼ理論値に収束する
実験を繰り返すことで「確率は長期的には安定する」という法則が実感できます。
なぜ確率実験を繰り返す必要があるのか【理科・統計との関係】
確率の考え方は、身近なところにも使われています。
- 天気予報:過去のデータを大量に集めて予測
- 医学実験:薬の効果を調べるために多くの人を対象に試す
- ゲーム:ガチャの確率も大量の試行回数で検証できる
「たくさん試すほど正しい結果に近づく」というのは、科学や統計に共通する考え方です。
まとめ|サイコロ確率の実験は自由研究・家庭学習に最適
- サイコロの反対の目は合計7
- 2個のサイコロを振ると合計は2〜12になる
- 一番出やすいのは「7」、次は「6」と「8」
- 回数を増やすと確率通りに近づく(大数の法則)
サイコロの確率実験は、親子で楽しく取り組める自由研究テーマです。
ぜひ家庭でチャレンジし、学びながら遊びのように楽しんでみてください!
記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)
STEAM教育デザイナー / MOANAVIスクールディレクター
理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。
📚 経歴・資格
✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者
✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)
✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)
✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演
✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説