
【非認知能力の育て方】
横浜市のオルタナティブスクール(フリースクール)
MOANAVIが実践する学びとは?
「子どもの学力だけでなく、生きる力も育てたい」と考えていませんか?
非認知能力は、自己肯定感・粘り強さ・コミュニケーション力など、人生を豊かにする重要な力です。
この記事では、
✅ 非認知能力とは何か?
✅ 家庭でできる育て方
✅ 横浜市のフリースクールMOANAVIが実践するカリキュラムと非認知能力の関係
を詳しく解説します!
1. 非認知能力とは? なぜ今注目されているのか
1-1. 非認知能力の具体例
非認知能力とは、テストの点数では測れない「生きる力」のことです。
例えば、
- 自己肯定感(自分を信じて行動できる力)
- 粘り強さ(困難に負けず、挑戦し続ける力)
- コミュニケーション力(相手と意思疎通し、協力できる力)
- 創造力(新しいアイデアを生み出し、形にする力)
- 共感力(他者の気持ちを理解し、支え合う力)
- 自己調整力(感情をコントロールし、冷静に考える力)
1-2. なぜ非認知能力が重要なのか?
AIが発展する時代、「知識を覚える」だけではなく、「考え、行動する」力が求められるようになりました。
そのため、学力だけでなく自分で問題を解決し、他者と協力しながら生き抜く力(非認知能力)が大切になります。
2. 非認知能力の育て方:家庭でできる実践方法
2-1. 乳幼児期(0〜6歳)にできること
✅ たくさん話しかける → 言語力と自己肯定感を育てる
✅ 自由に遊ばせる → 創造力と好奇心を伸ばす
✅ 「失敗しても大丈夫」と伝える → 挑戦する力を育む
2-2. 小学生期にできること
✅ 習い事や課外活動に参加させる → 好奇心や社交性をUP!
✅ 家事を手伝わせる → 自立心と責任感を養う
✅ 目標を一緒に決める → 計画力と達成感を味わう
💡 ポイント:「できたこと」に注目してほめる!
「テストの点数が良かったね」よりも「最後まであきらめずに頑張ったね!」と声をかけることで、自己肯定感や粘り強さが育ちます。
3. MOANAVIのカリキュラムと非認知能力の関係
MOANAVIでは、「科学」「言語」「人間」「創造」の4つの枠組みで学びを提供し、非認知能力の発達を促しています。
3-1. 「科学」の枠組み × 論理的思考・問題解決力
🔍 どんな非認知能力が育つ?
✅ 探究心(「なぜ?」を大切にし、疑問を追求する力)
✅ 問題解決力(自ら考え、試行錯誤する力)
✅ 粘り強さ(最後までやり遂げる力)
📝 具体的な活動例
- 自然環境の調査:フィールドワークを行い、データを分析することで、試行錯誤する力を養う
- 科学実験:仮説を立て、実験し、結果を分析することで、論理的思考力を鍛える
- 算数ゲーム:買い物ゲームやモノポリーで、数的感覚や経済感覚を実践的に学ぶ
➡ MOANAVIの「科学」では、知識の詰め込みではなく、「なぜ?」を大切にし、考える力を育てます。
3-2. 「言語」の枠組み × コミュニケーション能力・自己表現力
🗣 どんな非認知能力が育つ?
✅ 表現力(自分の考えを伝える力)
✅ 傾聴力(相手の話を理解し、共感する力)
✅ 論理的思考力(意見を整理し、説得力を持って伝える力)
📝 具体的な活動例
- ディスカッション:意見を伝え、相手の話を聞く力を育てる
- スピーチ練習:自分の考えをまとめ、発表することで、伝える力を向上させる
- 演劇や寸劇:台本を覚え、役になりきることで、感情表現やチームワークを学ぶ
➡ MOANAVIの「言語」では、読む・書くだけでなく、実践的なアウトプットを重視します。
3-3. 「人間」の枠組み × 社会性・リーダーシップ
🤝 どんな非認知能力が育つ?
✅ 協調性(仲間と協力して目標を達成する力)
✅ リーダーシップ(グループをまとめ、方向性を示す力)
✅ 社会貢献意識(自分の行動が社会にどう影響するかを考える力)
📝 具体的な活動例
- お祭りの企画・運営:イベントを計画し、実行することで、主体性や責任感を育む
- ボランティア活動:地域活動を通じて、人との関わりや感謝の気持ちを学ぶ
➡ MOANAVIの「人間」では、社会とつながる経験を通じて、自分の役割を理解します。
3-4. 「創造」の枠組み × 創造力・チャレンジ精神
🎨 どんな非認知能力が育つ?
✅ 創造力(新しいアイデアを形にする力)
✅ 挑戦する力(失敗を恐れず、トライし続ける力)
✅ 自己表現力(自分らしさを発揮する力)
📝 具体的な活動例
- アートプロジェクト:絵画や工作で自由に表現する
- 映画作り:ストーリーを考え、映像作品を制作する
➡ MOANAVIの「創造」では、自由な発想を大切にし、表現する力を伸ばします。
4. FAQ(よくある質問)
Q1: 非認知能力を育てるには何歳から始めるのがいいですか?
A1: 非認知能力の育成は早ければ早いほど効果的です。特に、乳幼児期(0〜6歳)から言語や社会性を育てることが大切です。年齢に応じて、遊びを通じて好奇心を刺激したり、言葉でコミュニケーションを図ったりすることが効果的です。
Q2: 学力とのバランスはどうすればいいですか?
A2: 両方を育てる」ことが大切!学力を高めることも大切ですが、非認知能力の育成はそれ以上に重要です。学力を育てる勉強だけでなく、他者と協力する力や創造力を育む活動にも取り組むことで、バランスよく成長することができます。
Q3: 家庭でできる簡単な方法は?
A3: 家庭でできる方法としては、「成功体験を与える」「失敗しても大丈夫と励ます」「家族でコミュニケーションを大切にする」ことが挙げられます。例えば、一緒に料理をしたり、ボードゲームを楽しんだりすることが非認知能力の育成に役立ちます。
MOANAVIについて
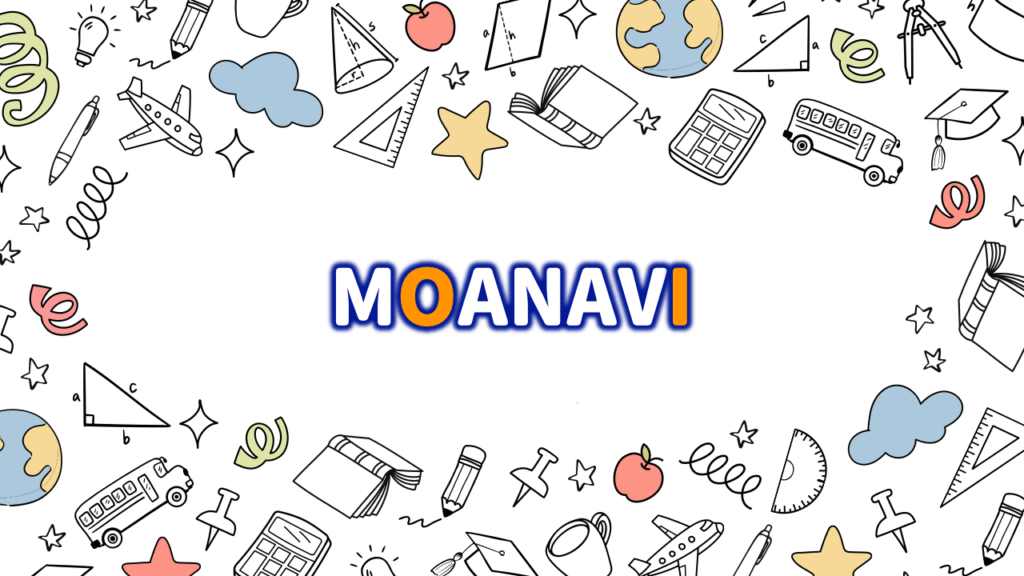
MOANAVIは、子どもたちが「考える力」「伝える力」「協力する力」「創造する力」を育むことを目指すオルタナティブスクール(フリースクール)です。従来の学びの枠組みにとらわれることなく、「科学」「言語」「人間」「創造」という4つの柱で、子ども一人ひとりの個性や可能性を最大限に引き出すカリキュラムを提供しています。
私たちの教育の特徴は、単なる知識の習得にとどまらず、実社会で役立つ非認知能力を育てることにあります。社会で活躍するために必要な力、すなわち「自己肯定感」「問題解決力」「協力性」「創造力」を養い、子どもたちが自分の力で道を切り開いていけるようサポートしています。
MOANAVIの学びは、
- 知識をただ詰め込むのではなく、自ら考え、挑戦する力を育てます。
- 他者と協力して目標を達成することで、社会性を培います。
- 失敗を恐れず挑戦する心を持つことで、成長し続ける力を身につけます。
もし、あなたの子どもが今後の時代を力強く生き抜くために必要な力を育てることに興味があるのであれば、MOANAVIでの学びがその第一歩となることでしょう。
私たちと一緒に、「学び」と「成長」の無限の可能性を広げていきましょう!
記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)
STEAM教育デザイナー / 株式会社MOANAVI代表取締役
理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。
📚 経歴・資格
✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者
✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)
✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)
✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演
✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説







