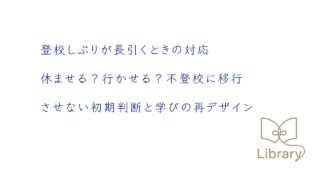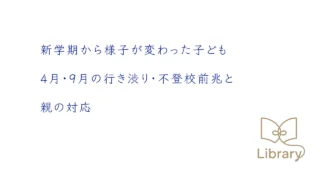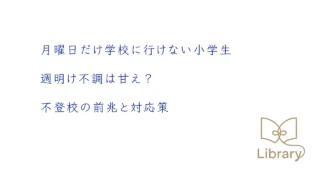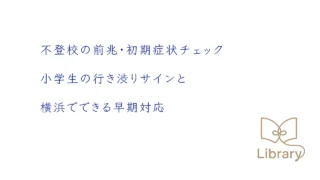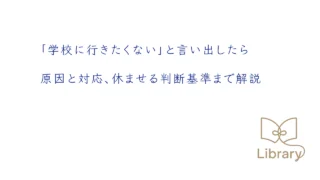小学生の家庭学習を効果的にサポートする方法とは?
ZPDと形成的アセスメントの活用
家庭学習で子どもの学習効果を高めたいですか?この記事では、子どもが自力で学ぶ力を伸ばすための「発達の最近接領域(ZPD)」と「形成的アセスメント」の活用方法について解説します。学びの適切なサポート方法を知り、親子で楽しく効果的な学習を進めましょう。
小学生の家庭学習で大切なこと
小学生の家庭学習では、「自分で考える力」を伸ばすことがとても大切です。しかし、ただ問題を解かせたり、答えを教えたりするだけでは、子どもは本当の意味で成長できません。そこで注目したいのが、発達の最近接領域(ZPD)と形成的アセスメントという考え方です。
- 発達の最近接領域(ZPD) …「一人ではできないが、大人のサポートがあればできること」の範囲。
- 形成的アセスメント … 学習の途中で理解度を確認し、適切なフィードバックをすることで学びを深める方法。
この2つの視点を意識すれば、子どもが「自分で考え、学ぶ力」を自然と身につけられるようになります。
発達の最近接領域(ZPD)とは?
ZPDの基本的な考え方
ZPD(発達の最近接領域)とは、子どもが一人ではできないが、大人のサポートがあればできることの範囲を指します。
- 子どもが「ちょっと頑張ればできる」レベルを見極める。
- 必要以上に手助けをしすぎず、適切なヒントを与える。
- 段階的にサポートを減らし、最終的に子どもが自力でできるようにする。
例えば、自転車に乗る練習を考えてみましょう。
- 最初は補助輪付きの自転車で練習する(サポートあり)。
- 親が後ろから支えてバランスを取る(少しずつ自立)。
- 最終的に一人で乗れるようになる(ZPDを超えて独力でできる)。
このように、子どもの成長に合わせて適切なサポートをすることが大切です。
ZPDを活かした家庭学習のコツ
家庭学習でも、この考え方を取り入れると効果的です。
- いきなり答えを教えず、ヒントを出す
- 「この問題、どこまで分かった?」と質問し、考えさせる。
- 手伝いすぎない
- 「ここまでできたね。じゃあ次はどうすればいいかな?」と声をかける。
- できたらしっかり褒める
- 「一人で解けたね!すごい!」と成功体験を積ませる。
このように、ちょうど良い難易度の課題に取り組ませることで、子どもの学びをサポートできます。
形成的アセスメントとは?
形成的アセスメントの基本
形成的アセスメントとは、学習の途中で理解度を確認し、適切なフィードバックを行うことです。
- ただ正解・不正解を伝えるのではなく、「どこでつまずいたのか?」を考える。
- 子どもが「どうすればもっとよくできるか」を意識できるようにする。
- こまめに振り返ることで、学習の定着度を高める。
家庭でできる形成的アセスメントの方法
家庭学習で取り入れやすい方法を紹介します。
- 子どもに説明させる
- 「どうやって解いたの?」と聞き、自分の言葉で説明させる。
- 間違えたら、考えさせる
- 「ここが間違ってるよ」ではなく、「なぜこの答えになったと思う?」と問いかける。
- 学習の振り返りをする
- 「今日学んだことを3つ言ってみよう!」など、まとめる習慣をつける。
- 小さな目標を立てる
- 「今日は漢字を5個覚える」「算数の文章題を1問解く」など、達成しやすい目標を設定する。
こうした工夫をすることで、子どもは「学び方」を身につけ、自己調整学習ができるようになります。
まとめ
📌 ZPDの視点 → 「ちょうどいいサポート」で子どもの成長を促す
📌 形成的アセスメントの視点 → 学習の途中で理解度を確認し、適切なフィードバックをする
📌 子どもが自分で考え、学ぶ力をつけることが大切!
家庭学習では、「勉強を教える」というよりも、「学び方をサポートする」ことが重要です。ZPDと形成的アセスメントを活用して、子どもが主体的に学ぶ環境を整えていきましょう。
MOANAVIのご紹介

MOANAVIでは、対話と体験を大切にした学習を通じて、子どもたちの「自ら学ぶ力」を育んでいます。ZPDや形成的アセスメントの考え方を取り入れながら、個々の子どもに合わせたサポートを行っています。
お子さんの学習に関するご相談や、MOANAVIの教育プログラムに興味がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)
STEAM教育デザイナー / 株式会社MOANAVI代表取締役
理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。
📚 経歴・資格
✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者
✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)
✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)
✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演
✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説