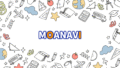GW明けに学校へ行きたくない子どもたち
不登校の理由と親ができるサポート
はじめに
ゴールデンウィークが終わったあと、「学校に行きたくない」「朝起きられない」「お腹が痛い」と訴える子どもが増えることをご存じでしょうか。教育現場では、GW明けは不登校が急増する時期としてよく知られています。
保護者にとっては「また始まったばかりなのに…」と戸惑い、不安や焦りを抱く時期でもあります。本記事では、なぜGW明けに不登校が増えるのか、その背景と具体的なサポート方法を整理しました。さらに、学校以外の学び場としてMOANAVIがどのように子どもを支えているのかも紹介します。
ゴールデンウィーク明けに不登校が増える4つの理由
1. GW明けの生活リズムの乱れ
連休中は夜更かし・朝寝坊になりやすく、生活リズムが一気に崩れます。急に元の学校生活に戻ろうとすると、心身に大きな負担となり「朝起きられない」状態が続いてしまうのです。
2. 新年度の疲れが反動として出る
4月は新しいクラスや先生、友人関係など、子どもにとって大きな環境変化の時期です。GWまでは頑張れても、休みで一息ついたときに「実はしんどかった」と気づき、反動として不登校につながることがあります。
3. 勉強が本格化し、つまずきやすい
新学期の授業は、GW明けから本格的に難易度が上がります。「内容がわからない」「質問できない」という小さなつまずきが積み重なり、「行きたくない」気持ちに直結することもあります。
4. 周囲と比べて自信を失う
友人関係や学力、運動面での比較により「自分はできない」「周りと違う」と感じると、学校が居心地の悪い場所になってしまいます。
Q&A|GW明け不登校に関する保護者のよくある疑問
Q1. GW明けの不登校は一時的ですか?
→ 一時的に休めば回復する子もいますが、無理に登校を迫ると長期化するリスクがあります。早めに安心できる環境を整えることが大切です。
Q2. どのくらい休んだら学校や専門機関に相談すべきですか?
→ 数日続く場合でも、まずは担任やスクールカウンセラーに相談をおすすめします。家庭だけで抱え込まず、外部の支援を早めに取り入れることで回復がスムーズになります。
Q3. 無理に登校させたほうがよいですか?
→ 体調不良と同じように「心にも休養が必要」と考えてください。無理に登校を促すと逆効果になることが多く、「安心できる環境」を優先することが大切です。
保護者ができる6つのサポート
1. 気持ちを否定せず受け止める
「学校に行きたくない」と言ったときに「甘えないで」と返すと、子どもはさらに心を閉ざしてしまいます。「そう感じているんだね」と気持ちを認める姿勢が回復の第一歩です。
2. 小さな行動を認めて自信につなげる
「今日は起きられたね」「ランドセルを開けたね」と、小さな一歩を肯定する声かけが自己肯定感の回復に役立ちます。
3. 学校以外の安心できる居場所を持たせる
「学校に行けなくても安心して過ごせる場」があるだけで、子どもは「逃げ場がある」と感じられます。居場所があることで、エネルギーを回復し、再登校の可能性も広がります。
4. 勉強の遅れを責めない
「何ページ進んだか」よりも「どんな気持ちで取り組めたか」に目を向けましょう。学びは取り戻せますが、安心感は一度失うと回復に時間がかかります。
5. 保護者自身も相談できる場所を持つ
子どもだけでなく保護者も孤立しがちです。学校・専門機関・地域の団体などとつながることが、親子双方の安心につながります。
6. 「学校に戻す」より「心の回復」を優先する
不登校は「怠け」ではなく、心のエネルギー切れのサインです。まずは休むことを認め、少しずつ「やってみたい」を取り戻すことを大切にしましょう。
MOANAVIでのサポート事例
MOANAVIでは、不登校や行き渋りのある子どもが安心して過ごせる学びの場を提供しています。
- 自己調整学習:自分に合った量やペースで学ぶことで小さな達成感を積み重ねる
- STEAM教育・プロジェクト学習:体験を通して「やってみたい」を引き出す
- STUDY POINT制度:努力や行動を可視化し、子どもの自信につなげる
- 保護者伴走サポート:無理に学校復帰を急がず、「今できること」に寄り添う支援
実際に、MOANAVIに通う中で「自分のペースで学べる」「仲間ができた」と感じ、少しずつ笑顔を取り戻していく子どもたちの姿を多く見てきました。
まとめ|GW明け不登校は「心のエネルギー切れ」のサイン
ゴールデンウィーク明けに不登校が増えるのは、子どもの弱さではなく自然な現象です。大切なのは学校に行けるかどうかよりも、「今どんな気持ちでいるか」「どんな支えが必要か」に目を向けること。
家庭でのサポートに加えて、MOANAVIのような安心できる学びの場を組み合わせることで、子どもは「またやってみたい」と思えるエネルギーを取り戻せます。
📌 もし「子どもに合う場所が見つからない」と悩んでいる方は、ぜひ一度ご相談ください。
記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)
STEAM教育デザイナー / MOANAVIスクールディレクター
理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。
📚 経歴・資格
✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者
✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)
✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)
✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演
✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説