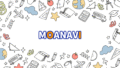小中学校で毎日4時間以上も授業を受けているのに、どうして学力が上がらないのでしょうか。
もっとたくさん授業を受けさせた方がいい?
みんなが通っている塾に通わせた方がいい?
勉強が苦手な理由が分からないまま塾を選んでいませんか?

勉強が苦手な理由が分からないまま塾を選んでいませんか?
残念ながら、学校の授業を受けて学力が上がらないお子さんの場合、どんなに授業時間を増やしても、期待するほどの学力の向上は見込めません。それは、授業の時間が勉強の時間になっていないからです。
授業時間≠勉強時間
当たり前のことですが、ただ席に座っているだけでは勉強したことにはなりません。授業を受けている時間が勉強をしている時間とは限らないからです。
学力を向上させるためには、子ども自身が自分の学びの主人公となっている勉強時間が必要です。
勉強が苦手な理由は子ども一人ひとり違います
勉強内容に関心がもてない?
Youtubeやゲーム、SNSへの依存が高い?
友達や先生との人間関係に悩んでいる?
長時間集中して取り組むことが難しい?
学習障害等による影響?
勉強の仕方が分からない?
子どもたちは「勉強が苦手な理由が分からない」「どうすれば勉強できるようになるのか分からない」ことを、「勉強が嫌い」という言葉でまとめてしまいがちです。
そんな状態で時間と量を増やされても、ますます勉強が嫌いになるだけです。
まずは「勉強が嫌い」ではなく、「こういう理由で勉強が苦手」と自分で理解して、勉強時間を増やしていくことが大切です。
学びの主人公になっている子どもは、学校の授業だけで年間に800時間以上もの時間を積み上げています。この時間をどう過ごすべきなのかを改善しないまま、塾や通信教育の教材を増やしたところで、学力は向上しません。
一般的な塾や通信教育は、勉強が苦手な子どもたちのためのものではなく、勉強が得意な子どもたちがもっと得意になるためのものなのです。
どうすれば学びの主人公になれるの?
学校の成績は、育成を目指す資質・能力に合わせて3観点で評価されています。
知識・技能
思考力・判断力・表現力等
主体的に学習に取り組む態度
文部科学省が示す最新の学習指導要領によると、知識・技能とは、「何を知っているか、何ができるか」であり、思考力・判断力・表現力等とは、「知っていること・できることをどう使うか」という資質・能力です。また、主体的に学習に取り組む態度とは、自己の感情や行動を統制する能力、自らの思考のプロセス等を客観的に捉える力など、いわゆる「メタ認知」に関する資質・能力です。
学びの主人公とは、教室でたくさん手を挙げて発言することや、ものしり博士であること、器用であることなどではありません。
今の自分にできることやできないこと、分かっていることや分かっていないこと、どのように考えたり表現したりすればよいのかという方略についてメタ認知を行い、自分の学びのルートを決定することができる状態が「学びの主人公になっている」状態です。
どのように学べばいいの?
勉強が苦手な子どもたちは、学びの主人公になれていません。学びの主人公になるためにはメタ認知が重要ですが、メタ認知を身に付けるためには先生や仲間と協働的に学ぶ経験の積み重ねが重要です。
メタ認知とは?
メタ認知とは、「自分を見つめるもう一人の自分」のイメージです。
三宮(2008)によるとメタ認知的知識とメタ認知的活動に分類することができます。また、メタ認知的活動はメタ認知的モニタリングとメタ認知的コントロールに分けることができます。
メタ認知的モニタリングとは、課題の困難度や達成度を評価したり、分析したりすることです。
メタ認知的コントロールとは、目標設定や修正、計画、方略選択などを行うことです。
効果的に学習を進めるためには、メタ認知を働かせ、学びの主人公になることが重要です。
また、自分の学びの状況を適切に把握するためには、適切なフィードバックが重要になります。
学習の環境
ブランスフォードら(2002)は、「学習者中心」「知識中心」「評価中心」「共同体中心」という4つの視点から学習環境をデザインする際に考慮すべき問題を検討しました。
学習者中心の学習環境をデザインするためには、子どもが知っていることや気にしていること、できることやしたいことが何かということを教師が理解しておく必要があります。
知識中心の学習環境をデザインするためには、「理解に基づく学習」を通して真の意味での「知力をもつ」ように支援することが必要です。そのためには読み・書き・計算等のリテラシーの習得も必要です。
評価中心の学習環境をデザインするためには、子どもに表現活動を促し、適切なタイミングで適切な評価(アセスメント)を行い、その情報をフィードバックする必要があります。
共同体中心の学習環境をデザインするためには、学校と家庭と地域が連携し、学校での学習と学校外での学習をつなぐことが必要です。
ブランスフォードらは、学校で過ごす時間、睡眠時間、家庭で過ごす時間を比較した時、家庭が53%、睡眠が33%、学校が14%であることから「子どもの学習にとって鍵となる環境は、何よりもまず家族である。」と述べています。
家庭で過ごす時間の3分の1をテレビなどに費やすとすると、学校で学ぶ時間よりもテレビなどが長くなってしまいます。
家庭での学習においても、お子さんをが学びの主人公となれるような学習環境をデザインしていく必要があります。
とはいえ、各ご家庭でお子さんが学びの主人公になれるような学習環境をデザインすることは大変なことです。そのため、お子さんの学びをアウトソーシングできる様々な習い事がたくさん用意されています。
お子さんが学びを楽しみ、主体的に学習に取り組めるようになれば、家庭での過ごし方が変わり、お子さんの学力が向上することが期待できます。
習い事は、知識や技能を高めるだけでなく、お子さんが学びの主人公となり、自分から学び続けられるようになるようなものを選びましょう。
MOANAVIの学習環境
MOANAVIでは、子ども一人ひとりの「今」に合わせたカリキュラムを、子どもたちがメタ認知を働かせながら学習できるように、お子さんと一緒に作り上げていきます。
また、STEAM教育で対話と体験を大切にした学習を行うことで、お子さんがこれから学びを楽しみ続けるために必要なマインドセットを構築していきます。
MOANAVIでは、子ども同士、子どもと先生、先生同士がたくさん語り合います。
自分の話を聞いてもらうこと、相手の話を聞くことは楽しいだけでなく、学びにとって重要な役割を果たします。学習内容は一人ひとりに合わせた個別指導ですが、みんなと一緒にオープンに学べる環境づくりをしています。
STEAM教育とは
現代社会では、新たな問題や課題に対して創造的なアプローチが求められています。そのため、教育界でいま最も注目を集めているのがSTEAM教育です。
STEAM教育は科学、技術、工学、アート、数学を統合した総合的な学習領域です。
MOANAVIの個別指導
MOANAVIの個別指導では、お子さんと相談しながら、お子さんの学びに合わせて課題を設定していきます。学校で学んでいる内容や、それに対する理解度はもちろん、お子さんの学力の傾向、その日の体調やモチベーションに合わせて、カリキュラムをカスタマイズしています。
学習した内容はファイリングしてポートフォリオを作成しています。目に見える形で学習の成果が積み上がっていくので、子どもたちのモチベーションにつながっています。1年間でファイル4冊分、およそ2000ページもの学習に取り組む子どもたちもいます。
一人ひとりの学力に合わせて学びを進めていくので、お子さんの実際の学年に関わらず、学びをどんどん進めたり、ゆっくり学び直したりしています。できないこと、分からないところは、少しずつ時間をおいて何度も反復学習を行い、確実に習得できるようにしています。
学力アップは学びのつながりが大切!急がば回れ!基礎からしっかりつなげていきます。
MOANAVIのSTEAM教育
MOANAVIのSTEAM教育では特定の分野ではなく、科学実験観察、プログラミング、工作、アート、プレゼンテーション、作文、論理的思考を伴うボードゲームなど、対話と体験を大切にした様々な活動に総合的に取り組みます。
共通することは子どもたちの内面にあるものを「表現する」ことです。MOANAVIではこれらの表現活動を「ものづくり」と呼んでいます。
MOANAVIでは、子どもたちのものづくりを通して、一人ひとりの学びの「今」を見取り、よりよい学びにつなげています。また、ものづくりを通して、自分たちの力で新しい価値を創造する喜びを実感できるようにしています。
MOANAVIの個別指導+STEAM教育
MOANAVIでは、平日に毎日定額で通える個別指導+STEAM教育コースを開講しています。
毎日通えることのメリット
毎日通うことで、毎日決まった時間に学習する習慣が身につきます。
毎日通うことで、勉強が当たり前の習慣となります。歯磨きするのを忘れると落ち着かなくなるのと同じくらい、勉強しないと落ち着かない気持ちになるので、自然と勉強するようになります。
これは人間に備わっている恒常性の働きによるものです。恒常性とはなるべく「変わらないようにしよう」とする心身の働きです。
「勉強しなきゃ」と思っても、勉強の習慣がない状態を恒常性が維持しようとしますので、週1〜2回くらいでは、なかなか勉強の習慣を身につけることはできません。
「勉強しなきゃ」と思ったら、最初の2週間が習慣化の鍵となります。
2週間毎日勉強を続けると、勉強をする状態が通常になるので、恒常性に働きにより、今度は勉強をやめにくくなるのです。
また、一度に長時間の勉強を行うことは慣れないうちは大変なことです。集中が持続している短時間の勉強を毎日繰り返す方が学力は向上します。
勉強が自分ごとになる個別指導とSTEAM教育を毎日楽しめます
「また明日ね!」と声を掛け合える先生や仲間たちと一緒に、毎日楽しく学んでいます。
前半は個別指導でじっくりと学び、後半はSTEAM教育を軸とした、ものづくりや発表などの表現活動に取り組みます。
MOANAVIは、子どもたち一人ひとりが学びの主人公となれる場所です。
記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)
STEAM教育デザイナー / 株式会社MOANAVI代表取締役
理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。
📚 経歴・資格
✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者
✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)
✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)
✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演
✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説