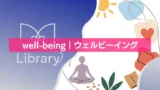レジリエンスとは?
子どもの心のしなやかさを育てる家庭と学校の実践
保護者向けやさしい解説
子どもが失敗したとき、落ち込んだとき、親としてどんな言葉をかければいいのでしょうか。
「強くなってほしい」と願う一方で、無理をさせてしまうこともあります。
そんなときに大切なのが、「レジリエンス(resilience)」――心のしなやかさです。
これは、つらいことを跳ね返す「強さ」ではなく、
困難を受け止めながら前に進む「柔軟さ」を指します。
いま、教育や心理の世界では、このレジリエンスを育てる取り組みが注目されています。
ストレスや不安の多い時代に、子どもが安心して挑戦し、失敗から学び、
また立ち上がれる力をどう育てるか――それは家庭や学校に共通する大切なテーマです。
この記事では、
レジリエンスの意味と背景、家庭・学校での具体的な実践例、
そして日常の中でできるシンプルなアイデアまで、やさしく解説します。
「失敗しても大丈夫」と笑って言える子どもを育てるために、
今日からできることを一緒に考えてみましょう。
レジリエンスとは?|心理学で注目される「折れない心」とは何か
レジリエンスの意味と語源
「レジリエンス(resilience)」という言葉は、もともと英語で「はね返す力」「弾力」「回復力」といった意味を持っています。
たとえば、ゴムボールを強く押しても、手を離すとすぐに元に戻ります。
その“もとに戻る力”が、心理学で言うレジリエンスに近いイメージです。
ただし、人の心の場合は「押されたら元に戻る」という単純な話ではありません。
失敗やつらい経験のあとに、以前よりも強く、優しく、柔らかくなって立ち直る力――それがレジリエンスです。
つまり「ただ回復する」だけでなく、「経験を糧に成長する力」と言えます。
心理学と教育で注目される理由
レジリエンスという考え方は、1970年代ごろから心理学の分野で注目され始めました。
きっかけとなったのは、アメリカ・ハワイで行われた「カウアイ研究」と呼ばれる長期調査です。
研究では、貧困や家庭不和など厳しい環境で育った子どもたちの中に、驚くほど前向きに成長する子がいることがわかりました。
彼らは困難を経験しても、学び続け、友人関係を築き、自分の人生を切り開いていったのです。
その違いを生んでいたのが「レジリエンス」――つまり、逆境を乗り越える力でした。
以来、レジリエンスは教育・医療・福祉などあらゆる分野で研究され、
現在では「子どもの成長に欠かせない非認知能力のひとつ」として注目されています。
「強い心」ではなく「しなやかな心」
よく「心を強くしなさい」と言われますが、レジリエンスの本質は「強さ」ではありません。
むしろ、「折れないように硬くなる」よりも、「しなやかに形を変えて立ち直る」力のほうが大切です。
たとえば、木の枝を想像してみてください。
硬い枝は強風に折れてしまいますが、しなやかな枝は風に合わせてしなることで折れません。
レジリエンスとはまさにこの「しなやかさ」。
子どもがストレスや失敗に出会ったとき、その経験を跳ね返すのではなく、受けとめながら前に進む力です。
レジリエンスを構成する3つの要素
心理学者たちは、レジリエンスを「性格ではなくスキル」だと考えています。
つまり、誰でも後天的に育てることができる力です。
その中核となるのが、次の3つの要素です。
- 自己認識(Self-awareness)
自分の感情や考えを正しく理解する力。
「いま悲しい」「自分は怒っている」と気づけることで、感情に流されずに対処できるようになります。 - 人とのつながり(Relationship)
支えてくれる人がいること、助けを求められる関係を築くこと。
孤立せずに誰かとつながることで、立ち直る力が大きくなります。 - 問題解決力(Problem solving)
起こったことを受け入れ、次にどう動くかを考える力。
「なぜ自分だけが…」ではなく、「これからどうすればいいか」と切り替える思考を持つことです。
この3つは、学校の勉強だけでなく、家庭の会話や遊びの中でも育てることができます。
現代社会で求められる「レジリエンス教育」
AIやSNS、グローバル化など、子どもたちを取り巻く環境は日々大きく変化しています。
知識を覚えるだけでは生き抜けない時代に、注目されているのが「レジリエンス教育」です。
OECD(経済協力開発機構)や文部科学省も、
これからの教育で重視すべき力として「非認知能力」や「ウェルビーイング(幸福感)」を挙げています。
その根幹にあるのが、変化に柔軟に対応し、自分の軸を持って生きる力=レジリエンスです。
MOANAVIでも、子どもたちが自分のペースで挑戦と失敗をくり返しながら、
「もう一度やってみよう」「今度はこうしてみよう」と前向きに行動できる学びを大切にしています。
これはまさに、学びの中でレジリエンスを育てる実践のひとつです。
レジリエンスは誰にでも育てられる
レジリエンスは「特別な人だけが持つ才能」ではありません。
どんな子にも、どんな大人にも、状況を受け止めて立ち上がる力が眠っています。
その力を引き出すには、安全な環境と支えてくれる人の存在が欠かせません。
たとえ困難に直面しても、「大丈夫」「あなたならできる」と支えてくれる人がいる。
その経験こそが、子どもの中にしなやかな根を伸ばしていきます。
家庭や学校でできるレジリエンスの育て方は、このあとで具体的に紹介していきます。
まずは、「レジリエンスとは、失敗を恐れず、経験を糧にして前へ進む力」であることを、しっかりと心に留めておきましょう。
なぜ子どもにレジリエンスが必要なのか|不登校・ストレス・自信の低下との関係
現代の子どもを取り巻くストレス環境
子どもたちが成長する現代社会は、大人が想像する以上に複雑で、変化のスピードも速くなっています。
SNSを通じたつながりの中で他人と比べる機会が増え、常に「評価される」「見られている」というプレッシャーを感じている子も少なくありません。
学校では学力競争や友人関係、家庭では親の期待や生活リズムの変化など、
小学生の段階からすでに多くのストレス要因を抱えています。
また、気候変動や社会不安、災害のニュースなど、
子どもたちは“世界の問題”にもリアルタイムで触れるようになりました。
これらは無意識のうちに心の負担を増やし、「どうせ自分には無理」「失敗したくない」といった無力感を生み出します。
不登校・自己肯定感の低下との深い関係
文部科学省の調査では、全国の不登校児童生徒数は年々増加傾向にあります。
背景には学力や進路の悩みだけでなく、「失敗できない社会」への不安が見え隠れしています。
子どもたちは、評価やテストの点数など“結果”で判断される場面が多いため、
「うまくできない自分には価値がない」と感じてしまいがちです。
この“完璧主義”が続くと、挑戦する意欲が失われ、失敗を避けるようになります。
しかし、実際の成長は「失敗」と「立ち直り」の繰り返しの中にあります。
レジリエンスが低い状態では、失敗からの回復に時間がかかり、自己肯定感も下がっていきます。
一方で、レジリエンスを持っている子どもは、
「できなかったこと」を「次のチャンス」として捉え直し、前向きに挑戦し続けることができます。
成功体験より「回復体験」が心を育てる
多くの保護者が「自信をつけてほしい」と願い、子どもに成功体験を積ませようとします。
もちろんそれは大切ですが、本当の意味で心を強くするのは、成功よりも“回復体験”です。
たとえば、テストで思うような点が取れなかったとき。
失敗を叱らず、「次にどうすればいいかな?」と一緒に考える経験が、レジリエンスを育てます。
あるいは、友だちとのトラブルを自分の言葉で解決できたとき。
その過程こそが、立ち直る力のトレーニングになります。
大人が先回りして問題を解決してしまうと、子どもは“回復の練習”をする機会を失います。
レジリエンス教育とは、子どもに「困難を自分で整える経験」を積ませることでもあるのです。
「自己調整力」とレジリエンスの関係
レジリエンスは単なる「我慢」や「ポジティブ思考」ではありません。
自分の感情を理解し、状況に合わせて行動を調整できる**自己調整力(Self-regulation)**と深く関係しています。
自己調整力がある子どもは、落ち込んだときにも「いま自分は悲しい」「でもできることを探そう」と切り替えることができます。
つまり、レジリエンスは「心の筋肉」であり、自己調整力は「その筋肉を動かす力」なのです。
社会が求める「生きる力」としてのレジリエンス
OECDが提唱する「Education 2030」でも、
次世代の教育目標として「変化に対応し、自らを再構築できる力」が強調されています。
AIが進化し、予測不能な時代を生きる子どもたちにとって、
知識よりも「どう立ち直るか」「どう再挑戦するか」が生きるカギになるとされています。
レジリエンスは、この“変化を楽しめる力”でもあります。
「予定どおりにいかなくても、なんとかなる」
「うまくいかないときこそ、成長のチャンス」
そうした考え方を育てることが、子どもが未来を生き抜くための最大の支えになるのです。
レジリエンスは家庭と学校で育て合うもの
最後に大切なのは、レジリエンスを“子どもだけに求めない”ことです。
親や教師が完璧である必要はありません。
むしろ、大人が失敗したときに「自分も落ち込むことがある」「でも次に活かしたい」と口にする姿を見せることこそ、最高の教材です。
家庭や学校での「失敗を責めない文化」「挑戦を称える空気」が、
子どもたちのレジリエンスを自然に育てていきます。
家庭で育むレジリエンスの方法|親ができる声かけと日常習慣
家庭は「安心して失敗できる場所」
レジリエンスは、失敗やストレスを“避ける”力ではなく、“乗り越える”力です。
つまり、日常の中で「うまくいかない経験」をどのように受け止めるかが育ちのカギになります。
学校や社会では評価がつきやすいため、子どもたちは「できなかったら怒られる」「恥ずかしい」と感じることも多いもの。
だからこそ家庭は、安心して失敗できる場所であることが重要です。
親が「間違えてもいいよ」「挑戦してみよう」と言葉で伝えるだけでなく、
実際に「失敗してもやり直せる」「挑戦が認められる」体験を積ませることが、レジリエンスを育てます。
子どもの感情を否定しない
レジリエンスを育てるうえで最初のステップは、感情を否定しないことです。
「泣かないの」「そんなことで怒らないの」といった言葉は、子どもにとって「感情を出すことはいけない」と学習するきっかけになります。
感情を抑えるのではなく、「悲しいね」「悔しかったね」と言葉にして共感することが、心の整理の第一歩です。
そのうえで、「次はどうしようか」と未来に目を向ける声かけをすると、気持ちの切り替えが自然にできるようになります。
例:声かけの変換
- ✗「そんなことで泣かないの」
- 〇「悲しかったね。どうすれば次はうまくいくかな?」
このように、感情を受け止めたあとに思考を促すことで、子どもは“感情を自分で扱う力”を身につけていきます。
「失敗ノート」で回復の練習をする
家庭で簡単にできるおすすめの方法が、「失敗ノート」です。
子どもが失敗したり落ち込んだりしたときに、
・何がうまくいかなかったのか
・そのときどんな気持ちだったのか
・次にどうしたいか
を書き出してみます。
書くことで、自分の感情を客観的に整理でき、
「失敗は悪いことではない」「気持ちを立て直せる」と実感できます。
親も一緒に書いて見せると、子どもは“立ち直る力”が自然と身につきます。
「親が完璧ではなく、試行錯誤している姿」を見せることこそ、子どもにとっての最高の学びです。
「できたことリスト」で自己肯定感を育てる
失敗を受け止める一方で、「できたこと」を言葉にして記録する習慣も、レジリエンスを支える大切な柱です。
人はつい「できなかったこと」ばかりに目が向きがちですが、
1日の中には小さな成功が必ずあります。
たとえば「朝、自分で起きられた」「友だちにあいさつできた」「宿題をあきらめずにやった」――。
こうした“小さな達成”を毎日ひとつずつ書き出すだけで、子どもの心に「自分は成長している」という実感が生まれます。
これは「自己効力感(self-efficacy)」と呼ばれるもので、
「やればできる」「またやってみよう」という前向きな行動を生み出す原動力になります。
親自身のレジリエンスを見せる
子どもは、親の言葉よりも“親の姿”を見ています。
親がストレスにどう向き合っているか、落ち込んだあとどう立ち直るか――その姿を通して、レジリエンスの「モデル」を学びます。
たとえば、仕事でミスをしたときに「もうダメだ」とふさぎこむのではなく、
「失敗しちゃったけど、次はこうしてみる」と前向きに話す。
それだけで、子どもに「失敗=再挑戦のチャンス」という考え方が伝わります。
大人が自分の感情を整え、立て直す姿を見せることで、
子どもは「困っても大丈夫」「生きるって、うまくいかないこともある」と自然に学んでいきます。
家庭でできるレジリエンス・ワーク例
レジリエンスは、難しいトレーニングをしなくても、日常生活の中で育てられます。
以下のようなシンプルなワークを習慣化することで、心の柔軟さを少しずつ強めていけます。
- 「ありがとうノート」:一日の終わりに、感謝したことを家族で一つずつ書く
- 「できたことシェアタイム」:夕食のときに一日の“がんばった瞬間”を話す
- 「もし○○だったらどうする?」:想像の中でトラブル対応を考えるロールプレイ
- 「深呼吸チャレンジ」:怒ったり焦ったりしたときに、5秒間深呼吸して落ち着く練習
これらはどれも、自分の感情に気づき、行動を調整する練習です。
家庭でのこうした小さな習慣が、レジリエンスを支える大きな力になります。
家族全体で“しなやかに生きる文化”をつくる
家庭の空気は、子どもの心の基盤になります。
完璧さや正解を求めるよりも、「失敗してもいい」「人はいつでも変われる」という温かい文化を持つことが何よりの土台です。
親子で笑い合い、時には悩み、支え合う。
そうした日常の中で、子どもは「困難に出会っても自分は大丈夫」と感じられるようになります。
それが、どんな教材よりも強い“生きる力の授業”なのです。
学校でのレジリエンス教育の実践例|安心して挑戦できる教室づくり
学校がレジリエンスを育てる場になるために
子どもが1日の多くを過ごす学校は、学力だけでなく「生きる力」を育てる重要な場所です。
そこでは知識を学ぶだけでなく、仲間と協力し、意見がぶつかり、時には失敗も経験します。
まさにレジリエンスを育てる「実践の場」そのものです。
しかし現実には、学校生活の中で「失敗が怖い」「間違えたら笑われる」と感じている子どもも多くいます。
このような心理的な緊張状態のままでは、挑戦や学びの深まりは生まれにくくなります。
だからこそ今、教育現場では「安心して失敗できる環境づくり」が注目されています。
その基盤となるのが、レジリエンス教育です。
学級経営における「安心・挑戦・承認」の3つの柱
レジリエンスを育む学級経営には、3つの柱があります。
- 安心(Safety)
失敗しても笑われない、間違いを責められない環境をつくること。
たとえば教師が自ら「先生も計算ミスした!」と笑って見せるだけで、教室の空気は柔らかくなります。 - 挑戦(Challenge)
子どもたちが新しいことに挑戦できる場をつくること。
テストや成績だけではなく、「できるようになった過程」や「工夫した行動」を認める文化が大切です。 - 承認(Recognition)
がんばった努力や工夫を認め合うこと。
小さな前進をクラス全体で共有する「よかった探し」などの時間を設けると、自己効力感が高まります。
これらの3要素を日常の学級経営に取り入れることで、
子どもたちは「安心して挑戦し、また立ち上がれる」心の土台を築くことができます。
「失敗を恐れない文化」をつくる授業の工夫
レジリエンス教育の基本は、「失敗=成長のチャンス」という価値観を子どもたちと共有することです。
そのためには、授業の中に“試行錯誤を歓迎する仕掛け”を取り入れることが効果的です。
たとえば理科の実験で予想と違う結果が出たとき、
教師が「失敗だったね」ではなく、「なぜ違ったんだろう?」と問いかける。
その一言で、子どもは「考えること」自体が大切だと感じられるようになります。
また、グループ活動や探究型学習では、子ども同士が支え合いながら問題を解決する経験を重ねます。
互いの意見を尊重し、失敗を共有するプロセスそのものがレジリエンスのトレーニングになるのです。
教師自身のレジリエンスが学級を変える
レジリエンス教育は、子どもに向けた取り組みであると同時に、教師自身の在り方とも深く関係しています。
忙しさやプレッシャーの中で、教師がストレスをため込んでしまうと、教室の雰囲気にもそれが伝わります。
逆に、教師が失敗や課題に向き合う姿勢をオープンにすると、子どもたちは安心します。
「先生も悩むんだ」「うまくいかない日もあるんだ」と感じることで、完璧を求めなくなります。
たとえば、授業でトラブルが起きたときに「次はこうしてみよう」と言葉にして見せるだけでも、
子どもたちにとっては強力な“レジリエンスモデル”になります。
文部科学省も「教師のメンタルヘルス」や「ウェルビーイング教育」を重視する方向に舵を切っており、
レジリエンスは今後の教育現場のキーワードになると考えられています。
授業に取り入れられるレジリエンス教育の実践例
学校現場では、レジリエンスを育てる活動が少しずつ広がっています。
ここでは、すぐに取り入れられる実践例をいくつか紹介します。
- ふりかえりジャーナル
毎日の授業後に「できたこと」「うまくいかなかったこと」「次に挑戦したいこと」を書く活動。
自分の感情や成長を見つめる習慣が生まれます。 - ペアリフレクション(振り返り対話)
隣の席の友だちと1分間ずつ、今日の失敗やうれしかったことを話す。
互いに共感し合うことで、クラスに温かいつながりが生まれます。 - チャレンジカード
「今日の挑戦」「明日の挑戦」をカードに書いて教室に掲示。
挑戦が“可視化”されることで、クラス全体に前向きなムードが広がります。
こうした活動は、特別な時間をとらなくても日常の中で自然にできる取り組みです。
大切なのは、「完璧にやる」ことよりも「挑戦する過程を大切にする」姿勢を持ち続けることです。
探究学習とSTEAM教育が支えるレジリエンス
近年注目されているSTEAM教育(科学・技術・工学・芸術・数学の統合学習)は、
まさにレジリエンスを育てるのに適した学びのスタイルです。
答えが一つに決まらない課題に取り組む中で、
子どもたちは「試してみる」「修正する」「協力する」というプロセスを自然に体験します。
これは、MOANAVIが大切にしている“自己調整学習”そのものです。
探究学習では、結果よりも過程に焦点を当てるため、
「失敗してもいい」「考え続けることが大事」という価値観が根づきます。
この繰り返しが、子どものレジリエンスを深く、確かなものにしていきます。


教室が「安全基地」になるとき
レジリエンスは、安心できる環境の中でしか育ちません。
子どもが「このクラスなら大丈夫」「自分の考えを話してもいい」と思えるとき、
初めて心は自由に伸びていきます。
教師が子どもを信じ、クラス全体で支え合う雰囲気ができたとき、
学校は単なる“学びの場”から“生きる力を育てる場”へと変わります。
その変化こそが、レジリエンス教育の本質です。
子どものレジリエンスを高めるトレーニング法と実践ワーク
レジリエンスは「心の筋トレ」である
レジリエンスは生まれつきの性格ではなく、後天的に育てることができるスキルです。
つまり、体の筋肉と同じように“心にもトレーニング”が必要です。
大切なのは、落ち込んだり失敗したりするたびに「どう立ち直るか」を意識的に練習すること。
そうした繰り返しによって、心のしなやかさが強くなっていきます。
心理学者カレン・ライヘンバーグ博士は、レジリエンスを「跳ね返す力ではなく、状況を受け止めて形を変える力」と表現しています。
つまり、無理に前向きになろうとするのではなく、感情を認めて再構築するプロセスが大切なのです。
感情を「見える化」するトレーニング
子どもがストレスや失敗を感じたとき、多くの場合は「自分でもよくわからない不安」に包まれています。
その“見えない気持ち”を言葉や形にして整理することが、回復への第一歩です。
感情メーター
紙に「うれしい・悲しい・怒り・不安・びっくり」などの感情を描き、
その日の自分の気持ちをシールや色で表すだけの簡単なワークです。
毎日続けると、「あ、今は悲しいんだ」「でも昨日よりはマシ」と気づけるようになります。
これは感情をコントロールする力=自己調整力を高める練習になります。
感情カードで対話する
家庭や学校で「いまどんな気持ち?」と聞いても、言葉にしにくい子どもは多いものです。
カードに「くやしい」「ドキドキ」「ほっとした」などの言葉や顔イラストを書いておき、
選んで見せるだけでも感情を伝える手段になります。
感情を表現できることは、ストレスを軽減し、レジリエンスを高める第一歩です。
ABC理論を使った「考え方のクセ」を整える練習
心理学では、同じ出来事に対して人がどのように感じ、行動するかは“考え方のクセ”によって変わるとされています。
その仕組みを整理するために使われるのが、ABC理論です。
- A(Activating event):出来事
- B(Belief):そのときの考え方・受け止め方
- C(Consequence):結果としての感情・行動
たとえばテストでミスをしたとき、
「A=ミスをした」「B=自分は頭が悪い」「C=もう勉強したくない」
という流れになることがあります。
でも、「B=今回はたまたま間違えた。次は気をつけよう」に変えるだけで、
「C=もう一度やってみよう」という前向きな行動につながります。
子どもと一緒に、「A」「B」「C」を書き出して考えてみるだけでも、
気持ちの整理がしやすくなり、ネガティブな思考を客観的に見られるようになります。
成長マインドセットで「まだできない」を受け入れる
心理学者キャロル・ドゥエックが提唱した「成長マインドセット(growth mindset)」は、
レジリエンスを支える大切な考え方のひとつです。
「自分にはできない」ではなく「まだできない(not yet)」と考える。
この“まだ”の一言が、挑戦する勇気を守る盾になります。
固定マインドセット(できる・できないが決まっている)では、失敗は“恥”になります。
一方、成長マインドセットでは、失敗は“成長の材料”になります。
家庭でも、「がんばったね」「工夫したね」と努力のプロセスをほめることで、
「やれば伸びる」という感覚を育てることができます。
ポジティブ再評価(リフレーミング)の練習
レジリエンスを高めるもう一つの方法が、**リフレーミング(reframing)**です。
これは、出来事を「別の角度から見直す」練習です。
たとえば、
「失敗した」→「新しいやり方を見つけるチャンスだった」
「怒られた」→「もっとよくするために教えてもらえた」
このように、出来事の枠(フレーム)を変えるだけで、感情の方向性がポジティブになります。
家庭では、「じゃあ、違う見方をすると?」と軽く聞くだけでも十分です。
何度も繰り返すことで、自然に柔軟な思考パターンが身につきます。
マインドフルネスで心をリセットする習慣
マインドフルネスとは、「いまこの瞬間に意識を向ける」練習法です。
深呼吸をしながら自分の体や感情を感じ取ることで、ストレスを和らげ、集中力を高めます。
子ども向けには次のような方法が効果的です。
- 「3分間呼吸タイム」:吸う・吐くに集中しながら3分間目を閉じる
- 「気づき散歩」:歩きながら、音・匂い・風などを静かに感じ取る
- 「心の天気予報」:いまの気持ちを「晴れ」「曇り」「雨」で表現する
マインドフルネスは特別な瞑想ではなく、
「一度立ち止まって、自分を感じる」習慣そのものです。
これができると、感情に流されにくくなり、レジリエンスが高まります。
続けるほどに“立ち直る力”は強くなる
レジリエンスのトレーニングに即効性はありません。
しかし、小さな練習をコツコツ続けることで、確実に変化が見えてきます。
落ち込んだときに「前よりも早く立ち直れた」
失敗しても「もう一度やってみようと思えた」
そんな経験の積み重ねこそが、真のレジリエンスを形づくります。
家庭でも学校でも、完璧を目指す必要はありません。
大切なのは、「失敗を恐れない」「挑戦を認める」空気を日常の中につくること。
それが、子どもたちの未来を支える最大の“心の筋トレ”になります。
家庭と学校が連携して育てるレジリエンス|親・教師・地域の協働
子どものレジリエンスは「ひとりでは育たない」
レジリエンスは、子どもの内面に宿る力であると同時に、まわりの人との関係の中で育つ力でもあります。
どんなに強い心を持っていても、支えてくれる大人や仲間がいなければ、その力を発揮し続けることはできません。
心理学では、「レジリエンスの社会的基盤(social support)」という考え方があります。
それは、人とのつながりがストレスを和らげ、回復力を高めるというものです。
つまり、レジリエンスは「個人の力」ではなく、「環境と関係が育てる力」なのです。
だからこそ、家庭・学校・地域がそれぞれの立場から子どもを支え合い、
同じ方向を向いて子どもの“しなやかな心”を育てていくことが欠かせません。
家庭:安心の「拠点」としての役割
家庭は、子どもにとっての**安全基地(secure base)**です。
外で何か失敗しても、「ここに戻れば大丈夫」と感じられる居場所があること。
それが、挑戦へのエネルギーになります。
親が子どもにできる最も大切なサポートは、「解決」よりも「共感」です。
「どうしたの?」ではなく、「つらかったね」「くやしかったね」と気持ちを受け止めること。
これだけで、子どもは心のバランスを取り戻しやすくなります。
また、家庭の中で“レジリエンスを実践する姿”を見せることも効果的です。
親が落ち込んだときに、「今日は失敗したけど、次に生かしたい」と言葉にする。
それが、言葉以上の教育になります。
学校:安心して挑戦できる「社会の縮図」
学校は、子どもにとって初めての“社会”です。
多様な価値観や意見の中で、自分を表現し、協力し、衝突しながら関係を築いていく。
そのすべての経験が、レジリエンスを鍛える学びになります。
教師ができるサポートは、「挑戦を見守る姿勢」と「失敗を肯定する言葉」です。
テストの点数や成果だけでなく、「最後まで取り組めたね」「工夫したところがよかったよ」と過程を認める。
それが、子どもの自己効力感を高め、次の挑戦への意欲につながります。
また、学校全体で「失敗を笑わない文化」「支え合う文化」をつくることも大切です。
学級会やふりかえりの時間などを通して、互いのがんばりを認め合う習慣を根づかせていくことで、
学校全体が“レジリエントなコミュニティ”へと育っていきます。
親と教師が連携することで生まれる「安心の輪」
家庭と学校が同じ方向を向いていれば、子どもは迷わずに前へ進むことができます。
たとえば、家庭で「失敗しても大丈夫」と言っても、学校で「なんでできないの?」と責められれば、
子どもは安心して挑戦することができません。
一方、家庭と学校のメッセージが一致していれば、子どもは安心して自分の力を発揮できます。
そのために必要なのは、“情報共有”と“信頼”です。
保護者が「学校での子どもの様子を知りたい」と関心を持ち、
教師が「家庭での努力や不安」を丁寧に聞く――。
この往復があるだけで、子どもを取り巻く空気は大きく変わります。
保護者会や個別懇談は、単なる報告の場ではなく、レジリエンスを育てる協働の場として機能させたいものです。
地域:多様な大人との出会いが「心の支え」を広げる
子どものレジリエンスを長期的に支えるのは、家庭や学校だけではありません。
地域社会の中で、多様な大人と関わる経験も大きな意味を持ちます。
近所の人にあいさつをしたり、地域のボランティアやイベントに参加したりする中で、
子どもは「自分は誰かに見守られている」「自分の存在には価値がある」と感じます。
これは心理学でいう“関係的自己肯定感”を育てる重要な体験です。
地域の人が子どもに「よく頑張ってるね」「元気だね」と声をかけるだけでも、
それは一種の“レジリエンスサポート”になります。
子どもが多様な人に支えられながら成長する環境を整えることが、社会全体の課題です。
「支え合う文化」を社会全体に
近年、教育現場では「ウェルビーイング(幸福)」や「非認知能力」という言葉が重視されています。
どちらも、レジリエンスと深く関係する概念です。
心が満たされ、安心して挑戦できる社会をつくるためには、
個人の努力だけでなく、周囲の理解と支援のネットワークが欠かせません。
つまり、レジリエンスは“教育のテーマ”であると同時に、“社会のテーマ”でもあります。
大人が互いに支え合う姿を見せることが、次の世代への最大のメッセージになるのです。
子どもの未来を支える「つながりの力」
子どもが困難を乗り越えられるかどうかは、
その子自身の強さだけでなく、「支えてくれる人がいる」という実感にかかっています。
そのために必要なのは、家庭・学校・地域が壁をつくらず、互いに信頼し合うこと。
失敗してもやり直せる。
悩んでも相談できる。
そうした“つながりのある社会”こそが、子どもにとっての最高のレジリエンス教育です。
家庭でできるレジリエンス育成アイデア集
毎日の小さな習慣が「心のしなやかさ」を育てる
レジリエンスを高める特別な教材や訓練は必要ありません。
むしろ、家庭の中でのちょっとした会話や生活習慣が、子どもの心を育てます。
日常の中に“気づき・共感・挑戦”を生み出す工夫を取り入れることで、
子どもは少しずつ「立ち直る力」を身につけていきます。
ここでは、家庭で簡単に実践できるレジリエンス育成のアイデアを紹介します。
どれも時間や特別な準備を必要としない、小さな行動から始められるものばかりです。
「ありがとう探し」|ポジティブ感情を見つける習慣
1日の終わりに、「今日、ありがとうと思ったこと」を家族で一つずつ話し合う時間をつくります。
どんなに小さなことでも構いません。
「お弁当がおいしかった」「宿題を手伝ってもらった」「友だちが声をかけてくれた」など、
“感謝”に目を向けることで、子どもは自然にポジティブな感情を育てていきます。
感謝の言葉を言葉にすることは、心理学的にも幸福感とストレス耐性を高める効果があるとされています。
この習慣を続けるだけで、「つらいことの中にも良い面を見つけられる心」が育ちます。
「できたことノート」|自信を“見える形”にする
寝る前の数分を使って、1日の中で「できたこと」を3つ書き出します。
それは勉強の成果でなくてもOK。
「最後まで片づけた」「あきらめずに説明した」「泣きながらもがんばった」など、
小さな前進を記録していくことが目的です。
ノートを見返したとき、たくさんの「自分はできる」という証拠が積み重なっていることに気づきます。
この体験が、失敗しても立ち直るための自信=レジリエンスの基礎になります。
「もし〜だったら?」トーク|柔軟な思考を育てる
食卓やお風呂などのリラックスタイムに、「もし○○だったらどうする?」という想定トークをしてみましょう。
たとえば――
- もしテストで失敗したら?
- もし友だちとけんかしたら?
- もし誰かが困っていたら?
正解を求めるのではなく、考えること自体を楽しむのがポイントです。
こうした会話を通して、子どもは「状況を想像し、自分で対処法を考える力」を身につけます。
これはまさに、レジリエンスの中核である「問題解決力」を育てる練習です。
「気持ちの天気予報」|感情を表す練習
感情を言葉で表すのが苦手な子どもには、「今日の気分はどんな天気?」と聞く方法が効果的です。
「晴れ」「曇り」「雨」「雷」など、天気にたとえることで、感情を伝えるハードルが下がります。
親も一緒に答えることで、「大人もいろんな気分になる」と伝えられます。
感情を共有する時間を持つことで、子どもは「気持ちは変わっても大丈夫」という安心感を得ます。
「ポジティブ変換ゲーム」|ものの見方を柔らかくする
家族で楽しめるリフレーミング(視点を変える)ゲームです。
たとえば――
- 「宿題が多くていやだ」→「たくさん練習できるチャンス」
- 「雨で遊べない」→「家でのんびりできる時間」
最初は笑いながらで構いません。
大切なのは、物事を“違う角度で見る”練習を繰り返すこと。
この発想の柔軟さが、ストレスに強い心をつくります。
「家族チャレンジデー」|挑戦を称える文化をつくる
月に1回、家族全員が何かひとつ新しいことに挑戦する日を決めます。
それは「新しい料理を作る」「知らない場所に行く」「苦手なことを試す」など、なんでもOK。
成功しても失敗しても、“挑戦したこと自体”を称えるのがポイントです。
終わったあとに「どうだった?」「どんな気持ちだった?」と話し合うことで、
挑戦のプロセスを共有できます。
このような家庭文化が、「挑戦しても大丈夫」「次もやってみよう」という雰囲気を生み出します。
「5秒ルール」|感情を落ち着けるミニトレーニング
怒りや焦りを感じたときに「5秒だけ深呼吸する」――。
このシンプルな習慣が、感情の暴発を防ぎ、冷静に考える力を鍛えます。
特に感情のコントロールが苦手な子どもには、「怒りがきたら5秒吸って、5秒吐く」を一緒に練習するとよいでしょう。
感情をコントロールできる経験を積むことで、「自分の気持ちは自分で扱える」という感覚が生まれます。
それが、ストレスに押しつぶされないための強い心を育てます。
「がんばりを言葉で伝える」文化を家庭に
レジリエンスは、「あなたはちゃんとがんばってるよ」という承認の言葉によっても育ちます。
家庭の中で「ありがとう」「助かった」「よく頑張ったね」と言葉にして伝える習慣を持つだけで、
子どもの安心感と自信がぐんと高まります。
同時に、子どもからの「ありがとう」も受け取るようにしましょう。
双方向の感謝の言葉が飛び交う家庭は、心理的にとてもレジリエントです。
日常の中で「しなやかに生きる練習」を
レジリエンスは、特別な教育ではなく生活そのものの中で育つ力です。
家族で笑い合い、失敗を笑い飛ばし、支え合う。
その積み重ねが、どんな困難にも折れない心をつくります。
子どもが成長していく過程で、すぐに成果が見えない時期もあるでしょう。
けれど、日々のこうした小さな習慣が、やがて「生きる力」として花開くのです。
まとめ|しなやかな心は教えるものではなく、共に育てるもの
「心を強くする」ではなく、「心を柔らかくする」
レジリエンスという言葉を聞くと、「強くなる」「我慢する」というイメージを持つ人も少なくありません。
けれど、本当のレジリエンスとは“硬い心”ではなく、柔らかい心のことです。
外からの衝撃に負けずにしなやかに形を変え、また立ち上がる。
それは、折れない鉄ではなく、風に揺れても根を張る竹のような力です。
この「しなやかさ」は、我慢や根性で得られるものではありません。
安心できる人間関係、認められる経験、自分を見つめる時間――
そうした温かな環境の中で、少しずつ育っていくものです。
レジリエンスは「誰かとつながる力」でもある
レジリエンスというと、個人の“内面的な強さ”だと思われがちですが、
実はその根底にあるのは「人とのつながり」です。
落ち込んだときに話を聞いてくれる人がいる。
挑戦したときに「よくやったね」と認めてくれる人がいる。
困ったときに「一緒に考えよう」と寄り添ってくれる人がいる。
こうした関係の中で、人は何度でも立ち上がることができます。
だからこそ、レジリエンスを育てることは、つながりを育てることでもあるのです。
家庭での対話、学校での支え合い、地域の人とのあいさつ――
それらすべてが、子どもの心を支える見えない糸となります。
失敗を「終わり」ではなく「始まり」に
多くの子どもたちは、失敗を“終わり”の合図だと思っています。
けれど、レジリエンスのある人は、失敗を“新しいスタートライン”として見つめ直すことができます。
「どうしてこうなったんだろう?」
「次は何を変えればいいんだろう?」
そう考える姿勢こそが、成長を生み出す源です。
そしてそれは、子どもだけでなく、大人にも必要な視点です。
親も教師も、完璧ではありません。
うまくいかない日があっていい。悩んでいい。
むしろ、そんな姿を子どもに見せることが、最高のレジリエンス教育になります。
「大人も立ち直る」「誰でもやり直せる」――その現実こそが、子どもへの最大の励ましです。
「安心」と「挑戦」が両立する社会へ
レジリエンスを育てるためには、安心できる環境と、挑戦できる環境の両方が必要です。
安心だけでは成長が止まり、挑戦だけでは心が折れてしまう。
この2つがバランスよく存在することで、人はしなやかに生きられるようになります。
家庭では、感情を受け止め、失敗を責めない空気をつくる。
学校では、努力の過程を認め、挑戦を称える文化を育てる。
地域では、子どもたちのがんばりを温かく見守る。
そうした環境のつながりが、子どもの中に「自分は大丈夫」という感覚を根づかせます。
それが、社会全体のレジリエンスを高めることにもつながるのです。
レジリエンスは「生きる力」そのもの
これからの時代、変化はますます激しくなります。
AI、気候変動、価値観の多様化――どんな未来が来ても、
生きる上でいちばん必要なのは、“もう一度立ち上がる力”です。
その力を持つ人は、失敗を恐れずに挑戦し、他者を責めずに受け止め、
誰かが困っていれば支え合える人です。
レジリエンスとは、単に自分を守る力ではなく、誰かと共に生きる力でもあるのです。
子どもと共に育つレジリエンス
最後に、忘れてはならないことがあります。
それは、**レジリエンスは「子どもに教えるもの」ではなく、「共に育てていくもの」**だということです。
親も教師も、完璧な存在ではありません。
だからこそ、子どもと一緒に悩み、考え、立ち直る。
その姿の中にこそ、本当の教育があります。
「大丈夫、一緒に考えよう」
その一言が、子どもの未来を支える力になります。
そしてそれは、同時に大人自身のレジリエンスを育てる時間でもあります。
私たちが子どもに渡したいのは、「失敗しない方法」ではなく、
**「失敗しても大丈夫な生き方」**です。
それが、これからの時代を生きるすべての子どもたちに贈りたい、
いちばん確かな「心の教育」なのです。
記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)
STEAM教育デザイナー / MOANAVIスクールディレクター
理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。
📚 経歴・資格
✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者
✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)
✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)
✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演
✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説