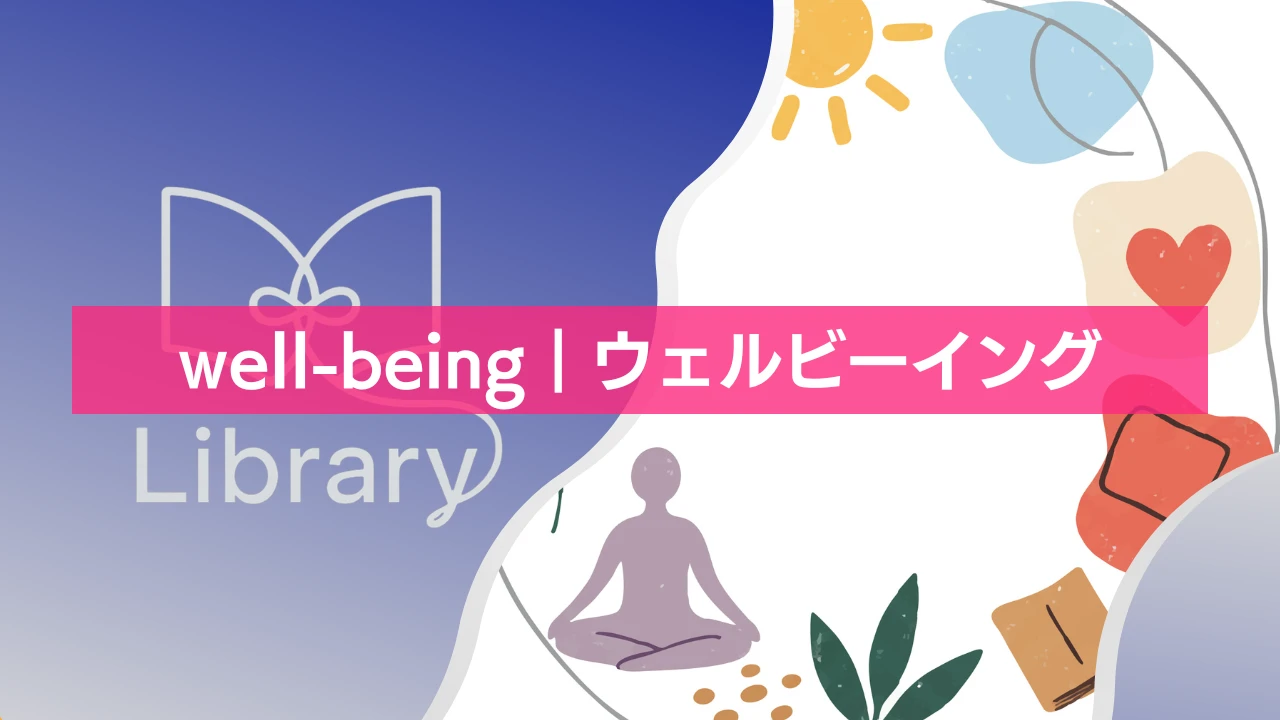
「幸せに生きるって、どういうことだろう?」
そんな問いに答えてくれる言葉が、**well-being(ウェルビーイング)**です。
英語で「well=よく」「being=生きる」という意味をもつこの言葉は、
心・体・社会のバランスがとれた“よい生き方”を表します。
この記事では、well-beingの意味や健康との関係、
「幸せ」とのちがい、教育や社会とのつながりをやさしく解説。
北欧との比較や、家庭でできる実践、自由研究のアイデアまで紹介します。
読めば、**「幸せとは何か」「どう生きたいか」**を自分で考える力が育つはずです。
- well-beingとは?意味をわかりやすく解説|心と体と社会のバランスがとれた“よい生き方”
- 健康とwell-beingの関係とは?|病気でないだけでは「健康」と言えない理由
- 幸せとwell-beingの違いとは?|一時的な喜びと続く満足感のちがい
- 教育におけるwell-beingとは?|勉強よりも「自分らしく生きる力」を育てる
- 社会とwell-beingの関係|GDPでは測れない“人の幸せ”を大切にする時代へ
- 日本と世界のwell-being比較|幸福度ランキングに見る北欧と日本のちがい
- 自分のwell-beingを高める方法|今日からできる小さな幸せの習慣5選
- 家庭のwell-beingを育てる|家族の“安心とつながり”を守るコミュニケーション
- 自由研究で学ぶwell-being|幸せを科学する実験・アンケート・グラフのアイデア
- おさらいクイズ|well-beingの意味・健康・幸福・社会を復習
- まとめ|well-beingは「心の中にある幸せの地図」
well-beingとは?意味をわかりやすく解説|心と体と社会のバランスがとれた“よい生き方”
ニュースや本、学校の資料などで「ウェルビーイング(well-being)」という言葉を見たことはありませんか?
英語で書くと “well-being”。
「well(よく)」+「being(存在する)」を合わせて、
「よく生きている状態」や「心地よく生きること」 を意味します。
日本語ではよく「幸せ」や「健康」と訳されますが、
実はそれだけではありません。
well-beingは、「体の健康」「心の落ち着き」「人とのつながり」など、
心・体・社会の3つのバランスがとれた状態を表しています。
この言葉を広めたのは、世界保健機関(WHO)です。
WHOは「健康とは、単に病気でないことや弱っていないことではなく、
身体的・精神的・社会的に完全に満たされた状態のことである」と定義しました。
つまり、「元気だけど孤独」や「友だちはいるけど心が疲れている」――
そんなときは、健康とは言えないのです。
well-beingは、“ただ生きる”ではなく、“よりよく生きる” ことをめざす考え方です。
たとえば、好きなことを楽しみながら学んだり、
誰かの役に立って「ありがとう」と言われたりする瞬間。
それがまさにwell-beingの状態です。
現代社会では、学校や会社、家庭でもストレスを感じやすく、
「心」や「人間関係」の健康が大きなテーマになっています。
そんな中で、well-beingという言葉は
「点数よりも、心の安心」「競争よりも、共感」
という新しい価値観を広げています。
また、国や企業もこの考え方を大切にしはじめています。
たとえば、社員が安心して働ける環境を整えたり、
地域の人がつながる活動を支援したり――
社会全体が「人の幸福」を中心に動くようになってきているのです。
well-beingとは、「誰かに決められる幸せ」ではなく、
自分の中で感じる“生きる心地よさ”。
そして、その心地よさがまわりの人にも伝わり、
やがて社会全体を温かくしていく――。
それが、この言葉に込められた本当の意味なのです。
クイズ①
「well-being(ウェルビーイング)」の正しい意味はどれでしょう?
- 病気がなく、体が元気な状態
- 心・体・社会のバランスがとれ、安心して生きられる状態
- お金がたくさんあって、ぜいたくに暮らせる状態
正解は 2 です。
👉 well-beingは「健康」だけでなく「心の落ち着き」や「人とのつながり」など、
体・心・社会すべてが満たされた“よい生き方”を指します。
健康とwell-beingの関係とは?|病気でないだけでは「健康」と言えない理由
「健康」と聞くと、多くの人が「病気がない」「ケガをしていない」という状態を思い浮かべます。
でも、それだけでは本当の健康とは言えないのです。
世界保健機関(WHO)は、健康をこう定義しています。
「健康とは、病気がない状態ではなく、
身体的・精神的・社会的に完全に満たされた状態である。」
この考え方は、まさにwell-being(ウェルビーイング)の出発点です。
つまり、体が元気でも、心が疲れていたり、友だちとの関係に悩んでいたりすれば、
それは“本当の健康”とは言えません。
💪 体の健康(身体的 well-being)
体の健康は、バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠などによって守られます。
でも、体が元気でも、ストレスや不安が大きいと体調をくずすこともあります。
たとえば、「テストが近くて眠れない」「友だちとのトラブルでお腹が痛くなる」――
そんな経験がある人もいるのではないでしょうか?
心と体はつながっているのです。
💬 心の健康(精神的 well-being)
心の健康は、「自分を信じる力」「前向きに考える力」などを指します。
失敗しても立ち直る「レジリエンス(回復力)」もその一つです。
自分の気持ちを言葉にしたり、誰かに話を聞いてもらったりすることは、
心の健康を守る大切な方法です。
🧩 社会的健康(social well-being)
人との関係も、健康に深く関係しています。
家族や友だち、先生などとつながりを感じられることは、心の支えになります。
反対に、孤独を感じると心のエネルギーが下がり、やる気が出なくなることもあります。
「ありがとう」「おはよう」と言い合える関係を大切にすることが、
社会的なwell-beingを高める第一歩なのです。
🌿 健康は「つながり」で守られる
この3つ――体・心・社会――がバランスよく保たれている状態こそ、
本当の健康=well-beingといえます。
だから、どれか一つが欠けても、人は生きづらさを感じるのです。
健康とは、体を治すだけでなく、自分とまわりを大切にする生き方そのもの。
そしてそれを支えるのが、well-beingの考え方です。
クイズ②
WHO(世界保健機関)の定義に最も近い「健康」の考え方はどれでしょう?
- 病気やケガがなく、体が元気な状態
- 心と体のどちらかが健康なら問題ない状態
- 体・心・社会の3つが満たされ、安心して生きられる状態
正解は 3 です。
👉 健康とは「病気がないこと」ではなく、「体・心・社会が満たされた状態」。
well-beingはその“バランスのとれた生き方”を目指しています。
幸せとwell-beingの違いとは?|一時的な喜びと続く満足感のちがい
「幸せ」と聞くと、どんなことを思い浮かべますか?
好きなものを食べているとき、テストでいい点をとったとき、ほめられたとき――
そうした瞬間に感じる「うれしい!」「楽しい!」という気持ちも、たしかに幸せです。
でも、**well-being(ウェルビーイング)**はそれとは少しちがいます。
well-beingは、**「一時的な喜び」ではなく、「長く続く心の安定」**を指します。
つまり、たとえ今日少し落ち込むことがあっても、
「明日はきっと大丈夫」「自分には支えてくれる人がいる」と思えるような、
“安心して生きている状態”がwell-beingなのです。
🌞 「快楽の幸福」と「充実の幸福」
心理学では、幸福には2つのタイプがあると言われています。
1つめは、「快楽型の幸福」。
おいしいごはんを食べたり、ゲームで勝ったりするときのような、
短い時間で感じる“うれしさ”です。
もう1つは、「充実型の幸福」。
何かをがんばったあとに感じる「やりきった!」という達成感や、
人の役に立ったときに感じる深い満足感です。
well-beingは、この「充実型の幸福」に近い考え方です。
一瞬の喜びではなく、「生きていてよかった」と思える持続的な幸せを大切にします。
🌱 幸せの感じ方は人それぞれ
同じ出来事でも、幸せを感じるかどうかは人によって違います。
たとえば、テストで80点を取ったとき、
「うれしい!」と思う人もいれば、「あと少しで満点だったのに…」と思う人もいます。
大切なのは、人と比べて決める幸せではなく、自分がどう感じるかです。
自分のペースで、毎日の中にある小さな幸せを見つけることが、
well-beingを高める第一歩になります。
💬 幸せを“点”ではなく“線”で見る
幸せを「点」でとらえると、「今うまくいっている」「今日はつらい」といった波に左右されます。
でも、「線」で見ると、失敗やつまずきも成長の一部として受け止められます。
well-beingは、人生を“点の幸せの集まり”ではなく、
“つながる物語”としてとらえる考え方です。
💡 幸せの本質とは
well-beingとは、「今この瞬間が楽しい」だけでなく、
**「生きていることそのものに意味がある」**と感じる状態。
誰かの役に立てた、感謝された、自分を認められた――
そうした体験が、長く心に残る幸福をつくります。
クイズ③
次のうち、well-being(ウェルビーイング)の考え方にもっとも近いものはどれでしょう?
- 一時的な喜びではなく、心の安定や生きがいが続く状態
- テストでいい点を取ったときのうれしさ
- ごほうびをもらって感じる楽しさ
正解は 1 です。
👉 well-beingは「続く満足感」や「生きる心地よさ」を大切にする考え方。
一瞬の喜びではなく、心の豊かさが続くことがポイントです。
教育におけるwell-beingとは?|勉強よりも「自分らしく生きる力」を育てる
「いい点を取る」「テストで上に行く」――
学校では、どうしても数字で評価される場面が多いですよね。
けれど、本当の学びのゴールは“点数”ではなく、“幸せに生きる力”を育てること。
それこそが、教育における well-being(ウェルビーイング) の考え方です。
🌱 教育の目的が変わりつつある
文部科学省は近年、「ウェルビーイング教育」という言葉を掲げています。
これは、「知識の量」ではなく「生きる力」「人とのつながり」「心の健康」を重視する教育です。
AIやロボットが進化するこれからの社会では、
“知っていること”よりも、“どう感じ、どう考えるか”が求められます。
だからこそ、自分らしく学び、他者と協力し、よりよく生きる力が必要なのです。
💬 「できる」より「感じる」学びへ
たとえば理科の実験で失敗しても、なぜうまくいかなかったかを考えたり、
友だちと協力して再挑戦したりする過程にこそ価値があります。
well-beingの学びとは、結果ではなくプロセスを楽しむ学びです。
「うまくいかなかったけど、次はこうしてみよう!」
そんな前向きな姿勢が、自分の中の幸せを育てていきます。
🤝 学校は「安心して自分でいられる場所」に
well-beingのある学校とは、
「まちがえても大丈夫」「一人ひとりが尊重される」空気がある場所です。
先生に話を聞いてもらえたり、友だちが助けてくれたり――
そうした“安心できる関係”が、心の健康を守ります。
勉強が苦手でも、運動が得意でも、どんな子にも「自分の輝ける場」があること。
それが教育におけるwell-beingの原点です。
💡 「自分らしく生きる」ことが学びのゴール
これからの学校では、知識だけでなく、
「自分は何が好きか」「どんなときに幸せを感じるか」を見つける学びが大切になります。
それは、将来の職業を選ぶときだけでなく、
日々の生活で「どう生きるか」を考える力にもつながります。
教育のwell-beingとは、
「学ぶ=自分を成長させる楽しみ」 だと気づくことなのです。
クイズ④
教育におけるwell-beingの考え方として、正しいものはどれでしょう?
- 勉強の量を増やし、テストの点数を上げることを目指す
- 学びを通して「心の健康」や「自分らしさ」を育てることを大切にする
- 競争に勝ち続けることが、幸せにつながると考える
正解は 2 です。
👉 well-being教育は、知識だけでなく「心の成長」や「安心できる学びの環境」を重視します。
“自分らしく生きる力”を育てることが本当の学びの目的です。
社会とwell-beingの関係|GDPでは測れない“人の幸せ”を大切にする時代へ
「GDPが上がった」「経済が成長した」――
ニュースではよく耳にする言葉ですが、
それが本当に私たちの幸せを表しているとは限りません。
GDP(国内総生産)は、国の経済の大きさを示す数字です。
でも、たとえば誰かが病気になって医療費が増えても、
災害のあとに復旧工事が増えても、GDPは“増加”として計算されます。
つまり、お金の動きは大きくなっても、人の幸せが増えるとは限らないのです。
🌱 GDPでは見えない“心の豊かさ”
「豊かさ」をお金だけで測る時代は終わりつつあります。
どれだけ便利になっても、ストレスが多く、孤独を感じていれば、
本当の意味で豊かとは言えません。
だからこそ今、世界では「well-being(ウェルビーイング)」という
“人の幸せ”を中心に考える社会のものさしが注目されています。
💡 経済と幸福をつなぐ新しい考え方
国連やOECD(経済協力開発機構)は、
「GDPに加えて幸福度を重視する指標を取り入れよう」と動いています。
教育・医療・人間関係・環境などを総合的に評価することで、
「どんな社会が人を幸せにするのか」を見直しているのです。
たとえば、ブータン王国では「国民総幸福量(GNH)」という独自の指標を導入し、
お金よりも“心の豊かさ”を国づくりの中心にしています。
🤝 企業や自治体も「人の幸せ」を重視
日本でも、企業が「ウェルビーイング経営」を始めています。
働く人の健康を守り、休みやすい制度をつくることが、
結果的に仕事の質を上げ、社会全体を元気にする――
そんな動きが広がっているのです。
また、自治体では地域のつながりを強めたり、
子どもから高齢者まで安心して暮らせるまちづくりを進めたりしています。
🌏 社会全体の目標は「幸せの循環」へ
経済だけでなく、人と人の関係や心の健康を育てる社会へ。
それがwell-being社会の目指す姿です。
「豊かに暮らす」とは、お金を持つことではなく、
お互いを思いやり、支え合うこと。
小さな幸せがつながることで、
社会全体があたたかくなる――
そんな未来を、世界中の国々が目指しています。
クイズ⑤
GDPだけでは測れない「社会の豊かさ」を考えるときに、
注目されている考え方はどれでしょう?
- well-being(ウェルビーイング)
- エネルギー効率
- 為替レート
正解は 1 です。
👉 well-beingは、「お金の大きさ」ではなく「人の幸せ」を重視する新しい社会の指標。
世界中で“幸福の質”を大切にする動きが広がっています。
日本と世界のwell-being比較|幸福度ランキングに見る北欧と日本のちがい
「世界でいちばん幸せな国はどこ?」
この質問に答えるヒントとなるのが、**「世界幸福度ランキング」**です。
これは国連が毎年発表しているもので、
「人々がどれくらい幸せだと感じているか」を、
データにもとづいて世界の国々で比べたものです。
🌿 世界の上位は北欧諸国
最近のランキングでは、フィンランド・デンマーク・アイスランドなどの北欧の国々が上位に並びます。
寒い地域なのに、どうして幸福度が高いのでしょう?
その理由のひとつは、**「人と社会の信頼」**です。
北欧では、政治や教育、医療などへの信頼が高く、
「困ったときはお互いさま」という文化が根づいています。
子どもからお年寄りまで、安心して生活できる仕組みが整っているのです。
💡 教育と福祉がwell-beingを支える
北欧の国々では、教育や医療がほぼ無料で受けられます。
また、仕事と家庭を両立できるように、
育児休暇や働き方の制度がしっかり整っています。
お金の多さではなく、
**「誰もが自分らしく生きられる社会」**が幸福度を高めているのです。
🇯🇵 日本の幸福度が低めな理由
一方で、日本は毎年ランキングの40位前後にとどまっています。
これは、経済的には豊かでも、
「人とのつながり」や「休息の時間」が不足していることが大きな要因とされています。
長時間労働、競争の激しさ、
「がんばらなきゃ」と思いすぎる文化が、
心のwell-beingを下げてしまっているのです。
ただし、日本にも独自の良さがあります。
四季を感じる文化や、相手を思いやる礼儀、
自然や伝統を大切にする心は、
**「静かな幸福(quiet happiness)」**と呼ばれ、
世界から注目されています。
🌏 幸福の形は一つではない
北欧のように「制度で守られる幸せ」もあれば、
日本のように「日常の中で感じる幸せ」もあります。
大切なのは、“どちらが上か”ではなく、
自分たちに合ったwell-beingの形を見つけること。
数字で測れない温かさの中にも、
たしかな幸せがあるのです。
クイズ⑥
世界幸福度ランキングで上位に入る国の特徴として、
最も当てはまるものはどれでしょう?
- 経済的に豊かで競争が激しい国
- 人とのつながりが少なく、個人主義が強い国
- 教育や医療が充実し、人々の信頼が高い国
正解は 3 です。
👉 フィンランドやデンマークなどの北欧諸国は、
教育・福祉・信頼のバランスがとれた社会を実現しています。
人が安心して暮らせることが、well-beingを支えています。
自分のwell-beingを高める方法|今日からできる小さな幸せの習慣5選
well-being(ウェルビーイング)は、特別な人だけのものではありません。
どんな人でも、小さな工夫の積み重ねで“幸せを感じやすい心”を育てることができるのです。
ここでは、毎日の生活の中でできる「5つの習慣」を紹介します。
① 睡眠・食事・運動のリズムをととのえる
基本的なことに思えるけれど、実はとても大切です。
夜ふかしが続いたり、朝ごはんを抜いたりすると、
心も体もバランスをくずしやすくなります。
「早寝・早起き・朝ごはん」は、心の健康を守る第一歩です。
1日のリズムを整えると、不思議と気持ちも前向きになります。
② 「ありがとう」を言葉にする
人に感謝の気持ちを伝えると、自分の気持ちも温かくなります。
「言う側」も「言われる側」も幸せになる魔法の言葉――それが「ありがとう」です。
心理学の研究でも、「感謝を口にする人ほど幸福度が高い」という結果が出ています。
家族・友だち・先生、どんな相手にも「ありがとう」を伝えてみましょう。
③ 自分や他人を比べすぎない
SNSなどを見ていると、
「自分はあの人よりダメかも…」と感じることがあるかもしれません。
でも、幸せは人と比べるものではなく、自分の中で感じるものです。
昨日の自分より少し前に進めたら、それだけで十分。
“自分ペースの幸せ”を大切にしましょう。
④ 自分の「好き」を少しずつふやす
好きな音楽を聴く、好きな本を読む、好きな人と話す――
そんな時間が増えると、心のエネルギーが回復します。
「好き」は、自分らしさをつくる大切な要素です。
宿題や仕事の合間にも、“自分が心地よくなれる時間”を少し入れてみましょう。
⑤ 困ったら誰かに話す勇気をもつ
悩みをひとりで抱えこむと、心の中に“もやもや”がたまります。
誰かに話すだけでも、気持ちは軽くなるもの。
家族・友だち・先生――あなたを支えてくれる人は必ずいます。
話すことは弱さではなく、well-beingを守るための“強さ”なのです。
💬 ちいさな行動が「心の健康」を育てる
well-beingを高めるコツは、
「がんばる」よりも「気づく」こと。
今日の自分の気持ちを少しだけ観察して、
「今、どんなことに幸せを感じたかな?」と考えてみましょう。
幸せは遠くにあるものではなく、日常の中にひっそりと隠れています。
クイズ⑦
自分のwell-beingを高めるために、もっとも大切な考え方はどれでしょう?
- ほかの人と比べて、勝つことを目指す
- 小さな幸せや感謝を日常の中で見つける
- 幸せはお金や物の多さで決まる
正解は 2 です。
👉 well-beingは「小さな感謝」「自分の好きなこと」「つながり」から生まれます。
毎日の中で幸せを“見つける力”を育てることが大切です。
家庭のwell-beingを育てる|家族の“安心とつながり”を守るコミュニケーション
well-being(ウェルビーイング)は、学校や社会だけでなく、
家庭の中からも育てることができます。
家は、勉強や仕事で疲れた心を休める場所。
同時に、「自分はここにいていい」と思える“安心のよりどころ”でもあります。
家庭のwell-beingを高めるカギは、**「安心」と「つながり」**にあります。
🌿 「おかえり」「ただいま」から始まる幸福
何気ないあいさつや会話には、家族のつながりを感じる力があります。
「おかえり」「ただいま」「いってらっしゃい」「おやすみ」――
このような言葉を交わすことで、
「自分は受け入れられている」と感じることができます。
言葉は小さいけれど、心を支える大きな力になるのです。
💬 「今日よかったこと」を話してみよう
1日の終わりに、「今日うれしかったこと」を家族で話す習慣をつくってみましょう。
「お昼の給食がおいしかった」「友だちにありがとうを言われた」など、
どんなに小さなことでもOK。
感謝やうれしさを共有すると、家庭の空気がふんわりと明るくなります。
ポジティブな会話は、well-beingを自然に育てます。
📱 スマホやテレビを“ちょっと休む”時間を
家族が集まっていても、それぞれがスマホを見ていると、
「一緒にいるのに孤独」という状態になってしまいます。
夕食のときだけでもデジタル機器を置き、
目を合わせて話す時間をつくってみましょう。
会話は「心の運動」です。
話す・聞く・笑うことが、家族の幸福度をぐんと上げてくれます。
🌸 「がんばりすぎない家族」でいい
家庭のwell-beingを高めるうえで大切なのは、
完璧を求めすぎないことです。
「今日は疲れたね」「ムリしなくていいよ」と声をかけ合うだけで、
心が軽くなります。
家族みんなが“がんばらない日”を持つことは、
well-beingを守る大切な習慣です。
💡 家族のwell-beingが社会を支える
家庭の中に安心と笑顔があれば、
子どもも大人も外の世界で前向きに行動できます。
家族の幸福は、社会全体の幸福につながっているのです。
「家の中があたたかい」――それこそが、
well-being社会のいちばん小さな出発点なのです。
クイズ⑧
家庭のwell-beingを高めるために、もっとも大切なことはどれでしょう?
- あいさつや会話など、家族のつながりを大切にする
- 家族全員が完ぺきに同じ生活リズムで過ごす
- 家族それぞれが黙ってスマホを見る時間を増やす
正解は 1 です。
👉 家族のあいさつや会話、感謝の言葉は「安心の土台」。
小さな声かけが、家庭のwell-beingを育てる大きな力になります。
自由研究で学ぶwell-being|幸せを科学する実験・アンケート・グラフのアイデア
well-being(ウェルビーイング)は、「心の健康」や「幸せ」をテーマにした、
今、世界中で注目されている考え方です。
じつはこのテーマ、自由研究にもぴったりなんです。
「人が幸せを感じるのはどんなとき?」「心の健康を保つには?」――
こうした身近な疑問を、自分で調べ、データでまとめることができます。
🌱 ① アンケートで「幸せを感じる瞬間」を調べよう
家族や友だち、クラスの人などに、
「どんなときに幸せを感じますか?」と質問してみましょう。
選択肢をつけるとまとめやすくなります。
例:
- おいしいごはんを食べたとき
- 友だちと遊んだとき
- ありがとうと言われたとき
- ゆっくり休めたとき
結果を円グラフにすると、人によって“幸せの形”がちがうことが一目で分かります。
さらに、男女や年齢での違いを比べてもおもしろいですよ。
💬 ② 自分の「1日しあわせグラフ」をつくってみよう
1日の中で、どんな時間にどんな気分だったかをメモして、
時間ごとにグラフにしてみましょう。
例:
- 朝ごはん→😊(楽しい)
- 授業→😐(ふつう)
- 友だちと話す→😄(うれしい)
- 宿題→😣(たいへん)
グラフにすると、「どんなことが自分のwell-beingを上げてくれるか」や、
「どんなときに疲れやすいか」が見えてきます。
それをもとに、**“自分らしい一日の過ごし方”**を考えるのも良い研究になります。
📊 ③ 世界と日本の幸福度を比べよう
国連の「世界幸福度ランキング」を調べて、
日本と上位の国(フィンランド・デンマークなど)を比べてみましょう。
- GDP(経済の豊かさ)
- 教育や医療の制度
- 人々の信頼やつながり
など、どの要素が幸福度に関係しているかをまとめると、
「数字では測れない幸せのちがい」が分かります。
💡 ④ 「ありがとう」の力を調べる実験
数日間、「ありがとう」を多く使った日と、
あまり言わなかった日を比べて、
「気分」や「周りとの関係」にどんな変化があったかを記録します。
自分自身の気持ちの変化を観察する、小さな心理学実験です。
🪶 ⑤ 研究のまとめ方のポイント
- グラフ・表・メモを多く使う
- 結果だけでなく「気づき」や「感想」を書く
- 「人によって幸せの形がちがう」という結論で締めくくる
✨ まとめ
well-beingの自由研究では、正解を探すよりも、
「自分と周りの人の幸せ」を見つめ直すことがいちばん大切です。
身近な人たちと協力して調べれば、
研究そのものがすでにwell-beingな時間になります。
おさらいクイズ|well-beingの意味・健康・幸福・社会を復習
ここまでの記事で学んだ「well-being(ウェルビーイング)」について、
どれくらい覚えているかな?
心・体・社会のつながりをもう一度ふり返ってみよう!
クイズ①
well-being(ウェルビーイング)とは、どんな状態を表す言葉でしょう?
- 病気がないだけの健康な状態
- 心・体・社会のバランスがとれ、安心して生きられる状態
- お金がたくさんあってぜいたくに暮らせる状態
正解は 2 です。
👉 well-beingは「心・体・社会」が満たされている“よい生き方”のこと。
健康や幸せを広く含む考え方です。
クイズ②
WHO(世界保健機関)の「健康」の定義として、正しいものはどれでしょう?
- 体に病気がなく、元気で動ける状態
- 身体的・精神的・社会的に完全に満たされた状態
- 体が強く、運動ができる状態
正解は 2 です。
👉 健康とは「病気がないこと」ではなく、
心も社会もふくめて満たされた状態を指します。
クイズ③
well-beingと「幸せ」のちがいを正しく表しているのはどれ?
- 一時的な喜びではなく、続く安心感や生きがいを重視する
- 幸せはお金の量で決まると考える
- 喜びや楽しさだけを求める生き方をすすめる
正解は 1 です。
👉 well-beingは「うれしい!」という瞬間の幸福よりも、
“生きる心地よさ”や“持続的な安心”を大切にします。
クイズ④
社会の中でwell-beingが注目されている理由として、もっとも近いものはどれ?
- GDP(経済の大きさ)より、人の幸せを重視する動きが広がっているから
- お金を使わないと幸せを感じられない人が増えたから
- 経済の発展を止めるために新しい指標をつくったから
正解は 1 です。
👉 世界では、GDPでは測れない“人の幸福”を大切にする社会づくりが進んでいます。
クイズ⑤
自分のwell-beingを高めるために、最もよい行動はどれ?
- SNSでほかの人と自分をくらべる
- 小さな感謝やうれしい出来事を見つける
- ずっと一人でがんばり続ける
正解は 2 です。
👉 well-beingは「ありがとう」「うれしい」「楽しい」といった
小さな幸せを意識することで高まります。
🌈 ふりかえりメッセージ
well-beingは、特別な人だけのものではありません。
一人ひとりが「自分らしく」「安心して」「つながって」生きること。
それが、心と社会の幸せをつくるいちばんの力です。
まとめ|well-beingは「心の中にある幸せの地図」
well-being(ウェルビーイング)とは、
お金や成績のように数字で測れるものではなく、
**「自分がどんなふうに生きたいか」を指し示す“心の地図”**のようなものです。
それは、体が健康であることだけでなく、
心が落ち着き、人とのつながりを感じながら生きられる状態のこと。
“よく生きる”とは、何かを完ぺきにこなすことではなく、
日々の中で自分らしい幸せを見つけていくことなのです。
学校での学び、家庭での会話、社会とのかかわり――
そのどれもがwell-beingをつくる大切なピース。
「うれしい」「ありがとう」「助けてくれてうれしい」――
そうした小さな言葉や気持ちが集まって、
心の中に自分だけの“幸せの地図”が広がっていきます。
そしてその地図は、まわりの人とも重なり合いながら、
社会全体をあたたかくしていきます。
well-beingとは、自分の幸せと、他の人の幸せを同じように大切にする生き方。
その小さな一歩が、未来の豊かな世界をつくっていくのです。
📚 学びの本棚から、次の1冊を
このテーマに関連する教材・読み物を、本棚を眺めるように探せます。
→ MOANAVI Library をひらく
この記事を書いた人
西田 俊章(MOANAVIスクールディレクター/STEAM教育デザイナー)
公立小学校で20年以上、先生として子どもたちを指導し、教科書の執筆も担当しました。
現在はMOANAVIを運営し、子どもたちが「科学・言語・人間・創造」をテーマに学ぶ場をデザインしています。



