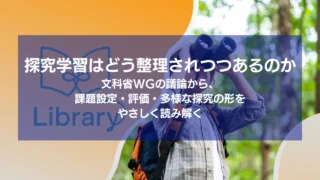【夏休み、家庭学習が進まない…】
子どもが“やる気”になる5つの工夫と親の関わり方
「せっかくの夏休み、少しは勉強してほしい…」「声をかけても全然やる気にならない」
そんな悩みを抱える保護者の方も多いのではないでしょうか?
本記事では、教育心理学や子どもの発達理論をもとに、子どもが“自分から学ぶようになる”ための5つの工夫をご紹介します。
がんばってほしい気持ちが空回りする前に、親の関わり方を少し見直してみませんか?
1.スケジュールは「自分で決める」から効果がある
親が決めたスケジュールでは子どもは動きません。大切なのは、“自分で決めた”という実感です。
教育心理学では、子どもが行動に主体性を感じると、意欲が高まりやすいことが示されています(Deci & Ryanの自己決定理論より)。
✅ 工夫の例:
- 「今日やることリスト」を一緒に書き、そこから子どもに3つ選ばせる
- 「朝のうちに1つ終わらせておくと午後がラク」など、タイミングも子どもに決めさせる
📣 声かけ例:
「どれからやる?好きな順でいいよ」
「今日はどれを終わらせておきたい?」
2.学びは“机の上”だけじゃない。関心を育てる工夫を
「勉強しなさい」と言うよりも、まずは子どもの“なんで?”に寄り添うことが大切です。
教育学者ブルーナーは、学習のスタートは“意味のある経験”であるべきだと述べています。
✅ 活動例:
- 料理やお菓子作りで分量・時間・理科の要素を扱う
- 自然体験(虫取り、星の観察)を通して記録や調べ学習へつなげる
- 好きなテーマを調べて「ミニ自由研究」にする
📣 声かけ例:
「これって理科で出てくるやつじゃない?」
「あとで図鑑で調べてみようか!」
3.「できたこと」より「がんばった過程」を見つけて声をかける
子どもは、行動を認められるとやる気になります。成果ばかりを褒めると、完璧主義やプレッシャーにつながることもあります。
教育心理学者キャロル・ドゥエックの研究では、「努力や工夫を認められた子どもほど、学びへの姿勢が前向きになる」とされています。
✅ 工夫の例:
- 終わった量よりも、集中していた時間や工夫の方法に注目する
- 間違えた時こそ、「気づけたことがすごい」と声をかける
📣 声かけ例:
「今日、自分から始めてたの気づいたよ」
「最後までやろうとしてたの、よかったね」
4.学びやすい環境を“整える”だけで集中力は変わる
子どもは音や光、周囲の気配にとても敏感です。
静かで整理された空間は、学習への集中を高めます。これは学習環境デザインの研究でも明らかになっています(Barrett et al., 2015)。
✅ 環境の整え方:
- テレビやスマホの音が入らない、決まった「学習スポット」を作る
- タイマーを使って「15分集中→5分休憩」のリズムを作る
- 「勉強コーナー」を親子で一緒に整えてモチベーションアップ
5.家庭だけでがんばろうとしない。「外の学び場」も活用を
夏休みは親子の距離が近くなるぶん、摩擦も起きやすくなります。
無理に家庭内だけで完結させず、外の場や人の力に頼ることも必要です。
✅ こんな方法があります:
- 図書館・自習室など、「やる気になる場所」に出かけてみる
- 近所の学習イベントやワークショップに参加する
- 教室や塾、フリースクールなど、家庭以外の選択肢も検討する
学び方はひとつじゃない。子どもに合った「続く学び」を
子どもが「やらない」「進まない」の裏には、必ず理由があります。
大切なのは、「やる気がない」と決めつけるのではなく、その子に合った学び方や関わり方を見つけていくことです。
MOANAVIでは、子ども一人ひとりの“やってみたい気持ち”を大切にしながら、
自分のペースで学びに向かえる環境づくりを行っています。
✔️ 夏休みの学びに悩んだら、まずは一度ご相談ください。
無料体験・見学も受付中です。
記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)
STEAM教育デザイナー / 株式会社MOANAVI代表取締役
理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。
📚 経歴・資格
✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者
✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)
✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)
✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演
✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説