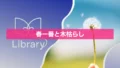買い物をするとついてくる「消費税」。でも、そのお金はどこへ行くのでしょう?
学校や道路、病院など、わたしたちのくらしを支える多くのものは、
みんなが出し合う「税金」で成り立っています。
この記事では、税金の意味と使い道、
そしてニュースでもよく耳にする「増税」「減税」が何を意味するのかを、
やさしく解説します。
最後には自由研究に使えるアイデアも紹介!
身の回りの社会を“お金の流れ”から見つめてみましょう。
税金とは?|意味と仕組みをわかりやすく解説
私たちが毎日あたりまえに使っている道や橋、学校や図書館、病院や消防車。
これらを動かすためのお金は、いったいどこから来ているのでしょう?
その答えが――**「税金(ぜいきん)」**です。
税金とは、みんなが少しずつお金を出し合って、
国や地域の社会を動かすための「みんなの共同のお財布」です。
たとえば学校の教科書は無料で配られますが、その印刷代や送料も税金から出ています。
道路を直したり、病院で救急車を使ったり、警察や消防が活動したりできるのも、
みんなが払った税金があるからこそ。
つまり税金は、**社会を支えるための“みんなの力”**なのです。
税金は「払わされるお金」ではなく、
「よりよい社会をつくるために出し合うお金」。
もし税金がなくなったら――
道路がこわれても直せず、先生やお医者さんにお給料も払えなくなり、
私たちのくらしはあっという間に困ってしまいます。
税金には、国に払うもの(国税)と、市区町村や県に払うもの(地方税)があります。
国税は、国が行う事業(教育、防衛、社会保障など)に、
地方税は、地域の道路整備やゴミ収集などに使われます。
それぞれが連携しながら、「みんなのくらし」を守る仕組みをつくっているのです。
また、税金にはいろいろな種類があります。
お店で買い物をしたときに払う「消費税」、
働いて得たお金にかかる「所得税」、
会社がもうけた分にかかる「法人税」などです。
これらが合わさって、国の大切な収入源になります。
そして、税金を集めて使う仕組みの中心にあるのが「国の予算」です。
国は、集まった税金をどの分野にどれだけ使うかを毎年決めています。
この「お金の流れ」が、社会全体の動きを生み出しているのです。
税金を理解することは、社会の仕組みを知ること。
そして「自分も社会の一員である」という実感につながります。
クイズ①
次のうち、税金の説明として正しいものはどれでしょう?
- 国が自由に使うためのお金
- みんなで社会を支えるために出し合うお金
- 企業だけが払う特別なお金
正解は 2 です。👉
税金は、国民みんなで社会を動かすために出し合うお金。
学校、道路、病院など、わたしたちの生活の中に広く使われています。
税金の使い道を図解で解説|社会を支える5つの分野と身近な例
みんなが払った税金は、どこで、どのように使われているのでしょうか?
税金の使い道を大きく分けると、5つの分野があります。
それは「社会保障」「教育」「防衛」「公共事業」「地方交付金」です。
🏥 ① 社会保障(しゃかいほしょう)
病気やけがをしたとき、だれでも病院に行けるのは健康保険のおかげ。
また、高齢者の年金や介護のしくみも、税金が支えています。
社会保障は「すべての人が安心して暮らせる社会」をつくるための大切な使い道です。
🏫 ② 教育
小学校や中学校の先生のお給料、教科書、学校の建物の修理や冷暖房など、
子どもたちの学びを支えるお金も税金でまかなわれています。
みんなが安心して勉強できるようにすることは、国の未来への投資でもあります。
🛡 ③ 防衛(ぼうえい)
日本を守るための自衛隊の活動費や、災害時の支援などにも税金が使われています。
地震や台風が起きたときに被害を減らすための対策費も、
国民の安全を守る「防衛」の一部です。
🚧 ④ 公共事業(こうきょうじぎょう)
道路・橋・上下水道・公園など、みんなが使うものを整備するお金です。
信号機を直したり、新しい橋をつくったりするのも公共事業の仕事。
これらは「社会のインフラ(基盤)」を維持するために欠かせません。
🏙 ⑤ 地方交付金(ちほうこうふきん)
国全体の税金の一部を、地方(県や市区町村)に分けるお金です。
地域によって人口や税収に差があるため、全国どこでも同じように暮らせるよう、
国が「分け合う仕組み」として税金を配分しています。
このように税金は、私たちのくらしのすみずみにまで関わっています。
学校の廊下の電気、バス停の屋根、図書館の本棚――
普段は意識していなくても、「見えないところで税金が働いている」んですね。
国は毎年、これらの分野にどれくらいのお金を使うかを「予算」として決めています。
たとえば社会保障には多くの予算が使われ、
少子高齢化が進む今では、その割合が年々増えています。
一方で、教育や防災なども国の未来を支える重要な投資です。
税金の使い方を知ることは、「社会の優先順位」を知ることでもあります。
どんなことに力を入れるかで、国の未来の形が変わっていくのです。
クイズ②
次のうち、税金が使われていない分野はどれでしょう?
- 学校の建物を建てるお金
- 病院の医療費を助けるお金
- コンビニの商品を仕入れるお金
正解は 3 です。👉
コンビニの商品を仕入れるのはお店の仕事で、税金ではありません。
学校・病院・道路など、「みんなで使うもの」に税金は使われています。
国の予算と税金の関係|国のお金の“入口と出口”を見てみよう
国のしくみは、ひとことで言うと「お金の流れ」で動いています。
国のお金には「入口(収入)」と「出口(支出)」があり、
この両方のバランスが取れていることが、社会を安定させるカギになります。
まず、「入口」――それが 税金 です。
国の収入の約6〜7割は、私たちが払う税金によってまかなわれています。
代表的なのは「所得税」「消費税」「法人税」。
所得税は働いて得たお金から、消費税は買い物をしたときに、
法人税は会社がもうけた利益から、それぞれ納められます。
このように、国には毎年たくさんのお金が集まりますが、
同時に「出口」となる支出も大きいのが現実です。
国の支出は、主に「社会保障」「教育」「防衛」「公共事業」「地方交付金」などに分かれ、
それぞれが国民の生活を支えています。
たとえば、2025年度の日本の一般会計予算はおよそ112兆円。
そのうち社会保障費が約3分の1を占め、年金・医療・介護などに使われます。
教育・科学分野、防災・防衛、インフラ整備なども欠かせません。
つまり国は、集めたお金を「どこに、どれくらい」使うかを
慎重に計画しているのです。
ただし、ここで問題になるのが、税金だけでは足りないという現実。
支出が収入を上回るとき、国は「国債(こくさい)」という借金をして足りない分を補います。
この仕組みを「財政赤字(ざいせいあかじ)」と呼びます。
赤字が続くと、将来の世代に負担がかかるため、
政府は「どのくらい税金を集めるか」「どの分野に使うか」を常に調整しているのです。
このように、税金は「ただ集められるだけ」ではなく、
国全体の経済をコントロールする重要なスイッチでもあります。
景気が悪くなったときには減税や公共事業を行い、
景気が過熱しすぎたときには増税してバランスを取ることもあります。
つまり、税金の流れを知ることは、
「国の経済がどう動いているか」を知ることでもあるのです。
クイズ③
次のうち、国が借金(国債)をしてまでお金を使う理由として最も正しいものはどれでしょう?
- 政府がもっとぜいたくをしたいから
- 国民のくらしを守るために足りない分をまかなうため
- 企業が税金を払いたくないから
正解は 2 です。👉
国は、税金だけでは足りないときに国債を発行してお金を集めます。
そのお金は、災害対策や医療・教育など、国民の生活を支えるために使われています。
増税と減税のしくみ|景気とつながる政府の経済コントロール
税金の使い道を考えるときに、もうひとつ大事なのが「どのくらい集めるか」という問題です。
この集める量を変えること――それが 増税(ぞうぜい) と 減税(げんぜい) です。
「増税」は、税金の額を上げること。
「減税」は、税金の額を下げること。
単純に聞くと「減税のほうがうれしい」と思うかもしれませんが、
実はどちらも社会にとって大切な意味があります。
💰 増税のねらい:社会を支えるための財源を確保
国や地域は、教育、医療、年金、防災などに多くのお金を使っています。
しかし、人口が減り高齢者が増えると、支出はどんどん増えていきます。
そのときに必要になるのが「増税」。
税収(国に入るお金)を増やして、国の財政を安定させるのが目的です。
ただし、増税すると私たちの手元に残るお金が減り、
買い物をひかえる人が増えるため、景気が悪くなることもあります。
🛍 減税のねらい:景気を回復させるための“刺激”
反対に「減税」は、国があえて税金を少なくして、
人々が使えるお金を増やし、買い物や投資を活発にする政策です。
景気が悪く、経済が冷えこんでいるときに行われることが多く、
「消費税の引き下げ」「所得税の減額」「給付金」などがその一例です。
一時的に国の収入は減りますが、人々の消費が増えることで、
結果的に経済全体が元気になることをねらっています。
⚖️ どちらが正しい? それは“状況しだい”
増税も減税も、どちらか一方が正しいわけではありません。
大切なのは、「今、どんな社会の状態なのか」を見て判断することです。
たとえば、災害復興や高齢化が進むときには増税が必要かもしれません。
一方で、景気が落ちこんでいるときには減税で支えることが大切です。
このように政府は、税金を通して景気の流れをコントロールしています。
それを「財政政策(ざいせいせいさく)」と呼びます。
みんなの暮らしを安定させるために、
政府は毎年の予算や経済の動きを見ながら、このバランスを取っているのです。
税金は、集めすぎても、集めなさすぎても、社会がうまく回りません。
だからこそ、「増税」「減税」を考えることは、
「わたしたちの社会をどう支えるか」を考えることでもあります。
この章で学んだことをもとに、次の章では
自分で調べてみる「税金の自由研究アイデア」を紹介します。
自由研究に使える!税金の使い方・増税と減税の調べ学習アイデア集
税金は、わたしたちのくらしを支える大切なお金。
けれども「どんなふうに使われているの?」「増税や減税で何が変わるの?」など、
くわしく知る機会はあまりありません。
そこで、税金をテーマにした自由研究に挑戦してみましょう!
身の回りの社会を調べることで、経済や政治がぐっと身近に感じられます。
💡 アイデア①:わたしたちのまちの税金の使い道を調べよう
まずは、自分の住んでいる市や町のホームページを見てみましょう。
「予算」「財政」などのページには、税金がどんなことに使われているかが書かれています。
たとえば、公園の整備、道路の補修、図書館の運営、学校の改修など。
気づかないところで税金が活躍していることがわかります。
グラフや円チャートにまとめると、発表でもわかりやすくなります。
💰 アイデア②:国の予算をグラフにしてみよう
国の税金の使い道を、財務省の「予算の使い道」サイトなどで調べてみましょう。
社会保障・教育・防衛・公共事業など、どの分野にどのくらい使われているかを
グラフや色分け表にまとめてみます。
「どの分野に一番お金がかかっているのか?」を考えると、
国が今どんなことを大切にしているかが見えてきます。
🔄 アイデア③:増税・減税のシミュレーションをしてみよう
もし消費税が1%上がったら、家族の1か月の支出はどう変わる?
もし逆に1%下がったら、どれくらいお金が残る?
おこづかいやおうちの買い物を例に計算してみると、
税金の変化がくらしにどんな影響を与えるかが実感できます。
「増税と減税、どちらが社会にとってよいか」を自分の考えでまとめてみましょう。
🧮 アイデア④:税金の“ありがとうマップ”を作ろう
自分のまちや学校の中で、「税金が使われているもの」を探してみましょう。
たとえば、通学路の街灯、信号機、給食センター、公園の遊具など。
地図にマークをつけて“税金のありがとうマップ”を作ると、
目に見えない税金のはたらきが見えてきます。
写真を撮ってスライドにすれば、発表資料としても使えます。
🌏 発展アイデア:世界の税金の使い方と比べてみよう
日本と外国では、税金の使い方や割合が少しずつ違います。
たとえば北欧の国では、税金は高いけれど教育や医療がすべて無料。
アメリカでは税金が低めで、その分は自分で保険や教育費を払う仕組みです。
「税金の高さ=幸せ」ではなく、どんな社会を目指しているかを考えることが大切です。
自由研究のテーマとして税金を選ぶと、
「お金の流れ」だけでなく、「社会をどう支えるか」という深い学びにつながります。
調べて、まとめて、考えてみる。
それが、未来の社会をつくる第一歩です。
おさらいクイズ|税金の役割と増税・減税のちがいを確認しよう
ここまで学んだ「税金のしくみ」や「増税・減税の考え方」をおさらいしましょう!
3問すべて正解できたら、あなたはもう“税金マスター”です💰✨
クイズ①
税金のいちばんの目的として正しいものはどれでしょう?
- 国民が自分のために使うお金を貯めるため
- 社会を支えるために、みんなでお金を出し合うこと
- 企業のもうけを増やすため
正解は 2 です。👉
税金は、国や地域の公共サービス(教育・福祉・防災など)を支えるお金。
みんなで出し合って、社会全体を支えるために使われます。
クイズ②
次のうち、税金が使われていないものはどれでしょう?
- 学校の教科書の印刷代
- 公園のベンチの設置費用
- スーパーの商品を仕入れるお金
正解は 3 です。👉
スーパーの商品を仕入れるのはお店の費用。
税金は「みんなで使う場所」や「公共サービス」に使われています。
クイズ③
増税と減税の関係について正しく説明しているのはどれでしょう?
- 増税は景気を良くするために行われる
- 減税は国の収入を増やすために行われる
- 増税は国の財政を安定させ、減税は景気を回復させるために使われる
正解は 3 です。👉
増税は国の支出をまかなうための安定策、
減税は経済を元気にするための刺激策。
どちらも状況に合わせて使い分けることが大切です。
まとめ|税金を知ることは社会を考える第一歩
税金は、わたしたちのくらしを見えないところで支えている大切なお金です。
学校、病院、道路、消防、図書館――そのどれもが税金で動いています。
税金のことを学ぶと、社会のしくみが少しずつ見えてきます。
「お金を取られる」ではなく、「みんなで社会を支えるために出し合う」もの。
そう考えると、税金は“ありがとうのお金”にも感じられます。
そして、増税や減税はただのニュースではなく、
わたしたちの生活や未来に関わる大切なテーマです。
「どうすればよりよい社会をつくれるか」――
その答えを探す第一歩が、“税金を知ること”なのです。
📚 学びの本棚から、次の1冊を
このテーマに関連する教材・読み物を、本棚を眺めるように探せます。
→ MOANAVI Library をひらく
この記事を書いた人
西田 俊章(MOANAVIスクールディレクター/STEAM教育デザイナー)
公立小学校で20年以上、先生として子どもたちを指導し、教科書の執筆も担当しました。
現在はMOANAVIを運営し、子どもたちが「科学・言語・人間・創造」をテーマに学ぶ場をデザインしています。