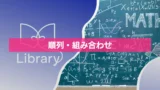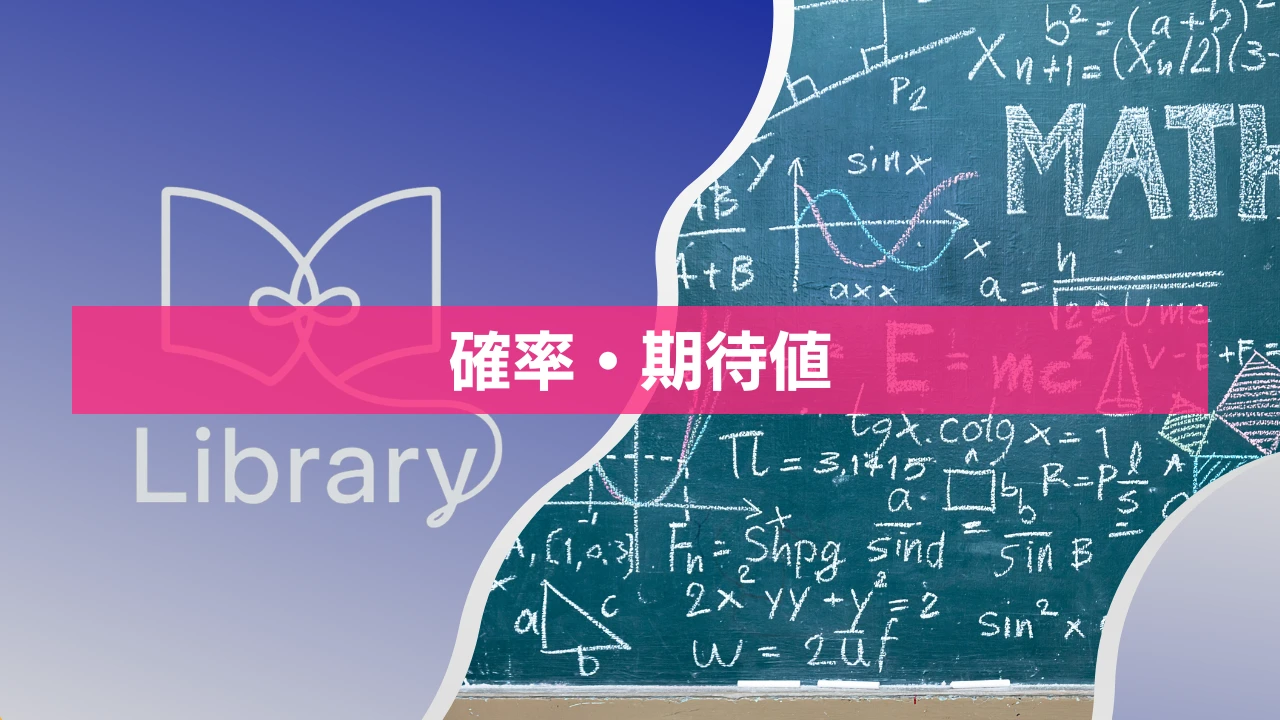
「サイコロをふったら“1”が出る確率はどれくらい?」「くじを引いたら当たる確率は?」
そんな“運まかせ”のように見える出来事も、実は数学で説明できるって知っていましたか?
この記事では、確率と期待値の基本をやさしく解説します。
確率は「あることが起こるかもしれない“可能性”」、
期待値は「たくさんくり返したときに出てくる“平均的な結果”」を表す考え方です。
サイコロ・コイン・ガチャ・天気予報など、
身近な例を使いながら「運を科学する」方法を学んでいきましょう。
自由研究や授業の発展学習にも使える、実験アイデアやクイズつき!
前回の記事「順列・組み合わせ|並べ方と選び方のちがいをやさしく解説」と合わせて読むと、
確率の計算がさらにスッキリ理解できます。
確率とは?|「起こりやすさ」を数であらわす考え方をやさしく解説
たとえば、サイコロをふったときに「1」が出ること、
コインを投げたときに「表」が出ること、
友だちとジャンケンをしたときに「勝つこと」——
こうした出来事はどれも「起こるかもしれない」ことですよね。
このような“起こりやすさ”を数であらわしたものが、**確率(probability)**です。
確率は「ある結果がどれくらい起こりそうか」を、
0〜1までの数(または0%〜100%)で表します。
- 起こらないこと → 確率 0(0%)
- 必ず起こること → 確率 1(100%)
- 半分の確率で起こること → 0.5(50%)
つまり、確率とは“運”を数で説明する数学のことばなのです。
🎲 サイコロの例で考えてみよう
サイコロの目は 1・2・3・4・5・6 の6種類。
1つの目が出る確率は、**「1/6(約16.7%)」**です。
この「1/6」は、
「6通りの結果の中から、望む結果(1の目)が1通りある」
という意味。
このように、確率は
確率 =(望む結果の数)÷(全体の結果の数)
という式で求められます。
☁️「運まかせ」ではなく「考える数学」
確率を学ぶと、
「ラッキー」や「偶然」を“数で整理して考える力”がつきます。
たとえば天気予報で「明日の雨の確率は70%」と聞いたとき、
これは「10日間で同じような条件があれば、7日は雨が降るかもしれない」
という意味になります。
未来のことをまったく予測できないわけではなく、
たくさんのデータをもとに「起こりやすさ」を考える力が確率なのです。
💡 確率の考え方はどんなときに役立つ?
- サイコロやくじ引きなど、ゲームのしくみを理解できる
- 天気・交通・スポーツなど、予測に基づいた判断ができる
- 「なんとなく」ではなく、数字で考える習慣が身につく
こうした力は、これからの時代に欠かせない「論理的思考」の土台になります。
🔢 クイズ①
次のうち、「確率」を正しく説明しているのはどれでしょう?
- 必ず起こることを数であらわしたもの
- 起こるかもしれないことの“起こりやすさ”を数であらわしたもの
- 偶然にまかせて結果を決めること
正解は 2 です。
👉 確率は、「起こるかもしれないこと」の起こりやすさを数で表したもの。
“運”を数字で考えるのが、確率の出発点です。
サイコロ・コイン・くじ引きで確率を学ぼう|基本の求め方と考え方
確率を学ぶいちばんの近道は、「身近なもので実際に考えてみること」です。
ここでは、サイコロ・コイン・くじ引きという3つの例を使って、
確率の基本的な求め方と考え方をわかりやすく整理していきましょう。
🎲 サイコロの確率を考えよう
サイコロには 1〜6 の6つの目があります。
どの目も出る可能性は同じです。
たとえば「1」が出る確率は、
1/6(約16.7%)。
式で書くと、
確率 = 望む結果の数 ÷ 全体の結果の数
→ 1 ÷ 6 = 1/6
同じように「偶数が出る確率」を考えると、
偶数は 2・4・6 の3通り。
全体6通りのうち3通りだから、
**3/6=1/2(50%)**になります。
つまり、確率は「すべての結果を同じ条件でならべて考える」ことで求められるのです。
🪙 コインの確率はどうなる?
コインを1回投げると、「表」と「裏」が1回ずつ出る可能性があります。
「表」が出る確率は、
1 ÷ 2 = 1/2(50%)
とてもシンプルですね。
2回、3回と投げていくと、「2回連続で表」「1回だけ裏」など、
組み合わせが増えていきます。
このときに役立つのが、前回学んだ順列・組み合わせの考え方です。
👉 並べ方と選び方のちがいをおさらいしたい人は、
順列・組み合わせ|並べ方と選び方のちがいをやさしく解説
もチェックしてみましょう。
🎯 くじ引きの確率を考えよう
10本のくじのうち、当たりが1本だけ入っているとき、
「当たる確率」はどうなるでしょう?
確率 = 当たり(1) ÷ 全体(10) = 1/10(10%)
10人が1回ずつ引くなら、みんなが同じ確率で“当たる可能性”を持っていることになります。
もし1人が2回引けるなら、
確率は少し変わりますよね?
このように「条件」を変えることで、確率はさまざまに変化します。
🧠 確率を考える3つのポイント
- 全体の結果を数える(6通り、2通り、10通りなど)
- 望む結果の数を見つける(「1の目」「表」「当たり」など)
- 割り算で整理する(望む結果 ÷ 全体)
この3ステップを使えば、どんな確率問題も落ち着いて考えられます。
🔢 クイズ②
サイコロを2個ふったとき、出る目の合計が「7」になる確率はどれでしょう?
- 1/12
- 1/6
- 1/36
正解は 2 の「1/6」です。
👉 合計が7になる組み合わせは、(1,6)(2,5)(3,4)(4,3)(5,2)(6,1)の6通り。
全部で36通りあるので、6÷36=1/6 になります。
確率の計算と「順列・組み合わせ」|前の記事とあわせて理解しよう
ここまでで、確率は
「望む結果の数」 ÷ 「全体の結果の数」
で求められることを学びました。
では、その「結果の数」をどうやって数えればよいのでしょうか?
このとき役立つのが、前回の記事で学んだ 順列(並べ方) と 組み合わせ(選び方) です。
🔢 「場合の数」を整理することが、確率の第一歩
確率の計算では、まず「全体が何通りあるか」を考えます。
これを 全事象(ぜんじしょう) といいます。
たとえば、3人の中から2人を選ぶ場合、
全体の通り数は 組み合わせ の考え方で求められます。
つまり、「3人の中から2人を選ぶ方法」は3通り。
ここで「誰を選ぶか」がわかれば、確率を出す準備が整います。
🎲 「全体」と「望む結果」の両方を数える
たとえば、5人の中から2人をえらんで「ペアを作る」場面を考えてみましょう。
全体の通り数(すべてのペア)は:
\[ {}_5C_2 = \frac{5!}{2!(5-2)!} = 10 \]この10通りの中で、もし「特定の2人(AさんとBさん)」がペアになる確率を知りたいなら、
望む結果は1通り、全体は10通りなので、
1 ÷ 10 = 1/10
となります。
つまり、**確率は「組み合わせの中の1つを選ぶ割合」**でもあるのです。
🔁 「順列」と「組み合わせ」の使い分けを思い出そう
- 順列:順番を考える(例:1位・2位・3位を決める)
- 組み合わせ:順番を考えない(例:5人の中から2人を選ぶ)
確率では「順番を考えるかどうか」で使う公式が変わります。
もし「順番が大事な抽選」なら順列、
「誰が選ばれても同じ」なら組み合わせです。
🧩 「確率=比の考え方」を意識しよう
確率は、いくつかの結果を比で表す考え方です。
たとえば、赤いボール3個・青いボール2個の袋から1個を引くなら、
赤を引く確率 = 3 ÷ (3+2) = 3/5(60%)
ここでも順列や組み合わせの発想で「全体の通り数」を整理できます。
順番を考えなくても、「全体を数える力」が大事なのです。
🔢 クイズ③
5人の中から2人を選んでチームを作ります。
そのとき、特定のペア(AさんとBさん)が同じチームになる確率は?
- 1/5
- 1/10
- 2/5
正解は 2 の「1/10」です。
👉 5人から2人を選ぶ組み合わせは全部で10通り。
そのうち1通りが「AとB」なので、確率=1/10になります。
期待値とは?|「平均的にどうなるか」を考える数学の発想
「サイコロをふったとき、出る目の合計はだいたいどのくらい?」
「くじを引いたら、どのくらい当たると思う?」
そんな“だいたい”を数字で考えるのが、**期待値(きたいち)**です。
期待値とは、たくさんの結果を平均して「1回あたりどんな結果が出るか」を表す数学の考え方です。
🎲 サイコロの例で考える「期待値」
サイコロの目は 1〜6 の6通り。
1回だけでは何が出るかわかりませんが、100回、1000回とふっていくと、
だんだん「平均的な結果」が見えてきます。
すべての目の合計を平均すると、
\[ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) \div 6 = 3.5 \]この3.5が、サイコロ1回の期待値です。
もちろんサイコロには「3.5の目」はありませんが、
「たくさんふったときの平均が3.5になる」という意味なのです。
🪙 コインでも考えてみよう
コインを投げたとき、「表」が出たら1点、「裏」は0点と決めるとします。
このときの期待値は次のように計算できます。
つまり、1回コインを投げたときの期待値は 0.5点。
10回投げれば平均5回は表が出る、という考え方につながります。
これは「確率 × 結果の値」で求める期待値の基本式です。
📊 「期待値」と「確率」のちがい
- 確率:ある結果が「どれくらい起こりやすいか」
- 期待値:たくさんくり返したときの「平均的な結果」
つまり、確率は「チャンスの大きさ」、
期待値は「結果の見込み」を示す数値です。
ガチャやくじ引きのように、「当たる確率」と「当たったときの得点・賞品」を合わせて考えるとき、
期待値の考え方が役立ちます。
💡 実生活でも「期待値」は使われている
- 天気予報:「降水確率70%」は、10回中7回雨が降るという“期待”
- スポーツ:成功率を上げるための戦略
- AIやデータ分析:未来を予測するモデルの基本
つまり、期待値とは“運を平均で見つめるレンズ”なのです。
🔢 クイズ④
サイコロを1回ふったときの「出る目の期待値」はどれでしょう?
- 3
- 3.5
- 4
正解は 2 の「3.5」です。
👉 サイコロの1〜6の目の平均値は3.5。
1回では出ない数字でも、「たくさんふった平均」として表されます。
日常にある確率と期待値の活用例|身近な“データの見方”を学ぼう
確率や期待値は、ただの数字の勉強ではありません。
実は、私たちの生活のあらゆる場面で使われています。
「当たる・外れる」「成功・失敗」などの結果を数で整理することで、
未来を予測したり、よりよい判断をしたりできるようになるのです。
🎯 ガチャ・くじ引き・ゲームの確率
スマホゲームやお祭りのくじ引きには、必ず「当たる確率」があります。
たとえば、レアキャラが1%の確率で出るガチャを100回引くと、
1回あたりの期待値は1体×1%=0.01体。
つまり、平均すると100回に1回は当たる計算です。
でも、100回引いても出ない人がいるのはなぜでしょう?
それは「確率」は“起こりやすさ”であり、必ずそうなるとは限らないからです。
だからこそ確率は「運を数字でとらえる」力なのです。
☀️ 天気予報やニュースにある確率
「明日の降水確率は70%」という言葉も、まさに確率です。
これは「同じ条件の日が10回あったら、7回は雨が降る」という意味。
「70%なら絶対に雨」ではなく、「7割の確率で雨が起こりそう」という予測なのです。
同じように、地震の発生確率や交通渋滞の予測、感染症の流行なども、
確率や統計の考え方で分析されています。
確率を学ぶと「ニュースを数字で読み解く力」も身につきます。
⚙️ スポーツ・AI・データ分析にも確率の発想
スポーツの世界では、選手がどんな作戦をとるかも「成功確率」をもとに判断しています。
たとえばサッカーのPKでは、ゴールの左右どちらに蹴るかを「確率」で読み合っています。
また、AI(人工知能)は「確率的に最も正しい答え」を選び出すしくみです。
AIが天気を予測したり、写真を認識したりできるのも、
確率と期待値の計算をくり返して「正解に近い判断」をしているからなのです。
💡 確率・期待値の考え方が役立つ場面
- ゲームの結果を冷静に分析できる
- データを見て「たまたま」ではなく「傾向」で考えられる
- 感情ではなく数字で判断できるようになる
このように、確率と思考力は「情報の時代を生きる知恵」にもなっています。
🔢 クイズ⑤
「50%の確率で当たるくじ」を2回引きます。
1回も当たらない確率はどれでしょう?
- 50%
- 25%
- 0%
正解は 2 の「25%」です。
👉 1回当たらない確率が0.5(50%)なので、
2回連続で外れる確率は 0.5×0.5=0.25(25%)。
つまり、確率を使えば「思っているより起こりにくい・起こりやすい」が見えてくるのです。
自由研究に使えるアイデア|確率を“見える化”する実験をしよう
確率や期待値の学びを、実際の実験で確かめてみましょう。
机の上で考えるだけでなく、自分の手を使ってデータを集めると、
「確率って本当にそうなるのかな?」という疑問が、ワクワクする探究に変わります。
🎲 実験① サイコロを100回ふって「1」が出る回数を調べよう
サイコロの1の目が出る確率は 1/6(約16.7%)。
では、実際に100回ふってみるとどうなるでしょう?
- 出た目をノートに記録する
- 「1」が出た回数を数える
- 予想(16〜17回前後)と比べる
もし「1」が15回出たなら、確率は15/100=0.15(15%)。
理論値の1/6にかなり近いですね。
このように、実験をくり返すほど結果が平均値に近づくことを確かめられます。
これを**「大数の法則」**といいます。
🪙 実験② コインを100回投げて「表」が出る確率をグラフに
コインの表が出る確率は 1/2(50%)。
100回投げて表の回数を記録し、棒グラフにしてみましょう。
1回目・2回目・3回目……とくり返していくうちに、
結果が少しずつ「50%」に近づいていくのが見えるはずです。
これも確率の「平均的なふるまい」が目で見える実験です。
グラフ化することで、自由研究の完成度がぐっと上がります。
⚪ 実験③ くじ引き・ガチャを再現して確率を体験
紙コップや箱を使って、手作りの「くじ引き実験」もおすすめです。
- 紙に「当たり」を1枚、「はずれ」を9枚書いて10枚を混ぜる
- 1回引いたら結果を記録し、戻す or 戻さないで確率を比較
「戻さない」と確率が少しずつ変化します。
これが「条件付き確率」の考え方につながります。
ガチャのような確率イベントを再現して、
“期待値”がどう変わるかを考察してもおもしろいですね。
🧠 実験のまとめ方ポイント
- 仮説を立てる:「◯回に1回は出るはず」など予想を書く
- データを集める:表に整理(出た目・回数など)
- グラフにする:割合や変化が一目でわかるように
- 考察する:「理論値とどれくらい近かったか」
- 自由研究タイトル例:「本当に“1/6”になるのか?サイコロ100回実験」
このように、確率を“見える化”することで、
数字の裏にある「規則」や「ゆらぎ」を実感できます。
おさらいクイズ|確率と期待値の考え方をふりかえろう
ここまで学んできた「確率」と「期待値」。
どちらも“未来を考える数学”ですが、
違いをきちんと整理すると、数字を使って考える力がぐんと高まります。
ここでは、これまでのクイズを少し並べかえて復習してみましょう。
順番を変えてあるので、もう一度じっくり考えてみてください。
クイズ①
サイコロを1回ふったとき、出る目の期待値はいくつでしょう?
- 3
- 3.5
- 4
正解は 2 の「3.5」です。
👉 サイコロの6つの目の平均値(1+2+3+4+5+6)÷6=3.5。
「1回では出ないけど、たくさんやれば平均は3.5になる」という意味ですね。
クイズ②
次のうち、「確率」を正しく表しているのはどれでしょう?
- 起こるかもしれないことの“起こりやすさ”を数で表したもの
- 絶対に起こることを数で表したもの
- 結果を予測せずに運まかせにすること
正解は 1 です。
👉 確率は“起こるかもしれないこと”を0〜1(または0〜100%)の数で考えます。
クイズ③
5人の中から2人を選んでチームを作ります。
AさんとBさんが同じチームになる確率は?
- 1/5
- 1/10
- 2/5
正解は 2 の「1/10」です。
👉 5人から2人を選ぶ組み合わせは全部で10通り。
そのうち1通りが「AとB」なので確率=1/10になります。
クイズ④
「50%の確率で当たるくじ」を2回引いたとき、1回も当たらない確率は?
- 50%
- 25%
- 0%
正解は 2 の「25%」です。
👉 1回外れる確率が0.5(50%)なので、2回続けて外れる確率は 0.5×0.5=0.25(25%)。
クイズ⑤
「確率」と「期待値」のちがいを正しく説明しているのはどれ?
- 確率は“起こりやすさ”、期待値は“平均的な結果”を表す
- 確率は“平均”、期待値は“回数”を表す
- どちらも同じ意味で使われる
正解は 1 です。
👉 確率=“どれくらい起こるか”、期待値=“どんな結果が平均的に起こるか”。
似ているようで、実はちがう視点の考え方です。
🧠 ふりかえりまとめ
| キーワード | 意味・考え方 |
|---|---|
| 確率 | 「起こりやすさ」を0〜1の数で表す |
| 期待値 | 「たくさんの結果の平均」を数で表す |
| 組み合わせ | 「順番を考えない」選び方 |
| 順列 | 「順番を考える」並べ方 |
| 関係性 | 確率は「場合の数」で成り立ち、期待値は「確率×結果」で成り立つ |
「確率」と「期待値」は、どちらも“未来を予測するための数学”です。
数字を「運」ではなく「ルール」で考えること。
それが、考える力を育てる第一歩です。
まとめ|“運を科学する”思考で未来を予測しよう
確率や期待値は、いわば「運を科学する」ための数学です。
「たまたま」「偶然」で片づけてしまいがちな出来事も、
確率の目で見れば、“どれくらい起こりやすいか”を数字で説明できます。
さらに、期待値を使えば、“たくさんくり返したときの平均的な結果”を予測することもできます。
このように、確率と思考力を身につけると、
ゲームの結果、天気の変化、ニュースのデータなど、
身の回りの出来事を数字で考えられるようになります。
「なんとなく」ではなく、「論理的に」未来を見通す力が育つのです。
確率・期待値の考え方は、AIやデータ分析など、
これからの社会を支える分野にもつながっています。
数字の裏にある“法則”を見つける目を養い、
学びを次のテーマへとつなげていきましょう。
📚 学びの本棚から、次の1冊を
このテーマに関連する教材・読み物を、本棚を眺めるように探せます。
→ MOANAVI Library をひらく
この記事を書いた人
西田 俊章(MOANAVIスクールディレクター/STEAM教育デザイナー)
公立小学校で20年以上、先生として子どもたちを指導し、教科書の執筆も担当しました。
現在はMOANAVIを運営し、子どもたちが「科学・言語・人間・創造」をテーマに学ぶ場をデザインしています。