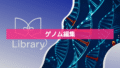あなたが食べているレタスやハーブ、
その中には「太陽の光を浴びて育ったもの」だけでなく、
“工場の中”で育った野菜もあることを知っていますか?
「えっ? 野菜を工場で?」――
そう、不思議に聞こえるかもしれません。
でも、**植物工場(しょくぶつこうじょう)**は、
今、世界中で注目されている“未来の農業”なんです。
植物工場では、太陽のかわりにLEDライトを使い、
温度や水をコンピュータでコントロールしながら、
一年中おいしい野菜を育てることができます。
台風や猛暑にも負けず、農薬を使わない安心な食べ物を作れるため、
食料問題や地球温暖化の解決にも役立つといわれています。
この記事では、
植物工場のしくみ・メリット・世界の例・AIとの連携・SDGsとの関係を、
小学生にもわかる言葉でやさしく解説します。
最後には自由研究のアイデアやクイズもついているので、
楽しく学びながら「未来の食」について考えてみましょう! 🌱
植物工場とは?天気や季節に左右されない“室内の畑”
みなさんは「植物工場」という言葉を聞いたことがありますか?
工場というと、車や家電をつくる場所を思い浮かべるかもしれません。
でも「植物工場」は、野菜や果物を育てるための工場なんです。
普通の畑では、植物は太陽の光と土と水で育ちます。
でも、天気や気温、季節に左右されるため、
台風や猛暑があると、収穫がうまくいかないこともあります。
そこで考え出されたのが、室内で環境をコントロールして植物を育てる方法――それが「植物工場」です。
太陽のかわりにLEDライトで光をあて、
土のかわりに**水や養液(ようえき)**を使い、
温度や湿度をコンピュータで管理します。
これなら、雨の日でも雪の日でも、まるで一年中“春”のような環境で野菜を育てることができます。
🌿 なぜ「工場」と呼ばれるの?
「工場」と呼ばれる理由は、植物を同じ条件で計画的に育てられるからです。
たとえば、1日目に芽が出て、5日目に葉がのび、15日目に収穫――。
まるで機械のように生育をコントロールできるのです。
このように「自然のリズム」ではなく、「人の科学の力」で育てる農業を
**“人工環境型農業”**といいます。
植物工場では、光・水・空気のすべてが「数値」で管理されるため、
同じ品質の野菜を何度でも生産できるのです。
🍅 どんなときに役立つの?
植物工場の最大の強みは、天候や気候に左右されないことです。
大雨や猛暑、寒波などが続いても、野菜を安定して育てられるため、
災害時の食料確保にも役立ちます。
また、虫が入らない清潔な環境なので、農薬を使わずに安心して食べられる野菜をつくることができます。
さらに、街の中のビルや地下など、畑がない場所でも作れるため、
食料を「地産地消(ちさんちしょう)」――つまり、地域で作って地域で食べることができるのです。
🌎 食料問題と地球環境のカギに
世界では、人口がどんどん増えており、
「将来、食料が足りなくなるかもしれない」と言われています。
植物工場は、そんな未来の食料問題を解決するための新しい農業として注目されています。
また、水の使用量を減らせることや、土地を傷つけない点でも、
**地球環境にやさしい“未来の畑”**といえるでしょう。
クイズ①
植物工場が「未来の農業」として注目されている理由として、正しいのはどれでしょう?
- 虫が入らないように完全に暗い部屋で育てるから
- 天気や季節に関係なく、計画的に野菜を育てられるから
- ロボットが全部自動で料理してくれるから
正解は 2 です。
👉 植物工場では、光・水・温度などをコントロールすることで、一年中安定して野菜を作ることができます。
どうやって育つの?光・水・空気をコントロールするしくみ
植物工場では、太陽・土・雨といった自然の力の代わりに、
科学の力で植物を育てるしくみを使っています。
つまり、光・水・空気・温度といった条件を人の手でコントロールすることで、
いつでも同じように野菜を育てられるのです。
💡 光合成を支える「人工の太陽」=LEDライト
植物が成長するには、「光合成」が欠かせません。
光合成とは、光のエネルギーを使って、二酸化炭素と水から栄養(でんぷんなど)を作るはたらきのこと。
植物工場では、太陽のかわりにLEDライトを使ってこの光を与えます。
LEDライトの色にも意味があります。
- 赤い光は、花や実をつける力を強める。
- 青い光は、葉や茎を丈夫にする。
この2色をバランスよく当てることで、植物が元気に育つように調整できるのです。
つまり、LEDは“人工の太陽”として、光の強さも時間も自由にコントロールできます。
💧 土のかわりに「水と養液」で育てる
植物工場の多くは、**水耕栽培(すいこうさいばい)**という方法を使っています。
これは、土を使わず、水にとかした養分(ようえき)を根から吸わせる栽培方法です。
水耕栽培のよいところは――
- 根がいつもきれいな水に触れていて病気になりにくい。
- 水をくり返し使えるので、水の節約になる。
- 虫がつきにくく、農薬がいらない。
さらに、AIやセンサーが水の量や養分の濃さを測って、
植物がちょうどいい環境を保てるように自動で調整しています。
🌬 温度・湿度・二酸化炭素も「数字で管理」
自然の畑では、気温が高すぎたり低すぎたりすると、植物はうまく育ちません。
でも植物工場では、部屋の中の温度・湿度・二酸化炭素の量をコンピュータで常にチェックしています。
たとえば、
- 気温が下がったら自動でヒーターがON
- 湿度が高すぎたら除湿機が作動
- 光合成に必要なCO₂(にさんかたんそ)を少しずつ追加
このように「環境を数字でコントロール」することで、
自然の気まぐれに左右されず、毎日同じ条件で植物を育てられるのです。
🤖 AIとIoTが支える“スマート農業”
最新の植物工場では、AI(人工知能)とIoT(モノのインターネット)が活やくしています。
AIは植物の成長データを分析し、
「今日は少し水が足りない」「光を強めよう」といった判断を自動で行います。
これにより、人間がいなくても野菜を見守れる“スマート農業”が実現しているのです。
クイズ②
植物工場でLEDライトを使う理由として、正しいものはどれでしょう?
- 見た目をきれいにするため
- 光の色や強さをコントロールして光合成を助けるため
- 電気をたくさん使うため
正解は 2 です。
👉 植物は光合成で育つため、植物工場ではLEDの赤と青の光を使って成長をコントロールしています。
植物工場のメリットとデメリットをくらべてみよう
植物工場は、「未来の農業」として世界中で注目されています。
でも、いいところ(メリット)ばかりではなく、課題(デメリット)もあります。
ここでは、両方の面をしっかり見比べながら、
“ほんとうに持続可能(じぞくかのう)な農業とは何か”を考えてみましょう。
🌞 メリット① 天気や季節に左右されずに育てられる
一番のメリットは、安定した生産ができることです。
外の畑では、台風や猛暑、寒波があると野菜が育たないことがありますが、
植物工場では室内の環境をコントロールできるため、
一年中、計画的に同じ野菜を作り続けられます。
これにより、スーパーに並ぶ野菜の価格も安定し、
「野菜が高くて買えない」という時期が減ります。
まさに、**食卓を支える“見えないヒーロー”**なのです。
🥬 メリット② 清潔・安全・安心な野菜が作れる
植物工場は、虫やほこりが入らないクリーンな部屋の中で野菜を育てます。
そのため、農薬を使わずに育てられるのが大きな特徴です。
農薬が減れば、環境への負担も軽くなり、
小さな子どもからお年寄りまで安心して食べられる“やさしい食”になります。
また、工場内では水もくり返し使えるため、
普通の畑に比べて約90%も節水できると言われています。
限られた水資源を大切にできることも、環境面での強みです。
⚡ デメリット① 電気代が高く、コストがかかる
植物工場には弱点もあります。
最大の課題は、電気をたくさん使うことです。
太陽の代わりにLEDライトを照らし、
冷暖房や湿度調整、AI管理などにも電力が必要です。
このため、電気代が高くなり、野菜の生産コストも上がってしまいます。
最近は、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを組み合わせて、
より省エネで運営できるよう改良が進められています。
💰 デメリット② 作れる種類が限られている
植物工場で育てられるのは、今のところ**葉もの野菜(レタス・ほうれん草など)**が中心です。
トマトやイチゴも作られていますが、
根菜(じゃがいも・にんじんなど)や大きな果物はまだ難しいのが現状です。
それでも、研究が進めば、
「植物工場で米を作る」「花を咲かせる」などの未来も夢ではありません。
⚖️ メリットとデメリットのバランスを考えよう
植物工場は、「環境にやさしい農業」としての可能性を持ちながらも、
エネルギー問題という新しい課題を抱えています。
つまり、自然の畑より便利でも、電気を使いすぎたら意味がないのです。
科学技術の力と環境への配慮――。
その両方を両立させることが、これからの時代の大きなテーマです。
クイズ③
植物工場のメリットとして正しいものはどれでしょう?
- 天気に左右されず、計画的に野菜を育てられる
- 農薬を多く使って虫を減らす
- どんな野菜でもかんたんに作れる
正解は 1 です。
👉 植物工場では、温度・光・水をコントロールできるため、天候に関係なく安定した生産ができます。
実際にどんな野菜を作っている?日本と世界の植物工場
植物工場と聞くと、なんだか未来の話のように感じるかもしれません。
でも、じつはすでに日本や世界のあちこちで“現実の技術”として動いています。
あなたがスーパーで見かけるあのレタス、
もしかしたら植物工場で作られたものかもしれませんよ。
🥬 日本の植物工場 ―「街の中の畑」が広がっている
日本では、特にレタスやベビーリーフ、ほうれん草、バジルなどの葉もの野菜が多く育てられています。
これらの野菜は軽くて育つのが早く、工場の中で管理しやすいためです。
たとえば、京都にある企業「スプレッド(SPREAD)」は、
1日に約3万株のレタスを自動で育てる世界最大級の植物工場を運営しています。
ベルトコンベアのように流れてくる苗をロボットが管理し、
LEDやセンサーで環境を最適化。
人の手をほとんど使わずに大量の野菜を生産しているのです。
また、東京や大阪では、高層ビルの中に“屋内農園”をつくる動きもあります。
オフィスの地下でレタスを育てたり、駅の近くでハーブを販売したりと、
まさに「街の中に畑がある」時代が始まっています。
🍓 フルーツや花も!進化する日本の技術
最近では、イチゴやミニトマト、観葉植物、花を育てる工場も登場しています。
特にイチゴの植物工場は海外からも人気で、
「日本の甘くてきれいなイチゴ」が世界中で注目されています。
さらに、気温や湿度を一定に保てるため、
花の生育や品質も安定。
ブーケや観賞用の花を出荷する専用の植物工場も増えています。
🌍 世界の植物工場 ― 食料問題を救う希望の技術
海外でも植物工場は急速に広がっています。
特に注目されているのがオランダ、アメリカ、シンガポールです。
- オランダ:国土が小さいのに世界有数の農業大国。
最新の温室技術と植物工場を組み合わせて「スマート農業」を推進中。 - アメリカ:砂漠地帯や都市部でも野菜を育てられる“垂直農業(バーティカルファーム)”が人気。
ベンチャー企業「AeroFarms」や「Plenty」は、LEDとAIで育てた野菜をスーパーに出荷しています。 - シンガポール:食料のほとんどを輸入に頼る国。
地元で野菜を生産するため、ビルの屋上やショッピングモールの中に植物工場を設置しています。
世界各地で、気候変動や人口増加による食料問題を解決する“カギ”として、
植物工場の技術が使われているのです。
🏭 日本と世界の共通点 ―「安定」と「持続可能」
どの国でも、共通して目指しているのは
**「安定した食料供給」と「環境へのやさしさ」**です。
自然に頼るだけではなく、科学の力で補うことで、
地球にやさしい農業の未来を作ろうとしています。
クイズ④
植物工場が世界で注目されている理由として、正しいものはどれでしょう?
- 見た目がかっこいいから
- 食料を安定して作る技術として、気候変動に強いから
- 動物も一緒に育てられるから
正解は 2 です。
👉 植物工場は、気候や災害の影響を受けにくく、食料不足の地域でも野菜を安定して生産できる技術だからです。
未来の植物工場 ― AI・再エネ・宇宙で広がる可能性
植物工場は、ただの“野菜の工場”ではありません。
これからの時代、AI(人工知能)や再生可能エネルギーと結びつくことで、
地球の未来を支える新しい産業へと進化しようとしています。
🤖 AIが見守る「自動栽培システム」
これまで植物工場の管理は人の手で行われていましたが、
最近ではAIがすべてを見守る“自動化システム”が進化しています。
AIはカメラやセンサーで植物の様子を観察し、
「今日は光が足りない」「水分が多すぎる」などを判断して、
LEDの明るさや養液の濃さを自動で調整します。
また、過去のデータを学習して、
「この気温では生育スピードが少し落ちる」といった傾向も予測可能に。
こうして、AIが“植物の声”を聞く時代が始まっています。
☀️ 再生可能エネルギーと組み合わせて地球にやさしく
植物工場は電気を多く使うため、エネルギー問題が課題でした。
そこで注目されているのが、再生可能エネルギーとの連携です。
- 太陽光発電でLEDや冷暖房を動かす
- 風力発電やバイオマス発電で電力を補う
- 工場から出るCO₂を再利用して光合成を助ける
このように、自然エネルギーをうまく取り入れることで、
電力を節約しながら「地球にやさしい植物工場」を実現する試みが進んでいます。
さらに、AIが電力の使い方を管理し、
ムダな電気を使わない“スマート・エコ工場”が広がりつつあります。
🚀 宇宙での植物工場 ― 「地球外の農業」へ!
未来の植物工場は、地球だけではありません。
NASA(アメリカ航空宇宙局)などでは、
宇宙ステーションや火星で植物を育てる研究が進んでいます。
宇宙では太陽光が弱く、空気や水も限られています。
そこで、LEDと循環システムを使って植物を育てる“宇宙植物工場”が登場。
宇宙飛行士が食べるサラダや酸素を作るためにも、
植物工場の技術が欠かせないのです。
この技術は、地球上の砂漠地帯や寒冷地など、
農業が難しい場所にも応用できます。
つまり、植物工場は**「宇宙でも地球でも食を支える技術」**なのです。
🌏 人と科学が協力する未来のかたち
AIが判断し、再エネが支え、植物が育つ――。
そんな未来の農業では、人間の役割は「作る」から「設計する」へ変わります。
どんな環境で、どんな食を生み出すか。
人と科学が協力して、“持続可能な地球”を守る時代がやってきているのです。
クイズ⑤
未来の植物工場の特徴として、正しいものはどれでしょう?
- 電気を使わずに植物を育てる
- AIや再生可能エネルギーを使って効率的に育てる
- 宇宙でしか使えない技術である
正解は 2 です。
👉 未来の植物工場では、AIが環境を調整し、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを活用して、より地球にやさしい栽培が行われています。
植物工場とSDGs ― 「持続可能な食」を実現するしくみ
植物工場は、ただ新しい農業技術というだけではありません。
地球の未来を守るための国際目標「SDGs(エス・ディー・ジーズ)」とも深く関係しています。
SDGsとは、2030年までに世界中の人が協力して目指す17のゴールのこと。
その中には「飢餓(きが)をなくす」「エネルギーを大切に使う」「気候変動に立ち向かう」など、
地球と人の幸せを守るための目標が並んでいます。
植物工場は、そのうちのいくつものSDGsの達成に役立つ技術なのです。
🍅 SDG 2:飢餓をゼロに ― 食料を安定して届ける
世界では今でも、気候変動や戦争、災害などで食料が足りない国があります。
植物工場なら、天気に左右されず、都市の中や砂漠のような場所でも野菜を作ることができます。
つまり、「どんな地域でも食料を安定して生産できる」――
それが、飢餓をなくすための大きな一歩になります。
さらに、保存や輸送の手間が減ることで、
「フードロス(食べ物のむだ)」を減らす効果もあります。
💧 SDG 6 & 7:水とエネルギーを大切に使う
植物工場では、水を循環して何度も使うシステムが導入されています。
畑のように水が地面にしみこむことがないため、
普通の農業に比べて使う水の量を約10分の1に減らせるのです。
また、再生可能エネルギー(太陽光・風力など)を活用することで、
電気をむだに使わず、CO₂の排出を抑えることができます。
このように、「水も電気も地球にやさしく使う」ことが、SDGsの精神につながっています。
🏙 SDG 11:住み続けられるまちづくりを
植物工場は、都市のビルや地下でも設置できるため、
「食料をまちの中で作る」ことができます。
これを**都市型農業(アーバンファーミング)**と呼びます。
災害が起きたときにも、近くで野菜が作れることで食料を確保できます。
また、子どもたちが見学や体験を通して“食と環境”を学べる場所にもなるのです。
🤝 SDG 9 & 17:科学と協力で未来をつくる
植物工場は、ひとつの企業だけでは成り立ちません。
AIやエネルギー、環境、流通など、さまざまな分野の人が協力して作り上げています。
つまり、SDGsのゴール17「パートナーシップで目標を達成しよう」を実現する場でもあるのです。
技術が進むほど、農業は「科学」と「協力」のプロジェクトへと進化しています。
🌎 持続可能な食の未来へ
植物工場は、SDGsの多くのゴールをつなぐ存在です。
「食べる人」「作る人」「支える技術」がつながることで、
地球にも人にもやさしい“持続可能な食のシステム”が生まれます。
私たち一人ひとりが、
「食べ物をむだにしない」「地球にやさしい選択をする」など、
できることから行動することも、SDGsの第一歩なのです。
クイズ⑥
植物工場がSDGsに貢献している理由として、正しいものはどれでしょう?
- 水を大量に使ってたくさん育てるから
- 科学の力で環境を守りながら食料を安定して作ることができるから
- 野菜を海外だけで作るから
正解は 2 です。
👉 植物工場は、限られた水やエネルギーを上手に使い、地球にやさしい方法で食料を生産することで、SDGsの目標に近づいています。
自由研究に使える!植物工場の学びアイデア
植物工場は、理科・社会・技術・環境のすべてがつながる「探究の宝箱」です。
自由研究のテーマとしてもとても人気があり、
「光と植物の関係」「水の使い方」「未来の農業」など、
いろいろな角度から調べることができます。
ここでは、小学生から中学生まで使えるアイデアを紹介します。
💡 アイデア①:光の色で植物の育ち方をくらべよう
植物は、光の色によって成長のしかたが変わります。
赤い光は花や実をつけやすく、青い光は葉や茎を強くします。
【やり方の例】
- 同じ種類の植物(豆苗やレタスなど)を3つ用意する。
- 赤・青・白のLEDライトをそれぞれ当てて育てる。
- 1週間ごとに高さや葉の数を観察・記録する。
結果をグラフにまとめると、光の条件による違いがよく分かります。
この実験は「光合成」「エネルギー」「生長」という理科の単元とつながります。
💧 アイデア②:ミニ植物工場を作ってみよう
ペットボトルや透明なケースを使って、
小さな植物工場を作ることもできます。
【準備するもの】
ペットボトル(2L)/スポンジ/水/液体肥料/LEDライト
【作り方】
- ペットボトルを半分に切り、下の部分に水と液体肥料を入れる。
- 上の部分にスポンジを置き、種をまく。
- 上からLEDライトを当てて育てる。
成長の様子を毎日観察して、温度や光の違いを比較しましょう。
“自分の部屋の中に小さな畑を作る”ような体験になります。
🌎 アイデア③:未来の農業を考えるレポートをつくろう
植物工場をテーマに、未来の食やエネルギーを考えるレポートもおすすめです。
たとえばこんな問いを考えてみましょう:
- 植物工場は地球温暖化を止められる?
- 宇宙での植物栽培は可能?
- AIが農業を変えるとしたら、人の仕事はどうなる?
調べ学習やインタビュー、イラスト、新聞形式など、自分の得意な方法でまとめると◎。
社会・理科・総合学習のどれにも発展させられます。
🧩 アイデア④:植物工場の模型やポスターをつくる
段ボールや紙コップを使って、植物工場の仕組みを模型にするのも楽しいです。
LEDの位置、水の流れ、風の通り道などを工夫して、
「理想の植物工場」をデザインしてみましょう。
ポスターを作る場合は、
タイトルを「未来の食をつくる植物工場」として、
光・水・AI・SDGsなどの要素をまとめると見栄えがします。
🔍 研究をまとめるときのコツ
- 観察だけでなく、「なぜそうなったのか?」を自分の言葉で書く。
- 写真やグラフを使うと、変化が一目でわかる。
- 最後に「地球や未来のためにできること」を一言まとめる。
自由研究は「実験+考察+未来の視点」でまとめると、一段と深い探究になります。
おさらいクイズ|植物工場のしくみと未来
クイズ①
植物工場の一番の特徴として、正しいものはどれでしょう?
- 外の畑と同じように自然の雨で育てる
- 室内で光や水、温度をコントロールして育てる
- 動物といっしょに育てる
正解は 2 です。
👉 植物工場は、天気や季節に関係なく、室内で光や水、温度を科学の力で調整して育てる“人工環境型農業”です。
クイズ②
植物工場でLEDライトを使う理由として、最も正しいのはどれでしょう?
- 明るい光で野菜をかっこよく見せるため
- 光の色や強さを調整して、光合成を助けるため
- 夜でも眩しくして眠らせないため
正解は 2 です。
👉 LEDライトは、赤い光と青い光のバランスで植物の成長をコントロールし、太陽の代わりに光合成を支えています。
クイズ③
植物工場のメリットとして正しくないものはどれでしょう?
- 天気に左右されない安定した生産
- 無農薬で清潔な環境
- 電気を全く使わないからコストが安い
正解は 3 です。
👉 植物工場は電力を多く使うため、電気代が高いという課題があります。今後は再生可能エネルギーの活用がポイントになります。
クイズ④
植物工場が世界で注目されている理由として、正しいものはどれでしょう?
- オシャレで写真映えするから
- 食料を安定して作ることができ、気候変動にも強いから
- 植物の代わりに人工の野菜を作るから
正解は 2 です。
👉 植物工場は、砂漠や寒冷地など農業が難しい場所でも食料を安定して作れるため、世界中で注目されています。
クイズ⑤
植物工場がSDGsに貢献している理由として、最も正しいのはどれでしょう?
- 水を大量に使って効率を上げているから
- 科学の力で環境を守りながら、食料を安定して生産できるから
- 高価な機械を使って経済を動かすため
正解は 2 です。
👉 植物工場は、水やエネルギーを大切に使いながら、地球にも人にもやさしい方法で食料を作る“持続可能な農業”を実現しています。
まとめ|科学の力で自然と共に生きる農業へ
植物工場の学びを通して、私たちはたくさんのことに気づきました。
それは、「自然の力をまねる科学のすごさ」と、「人間が地球とどう付き合うか」という問いです。
自然の畑では、太陽や雨、虫たちが助け合って植物を育てます。
一方、植物工場では、人間の知恵と技術がその役割を担います。
光をLEDに、土を養液に、天気をコンピュータに――。
まるで“地球の縮図”を小さな部屋の中につくっているようです。
🌿 科学の力が自然を支える時代へ
昔の農業は「自然に合わせる」ものでした。
しかし今の農業は、「自然と協力する」方向へと進んでいます。
植物工場のように、環境をコントロールする技術が発展すれば、
限られた土地や資源でも食料を育てることができます。
同時に、地球温暖化や気候変動の影響を減らす新しい方法としても期待されています。
けれど、科学の力が強くなればなるほど、
「どこまで人が自然を変えてよいのか」という問いも生まれます。
その答えを見つけるためには、ただ便利さを追うのではなく、
**“自然と共に生きる科学”**を考える姿勢が大切です。
🌍 SDGsの目標に向けて ― 私たちにできること
植物工場の技術は、SDGsの多くの目標とつながっていました。
「飢餓をなくす」「水とエネルギーを大切に使う」「気候変動に立ち向かう」。
これらはすべて、未来の地球を守るための約束です。
そしてその取り組みは、大人だけのものではありません。
食べ残しを減らす、電気を大切に使う、
身近な植物を育ててみる――。
そんな小さな行動が、地球の未来につながっていくのです。
🌱 “未来の農業”は、あなたの中にもある
植物工場は、科学・環境・社会・技術が交わる学びの象徴です。
AIや再エネの力を借りながら、人の知恵と工夫で自然を支える。
それはまさに、“未来の農業”の姿。
これからの時代に生きる私たちは、
自然を壊さず、支えながら利用する「協働の科学」を学んでいくことが求められています。
あなたが今日食べた野菜の一枚の葉にも、
科学者や農家、AIの力、そして自然の恵みがつながっています。
そのつながりを感じながら、「食べる」ことの大切さと感謝を忘れないようにしたいですね。
この記事を書いた人
西田 俊章(MOANAVIスクールディレクター/STEAM教育デザイナー)
公立小学校で20年以上、先生として子どもたちを指導し、教科書の執筆も担当しました。
現在はMOANAVIを運営し、子どもたちが「科学・言語・人間・創造」をテーマに学ぶ場をデザインしています。