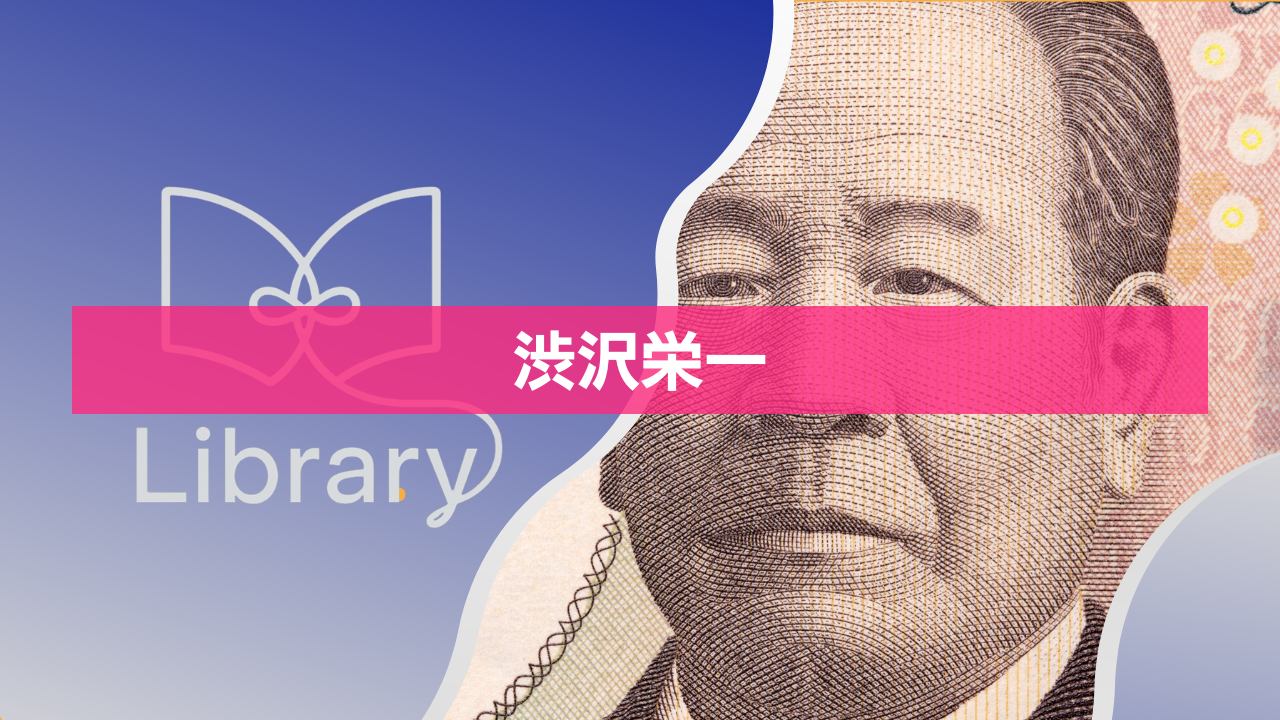
2024年から発行されている新しい1万円札。その肖像にえらばれたのが、渋沢栄一(しぶさわ えいいち) です。
でも「名前は聞いたことあるけど、どんな人?」「どうしてお札になったの?」と疑問に思う人も多いのではないでしょうか。
この記事では、小中学生にもわかりやすい言葉で、渋沢栄一の生涯・功績・考え方を紹介します。福沢諭吉との交流や、一橋大学とのつながりにもふれながら、自由研究や調べ学習にも役立つ内容をまとめました。途中でクイズもあるので、楽しみながら読んでみてくださいね。
渋沢栄一とは?【日本資本主義の父を小中学生向けに解説】
渋沢栄一は、1840年に埼玉県深谷市の農家に生まれました。幼いころから勉強が好きで、剣術にも熱心に取り組んだといわれています。
若いころは「尊王攘夷(そんのうじょうい)」の考え方に共感し、外国を追い払おうとする運動に参加したこともありました。しかし後に西洋の文明を知ることで考えを大きく変え、日本を近代化することに力を注ぐようになります。
その後は数多くの会社や銀行の設立に関わり、「日本資本主義の父」と呼ばれるようになりました。
👉 クイズ①
渋沢栄一は何と呼ばれているでしょう?
- 日本のお札の父
- 日本資本主義の父
- 日本銀行の父
正解は **2. 日本資本主義の父** です。
渋沢栄一がヨーロッパ留学できた理由とは?【パリ万博と一橋家】
渋沢栄一はどうして西洋の制度を知ることができたのでしょうか?
それは、1867年にフランス・パリで開かれた「万国博覧会」に、日本代表として派遣された**徳川昭武(とくがわあきたけ)**に随行したからです。昭武は将軍・徳川慶喜の弟で、渋沢はその家臣団の一員として選ばれたのです。
この旅は、今でいえば「超エリートの海外研修」のようなもの。渋沢はフランスやドイツなどを訪れ、銀行や会社、鉄道、近代的な都市づくりを自分の目で見ました。その体験が「日本もこうあるべきだ」という強い思いにつながります。
👉 クイズ②
渋沢栄一がヨーロッパに行けたのはなぜでしょう?
- 自分でお金を払って行った
- 幕府の留学生に選ばれた
- 一橋家に仕えていたから
正解は **3. 一橋家に仕えていたから** です。
渋沢栄一は何をした人?【功績と偉業をわかりやすく】
日本に帰ってきた渋沢は、明治新政府の大蔵省で働き、近代的な財政や税制度を整えました。ですが役人としての仕事は長く続けず、実業の世界に飛び込みます。
- 第一国立銀行(今のみずほ銀行の前身)を設立
- 東京ガス、東京海上保険、帝国ホテル、王子製紙、サッポロビール などの会社に関与
- 鉄道や保険、エネルギー、ホテル、教育など、社会の基盤になる分野に次々と会社を立ち上げた
合計で約500もの会社・団体に関わったといわれています。
👉 クイズ③
渋沢栄一がつくった日本初の銀行はどこでしょう?
- 日本銀行
- 第一国立銀行
- 東京銀行
正解は **2. 第一国立銀行** です。
渋沢栄一の考え方とは?【道徳経済合一の意味をわかりやすく】
渋沢栄一は「ただお金をもうければよい」という考え方には反対でした。
彼が生涯を通じて大切にしていたのは 「道徳経済合一(どうとくけいざいごういつ)」 という考え方です。
✅ 「道徳経済合一」とは?
- 「道徳」=人として正しいこと、みんなの幸せや安心
- 「経済」=お金をもうけたり、商売をしたりすること
この2つは本来バラバラではなく、一緒でなければならない、というのが渋沢の考えでした。
👉 つまり「お金もうけをしても、人をだましたり、社会をこわしたりしてはいけない」ということです。
むしろ「人々の生活をよくする商売こそ、長く続くし社会に役立つ」と信じていました。
✅ 当時としてはとても新しい考え方
明治の日本は、急に西洋の制度を取り入れてお金もうけが盛んになった時代。
その中で「利益だけを追いかけてはいけない」と言った渋沢は、とても先進的でした。
彼の言葉は、商売人や経営者だけでなく、普通の人にとっても大切な「生き方の指針」となりました。
✅ 現代とのつながり(SDGsとの関係)
いま世界で大切にされている SDGs(持続可能な開発目標) では、環境や人権、社会のためになる経済活動が求められています。
これはまさに渋沢の考えた「道徳経済合一」と同じ方向性です。
👉 例えば
- 環境にやさしい商品をつくる会社
- 子どもの教育や地域活動を支える企業
- フェアトレード(生産者に正しい利益が届く取引)
こうした活動はすべて「道徳と経済の両立」といえます。
✅ 子どもたちへのメッセージ
渋沢が残した言葉は、実は学校や家庭でも役立ちます。
- 勉強やクラブ活動で「自分のため」だけでなく「みんなのために」頑張る
- おこづかいを「全部お菓子」に使うのではなく「誰かの喜ぶこと」に使ってみる
こうした小さなことも「道徳経済合一」につながるのです。
👉 まとめると、渋沢栄一は 「お金はみんなの幸せのために使うべき」 と考えました。
これは100年以上前の言葉ですが、現代の私たちにも大切なヒントを与えてくれます。
渋沢栄一がつくった会社は今もある?【有名企業の一覧表】
渋沢栄一が関わった会社や団体の中には、子どもたちも名前を聞いたことがある有名企業がたくさんあります。
銀行・保険・鉄道・ホテル・食品・大学まで、日本の生活や学びに欠かせない組織がズラリと並びます。
| 分野 | 設立当時の名前 | 現在の会社・団体 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 銀行・金融 | 第一国立銀行 (1873) | みずほ銀行 | 日本初の銀行。現在のメガバンクへ発展。 |
| 金融・証券 | 東京株式取引所 (1878) | 東京証券取引所 | 日本最大の株式市場。 |
| 保険 | 東京海上保険会社 (1879) | 東京海上日動火災保険 | 国内最大の損害保険会社。 |
| 保険 | 明治生命保険 (1881) | 明治安田生命 | 日本の大手生命保険会社。 |
| 保険 | 日本火災海上保険 (1892) | 損保ジャパンの前身 | 現在の大手損保につながる。 |
| ホテル | 帝国ホテル (1887) | 帝国ホテル | 日本を代表する高級ホテル。 |
| エネルギー | 東京瓦斯会社 (1871) | 東京ガス | 首都圏のガスインフラを整備。 |
| エネルギー | 電気事業 (明治期) | 東京電力ホールディングス(前身) | 日本の電力供給の基盤。 |
| 建材 | 秩父セメント (1881) | 太平洋セメント | 国内大手セメントメーカー。 |
| 建材 | 日本煉瓦製造会社 (1887) | 現・日本煉瓦製造 | 日本初のレンガ工場。 |
| 製紙 | 王子製紙 (1873) | 日本製紙グループ | 教科書や新聞を支える製紙大手。 |
| 飲料 | 北海道開拓使麦酒醸造所 (1876) | サッポロビール | 日本のビール産業の始まり。 |
| 飲料 | 麒麟麦酒 (1907) | キリンビール | 渋沢が資金援助。 |
| 飲料 | アサヒビール (1889) | アサヒグループHD | 初期の経営を支援。 |
| 交通 | 日本鉄道 (1881) | JR東日本の前身 | 日本の鉄道整備を推進。 |
| 交通 | 京浜急行鉄道 (1898) | 京急電鉄 | 東京〜横浜を結ぶ鉄道。 |
| 交通 | 日本郵船 (1885) | 日本郵船(NYK) | 世界的な海運会社。 |
| 交通 | 大阪商船 (1884) | 商船三井(MOL) | 世界有数の海運会社。 |
| 医療・福祉 | 博愛社 (1877) | 日本赤十字社 | 災害救援・医療活動で知られる。 |
| 医療 | 東京慈恵医院 (1881) | 東京慈恵会医科大学 | 医学教育・医療に貢献。 |
| 医療 | 癌研究会 (1908) | 癌研有明病院 | 日本初のがん専門機関。 |
| 教育 | 商法講習所 (1875) | 一橋大学 | 商学の中心大学。 |
| 教育 | 東京女学館 (1877) | 東京女学館 | 女子教育の先駆け。 |
| 教育 | 同志社大学(支援) | 同志社大学 | キリスト教教育を支援。 |
| 教育 | 成蹊学園 (1912) | 成蹊大学・成蹊小中高 | 財団設立に尽力。 |
| 経済団体 | 東京商法会議所 (1878) | 東京商工会議所 | 日本経済の中心的団体。 |
| 経済団体 | 大阪商法会議所 (1878) | 大阪商工会議所 | 関西の経済を支える。 |
| 農業 | 日本農産 (1880年代) | 明治の農業協同組織の前身 | 農業近代化を推進。 |
| メディア | 時事新報 (1882) | 現・時事通信社の源流 | 渋沢が支援した新聞。 |
| 文化 | 東京芸術協会 (1887) | 東京芸術大学の源流 | 芸術教育を推進。 |
| 鉄鋼 | 八幡製鉄所 (1897) | 日本製鉄グループ | 日本の鉄鋼産業を牽引。 |
| 商社 | 東洋紡績 (1882) | 東洋紡 | 繊維産業大手。 |
| 商社 | 大阪紡績 (1882) | ユニチカの源流 | 日本紡績業の礎。 |
| 鉄道関連 | 日本車輌製造 (1896) | 日本車輌製造 | 鉄道車両メーカー。 |
| 食品 | 森永製菓(支援) | 森永製菓 | 菓子メーカー、設立に協力。 |
| 食品 | 明治製糖 (1901) | 明治ホールディングスの源流 | 食品産業を支えた。 |
| 商業 | 丸善 (1869設立に参画) | 丸善ジュンク堂書店 | 書籍流通の近代化を支援。 |
| 商業 | 高島屋(支援) | 高島屋 | 百貨店の近代化に尽力。 |
| 商業 | 三越(支援) | 三越伊勢丹HD | 百貨店の発展を助けた。 |
| 物流 | 国際汽船 (1896) | 商船三井グループに統合 | 海運大手の源流。 |
| 情報通信 | 電信事業 (明治期) | NTTの源流 | 通信網の整備に貢献。 |
| 科学 | 理化学研究所 (1917) | 理研 | 科学研究機関。 |
| 医療 | 聖路加国際病院(支援) | 聖路加国際病院 | 医療活動を支援。 |
| 教育 | 東京高等商業学校 (1887) | 現・東京大学経済学部に統合要素あり | 商業教育の発展を支援。 |
| 鉄道 | 山陽鉄道 (1888) | JR西日本の前身 | 西日本の鉄道網を整備。 |
| 農業 | 農商務省関連組織 | JAグループの源流 | 農業協同組織の原型。 |
| 国際交流 | 日米協会 (1917) | 日米協会 | 国際親善の団体。 |
これらの上場企業の時価総額の合計は56兆円以上で、日本の国家予算(約117兆円)の半分近くに相当します。
なぜ渋沢栄一は新しい1万円札に選ばれたのか?【理由をやさしく解説】
- 日本の近代化を経済の面から支えた
- 銀行・会社を多数つくり、社会インフラを整備した
- 教育や福祉にも力を入れた
- 「お金は社会のために」という思想が現代にも通じる
だからこそ「新しい1万円札にふさわしい人物」として選ばれたのです。
渋沢栄一と福沢諭吉の関係【旧1万円札と新1万円札の人物】
✅ 福沢諭吉と渋沢栄一、同じ時代に活躍した二人
1万円札といえば、長い間は 福沢諭吉(1835〜1901) が肖像でした。
彼は「学問のすゝめ」を書いたことで知られる思想家・教育者で、慶應義塾をつくり、日本に「学問の大切さ」を広めました。
一方、渋沢栄一(1840〜1931) は「日本資本主義の父」と呼ばれる実業家。銀行や会社をつくり、社会のしくみを整えていきました。
二人はわずか5歳ちがいで、どちらも江戸時代の終わりに生まれ、明治という新しい時代を駆け抜けた人でした。
✅ 実際に会って語り合った二人
「同じ時代に生きただけ」ではありません。
渋沢は福沢をとても尊敬しており、実際に慶應義塾を訪れて語り合った記録が残っています。
福沢が重んじたのは「学問によって人を育てること」。
渋沢が重んじたのは「経済活動によって社会を育てること」。
立場はちがっても、二人の目標は「日本を強くする」という点で同じでした。
渋沢はのちに、「福沢先生ほど日本人に影響を与えた人はいない」と語ったといいます。
✅ 「学問」と「経済」の両輪で近代化を推進
- 福沢諭吉 → 教育・思想の分野から近代化を推進
- 渋沢栄一 → 経済・企業の分野から近代化を推進
この二人の努力が合わさって、日本は近代国家への道を歩むことができました。
まるで 自転車の前輪と後輪 のように、どちらが欠けても進めなかったのです。
✅ 旧1万円札と新1万円札に込められた意味
旧1万円札は 「学問の力で日本を支えた福沢諭吉」。
新1万円札は 「経済の力で日本を支えた渋沢栄一」。
このつながりを知ると、ただの「お金」ではなく、日本の近代化を象徴する「物語」が1万円札に刻まれていることがわかります。
👉 まとめると、渋沢栄一と福沢諭吉は「思想」と「経済」というちがう分野で活躍しながらも、日本を近代国家へ導いた 盟友のような存在 でした。
だからこそ、二人がそろって1万円札に登場したのは、偶然ではなく歴史の必然といえるのです。
👉 クイズ④
渋沢栄一と福沢諭吉の関係について正しいのはどれでしょう?
- 年が50歳以上ちがい、会ったことはない
- 同じ時代を生き、実際に会って語り合った
- 兄弟であり、二人とも銀行をつくった
正解は **2. 同じ時代を生き、実際に会って語り合った** です。 福沢は「学問の力」、渋沢は「経済の力」で、日本の近代化を支えました。
渋沢栄一と一橋大学【商法講習所からの発展】
渋沢は経済だけでなく教育も重視しました。
特に大きな功績は 商法講習所の設立支援 です。この学校はのちに一橋大学となり、日本の経済人を多数育てる大学へ発展しました。
渋沢は「教育がなければ経済も発展しない」と考え、資金面や理念の面から支えました。
渋沢栄一おさらいクイズ【自由研究や授業に役立つ】
クイズ①
渋沢栄一はなぜ「日本資本主義の父」と呼ばれているでしょう?
- 日本で初めて総理大臣になったから
- 銀行や会社をたくさんつくり、経済の仕組みを整えたから
- 外国に日本の品物を売り歩いたから
正解は **2. 銀行や会社をたくさんつくり、経済の仕組みを整えたから** です。
クイズ②
渋沢栄一がつくった日本初の銀行はどれでしょう?
- 日本銀行
- 第一国立銀行
- 東京銀行
正解は **2. 第一国立銀行** です。
クイズ③
渋沢栄一と福沢諭吉の共通点はどれでしょう?
- どちらも西洋の考えを取り入れて日本を近代化した
- どちらも日本で最初の総理大臣になった
- どちらもお札のデザインを自分で決めた
正解は **1. どちらも西洋の考えを取り入れて日本を近代化した** です。
自由研究・調べ学習におすすめのテーマ【渋沢栄一を深掘り】
✅ 1. 渋沢が関わった会社をさらに調べて一覧化しよう
- 上の表から気になる会社を1つ選び、「いつ、なぜ、どんな目的で作られたのか」 を調べてみる。
- 例:帝国ホテルなら「外国のお客様を迎えるためにつくられた」など。
- 自分で年表やマップを作れば、社会科の調べ学習として提出できる。
- 会社の公式サイトを見れば、創業者の紹介ページに渋沢の名前が出ていることもある。
✅ 2. 「道徳経済合一」を自分の生活にあてはめてみよう
- 渋沢の考え方を、身近なおこづかいやお店に置きかえて考える。
- 例1:おこづかいを全部自分だけで使うのではなく、友達や家族が喜ぶ使い方を考える。
- 例2:お店が安さだけでなく「環境にやさしい商品」を売るのはなぜか?
- ワークシートを作り、「道徳」と「経済」をつなげる自分なりの事例を書き出してみよう。
👉 これは道徳の授業やSDGs学習にもつながるテーマになる。
✅ 3. 他のお札の人物と比べてまとめよう
- 新紙幣の仲間である 北里柴三郎(1000円札)・津田梅子(5000円札) と比較すると、自由研究の幅が広がる。
- 比べるポイント
- 生まれた時代や出身
- どんな分野で活躍したか(医療・教育・経済)
- それぞれの功績が今の社会にどう生きているか
- 表やポスターにまとめれば、**「新紙幣3人の研究」**としてインパクト大。
✅ 4. 渋沢の「1万円札」ストーリーを調べてみよう
- なぜ福沢諭吉から渋沢栄一に変わったのかを調べる。
- お札のデザインのひみつ(透かし・ホログラム・サイズ)も合わせて調べると面白い。
- 実際のお札を観察して、自分だけの「新旧1万円札比較ノート」を作ろう。
✅ 5. 渋沢栄一の教育支援を調べてみよう
- 一橋大学や東京女学館、成蹊学園などにどう関わったのかを調べる。
- 「経済だけでなく教育も支えた」という点をまとめると、社会と教育をつなぐ研究テーマになる。
👉 このように具体的にすると、**「調べる・考える・まとめる」**の3ステップがはっきりして、自由研究として提出しやすくなります。
まとめ
渋沢栄一は、農家の子から出発し、ヨーロッパで近代社会を学び、日本の経済や教育の土台を築いた人物です。
福沢諭吉と同じ時代に生き、学問と経済の両面から日本の近代化を支えました。
新しい1万円札に渋沢栄一が選ばれたのは、日本の未来にとっても大きな意味をもつのです。
この記事を書いた人
西田 俊章(MOANAVIスクールディレクター/STEAM教育デザイナー)
公立小学校で20年以上、先生として子どもたちを指導し、教科書の執筆も担当しました。
現在はMOANAVIを運営し、子どもたちが「科学・言語・人間・創造」をテーマに学ぶ場をデザインしています。



