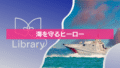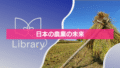「学校に行くこと」「遊ぶこと」「ごはんを食べること」──これって、あたりまえのことだと思っていませんか?
実は、世界では 「子どもにも守られるべき大切な権利(けんり)がある」 と決められているのです。
そのルールが 子どもの権利条約(こどものけんりじょうやく)。国連(こくれん)という国際組織がつくり、今では世界の190か国以上が守ると約束しています。
この記事では、小学生にもわかりやすく 子どもの権利条約の意味・4つの柱・日本の課題・SDGsとの関係 を紹介します。
最後には クイズ や 自由研究アイデア もあるので、ぜひ「子どもの人権博士」になってくださいね!
子どもの権利条約とは?【国連が定めた子どもの人権】
みんなは「子どもだからガマンしなさい」と言われたことはありますか?
もちろんマナーやルールは大切ですが、「子どもだからといって守られなくていい」ということではありません。
そこで国連(こくれん)は、1989年に 「子どもを守るための国際ルール」=子どもの権利条約 をつくりました。
この条約は「子どもは小さな大人ではなく、特別に守られるべき存在だ」という考えのもとに作られたのです。
日本は1994年にこの条約を受け入れ、今では世界190か国以上が「子どもの権利を大切にする」と約束しています。これは世界のほとんどの国が賛成している、とても重要なルールなのです。
子どもの権利条約ができた理由
昔の世界では、子どもが学校へ行けずに一日中働かされることや、戦争で犠牲になることが多くありました。
「これでは子どもたちが幸せに育てない!」という声が世界中で高まり、国連で話し合いが重ねられて生まれたのがこの条約です。
条約が伝えていること
この条約は「大人と同じように子どもにも基本的な人権がある」ことを明確にしています。
- ごはんを食べ、安心して 生きる権利
- 学校に行って学び、 育つ権利
- 意見を言い、大人に 聞いてもらう権利
- 差別や暴力から 守られる権利
つまり「子どもは保護されながらも、社会の一員として大切にされる」という考えが世界共通の約束になったのです。
👉 クイズ①
子どもの権利条約が国連で決められたのはいつでしょう?
- 1945年
- 1989年
- 2001年
正解は 2. 1989年 です。日本はその5年後の1994年に参加しました。
子どもの権利条約で守られる4つの基本的な権利【生きる・育つ・守られる・参加する】
子どもの権利条約にはたくさんの条文がありますが、その中で特に大切な4つの柱が「子どもの4つの権利」と呼ばれています。これは、すべての子どもが安心して成長できるために欠かせない約束です。
① 生きる権利(生存の権利)
子どもはだれでも「生きること」そのものが守られなければなりません。
ごはんを食べられること、病気になったらお医者さんにかかれること、安全な家で暮らせること――これらはすべて「生きる権利」に含まれます。
例えば、戦争や災害のときでも「子どもをまず守ろう」という考え方は、この権利があるからなのです。
② 育つ権利(発達の権利)
「学校に通って勉強すること」「遊ぶこと」「文化や芸術にふれること」も子どもの大切な権利です。
勉強や遊びは、将来の自分をつくるための栄養のようなもの。
もし勉強する機会がなかったり、ずっと働かされたりしたら、子どもは本当の意味で成長できません。だから世界中で「教育の機会を子どもに!」と呼びかけられています。
③ 守られる権利(保護の権利)
子どもはまだ成長の途中なので、大人の助けが必要です。
虐待、差別、戦争、搾取(むりやり働かされること)などから守られることも条約で決められています。
例えば、日本でも「18歳未満の子どもは危険な仕事をさせてはいけない」と労働基準法で決められています。これは条約の考え方が国内の法律にも取り入れられている例です。
④ 参加する権利(意見表明の権利)
子どもだって社会の一員です。自分の意見を言い、大人に聞いてもらう権利があります。
例えば、学校のルールを決めるときに「子どもの声を聞く会議」を開いたり、家庭でも「家族旅行はどこに行きたい?」と意見を出し合ったりすること。
これはただの「わがまま」ではなく、「参加する権利」の一部なのです。
👉 クイズ②
子どもの権利条約で守られる4つの柱に入っていないのはどれでしょう?
- 生きる権利
- 勉強する権利
- 大人になる権利
正解は 3. 大人になる権利 です。もちろん大人にはいずれなりますが、条約が守っているのは「子ども時代に必要な生きる・育つ・守られる・参加する権利」です。
日本と子どもの権利条約【日本はどう取り組んでいるの?】
子どもの権利条約は、世界の国々が集まってつくった「子どものための約束」です。
日本も1994年にこの条約を認め(批准し)、世界の国と同じように「子どもの権利を守ります」と約束しました。
日本が取り組んでいること
では、日本ではこの条約をどう活かしているのでしょうか?
- 教育を受ける権利の保障
義務教育(小学校・中学校)はすべての子どもが通えるように制度がつくられています。教科書も無料で配られるのは、「育つ権利」を守るためです。 - 子ども家庭庁の設立(2023年)
子どもの意見を尊重し、いじめや虐待をなくすために国として動く新しい役所です。「守られる権利」をしっかり守るための取り組みです。 - いじめ防止対策推進法(2013年)
学校でいじめを見逃さないように法律で決められています。子どもが安心して学校に通えるのは「守られる権利」があるからです。 - 子どもが意見を伝える機会
地方自治体(都道府県や市町村)では、「子ども会議」や「子ども議会」を開き、子どもが自分の意見を大人に伝えられるようにしています。これは「参加する権利」の実践です。
課題もまだある
ただし、日本でもすべての子どもの権利が十分に守られているわけではありません。
- 不登校の子どもが増えている
- いじめやネットトラブルが続いている
- 貧困で十分な教育や体験ができない家庭がある
こうした課題を解決することが、今後の日本の大きな宿題です。
👉 クイズ③
日本が子どもの権利条約に基づいて行っている取り組みとして正しいのはどれでしょう?
- 子ども家庭庁をつくった
- 子どもだけで国会を開いた
- 18歳未満は学校に行けないようにした
正解は 1. 子ども家庭庁をつくった です。子どもの声を大切にし、いじめや虐待をなくす取り組みを国として進めています。
世界と子どもの権利【どんな取り組みがあるの?】
子どもの権利条約は、世界のほとんどの国(196か国以上!)が参加している国際的な約束ごとです。
つまり「地球にいる子どもは、どの国でも大切にされるべき」という考えを世界中で共有しているのです。
国際的な取り組み
- ユニセフ(UNICEF)
国連児童基金とよばれる国際機関で、発展途上国の子どもたちに食料やワクチンを届けたり、学校を建てたりしています。戦争や災害があっても「生きる権利・育つ権利」が守られるように活動しています。 - 子どもの声を国際会議で届ける
子ども自身が会議に参加して、自分の国の問題を発表することがあります。これは「参加する権利」が世界規模で実現している例です。 - 学校に行けない子をなくす努力
世界ではまだ、約2億人もの子どもが学校に通えていません。国際社会は「すべての子どもに教育を!」を目標に、支援を続けています。
国ごとのユニークな工夫
- フィンランド:宿題やテストを少なくして、子どもの自由な学びを重視
- スウェーデン:18歳未満の体罰を禁止。家庭でも学校でも「叩くしつけ」は認められない
- ブラジル:子ども議会をつくり、政治に子どもの意見を反映
世界の課題もまだまだある
- 貧困で働かざるを得ない子ども(児童労働)がいる
- 戦争や紛争で学校に行けない子どもがいる
- 女の子だけ教育を受けられない国がある
子どもの権利条約は、こうした問題をなくして「すべての子どもが幸せに生きられる世界」を目指しています。
👉 クイズ④
世界で子どもの権利を守るために活動している国際機関はどれでしょう?
- ユニセフ(国連児童基金)
- FIFA(国際サッカー連盟)
- IOC(国際オリンピック委員会)
正解は 1. ユニセフ(国連児童基金) です。ユニセフは食料や教育、医療を通じて子どもの権利を守る活動をしています。
自由研究におすすめ!子どもの権利を調べてみよう
「子どもの権利条約」はニュースや社会科の教科書にも出てくるテーマです。
夏休みの自由研究や学校の調べ学習にぴったりの題材で、自分の生活や世界のニュースと結びつけやすいのがポイントです。
研究アイデア① 日本での取り組みを調べる
- 子ども家庭庁のホームページを見て、「どんなことをしているのか」をまとめる
- いじめ防止や不登校支援の制度について調べる
- 自分の学校や地域で「子どもの意見を聞く取り組み」があるかどうかを調べる
👉 レポート例:「日本では、子どもの声を聞くために子ども議会を開いています」など。
研究アイデア② 世界と比べてみる
- フィンランドやスウェーデンなど、海外の子どもの権利に関する取り組みを調べる
- 児童労働や教育格差の現状を、ユニセフのサイトなどで調べる
- 「日本と外国の違い」を表にすると、比較しやすい
👉 レポート例:「日本は義務教育が9年間あるけど、〇〇国では学校に行けない子もいる」
研究アイデア③ 子どもの声を集める
- クラスや友達に「子どもの権利って知ってる?」とアンケートをとる
- 「どんなことがもっと守られてほしい?」という質問をしてグラフにまとめる
- みんなの意見をまとめて「私のクラスの子どもの権利マップ」をつくる
👉 自分の生活と直結するので、オリジナリティが出ます。
研究アイデア④ 日常生活と結びつける
- 学校で自由に意見を言えた場面を書き出す → 「参加する権利」
- 健康診断や給食のことを書く → 「育つ権利」
- 家で安心して過ごせることを書く → 「守られる権利」
👉 「子どもの権利は自分の生活の中にある!」と気づく研究になります。
研究をまとめる工夫
- ポスター形式 … 4つの権利を絵や写真で表現
- 新聞形式 … 「〇〇新聞」としてニュース記事のようにまとめる
- スライド形式 … PowerPointやGoogleスライドで発表資料をつくる
おさらいクイズ|子どもの権利をふりかえろう!
ここまで読んで、子どもの権利条約についてたくさん学びましたね。最後にクイズでおさらいしてみましょう!
クイズ①
子どもの権利条約で大切にされている「4つの柱」はどれでしょう?
- 勉強する・遊ぶ・ゲームをする・おこづかいをもらう
- 生きる権利・育つ権利・守られる権利・参加する権利
- 大人になる権利・仕事する権利・運転する権利・選挙に行く権利
正解は 2. 生きる権利・育つ権利・守られる権利・参加する権利 です。これは世界中の子どもたちが大切にされるべき基本の権利です。
クイズ②
日本で子どもの権利を守るために作られた役所はどれでしょう?
- 子ども家庭庁
- 文房具庁
- アニメ庁
正解は 1. 子ども家庭庁 です。2023年に新しくできて、子どもをめぐる問題にしっかり取り組んでいます。
クイズ③
世界で子どもの権利を守るために活動している国際機関はどこでしょう?
- FIFA(国際サッカー連盟)
- ユニセフ(国連児童基金)
- NASA(アメリカ航空宇宙局)
正解は 2. ユニセフ(国連児童基金) です。食べ物やワクチン、教育を届けて、世界の子どもたちを守っています。
まとめ|子どもの権利は「みんなが安心して幸せに生きるための約束」
子どもの権利条約は、世界中の子どもたちが「生きる・育つ・守られる・参加する」ために作られた国際的な約束ごとです。
日本もこの約束を守る国のひとつで、学校や家庭、社会の中で少しずつ取り組みが広がっています。
- 子どもの権利は「遠い国の話」ではなく、私たちの日常の中にある
- いじめや貧困などの課題もあり、まだ改善すべき点が残っている
- 自由研究や授業を通して、自分の生活とつなげて考えることができる
👉 大切なのは、「子どもの権利は誰もが持っている当たり前のもの」ということ。
あなた自身にも、そして友達にも、同じようにこの権利があります。
だからこそ、「守られるのは当然なんだ」と自信を持ちつつ、「友達の権利も守れる人」になれるといいですね。
参考資料|子どもの権利条約 前文(全文)
子どもの権利に関する条約 前文
この条約の締約国は、
国際連合憲章において人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び平等で譲ることのできない権利を承認したことを考慮し、
国際連合は、世界人権宣言及び国際人権規約において、すべての人間が享有する権利及び自由を確認し、すべての人間が、自由及び尊厳をもってこれらの権利を享有することができるようにすることをめざしていることを考慮し、
家族は、社会の基本的な集団であり、子どもの成長及び幸福にとって自然かつ基本的な環境であること、子どもは、家庭において幸福、愛情及び理解のある雰囲気の中で育てられるべきであることを認識し、
子どもは、特別の保護及び援助を必要とすること、子どもは、生まれる前から及び出生後直ちに、適当な法的保護を受けるべきであることを考慮し、
子どもは、人格が十分に尊重されるべきであり、自由と尊厳をもって育てられなければならないことを認識し、
子どもは、健全な成長及び発達のために、愛情と理解のある家庭環境を必要とすることを認識し、
さらに、子どもに対し、特別の保護を与えなければならないことを国際連合は既に宣言していること、並びに子どもに関する権利の保障を内容とする国際的文書が既に存在することを想起し、
子どもの発達段階にかんがみ、子どもに固有の権利を特に認め、これを保障する必要があると考え、
次のとおり協定した。
(出典:国際連合「子どもの権利条約(Convention on the Rights of the Child)」日本語仮訳 外務省公式ページ)
👉 外務省|子どもの権利条約(日本語仮訳全文)
この記事を書いた人
西田 俊章(MOANAVIスクールディレクター/STEAM教育デザイナー)
公立小学校で20年以上、先生として子どもたちを指導し、教科書の執筆も担当しました。
現在はMOANAVIを運営し、子どもたちが「科学・言語・人間・創造」をテーマに学ぶ場をデザインしています。