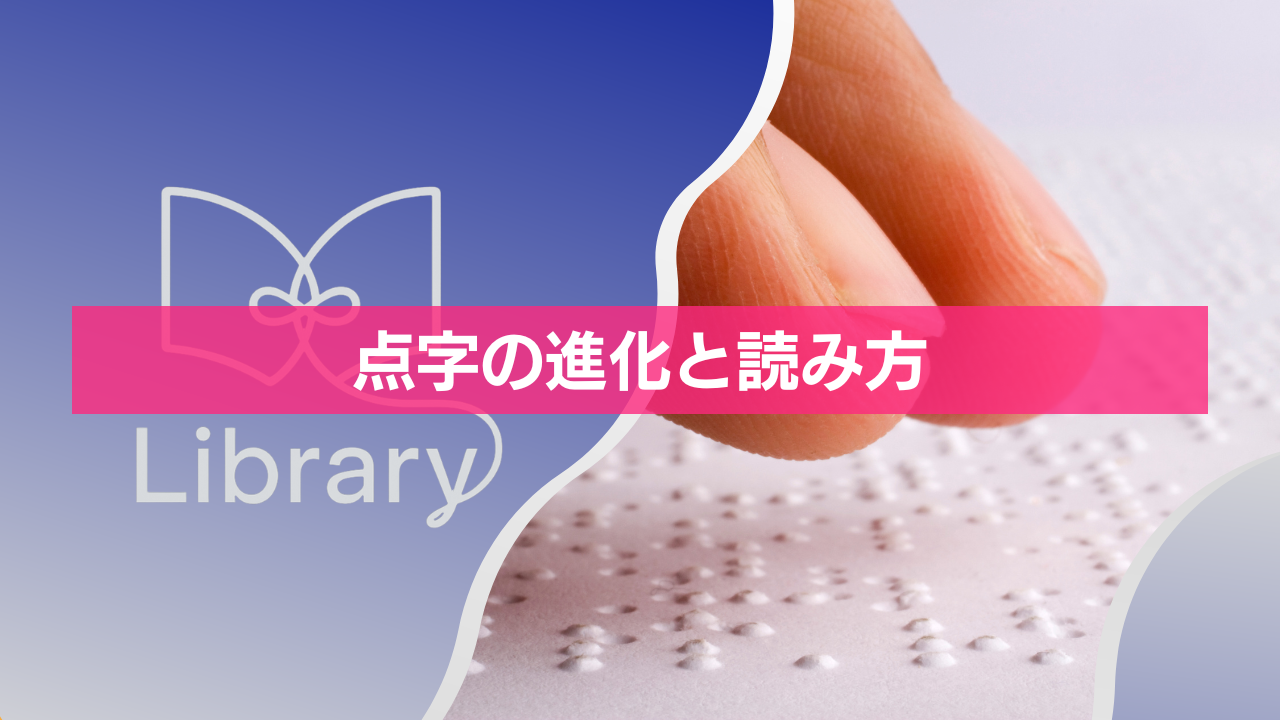
本や看板、スマートフォン――
私たちは毎日、目で「文字」を読んで情報を受け取っています。
では、もし目で見ることができなかったら、どうやって「読む」のでしょうか?
その答えが、**「点字(てんじ)」です。
点字は、小さな「6つの点」を組み合わせて、言葉や数字を表す特別な文字。
指で触れて読むことができる、世界中で使われている「もうひとつの文字の世界」**です。
この記事では、点字のしくみや歴史、そしてAIなどの新しい技術によって変わりつつある未来までを、
やさしく・おもしろく・深く解説します。
自由研究にも使える点字体験のアイデアも紹介しますので、
ぜひ「見えない文字」を通して、**人と人をつなぐ“伝える力”**について考えてみましょう。
点字とは ― 目の見えない人のための「触って読む文字」
「点字(てんじ)」とは、目の見えない人が指で読めるように作られた特別な文字のことです。
ふつうの文字は目で形を見て読みますが、点字は紙に小さな「でこぼこ(点)」を打って、それを指で触って読むのが大きなちがいです。
点字は、ひとつのマスの中に**6つの小さな点(2列×3段)があり、
その点の位置や組み合わせで「あ」「い」「う」や「A」「B」「C」などの文字を表します。
つまり、点の数や並び方が文字の“かたち”の代わりになるのです。
この6つの点の組み合わせだけで、世界中の言葉や数字を表すことができるなんて、まるで「秘密の暗号」**のようですね。
たとえば日本語の点字は「50音」をもとに作られています。
「か行」「さ行」など音のグループごとに規則があり、
点の位置を変えることで「あ」「か」「さ」などの違いを表します。
また、英語などのアルファベットを点字で書くときは、同じ6点式を使いますが、配置ルールが少し異なります。
点字は国ごとにその言語に合わせてルールがあり、世界共通の仕組みだけど内容はそれぞれというのが特徴です。
実は、私たちの身のまわりにも点字はたくさんあります。
たとえば、ペットボトルのキャップの上に「おさけ」「しょうゆ」などの点字があることに気づいたことはありますか?
お金(お札)にも点字のしるしがついていて、1,000円・5,000円・10,000円を指で区別できるようになっています。
エレベーターのボタンや駅の券売機の近くにも点字表示があり、
視覚に障害のある人も「自分で確かめながら」使えるように工夫されています。
こうした工夫は、「見えない人のためだけのもの」ではありません。
誰にとってもやさしいデザイン――つまりユニバーサルデザインの考え方につながっています。
点字を通して、「文字って、見るだけじゃなく、触っても読めるんだ」という発見をすると、
「人の感じ方ってこんなに多様なんだ」と思えるようになりますね。
クイズ①
日本のお札の点字は「数字」ではなく、何を表しているでしょう?
- 数字(1・5・10)
- お札の種類(1,000円・5,000円・10,000円)
- 発行年
正解は 2。
お札の「種類」を表しています。点の位置で金額を区別できるようになっているんです。
点字の歴史 ― ルイ・ブライユが発明した「光のない世界の文字」
点字を考え出したのは、今から200年ほど前、フランスの青年ルイ・ブライユ(Louis Braille)です。
ルイは1809年にフランスの小さな町で生まれました。幼いころ、父親の工房で遊んでいるときに工具で目をけがしてしまい、まもなく両目の視力を失いました。
しかし彼は学ぶことをあきらめず、「見えなくても本を読みたい」という強い思いを持ち続けました。
当時、視覚に障害のある人が読むための方法はほとんどなく、点字のような仕組みもありませんでした。
そんな中、ルイが10代のころに通っていた「パリ盲学校」で出会ったのが、**夜間に兵士が暗闇でも読めるように作られた“軍事用の点の文字”**でした。
これは「ナイト・ライティング(夜間通信)」と呼ばれ、紙に小さな点を打って情報を伝えるものでした。
ただしこの仕組みはとても複雑で、文字を覚えるのが難しく、使う人も少なかったのです。
ルイはこの仕組みに大きなヒントを得て、「もっとシンプルで、指で読みやすい文字にできないか」と考えました。
そして何年も試行錯誤を重ね、1829年、ついに**6つの点を使った点字(ブライユ式点字)**を完成させたのです。
この「6点の組み合わせ」というアイデアこそが、現在も世界中で使われている点字の基本になっています。
ブライユの点字は最初すぐには受け入れられませんでした。
多くの大人たちは「そんな点の文字なんて使いにくい」と言いましたが、
彼の教え子たちは点字を使うことで、自分で本を読める喜びを感じました。
「読むことができる」――その当たり前のことが、どれほど大切な力なのかを、ルイは自分の経験から知っていたのです。
ルイ・ブライユの発明は、やがて世界中に広まりました。
日本に点字が伝わったのは明治時代の終わりごろ。
日本では**石川倉次(いしかわ くらじ)**という人物が、日本語の音に合わせて点字を作り直しました。
日本語には「あ・い・う・え・お」などの音があり、フランス語とは仕組みがちがうため、独自の工夫が必要だったのです。
その結果、今私たちが使っている日本語の点字が誕生しました。
ブライユが亡くなったのは1852年。
しかし彼の考えた「6つの点の言葉」は、今も世界中で受け継がれ、
子どもも大人も、見える人も見えない人も、同じように学び合うための**「希望の文字」**となりました。
点字を発明したルイ・ブライユがヒントを得たのは、次のうちどれでしょう?
- 暗闇で読む軍事用の文字(ナイト・ライティング)
- 音楽の五線譜
- 星座の図
正解は 1。
ブライユは軍事用の「夜間通信文字」からヒントを得て、6点式の点字を考え出しました。
日本語の点字の読み方 ― ひらがな・カタカナ・数字のしくみ
日本語の点字は、英語のアルファベット点字とちがって、「音(おと)」をもとにした文字です。
つまり、「あ」「い」「う」「え」「お」や「か」「き」「く」「け」「こ」といった50音の発音をそのまま表す仕組みになっています。
たとえば、見た目がちがっても「は」と「ば」と「ぱ」は音が似ていますよね。
日本語点字では、6つの点のうち下の点を追加するだけで“濁音(が・ざ・だ・ば)”や“半濁音(ぱ)”を区別できるように工夫されています。
まるで、文字に「スイッチ」を入れるようにして音を変えているのです。
点字1マスの基本 ― 6つの点でできている!
点字は、たて3×よこ2の「点のマス」で1文字を表します。
点の位置は、左上から順に「1・2・3」、右側が「4・5・6」と番号で決まっていて、
この6つの中のどこを“打つか・打たないか”で文字が変わります。
たとえば、「あ」は左上と左真ん中(1と2の位置)に点があり、
「い」は右上と右真ん中(4と5の位置)に点がある――というように、
点の組み合わせでまるで暗号のように音を表すのです。
ひらがな・カタカナ・数字の表し方
日本語点字では、ひらがなを基本にしています。
でも、「カタカナ」や「数字」を使いたいときはどうするのでしょう?
実は、「数字のまえ」や「カタカナのまえ」に**特別なしるし(符号)**を打つことで区別できます。
たとえば、「数字」を表すときは「数字符」というマークを先につけて、そのあとに「あ~じ」などの決まった点字を続けて書くと「1~0」の数字になる仕組みです。
同じように「外来語」や「カタカナ語」には「カタカナ符」を使い、
「パソコン」や「アイスクリーム」などの言葉も表せます。
句読点(「、」「。」)や記号(「!」「?」)も、きちんと点字で表現できます。
つまり点字は、「読む」だけでなく「書く」こともできる立派な日本語の文字なのです。
点字を読むときのルール
点字は、左から右へ、上から下へという順番で読みます。
普通の文章と同じ方向ですね。
指の腹を使って、軽くなでるように点を感じ取ります。
一文字ずつではなく、単語や文のかたまりで読むようにすると、
スムーズに意味をつかめるようになります。
読む速度は、練習を重ねるうちにどんどん速くなるそうです。
まさに“指先の読書力”ですね。
点字を覚えるコツ
点字を覚えるには、実際に触って確かめるのがいちばんです。
紙に穴をあけて点を打つ「点字スレート」や、
子どもでも作れる「厚紙と押しピンの点字カード」を使って練習してみましょう。
最近では、スマホで点字を練習できるアプリや点字表もあり、
気軽に触れて学ぶことができます。
「音の文字」というしくみを知ると、言葉の成り立ちもより深く理解できるようになります。
クイズ③
日本語の点字は何をもとに作られているでしょう?
- ひらがなの読み(音)
- 漢字の形
- アルファベットの順番
正解は 1。
日本語の点字は、文字の形ではなく「音(おと)」をもとに作られています。
点字ブロックとバリアフリー ― 見える人も使っている「安全のデザイン」
みなさんは、駅のホームや歩道で見かける黄色いデコボコの道を見たことがありますか?
そう、それが「点字ブロック」です。
じつはこの点字ブロック、世界で初めて考えたのは日本の人なんです。
発明者は、岡山県の三宅精一(みやけ せいいち)さん。
1967年(昭和42年)に、「目の見えない人が安心して歩けるように」との思いから作りました。
いまでは世界中の駅や町で使われており、日本発のすばらしいバリアフリー技術として知られています。
点字ブロックの形の意味を知ろう
点字ブロックには、よく見ると2種類の形があります。
1つは、丸いポツポツが並んだ「点状ブロック」。
これは「ここで止まってください」「危険があります」という警告のサインです。
もう1つは、線が並んだ「線状ブロック」。
これは「この方向に進めます」という誘導のサインです。
たとえば駅のホームでは、線状ブロックが進む方向を示し、
ホームの端には点状ブロックが「ここから先は危ないよ」と知らせています。
このように、形のちがいで「止まる」と「進む」を伝える――
まさに足で読むサインといえますね。
点字ブロックは見える人にも役立っている
「点字ブロックは、目の見えない人のためのもの」と思われがちですが、
じつは、見える人にもとても大切なデザインです。
たとえば子どもやお年寄り、ベビーカーを押す人、夜道を歩く人なども、
ブロックの色や感触で「ここは通り道だ」「ここは注意しよう」と感じ取ることができます。
点字ブロックは、誰にとっても安全を守る**ユニバーサルデザイン(みんなのためのデザイン)**なのです。
バリアフリーとSDGsのつながり
点字ブロックの考え方は、「バリアフリー」という考え方にもつながっています。
バリア(Barrier)とは「障害」や「壁」という意味。
それを取りのぞいて、誰もが安心して生活できるようにするのがバリアフリーです。
さらに、世界の国々が協力して進めている**SDGs(持続可能な開発目標)**の中にも、
点字ブロックのような取り組みと関係する目標があります。
たとえば「目標10:人や国の不平等をなくそう」や、
「目標11:住み続けられるまちづくりを」などがそれです。
「見える」「見えない」にかかわらず、すべての人が安全にくらせるようにする――
そんな思いが、点字ブロックという形になって街中に広がっているのです。
日本から世界へ広がったやさしさの道
三宅精一さんが最初に点字ブロックを設置したのは、
岡山市の盲学校前の道路でした。
当時は誰もこのアイデアを理解してくれず、設置にも苦労しましたが、
少しずつその効果が認められ、全国へ、そして世界へと広まっていきました。
今ではヨーロッパ、アジア、アメリカなど、世界中の都市に点字ブロックが敷かれています。
街を歩くときに、黄色いブロックがどのように使われているかを観察してみましょう。
あなたの足の下にも、誰かを守る工夫があるかもしれません。
クイズ④
点字ブロックの「点」と「線」は、それぞれ何を意味しているでしょう?
- 点=止まる、線=進む
- 点=進む、線=止まる
- 点=休む、線=危険
正解は 1。
点状ブロックは「止まる・注意」、線状ブロックは「進む・誘導」を表しています。
点字の未来 ― AIとテクノロジーが変える読み書きのカタチ
これまで、点字は「紙に打つ」ものとして発展してきました。
しかし、いまの時代、点字の世界もデジタル化がどんどん進んでいます。
AI(人工知能)やロボット技術の発達によって、
「見えない人も、見える人と同じタイミングで情報を受け取れる社会」へと近づいているのです。
AIが点字を自動で作る時代に
これまで点字の本や資料を作るには、人が一つひとつ打ち込む必要がありました。
しかし今では、AIが自動で文字を点字に変換してくれるようになっています。
たとえば、パソコンやスマートフォンの文章をAIが読み取り、
そのまま点字データに変換して、点字ディスプレイに表示できるのです。
こうしたAI技術を使えば、ニュースや学校のプリント、メールなども、
視覚に障害のある人が同じスピードで読むことができるようになります。
「情報の時間差」をなくす――それがAIの大きな力です。
点字ディスプレイと音声技術の進化
最近では、「点字ディスプレイ」という電子機器も登場しています。
これは、画面の上にたくさんの小さなピンが並んでいて、
ピンが上下に動くことで文字を点字として表します。
たとえばスマートフォンやタブレットに接続すれば、
メールやインターネットの記事を点字で読むことができます。
さらに、音声読み上げ機能も進化しています。
AIの声は人間の声に近くなり、文章の内容や感情まで表現できるようになりました。
点字と音声の両方を使うことで、より正確に情報を理解できるようになるのです。
3Dプリンターやロボットによる新しい点字
AIだけでなく、3Dプリンターやロボット技術も点字の世界に変化を起こしています。
3Dプリンターを使えば、立体的な地図や図、科学の教材などに点字を入れることができます。
「この部分は山」「ここが川」というように、
触って地形や形を感じながら学ぶ“触覚教材”としての活用が広がっています。
また、ロボットが自動で点字を打ったり、
読み取った文字をリアルタイムで点字に変えてくれたりする技術も開発中です。
未来の教室では、AIロボットが子どもたちと一緒に点字の学習をサポートしてくれるかもしれませんね。
「誰もが読める社会」への一歩
テクノロジーの力で点字が身近になることで、
見えない人だけでなく、見える人も点字を学ぶきっかけが増えています。
AIが自動で翻訳してくれるなら、誰でも簡単に点字を使ってメッセージを送れる時代が来るでしょう。
「見えない」「見える」といったちがいをこえて、
すべての人が同じ情報を、同じタイミングで共有できる社会。
それが、点字の未来がめざす姿です。
テクノロジーの発展は、便利さだけでなく、
「人と人とをつなぐやさしさ」を広げる力も持っています。
AIやロボットの進化によって、点字はこれからも進化し続けるでしょう。
まさに、**科学と人間が協力してつくる“新しい言葉の形”**なのです。
クイズ⑤
AIが点字を自動で作れるようになると、どんなメリットがあるでしょう?
- 視覚障害のある人もすぐに情報を得られる
- 点字の読み方を忘れやすくなる
- 紙の点字がなくなる
正解は 1。AIが自動で点字を作ることで、視覚障害のある人も同じタイミングで情報を読めるようになります。
自由研究に使える!点字のしくみと作り方を体験しよう
点字の世界は、「見る」だけでなく「触ってわかる」学びです。
自分の指先で確かめながら仕組みを理解できるので、理科・社会・国語の自由研究にもぴったり!
ここでは、家や学校でできる簡単な点字体験のアイデアを紹介します。
厚紙と押しピンで作る「オリジナル点字カード」
いちばん手軽にできるのが、紙で点字を打つ実験です。
厚紙と押しピン、えんぴつ、定規があればOK。
まず、たて3×よこ2の「6つの点」のマスを書きます。
その中のどの点を打つかを決めて、押しピンで裏からポチポチと穴をあけましょう。
できあがったら、裏返して触ってみてください。
点がポコポコと浮き上がり、指で感じる文字になっています。
最初は「あ」や「い」など簡単な文字から作り、
なれてきたら「ありがとう」「ともだち」「がんばろう」など、
メッセージカードを作ってみるのもおすすめです。
お友だちとおたがいに打ちあって、「何て書いてあるか当てるクイズ」も楽しいですよ。
点字ブロックを観察して「安全のデザイン」を調べよう
自由研究では、「身近な点字ブロック」をテーマにするのもおすすめです。
駅や学校の近く、図書館や市役所などにある点字ブロックを観察して、
どんな場所にどんな形のブロックが使われているかを記録しましょう。
写真を撮って地図にまとめると、まち全体の安全の工夫が見えてきます。
「線のブロックは進む」「点のブロックは止まる」といった意味を調べて、
その違いがどのように使い分けられているのかを考察するのもよい課題になります。
SDGsの「バリアフリー」や「まちづくり」の視点を加えると、さらに探究的な研究に発展します。
AI点字翻訳やアプリで「未来の点字」にふれてみよう
スマートフォンやタブレットを使えば、AIが文字を点字に変える体験もできます。
無料の「点字翻訳サイト」や「点字練習アプリ」を使うと、
ふだん自分が書く文章を簡単に点字に変換できます。
文章を打ち込んで、画面に出てきた点字を紙にうつしてみると、
「目で見た文字が、点で表される」という変化が実感できます。
また、3Dプリンターが使える環境なら、
点字入りの名札やミニ地図、作品カードを作るのもおもしろいでしょう。
理科の工作や総合学習にもつなげやすく、“テクノロジーとやさしさ”をテーマにした自由研究として発表できます。
まとめ方のコツ
自由研究としてまとめるときは、次の流れを意識してみましょう。
- 調べたきっかけ(なぜ点字に興味をもったのか)
- 調べたこと(点字のしくみ、ブロックの形、AIのしくみなど)
- やってみたこと(カード作り、観察、アプリ体験など)
- わかったこと・気づいたこと(どんな工夫があるか、どんな未来が見えるか)
これをポスターやスライドにまとめれば、発表でも注目されるテーマになります。
点字の研究は、「やさしさ」と「科学の知恵」が一緒になった学びなのです。
おさらいクイズ|点字の進化と読み方
点字のしくみや歴史、そして未来のテクノロジーまで、
この記事ではたくさんのことを学びましたね。
どのくらい覚えているか、クイズでおさらいしてみましょう!
クイズ①
点字は、いくつの点の組み合わせで1文字を表しているでしょう?
- 4つ
- 6つ
- 8つ
正解は 2。点字は「2列×3段」の6つの点で文字を作っています。組み合わせを変えることで、言葉や数字を表せるのです。
クイズ②
点字を発明したルイ・ブライユがヒントを得たのは、どんな文字だったでしょう?
- 夜間用の軍事通信文字
- 音楽の五線譜
- 星座の図
正解は 1。ブライユは「ナイト・ライティング」と呼ばれる軍事用の点の文字からヒントを得て、6点式点字を発明しました。
クイズ③
日本語の点字は何をもとに作られているでしょう?
- 漢字の形
- ひらがなの読み(音)
- アルファベットの順番
正解は 2。日本語点字は文字の形ではなく、「あ」「い」「う」などの音をもとに作られています。
クイズ④
点字ブロックの「点」と「線」は、それぞれ何を意味しているでしょう?
- 点=止まる、線=進む
- 点=進む、線=止まる
- 点=休む、線=危険
正解は 1。点状ブロックは「止まる・注意」、線状ブロックは「進む・誘導」を意味しています。
クイズ⑤
AIが点字を自動で作れるようになると、どんなことができるようになるでしょう?
- 視覚障害のある人も同じタイミングで情報を得られる
- 紙の点字がなくなる
- 点字の練習が必要なくなる
正解は 1。AIが自動で点字を変換することで、視覚障害のある人もリアルタイムで情報を読めるようになります。
まとめ ― 点字が教えてくれる「伝える力」と「やさしさ」
点字は、単なる「見えない人の文字」ではありません。
それは、**「すべての人がつながるための言葉」**です。
目で見なくても、指で感じて読める。
そんなしくみを作り出したルイ・ブライユの発明は、
「どんな人にも学ぶ権利がある」という強い願いから生まれました。
その思いは、200年たった今でも世界中で受け継がれています。
日本では石川倉次が、日本語に合った点字を考案し、
さらに三宅精一が点字ブロックを発明しました。
それぞれの工夫が重なり、「見える」「見えない」をこえた社会のやさしさが形になりました。
そして現代では、AIやデジタル技術が点字の世界をさらに広げています。
点字ディスプレイや自動変換アプリによって、
情報の壁が少しずつなくなり、
見えない人も見える人も、同じタイミングで世界とつながることができるようになりました。
この流れはまさに、MOANAVIが大切にしている
**「科学・言語・人間・創造」**の学びそのものです。
点字には、「科学の工夫(Science)」と「人への思いやり(Human)」、
そして「言葉を伝える力(Language)」と「新しい未来をつくる創造性(Creativity)」がつまっています。
文字を読むとは、「誰かの気持ちを受け取ること」。
そして文字を書くとは、「自分の思いを伝えること」。
見える人も、見えない人も、伝え合うことで理解し合える――
点字は、そんな「心の架け橋」なのです。
この記事を書いた人
西田 俊章(MOANAVIスクールディレクター/STEAM教育デザイナー)
公立小学校で20年以上、先生として子どもたちを指導し、教科書の執筆も担当しました。
現在はMOANAVIを運営し、子どもたちが「科学・言語・人間・創造」をテーマに学ぶ場をデザインしています。



