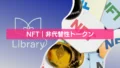ニュースやネットで「ブロックチェーン」という言葉を聞いたことはありますか?
ビットコインやNFTなどでも使われているこの技術は、
実は、**「信頼をつくるための新しいしくみ」**なんです。
ブロックチェーンは、データを「ブロック」と呼ばれる箱にまとめ、
それを「チェーン(鎖)」のようにつなげて記録します。
だれか1人が管理するのではなく、世界中のみんなでデータを見守る――
これが、ブロックチェーンのいちばんの特徴です。
この記事では、ブロックチェーンの仕組み・使い道・AIやNFTとの関係・SDGsとのつながりまで、
小学生・中学生にもわかるようにやさしく解説します。
紙カードを使った自由研究アイデアも紹介するので、
「未来の社会」を自分の手で体験してみましょう!
- ブロックチェーンとは?|インターネットの次に来る“信頼のしくみ”
- どうやって動いているの?|データを守る“つながるブロック”の仕組み
- 分散型ってどういうこと?|みんなで見守る“チームワークのネットワーク”
- お金だけじゃない!|社会を変えるブロックチェーンの活用例
- ブロックチェーンとAIのちがい|考えるのはAI、記録するのはブロックチェーン
- NFT・仮想通貨との関係|「デジタルの所有」を支えるブロックチェーン
- SDGsとブロックチェーン|透明な社会と未来の信頼をつくる技術
- 自由研究に使える!ブロックチェーンを紙とカードで体験してみよう
- おさらいクイズ|ブロックチェーンのしくみ・使い道・社会とのつながりをふりかえろう
- まとめ|「信頼をつくる技術」ブロックチェーンが変える未来社会
ブロックチェーンとは?|インターネットの次に来る“信頼のしくみ”
ニュースや本で「ブロックチェーン」という言葉を聞いたことはありますか?
これは、これからの社会でとても大切になる**「データをみんなで守るしくみ」**のことです。
たとえば、インターネットでは、たくさんの情報を送ったり受け取ったりできます。
でも、その情報が正しいかどうかを保証するのはむずかしいですよね。
もし、誰かがデータを書きかえたらどうなるでしょう?
「お金の取引」「成績データ」「契約書」などが改ざんされたら、
大きなトラブルになってしまいます。
そこで登場したのが、**ブロックチェーン(Blockchain)という技術です。
この技術は、インターネットの次の時代を支える「信頼のインフラ(しくみ)」**と呼ばれています。
🧩 ブロック+チェーン=みんなでつなぐデータの鎖
ブロックチェーンは、その名前の通り「ブロック」と「チェーン」でできています。
1つのブロックには、取引や情報の記録がまとめられています。
そしてそのブロックが、時間の順番通りに“チェーン(鎖)”のようにつながるのです。
たとえば、次のようなイメージです👇
ブロック1 → ブロック2 → ブロック3 → ……
1つ前のブロックの情報が、次のブロックの中にも入っているので、
途中でデータをこっそり書きかえることがとても難しくなります。
なぜなら、1つでも変えると、その後のすべてのブロックのつながりがくずれるからです。
🌍 「1人が管理」ではなく「みんなで見守る」
今までのインターネットでは、銀行や会社など、
**1つの場所(サーバー)**がデータをまとめて管理していました。
これを「中央集権型」といいます。
一方、ブロックチェーンはちがいます。
世界中のたくさんのコンピュータが同じデータを共有し、見張り合っているのです。
だれか1人がデータを変えようとしても、他の人がすぐに気づくしくみ。
まるで、みんなで守る金庫のような考え方です。
💬 未来の社会の「信頼のルール」になる技術
ブロックチェーンは、お金や契約、投票など、
「だれが・なにを・いつしたか」という記録を安全に残すことができます。
つまり、**「正しい記録をみんなで信じられる社会」**をつくるための技術なのです。
だから、ブロックチェーンは“インターネットの次に来る革命”とも呼ばれています。
データを共有するだけでなく、「信頼を共有する」――
そんな新しい時代が、もう始まっているのです。
クイズ①
「ブロックチェーン」の“ブロック”とは、何をあらわしているでしょう?
- 情報や取引などの記録をまとめたデータの箱
- 金庫のようなコンピュータそのもの
- ゲームで使う立方体のキャラクター
正解は 1 です。
👉 ブロックとは「データのまとまり」のこと。
それが時間の順番にチェーン(鎖)のようにつながって、改ざんできない記録をつくっています。
どうやって動いているの?|データを守る“つながるブロック”の仕組み
ブロックチェーンが「信頼できる技術」と呼ばれるのは、
しくみそのものがとてもかしこく設計されているからです。
ここでは、データをどのように守っているのか、やさしく見ていきましょう。
🧱 ブロックの中には何が入っている?
ブロックチェーンの「ブロック」は、いわばデータの箱です。
ひとつのブロックの中には、次のような情報が入っています。
- 取引や記録(だれが・いつ・なにをしたか)
- 前のブロックの「番号」や「暗号」
- 作られた時間やデータのしるし(ハッシュ値)
この「ハッシュ値(はっしゅち)」というのがポイントです。
ハッシュとは、データを特別な数のかたちに変換したもの。
たとえ1文字でもデータを変えると、まったくちがうハッシュ値になります。
つまり、「こっそり書きかえたらすぐにバレる」仕組みになっているのです。
🔗 チェーンでつながるから強い!
ブロックチェーンでは、新しいブロックが1つできるたびに、
その中にひとつ前のブロックのハッシュ値が書きこまれます。
ブロック1 → ブロック2(ブロック1のハッシュ入り) → ブロック3(ブロック2のハッシュ入り)……
このように、すべてのブロックが「鎖(チェーン)」のようにつながっていくのです。
もし途中のブロックを変えようとすると、
後ろのブロックすべてのハッシュ値がくずれてしまい、
ネットワーク全体に「この記録はおかしい!」と知らせが出るようになっています。
この「連続性」こそが、ブロックチェーン最大の強み。
1つのブロックを変えることが、ほぼ不可能なのです。
🧮 暗号と“みんなの確認”で守られる
ブロックが作られるときには、
世界中のコンピュータが協力してその中身を確認します。
これを「承認(しょうにん)」または「マイニング」と呼びます。
これはまるで、「みんなでノートを見せ合って間違いがないか確かめる」ようなもの。
1台のコンピュータではなく、何百・何千台ものコンピュータが同時に確認するため、
だれか1人がウソのデータを入れることはできません。
また、データは暗号化されていて、
中身を勝手に読んだり書きかえたりすることもできません。
ブロックチェーンは、**「暗号」+「チームのチェック」**のダブルガードで守られているのです。
🔐 改ざんがほぼ不可能な理由
- すべてのブロックがハッシュでつながっている
- 世界中のコンピュータが同じデータを持っている
- 書きかえると全員に「違反」がバレる
この3つの仕組みがあるため、
ブロックチェーンはとても安全で信頼性の高い技術といわれています。
お金の取引だけでなく、記録を守るための新しいルールとして広がっているのです。
クイズ②
なぜブロックチェーンのデータは、かんたんに書きかえられないのでしょう?
- 特別なパスワードを知っている人しか見られないから
- 世界中のコンピュータが同じ記録を持って確認しているから
- データが紙に書かれているから
正解は 2 です。
👉 ブロックチェーンでは、世界中のコンピュータが同じデータを分け合って確認しています。
1か所を変えても、他のコンピュータにすぐバレるため、改ざんがほぼ不可能なのです。
分散型ってどういうこと?|みんなで見守る“チームワークのネットワーク”
ブロックチェーンを説明するときによく出てくる言葉に、
**「分散型(ぶんさんがた)」**というものがあります。
ちょっとむずかしそうに聞こえますが、
これはブロックチェーンの“いちばん大事な考え方”です。
🏛 これまでの仕組みは「中央集権型」
私たちがふだん使っている銀行やネットショッピングのデータは、
多くの場合、ひとつの場所(サーバー)でまとめて管理されています。
このように、中心に「まとめ役」がいるしくみを「中央集権型」といいます。
たとえば銀行なら、だれがいくら持っているかは銀行がすべて知っています。
もしそのサーバーがこわれたり、悪意のある人に操作されたりしたら、
データは大変なことになってしまいます。
つまり、1つの場所にすべてをまかせることは、便利だけど弱点もあるのです。
🌍 ブロックチェーンは「みんなで管理する」しくみ
ブロックチェーンは、それとはまったく反対の考え方をとっています。
それが「分散型」。
1か所にデータを集めず、世界中のコンピュータが同じデータを持ち合っているのです。
たとえば、1000人が同じノートをコピーして持っているとします。
もし1人がノートの中をこっそり書きかえても、
ほかの999人のノートには本当の内容が残っているので、すぐにバレます。
つまり、みんなで見張り合うことで、ウソや改ざんを防ぐことができるのです。
このように、「分散型」はチームワークで信頼を守る仕組みともいえます。
🔁 「1人の管理者がいない=誰でも信頼できる」
ブロックチェーンでは、だれか1人の管理者が命令を出すのではなく、
世界中のノード(=コンピュータ)たちが同じルールで動きます。
そのため、だれかがルールを勝手に変えることはできません。
これを「非中央集権(ひちゅうおうしゅうけん)」とも呼びます。
つまり、「特別な人が上に立たない」「みんなが対等で信頼できる」世界です。
この考え方は、社会にもヒントをくれます。
情報も権力も1人の手に集中させず、みんなで分けて守る。
それが、ブロックチェーンの持つ“デジタル民主主義”の考え方なのです。
💬 日常生活の「分散型」ってどんなもの?
実は、ブロックチェーンのような考え方は、身近なところにもあります。
- クラスで1人がまとめるより、みんなで意見を出し合って決める → 「分散型の話し合い」
- サーバーに保存せず、みんなのパソコンで共有するファイル → 「分散型の保存」
- SNSでも、だれかが支配するより、利用者同士でルールを守る → 「分散型の運営」
このように考えると、ブロックチェーンの世界は、
未来の社会のチームワークモデルのようにも見えてきます。
🌐 分散型の強みとこれから
分散型の強さは「倒れにくさ」です。
1台のコンピュータが止まっても、他の多くが動いていれば全体は止まりません。
これを「耐障害性(たいしょうがいせい)」といい、災害時にも役立つ仕組みです。
また、情報をみんなで持つことで、**透明性(とうめいせい)**も高まります。
だれが何をしたかをみんなが確認できるから、不正が起きにくいのです。
このように、分散型は「安全」「強い」「公平」という3つの特長を持つ、
まさに未来社会の信頼の形といえます。
クイズ③
「分散型」のブロックチェーンが、中央集権型とちがうのはなぜでしょう?
- たくさんの人が同じデータを共有して見張り合っているから
- 特別なリーダーがすべてのデータを決めているから
- 情報を一か所にまとめておくから
正解は 1 です。
👉 ブロックチェーンの分散型は、世界中のコンピュータが同じデータを分け合い、
互いにチェックすることで信頼を守る仕組みです。チームワークで安全をつくるのです。
お金だけじゃない!|社会を変えるブロックチェーンの活用例
ブロックチェーンというと「ビットコイン」「仮想通貨」といった言葉を思い浮かべる人が多いでしょう。
でも実は、ブロックチェーンの使い道はお金だけではありません!
「データを正しく記録して、みんなで信頼できるようにする」――
このしくみは、社会のあらゆる場面で役立ち始めています。
🗳 投票のしくみを変える!――「正しく数える社会」
たとえば「選挙」や「投票」です。
ふつうは人が紙を集めて数えたり、コンピュータに入力したりしますよね。
でもそこにミスや不正があったら、結果が変わってしまうかもしれません。
ブロックチェーンを使えば、だれがいつ投票したかを記録しつつも、だれに投票したかは秘密にできる仕組みがつくれます。
しかも、その記録はあとから書きかえられません。
「正しく」「透明な」投票ができる――
それは民主主義の未来を支える大切な力になります。
🏥 医療・教育のデータを安全に守る
病院のカルテや学校の成績データなども、個人情報のかたまりです。
これらがもし流出したり、書きかえられたりしたら大問題です。
ブロックチェーンを使えば、
「だれが・いつ・どんな記録を見たか」を正確に残せます。
そのため、患者や生徒が自分のデータを安全に管理できる社会が実現します。
たとえば、転校しても成績が自動的に引きつがれたり、
病院が変わってもカルテの情報をすぐ共有できたり――
そんな便利で安全な未来がもう始まっています。
🍎 食品や製品の「うまれた道」を追いかける
スーパーで買う野菜やお肉、文房具やおもちゃなど。
それが「どこで作られたのか」「どうやって届いたのか」を知りたいと思ったことはありますか?
ブロックチェーンを使うと、生産から出荷、販売までの流れ(=トレーサビリティ)を記録できます。
つまり、「このりんごは〇〇県の△△さんの畑で育ちました」といった情報が、改ざんされずに残るのです。
消費者にとっては安心を、作る人にとっては信頼を生み出す技術です。
🎨 芸術・ゲーム・教育にも広がる!
ブロックチェーンの記録の仕組みは、アートや音楽の世界でも使われています。
デジタル作品を「だれのものか」証明する技術――それが**NFT(エヌエフティー)**です。
これは別の記事でくわしく説明しますが、
ブロックチェーンがあるからこそ、「デジタルでも本物を証明できる」ようになりました。
また、オンラインゲームの中でアイテムを安全に交換したり、
教育分野では「学習履歴(ポートフォリオ)」をブロックチェーンで記録する試みも進んでいます。
まさに、学ぶ・遊ぶ・作るすべてがブロックチェーンでつながる時代なのです。
🚛 災害・物流・募金にも役立つ!
災害時の支援物資や募金がどこに届いたのか――
これもブロックチェーンで「見える化」できます。
お金や物の流れが正しく記録されることで、
だれかが途中でごまかす心配がなくなるのです。
物流の分野でも、トラックや船の動きをリアルタイムで共有し、
「この商品は今どこにあるか」をすぐに確認できるようになります。
つまり、ブロックチェーンは“信頼の記録”を社会全体に広げる技術なのです。
クイズ④
ブロックチェーンの使い道として正しいものはどれでしょう?
- 料理のレシピを隠すこと
- 選挙・医療・食品などの記録を安全に残すこと
- ネットのスピードを上げること
正解は 2 です。
👉 ブロックチェーンは、「正しい記録を残して、だれでも確認できる」しくみ。
投票や医療、物流など、社会のいろんな場面で信頼を支えています。
ブロックチェーンとAIのちがい|考えるのはAI、記録するのはブロックチェーン
最近よく耳にする2つの言葉――「AI(人工知能)」と「ブロックチェーン」。
どちらも“未来の社会を変える技術”として注目されていますが、
その役割はまったくちがいます。
ここでは、AIとブロックチェーンのちがいを、やさしく整理してみましょう。
🧠 AIは「考える技術」
AIとは「Artificial Intelligence(人工知能)」のこと。
たくさんのデータを学習して、自分で判断したり予測したりできる技術です。
たとえば――
- 写真を見て「これは猫です」と判定する
- 天気のデータから「明日は雨がふる」と予測する
- 翻訳アプリで言葉の意味を理解して変換する
これらはすべてAIの得意分野です。
AIは人間のように考え、「判断」や「予測」を行う技術といえます。
💾 ブロックチェーンは「記録する技術」
一方のブロックチェーンは、考えたり予測したりはしません。
その代わり、AIなどが出したデータを正確に記録し、だれも書きかえられないように守ることが得意です。
つまり、AIが「考える頭」なら、ブロックチェーンは「信頼できる記録係」。
この2つは、役割がちがうけれど、おたがいを支え合う関係にあります。
🧩 AIとブロックチェーンが手を組むと?
たとえば、AIが医療のデータを分析して「この薬が効果的」と判断したとします。
でも、その結果をだれがいつ作ったのかがわからなければ、信頼できません。
そこで、ブロックチェーンの出番です。
AIが出した結果をブロックチェーンで記録すれば、
「だれが・いつ・どんな方法で出した結果か」が正確に残ります。
また、AIが集める大量のデータも、ブロックチェーンで管理すれば
「データの持ち主」「使われ方」「変更の履歴」を安全に追跡できます。
このように、AIとブロックチェーンは考える力と信頼を生む力のコンビなのです。
⚖️ ちがいをまとめると…
| ちがいの項目 | AI(人工知能) | ブロックチェーン |
|---|---|---|
| はたらき | 考える・学ぶ・予測する | 記録する・守る・共有する |
| 得意分野 | 翻訳・画像認識・会話・自動運転 | お金・投票・証明書・情報管理 |
| 人間にたとえると | 頭脳(Brain) | 記録係(Ledger) |
| 目的 | 判断の自動化 | 信頼の自動化 |
AIは“頭脳の代わり”として考え、
ブロックチェーンは“信頼のルール”として記録を守ります。
どちらも、人の力を助けるための技術なのです。
🌍 これからの社会での関係
未来の社会では、AIが考え、ブロックチェーンがその結果を記録する――
そんな協力関係がどんどん広がるでしょう。
たとえば、AIが作ったアートをブロックチェーンでNFT化して証明する。
AIが判断した医療データをブロックチェーンで共有する。
AIが自動で取引するシステムをブロックチェーンで安全に動かす。
これらはすべて、「考える力(AI)」と「信頼の力(ブロックチェーン)」が組み合わさって初めて実現します。
クイズ⑤
AIとブロックチェーンの関係を正しく表しているのはどれでしょう?
- AIが考え、ブロックチェーンがその結果を安全に記録する
- AIがブロックチェーンを作っている
- ブロックチェーンがAIを動かしている
正解は 1 です。
👉 AIは“考える”役目、ブロックチェーンは“記録して守る”役目。
この2つの協力が、未来の社会を支える大きなチームワークになるのです。
NFT・仮想通貨との関係|「デジタルの所有」を支えるブロックチェーン
ブロックチェーンの技術が最初に世界で注目されたのは、
「ビットコイン」などの仮想通貨(かそうつうか)が登場したときです。
そこから今では、NFTやデジタルアートなど、
お金以外の分野にもどんどん広がっています。
ここでは、ブロックチェーンがどのように「デジタルの信頼」を作っているのかを見てみましょう。
💰 仮想通貨ってなに?
仮想通貨とは、インターネット上だけで使える「デジタルのお金」です。
たとえばビットコインやイーサリアムなどが有名ですね。
このお金は、銀行が発行しているわけではありません。
世界中のコンピュータがブロックチェーンを使って、
「だれが・いつ・いくら送ったか」を記録しているのです。
たとえば、あなたがAさんに100円分のビットコインを送ると、
その取引がブロックに記録され、みんなのネットワークで共有されます。
つまり、だれもウソをつけないお金のルールができているのです。
ブロックチェーンがなければ、この「信頼できるお金のやり取り」は成立しません。
だからこそ、「仮想通貨=ブロックチェーンの最初の成功例」と言われているのです。
🖼 NFTってなに?
NFTは「Non-Fungible Token(ノン・ファンジブル・トークン)」の略で、
日本語では「代わりのきかないデジタル証明書」と言われます。
たとえば、インターネット上にある絵や音楽、動画などは、
だれでもコピーできてしまいますよね。
でもNFTでは、そのデジタル作品に「このデータの本物は○○さんのものです」という証明を
ブロックチェーン上に書きこむことができるのです。
つまり、NFTは**「デジタルの持ち主を証明する技術」**です。
しかもブロックチェーン上に記録されているので、
消されたり、書きかえられたりすることはありません。
🎨 デジタルアートから教育・スポーツまで
NFTの使われ方は、アートだけではありません。
たとえば――
- ゲームの中のアイテム(武器・キャラクター)を自分の資産として持てる
- アスリートやアーティストの記念カードをNFTでコレクションできる
- 学校の「成績証明書」や「資格証明」をNFTで安全に保存できる
これらはすべて、「ブロックチェーンが信頼を証明する」おかげで成り立っています。
これまで「形のないデータ」は信用されにくかったけれど、
NFTができたことで、デジタルにも“本物”が生まれたのです。
🌐 「信用のしくみ」が世界を変える
ブロックチェーンとNFTの関係をまとめると、こうなります👇
| 使い方 | ブロックチェーンの役わり | 例 |
|---|---|---|
| 仮想通貨 | お金の取引を安全に記録 | ビットコイン・イーサリアム |
| NFT | デジタルの持ち主を証明 | デジタルアート・音楽・証明書 |
ブロックチェーンは「お金」だけでなく、
「価値」や「信頼」をデジタルで記録するための“土台”です。
これによって、**インターネットの世界にも「本物」「所有」「信用」**という概念が生まれました。
⚖️ これからの社会では…
これからの時代、ブロックチェーンはお金だけでなく、
教育・医療・アート・行政など、あらゆる分野の「証明」に使われていきます。
紙の証明書がいらない社会、コピーができても“本物”がわかる社会――
それがブロックチェーンが目指す未来です。
クイズ⑥
NFTや仮想通貨にブロックチェーンが使われている理由として正しいのはどれ?
- データを書きかえられず、安全に記録できるから
- 早くインターネットを動かすため
- 音楽を作るため
正解は 1 です。
👉 ブロックチェーンは「改ざんできないデジタル台帳」。
仮想通貨やNFTが“本物”として認められるのは、この技術のおかげなのです。
SDGsとブロックチェーン|透明な社会と未来の信頼をつくる技術
ブロックチェーンは、ただのデジタル技術ではありません。
「正しい情報を、だれもが見える形で共有する」というしくみは、
世界が目指す**SDGs(持続可能な開発目標)**の実現にもつながっています。
ここでは、ブロックチェーンがどのように社会や地球の未来を支えているのかを見ていきましょう。
🌍 SDGsとは?
SDGsとは、国連が定めた2030年までに目指す17の世界共通目標のことです。
「貧困をなくそう」「エネルギーをみんなに」「気候変動に具体的な対策を」など、
世界が協力して解決すべき課題がまとめられています。
この目標を実現するには、国・企業・市民が正しく情報を共有し、信頼し合うことが欠かせません。
ここでブロックチェーンの「透明で改ざんできない」性質が役立つのです。
💸 透明な寄付・支援で「信頼の輪」を広げる
たとえば、寄付や募金をするとき――
「本当にそのお金が必要な人に届いているの?」と不安になることがありますね。
ブロックチェーンを使えば、
だれが、いつ、どこに、どれだけのお金を寄付したか、
そしてそのお金がどこでどう使われたかを記録できます。
この記録は世界中の人が確認でき、書きかえることもできません。
つまり、透明でウソのない寄付のしくみが作れるのです。
これはSDGsの目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」にも直結します。
「見える支援」「信頼できる支援」が、世界の連帯を強くしていくのです。
⚡ エネルギーの見える化で「環境」を守る
再生可能エネルギー(太陽光・風力など)をどれだけ使っているか、
その記録を正確に残すのもブロックチェーンの得意分野です。
たとえば、ある企業が「自社の工場では再エネを使っています」と発表したとします。
本当かどうかを証明するには、電力の流れを正しく記録する必要がありますよね。
ブロックチェーンを使えば、発電から消費までのデータを改ざんされずに残せます。
つまり、「再エネをどのくらい使ったか」を見える化して信頼できる報告ができるのです。
これはSDGsの目標7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」にも貢献します。
🏭 公正な取引で「働く人」を守る
ブロックチェーンは、製品ができるまでの“道のり”を追跡できる技術です。
これを「サプライチェーンの透明化」といいます。
たとえば、コーヒー豆やチョコレート。
農家の人たちがきちんとしたお金をもらっているか、
子どもが働かされていないかなどをブロックチェーンで確認できます。
これにより、**フェアトレード(公正な取引)**が守られ、
SDGsの目標8「働きがいも経済成長も」や目標12「つくる責任 つかう責任」にもつながるのです。
🌱 テクノロジーが生む“見える正義”
ブロックチェーンの最大の力は、
「正しいことを正しいままに残す」こと。
つまり、**見える正義(ビジュアル・ジャスティス)**を生み出す技術です。
情報が透明で、だれでも確かめられる社会では、
ウソやごまかしが通りにくくなります。
それは、環境にも、人にもやさしい未来をつくる第一歩です。
ブロックチェーンは、AIや再エネ技術と同じく、
テクノロジーで正義と信頼を形にする新しい道具なのです。
クイズ⑦
ブロックチェーンがSDGsの達成に役立つ理由として正しいのはどれ?
- 情報をみんなで共有し、正しく見える形で記録できるから
- コンピュータのスピードを上げるため
- 寄付を秘密にするため
正解は 1 です。
👉 ブロックチェーンは「透明で改ざんできない記録」を作れる技術。
寄付・再エネ・フェアトレードなど、SDGsの信頼を支える大切なしくみなのです。
自由研究に使える!ブロックチェーンを紙とカードで体験してみよう
ブロックチェーンというと、「むずかしそう」「パソコンがないとできない」と思うかもしれません。
でも、実は紙とカードを使えば、だれでもブロックチェーンのしくみを体験できます!
ここでは、小中学生でもできる簡単な自由研究のアイデアを紹介します。
🪵 用意するもの
身近な材料だけでOKです。
- 紙またはカード(5〜10枚)
- 鉛筆・ペン
- はさみ・テープ
- 数字スタンプやマーク(あれば便利)
これで準備完了!
🔢 ブロックをつくろう
まず、紙1枚を「ブロック」として使います。
それぞれのブロックに次のような情報を書いてみましょう。
- ブロックの番号(例:1、2、3…)
- 取引の内容(例:「Aさん→Bさんに100円送る」)
- 前のブロックの番号(またはハッシュの代わりに簡単な記号)
たとえば、こんな感じです👇
ブロック1
取引:A→Bに100円
前のブロック:なし
ブロック2
取引:B→Cに50円
前のブロック:①
こうして、**「前のブロックの情報を次のブロックにつなげる」**ことで、
データがつながっていくことを体験できます。
🔗 つなげて「チェーン」にしよう
できたブロックを、順番にテープでつないでみましょう。
1枚1枚がしっかり順番どおりに並んでいるはずです。
このとき、途中のブロック(たとえばブロック2)の内容をこっそり書きかえてみてください。
すると、次のブロック(ブロック3)に書かれた「前のブロックの記号」と合わなくなります。
👉 これが、「データを改ざんすると全体がくずれる」というブロックチェーンの特徴!
💬 チェックする「みんなのネットワーク」を再現
ブロックを作ったら、家族や友だちに「確認役」をしてもらいましょう。
みんなが同じ内容をコピーして持っているとします。
1人が内容を変えても、他の人が「ちがう!」と気づくはずです。
この体験で、ブロックチェーンの「分散型=みんなで守る仕組み」を再現できます。
🧠 自由研究のまとめ方
自由研究としてまとめるときは、次のような流れにすると分かりやすいです。
- ブロックチェーンとは何か(仕組みの説明)
- 紙カードを使った実験の方法
- 改ざんしてみたときの結果(写真や図で)
- 分かったこと・気づいたこと
- 現実の社会でどう使われているか(投票・NFTなど)
理科(情報の伝達)や社会(信頼の仕組み)ともつながる、STEAM的な研究テーマになります。
🌟 発展アイデア
- ブロックの内容を色や形で分けて「見えるブロックチェーン」を作る
- 改ざん実験をした結果をグラフでまとめる
- 学校や地域のルールを「ブロックチェーン化」してみる(記録と確認)
工夫次第で、**「自分だけのオリジナルブロックチェーン研究」**ができます!
おさらいクイズ|ブロックチェーンのしくみ・使い道・社会とのつながりをふりかえろう
ブロックチェーンの学びをふりかえって、どれだけ理解できたかチェックしてみましょう!
しくみ、特徴、社会での活用など、8問でおさらいします💾🌍
おさらいクイズ①
ブロックチェーンの「ブロック」とは、何をあらわしているでしょう?
- コンピュータの部品
- 情報や取引をまとめたデータの箱
- お金をためる金庫
正解:2
👉 ブロックは「データのまとまり」。たくさんのブロックが時間の順に並び、チェーンのようにつながっています。
おさらいクイズ②
ブロックチェーンのデータを勝手に書きかえられないのはなぜ?
- 暗号化され、世界中のコンピュータが同じ記録を確認しているから
- 特別な管理者がすべて見張っているから
- 一度保存すると削除できない設定だから
正解:1
👉 多くのコンピュータが同じ記録を持っていて、1つが変わるとすぐにズレが見つかるしくみです。
おさらいクイズ③
「分散型(ぶんさんがた)」の特徴として正しいものはどれ?
- 中心にリーダーがいて指示を出す
- 世界中の人が同じ情報を共有して見張り合う
- 情報を1か所にまとめて保管する
正解:2
👉 分散型は「みんなで見守るチームワークのネットワーク」。誰か1人の力に頼らないのが特徴です。
おさらいクイズ④
ブロックチェーンが使われるのは、どんな場面でしょう?
- お金の取引や投票、医療データの記録など
- ゲームのセーブデータ保存だけ
- 動画を再生するとき
正解:1
👉 ブロックチェーンは、社会のいろんな記録を「正しく」「安全に」残すために使われています。
おさらいクイズ⑤
AIとブロックチェーンの関係を正しく表しているのはどれ?
- AIが考え、ブロックチェーンが記録する
- ブロックチェーンがAIを操作する
- 同じ働きをしている
正解:1
👉 AIは「考える技術」、ブロックチェーンは「記録する技術」。おたがいに支え合う関係です。
おさらいクイズ⑥
NFTとはどんな技術?
- デジタル作品の「本物」を証明する技術
- 音楽を自動で作る技術
- お金を早く送る方法
正解:1
👉 NFTは、ブロックチェーンを使って「このデジタルデータはだれのものか」を証明する仕組みです。
おさらいクイズ⑦
ブロックチェーンがSDGsに役立つ理由として正しいのは?
- 情報を正しく見える形で共有できるから
- コンピュータをたくさん動かせるから
- 募金を秘密にできるから
正解:1
👉 ブロックチェーンは「透明で改ざんできない記録」を残せるため、公正で信頼できる社会づくりに貢献します。
おさらいクイズ⑧
ブロックチェーンの学びでいちばん大切な考え方はどれ?
- みんなで信頼を守り合う仕組みであること
- 1人がすべてのデータをコントロールすること
- データを見えないようにすること
正解:1
👉 ブロックチェーンは「みんなで信頼をつくる技術」。
データの安全と公正をチームワークで守る、新しい社会のしくみです。
まとめ|「信頼をつくる技術」ブロックチェーンが変える未来社会
ブロックチェーンは、データやお金を動かすための“ただの技術”ではありません。
それは、**「信頼をどうつくるか」**という人類の課題に答える、新しいルールのような存在です。
これまでの社会では、「信頼」は人や組織にゆだねられてきました。
銀行や会社、学校など――私たちは「誰かが正しく管理してくれている」と信じて動いてきました。
でもブロックチェーンでは、その信頼をみんなで分け合って守ることができます。
これはまさに、デジタル時代の新しい“チーム信頼”のかたちなのです。
💬 「だれかを信じる」から「しくみを信じる」へ
ブロックチェーンのすごいところは、「人を信じる」から「しくみを信じる」へと変えたこと。
たとえ知らない人同士でも、ブロックチェーンの記録があれば、
「この取引は正しい」と安心できる――それは“信頼の自動化”といえる仕組みです。
たとえば、選挙・医療・寄付・教育など、
正確さと公正さが求められる分野ほど、ブロックチェーンの価値が発揮されます。
だれもが確認でき、だれも書きかえられない社会。
それは、AI時代の「正義のインフラ」ともいえる存在です。
🌐 社会を変える「見える信頼」
ブロックチェーンの記録は、だれでも見られて、だれにもウソがつけない。
この「見える信頼」は、企業や政府の透明性を高めるだけでなく、
環境・福祉・教育など、あらゆる分野の信頼づくりに役立ちます。
たとえば、
- 募金や支援金の使い道を世界中で確認できる
- 農産物がどこで作られたかを確かめられる
- 成績や資格をデジタル証明として残せる
このように、ブロックチェーンは“正しい記録”を守ることで、
世界中の人たちをつなげる「信頼の言語」になっているのです。
🧠 AIとブロックチェーンが協力する未来
AI(人工知能)は考え、学び、判断します。
ブロックチェーンはその結果を正しく残し、だれも書きかえられないように守ります。
この2つが手を取り合えば、
「考える技術」+「信頼を守る技術」=よりよい社会をつくる力になります。
たとえば、AIが分析した医療データをブロックチェーンで共有したり、
AIが生み出した作品をNFTで所有したり――
技術と倫理がバランスを取る時代が、すでに始まっているのです。
🌏 「信頼」を中心にした未来社会へ
ブロックチェーンの本当の価値は、“信頼”をデジタルの世界に取り戻すこと。
情報があふれる今だからこそ、正しさ・透明さ・協力が求められます。
これからの社会では、「技術が人を信じ、人が技術を信じる」関係が重要になります。
ブロックチェーンは、その中心にある“信頼の橋”として、
世界をより公正で安心な場所へと導いていくでしょう。
📚 学びの本棚から、次の1冊を
このテーマに関連する教材・読み物を、本棚を眺めるように探せます。
→ MOANAVI Library をひらく
この記事を書いた人
西田 俊章(MOANAVIスクールディレクター/STEAM教育デザイナー)
公立小学校で20年以上、先生として子どもたちを指導し、教科書の執筆も担当しました。
現在はMOANAVIを運営し、子どもたちが「科学・言語・人間・創造」をテーマに学ぶ場をデザインしています。