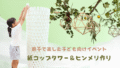学校以外の選択肢を知ろう
フリースクールとオルタナティブスクール、一条校の基礎知識
「子どもが学校に行けなくなったとき、どうしたらいいのだろう?」
そんな不安を抱える保護者は少なくありません。文部科学省の調査でも、不登校の小中学生は年々増えており、もはや珍しいことではなくなりました。
その中で、よく耳にするようになったのが「フリースクール」という言葉です。一方で「オルタナティブスクール」という言葉はまだ一般的ではなく、講演会などで説明すると「初めて聞いた」という声が多く上がります。また、教育関係者以外には「一条校」という用語もなじみが薄いのが現状です。
本記事では、一般の保護者の方にもわかりやすいように、フリースクールとオルタナティブスクールの違い、そして一条校との関係について整理します。子どもが安心して学べる場を探すうえでの参考になれば幸いです。
フリースクールとは?
定義と目的
フリースクールとは、学校に行けない、行きたくない子どもたちが安心して過ごせる「居場所」や「学びの場」を指します。文部科学省が直接定めた学校制度ではなく、民間団体やNPOなどが自主的に運営しています。
目的は「学校に戻すこと」だけではなく、子どもが自分らしく成長できるようにサポートすることです。
利用方法と費用の目安
利用の仕方は施設によってさまざまです。週に数日通う子もいれば、ほぼ毎日通う子もいます。費用は月額1万円程度から数万円まで幅広く、自治体によっては補助が出るケースもあります。
メリット
- 学校に行けなくても安心できる居場所ができる
- 子ども同士で気持ちを共有できる
- 学校のように画一的な評価ではなく、個別に合わせた学びが可能
デメリット
- 法的に「学校」ではないため、出席扱いにならない場合がある
- 学習内容が学校と同じではないため、進学に不安を感じる保護者もいる
- 費用が自己負担になることが多い
フリースクールは、学校と同じ役割を果たす場所ではありませんが、子どもが「安心できる場」を得ることによって心が安定し、次の一歩につながることが多いのです。
オルタナティブスクールとは?
海外での「オルタナティブ教育」の広がり
オルタナティブスクールとは、「既存の学校教育に代わる新しい学び方を提供する学校や学び場」のことです。海外では、モンテッソーリ教育やシュタイナー教育といった名前を耳にしたことがある方も多いでしょう。これらはオルタナティブ教育の代表例です。
日本のフリースクールとの違い
フリースクールが「不登校の子どもたちの居場所」として始まったのに対し、オルタナティブスクールは「教育理念や方法を大切にした学びの場」として設立されているケースが多い点が特徴です。
そのため、必ずしも不登校の子どもに限らず、「もっと自分らしい学びをしたい」「創造的な教育を受けたい」という子どもたちが通っています。
オルタナティブスクールの特徴
- 子ども自身の選択や意思を尊重する
- プロジェクト型学習や探究型学習を重視する
- 評価よりも「成長のプロセス」に重点を置く
- 異年齢の交流や地域とのつながりを大切にする
MOANAVIを例にした実践
横浜にあるMOANAVIもオルタナティブスクールのひとつです。
MOANAVIは「科学・言語・人間・創造」をテーマとしたSTEAM学習を通して、**4Cスキル(批判的思考力・コミュニケーション力・協働力・創造力)**を育てることを重視しています。
学びの取り組みを「STUDY POINT」という仕組みで可視化し、子どもたちが自分のペースで成長を実感できるように工夫しています。
また、今年度は子どもたち自身が企画・準備・運営を行う「お祭りプロジェクト」が進行中で、次年度以降続けるかどうかも含めて、子どもたちと相談しながら形を決めています。
「一条校」とは?
名称の由来
「一条校」という言葉は、学校教育法第1条で定められている学校を指します。小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学などがここに含まれます。
公立・私立学校を含む「認可された学校」
一条校は、国が定めた学習指導要領に基づき、教育課程や評価が行われる「認可校」です。私立であっても文部科学省や都道府県の認可を受けていれば一条校に含まれます。
フリースクールやオルタナティブスクールとの制度上の違い
フリースクールやオルタナティブスクールは一条校には含まれません。そのため、在籍しているだけでは義務教育の出席扱いにならない場合があります。ただし、近年では学校と連携して出席扱いにする例も増えています。
進学や単位認定との関わり
高校や大学への進学時には、出席日数や学習履歴が影響することがあります。フリースクールやオルタナティブスクールで学んでいても、在籍する学校との連携によって進学ルートは確保できるケースが多いです。
保護者が知っておきたい選び方のポイント
子どもの性格やニーズに合うかどうか
「安心して過ごしたい子」にはフリースクール、「探究心を活かしたい子」にはオルタナティブスクールといったように、子どもの個性によって合う場は異なります。
費用・通いやすさ・サポート体制を確認する
月謝や通いやすさはもちろん、スタッフや先生との相性も大切です。体験や見学で雰囲気を知ることをおすすめします。
実際に見学・体験して「雰囲気」を知る
パンフレットやホームページだけではわからないことも多いため、必ず現場での体験が重要です。子ども自身が「ここなら安心できそう」と感じられることが一番です。
まとめ ― 子どもに合った「学びの場」を探そう
フリースクール、オルタナティブスクール、一条校――それぞれに特徴や役割があります。
大切なのは「どれが正解か」ではなく、「わが子に合うのはどの学びの場か」を一緒に考えることです。
学校に行けないからといって未来が閉ざされるわけではありません。むしろ、学校以外の選択肢を知ることで、子どもが自分らしく成長できる可能性が広がります。
保護者ができることは、その選択肢を知り、子どもと一緒に「小さな一歩」を踏み出すことではないでしょうか。
MOANAVIについて
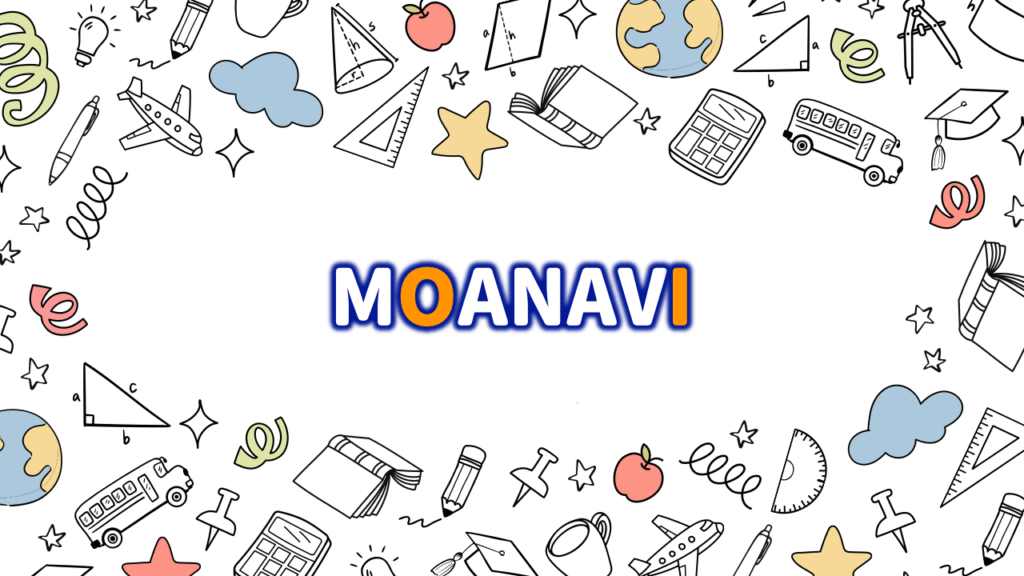
MOANAVIは、子どもたち一人ひとりが自分らしいペースで学べるオルタナティブスクールです。
「勉強が苦手」「学校に行きづらい」――そんな子どもたちが、小さな一歩から成長していける環境を大切にしています。
科学・言語・人間・創造の4つのテーマでSTEAM学習を展開し、4Cスキルを身につけることに重点を置いています。
また、学びを見える化する「STUDY POINTシステム」や、子どもたち自身が企画・運営する「お祭りプロジェクト」を通して、自己肯定感と学びの意欲を育てています。
もし今、お子さんのことで悩んでいるなら、ぜひ一度MOANAVIの学びの場にふれてみてください。
小さなきっかけが、大きな未来につながるかもしれません。
記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)
STEAM教育デザイナー / MOANAVIスクールディレクター
理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。
📚 経歴・資格
✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者
✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)
✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)
✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演
✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説