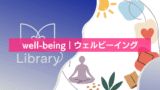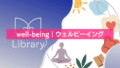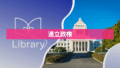2027年、横浜で世界中の花と人が集まる「横浜国際園芸博覧会(GREEN×EXPO 2027)」が開かれます。
テーマは 「幸せを創る明日の風景」。
花や緑、都市と人、そして“未来の幸せ”を考える大きなプロジェクトです。
この記事では、開催地の上瀬谷通信施設跡地の再開発や、横浜市の取り組み、
世界の花博との違い、家族で楽しめる体験エリア、SDGsとのつながりまでをわかりやすく解説します。
自由研究のアイデアにも使える「花と未来の学び」も紹介!
花が咲き、人が笑い、未来が育つ――。
Expo 2027は、**“花と緑が描く新しい幸福のかたち”**を世界に発信します。
- 横浜国際園芸博覧会(GREEN×EXPO 2027)とは?いつ・どこで開かれるの?
- 会場となる上瀬谷通信施設跡地|横浜の新しい“みどり都市”プロジェクト
- 横浜市の取り組みと予算|行政が支える花と未来のまちづくり
- テーマ「幸せを創る明日の風景」|花・緑・人がつながる未来都市とは
- GREEN×EXPO 2027のマスコット「トゥンクトゥンク(Tunku Tunku)」|花と未来をつなぐ精霊
- 国際園芸博覧会とは?世界と日本の花博の歴史
- 横浜博覧会 YES’89との違い|経済の時代から幸福と環境の時代へ
- GREEN×EXPO 2027の見どころ・体験エリア|子どもも家族も楽しめる博覧会
- GREEN×EXPO 2027とSDGs・well-being|“幸せな未来”をデザインする博覧会
- 自由研究に使える!花と未来の探究テーマ
- おさらいクイズ|Expo 2027と横浜の挑戦を復習!
- まとめ|花と未来でつながる都市・横浜から世界へ
横浜国際園芸博覧会(GREEN×EXPO 2027)とは?いつ・どこで開かれるの?
2027年、日本の横浜で世界中から注目を集める一大イベントが開かれます。
その名は 「横浜国際園芸博覧会(GREEN×EXPO 2027)」。
花・緑・人・都市がつながり、“幸せを創る明日の風景” をテーマにした、
地球規模の博覧会です。
会場となるのは、横浜市瀬谷区・旭区にまたがる「旧上瀬谷通信施設跡地」。
アメリカ軍の通信基地として使われていた広大な土地(約100ヘクタール)を再生し、
緑と花で彩られた“未来の都市モデル”として生まれ変わります。
この地が選ばれたのは、横浜が「港町の国際性」と「自然共生の都市構想」を
どちらも備えているからです。
開催期間は 2027年3月19日(金)から9月26日(日)までの192日間。
ちょうど春から秋にかけて、花がもっとも美しい季節に行われます。
期間中は、世界60か国以上の国と地域が参加し、
世界各地の花・園芸・緑化技術・都市デザインが一堂に集まる予定です。
主催は日本政府と横浜市、農林水産省、そして
**AIPH(国際園芸家協会)とBIE(博覧会国際事務局)**の公認を受けた国際博覧会。
この「A1クラス」認定というのは、花博の中でもっとも規模が大きく、
開催には国際的な信頼と準備が必要な格付けです。
過去にはオランダ、ドイツ、中国、カタールなどがこのクラスで開催してきました。
Expo 2027は、日本にとって約40年ぶりのA1クラス花博となります。
前回は1990年、大阪で開かれた「花の万博(EXPO’90)」でした。
つまり今回は、日本が再び“花と未来”をテーマに世界とつながる歴史的な舞台なのです。
来場者は 約1500万人 を見込んでおり、
経済効果だけでなく、教育・環境・観光の面でも大きな波及効果が期待されています。
Expo 2027の特徴は、単なる“花の祭典”ではなく、
**「人と自然の共生」「持続可能な都市」「幸福(well-being)」**を
同時に描く点にあります。
花や緑を楽しむだけでなく、環境保全・再生可能エネルギー・福祉など、
未来の都市のあり方を考える「体験型博覧会」になるのです。
横浜市の山中竹春市長は、博覧会を
「**市民が主役になれる“まちの実験場”**にしたい」と語っています。
市民ボランティアや学校との連携プログラムも進んでおり、
子どもたちが“花と未来”を学ぶ教材としても活用できる構想です。
さらに、地元企業や大学も参加する予定で、
地域全体で“みどりのレガシー(遺産)”を未来へ残す挑戦が進められています。
GREEN×EXPO 2027の公式ロゴは、
花の色と人の笑顔をモチーフにした「輪」のデザイン。
これは、「人と自然、都市と世界がつながる」ことを象徴しています。
華やかでありながら、環境と幸福をテーマにした博覧会として、
横浜から世界へ新しい価値観を発信する場となるでしょう。
クイズ①
GREEN×EXPO 2027(横浜国際園芸博覧会)について正しい説明はどれでしょう?
- 横浜市の上瀬谷通信施設跡地で開催される、花と緑の国際博覧会
- 大阪市の海沿いにある人工島で開催される建築の万博
- 東京の上野公園で開かれる国内限定の園芸展示会
正解は 1 です。
👉 GREEN×EXPO 2027は横浜市瀬谷区・旭区にまたがる「旧上瀬谷通信施設跡地」で開かれる国際博覧会。
花・緑・人・都市の共生をテーマに、世界中の国が参加する予定です。
会場となる上瀬谷通信施設跡地|横浜の新しい“みどり都市”プロジェクト
GREEN×EXPO 2027の会場となる「上瀬谷通信施設跡地(かみせやつうしんしせつあとち)」は、
横浜市瀬谷区と旭区にまたがる、**広さおよそ100ヘクタール(東京ドーム約20個分)**にもなる広大な土地です。
かつてここには、アメリカ海軍が使用していた通信施設があり、
1940年代から2015年までの約70年間、立ち入りが制限された“閉ざされたエリア”でした。
返還後、横浜市はこの場所を「次世代の環境都市づくり」の拠点にするため、
“グリーンインフラ”を活かした再開発計画を進めています。
グリーンインフラとは、木や花、土、水など自然の力を都市に取り入れ、
災害対策や温暖化防止にもつなげる仕組みのことです。
上瀬谷では、GREEN×EXPO 2027をきっかけに
「自然と人が調和した“みどりのまち”」をモデルとして世界に発信します。
博覧会会場は「花と緑のゾーン」「国際交流ゾーン」「未来都市ゾーン」に分けられ、
花の展示だけでなく、環境技術・スマート農業・再生エネルギーなど、
“未来の暮らし”を体験できるテーマパークのような空間になる予定です。
園芸と科学、アートと教育が一体化した空間として、
“花の博覧会”を超えた“未来共創の博覧会”をめざしています。
また、会場周辺では交通アクセスの整備も進んでいます。
相鉄線「瀬谷駅」から会場までを結ぶ新しい道路建設や、
臨時バスルートの計画、駐車場・シャトルバス運行なども検討中です。
市民が安全に訪れやすい“動線づくり”を重視しており、
バリアフリー設計や自転車道整備も含まれています。
博覧会後は、敷地の大部分が「上瀬谷公園」として再整備される予定です。
この公園には、防災拠点・災害時避難広場・環境教育施設なども設けられ、
市民の暮らしに長く役立つ“レガシー(遺産)”として残されます。
つまりGREEN×EXPO 2027は、半年間のイベントで終わらず、
**横浜の未来のまちづくりを進める「種」**になるのです。
地域の小中学校や高校とも連携し、
「上瀬谷みどり学習プログラム」や「花と未来プロジェクト」など、
こどもたちが環境問題を学び、まちづくりに参加する取り組みも始まっています。
また、周辺の農地や商店街も博覧会と連携し、
地産地消・地元農産物の販売・観光ルートの開発など、地域経済の活性化にもつながっています。
横浜市はこのプロジェクトを“100年後の横浜を見すえた挑戦”と位置づけています。
自然・防災・交通・教育・産業をひとつに結ぶ“統合型まちづくり”の象徴として、
GREEN×EXPO 2027の会場整備が進められているのです。
都市開発の中に花や緑を中心に据えたモデルは、
世界的にも注目を集めており、**「環境から発想する都市」**という
横浜の新しいアイデンティティを築こうとしています。
クイズ②
GREEN×EXPO 2027の会場「上瀬谷通信施設跡地」に関する説明で、正しいものはどれでしょう?
- アメリカ海軍の通信基地跡地で、現在は再開発が進められている
- 昔から市民の公園として利用されてきた場所で、今も桜並木が残る
- 横浜港近くの人工島に作られた埋め立て地である
正解は 1 です。
👉 上瀬谷通信施設跡地は、かつてアメリカ海軍の通信基地だった場所。
返還後、GREEN×EXPO 2027の会場として“みどり都市”へと生まれ変わる計画が進められています。
横浜市の取り組みと予算|行政が支える花と未来のまちづくり
GREEN×EXPO 2027(横浜国際園芸博覧会)は、単なるイベントではなく、
横浜市が未来の都市像を描くための国家級プロジェクトです。
横浜市はこの博覧会を、「花と緑を通じて幸せな社会をつくる挑戦」と位置づけ、
環境・観光・教育・福祉のすべてをつなぐ“まちづくり政策”として進めています。
まず注目されるのは、その予算規模の大きさです。
GREEN×EXPO 2027の総事業費は約800億円規模とされ、
そのうち横浜市が負担するのはおよそ700億円前後。
国(農林水産省など)と企業協賛、入場料収入なども合わせて運営されます。
この巨額の投資は単に博覧会を成功させるためではなく、
**「博覧会後も横浜の財産として残す仕組み」**をつくることが目的です。
横浜市はこのために、GREEN×EXPO 2027を「市民と共に創る博覧会」として設計しました。
市の予算には、
- 上瀬谷通信施設の基盤整備(道路・上下水道・電力)
- 公園・イベント広場・防災拠点整備
- 市民参加型の花壇・植栽プロジェクト
- 教育・文化連携プログラム
などが含まれています。
特に力を入れているのが、広報と市民参加です。
横浜市は公式サイト「GREEN×EXPO 2027 YOKOHAMA」を中心に、
市民向けにわかりやすい情報発信を行っています。
また、市の広報紙「広報よこはま」やSNS(X・Instagram・YouTubeなど)を通じて、
ロゴマークの意味や開催準備の進捗を定期的に紹介。
さらに、市内18区で出前説明会やパネル展示を開催し、
地域ごとに市民の意見を反映する仕組みを整えています。
博覧会のシンボルとなるロゴは、
「花びらの輪」がつながって人と自然の調和を表現したデザイン。
市民からの公募を経て決定され、現在は
「みどりのアンバサダー(市民応援団)」制度として、
地域の学校・企業・NPOなどが共同で広報を担っています。
また、ボランティア育成も横浜市の重要な取り組みです。
高校生・大学生・社会人が対象で、
「花と環境」「観光案内」「国際交流」などの分野に分かれて活動します。
将来的には3万人規模のボランティアチームを形成し、
市民が“運営の一員”として博覧会を支える計画です。
博覧会後の“レガシー(遺産)”も明確に描かれています。
会場となる上瀬谷通信施設跡地は、博覧会終了後に
**「上瀬谷公園」や「環境教育ゾーン」**として整備され、
市民が自然に親しみながら学べる拠点になります。
また、周辺道路・公共交通の整備はそのまま地域の利便性向上につながり、
長期的には横浜西部地域の都市価値を高める基盤となります。
このように、GREEN×EXPO 2027は“半年の博覧会”にとどまらず、
**「50年後の横浜を変えるまちづくりプロジェクト」**として進められているのです。
市民と行政が協力しながら、環境・幸福・教育を柱にした“未来都市”を育てる――
その挑戦が、いま着々と進行しています。
クイズ③
横浜市が進めているGREEN×EXPO 2027の取り組みとして、正しいものはどれでしょう?
- 市の費用をできるだけ抑え、短期間のイベントだけで終了する
- 予算をかけて基盤整備や市民参加を重視し、長期的なまちづくりにつなげる
- 海外の主催団体に運営を任せ、市の関与を最小限にする
正解は 2 です。
👉 GREEN×EXPO 2027は、市民と行政が協力して進めるまちづくり型の博覧会。
横浜市は700億円規模の投資を行い、環境・教育・交通などを含めた
「未来の横浜づくり」を見すえた長期プロジェクトとしています。
テーマ「幸せを創る明日の風景」|花・緑・人がつながる未来都市とは
GREEN×EXPO 2027のメインテーマは、
「幸せを創る明日の風景(Scenery of the Future for Happiness)」。
この言葉には、花や緑を通して“人がよりよく生きる未来”を描こうという願いが込められています。
「幸せ」というと、多くの人が“お金があること”“便利に暮らせること”を思い浮かべます。
しかし、GREEN×EXPO 2027が目指す幸せは、それよりもっと広く深いもの。
それは、人と自然が共に生き、心が満たされ、社会のつながりを感じられる幸せです。
この考え方は、近年注目されている well-being(ウェルビーイング)=「よりよく生きる」 という概念と強くつながっています。
横浜は、海・山・公園・街のすべてが近くにある「自然と都市の融合都市」。
GREEN×EXPO 2027ではその特性を生かし、都市の中で自然と共生するデザインを実際に体験できる展示を行います。
花や緑の空間だけでなく、
風や光、音、水などの自然エネルギーを活かした「五感で感じる展示」も予定されています。
つまり、見るだけでなく、“感じる・学ぶ・つながる”ことがこの博覧会の特徴なのです。
テーマに込められた「創る(Create)」という言葉も重要です。
GREEN×EXPO 2027では、来場者がただ受け身で観るのではなく、
自分たちで“未来の幸せ”をデザインする参加型の展示が多く計画されています。
たとえば、子どもたちが植物を植え、ドローンやAIを使って生育を観察するプログラムや、
世界各国の花の文化を学びながら自分の「理想の庭」をデザインする体験など。
こうした展示を通して、「幸せは誰かが作ってくれるものではなく、自分で育てていくもの」
というメッセージを伝えています。
また、このテーマは国際的にも大きな意義を持っています。
GREEN×EXPO 2027は、国連が掲げる SDGs(持続可能な開発目標) と深く関係しています。
特に、
- 目標3「すべての人に健康と福祉を」
- 目標11「住み続けられるまちづくりを」
- 目標13「気候変動に具体的な対策を」
といった項目を、花と緑を通して体験的に学べる設計になっています。
展示の一部では、都市のヒートアイランド対策、
生態系を守る緑化技術、再生可能エネルギーの活用なども紹介される予定です。
つまり「幸せを創る明日の風景」とは、
**環境のバランスを保ちながら、心と社会を豊かにする“新しい幸福の形”**を意味しているのです。
さらにGREEN×EXPO 2027の理念は、横浜市が進める「環境未来都市」構想とも重なります。
市民・企業・大学・行政が連携し、
環境にやさしい技術と人の心の豊かさを両立させる取り組みが進行中です。
横浜がこのテーマを掲げるのは、単なる花の街づくりではなく、
“人が自然の中で幸せに生きる”という世界共通の課題に答えるためなのです。
クイズ④
GREEN×EXPO 2027のテーマ「幸せを創る明日の風景」で伝えたいこととして、最も近いものはどれでしょう?
- 花をたくさん育てて経済的な成功を目指すこと
- 便利で近未来的な都市をつくることに集中すること
- 自然と人が共に生き、心と社会のつながりから幸せを育てること
正解は 3 です。
👉 GREEN×EXPO 2027が目指すのは、自然と人が調和し、社会のつながりを大切にする“持続可能な幸福”。
花と緑を通して、心・社会・地球のすべてが豊かになる未来を描いています。
GREEN×EXPO 2027のマスコット「トゥンクトゥンク(Tunku Tunku)」|花と未来をつなぐ精霊
2027年に横浜で開催される「国際園芸博覧会(GREEN×EXPO 2027)」には、
花や緑、人、そして未来をつなぐ不思議な仲間がいます。
その名は、公式マスコットキャラクターの 「トゥンクトゥンク(Tunku Tunku)」。
かわいらしい姿と奥深いメッセージで、すでに多くの人の注目を集めています。
この記事では、名前の由来や性格、デザイン、誕生の背景などを、
子どもにもわかりやすく、そして正確な情報で紹介します。
🌼 名前の由来と意味
「トゥンクトゥンク」という名前は、2024年6月22日に行われた「開催1000日前記者発表会」で発表されました。
公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会が実施した一般公募では、なんと6,076件もの応募があり、
その中から北原やえさんの作品「トゥンクトゥンク」が選ばれました。
発表当日は、GREEN×EXPO 2027の公式アンバサダーである芦田愛菜さんが登壇。
「私にとってマスコットキャラクターは、一緒に博覧会の魅力を発信していくパートナーのような存在です」と語り、
トゥンクトゥンクが「人と自然をつなぐシンボル」であることを紹介しました。
“トゥンク”という言葉は、心の鼓動や生命のリズムを表す音。
2回繰り返すことで「共に生きる」「響き合う」という意味になります。
つまりトゥンクトゥンクは、すべての命と心が共鳴する存在。
GREEN×EXPO 2027のテーマ「幸せを創る明日の風景」とも深く結びついており、
花や木、風、光、水――この星に生きるすべてのものが持つ“いのちのリズム”を感じ取る力を象徴しています。
🌱 トゥンクトゥンクの性格と特徴
トゥンクトゥンクは、はるか宇宙の彼方から地球に憧れてやってきた精霊です。
花や木、風や石、動物など、あらゆる命の「気持ち」に共鳴し、
その思いを人に伝えることができます。
地球がきれいで自然が元気なときには嬉しそうに踊り、
花を咲かせて笑顔を見せます。
けれど、地球が汚れてしまったり、環境が傷つくと、
悲しそうに静まりかえり、元気をなくしてしまいます。
その姿はまるで、**“地球の気持ちを映す鏡”**のようです。
性格はとても好奇心旺盛で、ドキドキ・ワクワクすることが大好き。
知らない世界を見るのが好きで、いつも枠を飛び越えようとします。
公式プロフィールにも「わくから外れて飛び出そうとする」とあり、
この「枠を越える」という性質は、GREEN×EXPO 2027が大切にする
**“多様性と創造の精神”**そのものを表しています。
夢は「みんなの気持ちがつながって、みんながなかよしになること」。
人と人、自然と都市、国と国――
すべてのつながりが調和して笑顔になる未来を目指しているのです。
💫 ビジュアルデザインと世界観
トゥンクトゥンクをデザインしたのは、映像ディレクター・アートディレクターの牧野惇(まきの あつし)さんです。
生命の多様性や自然の循環を表現するため、
芽吹き・雫・種子・細胞など“生命の始まり”をモチーフにしています。
色は、花や緑をイメージしたピンクやグリーンのグラデーション。
透明感のある光沢は水や空気のきらめきを表し、
丸く柔らかいフォルムは「命のぬくもり」と「自由な形」を象徴しています。
特徴的なのは、見る人によって表情が違って見えること。
笑っているようにも、考えているようにも見える――
この“あいまいさ”こそが、トゥンクトゥンクの魅力です。
それぞれの心に寄り添い、見る人の気持ちに共鳴するように設計されています。
🌍 トゥンクトゥンク誕生の背景
2024年6月22日に行われた記者発表会では、
マスコットの名前発表と同時に、市民参加の仕組み「メッセージ付き公式ロゴマーク」も紹介されました。
この制度は、「GREEN×EXPO 2027」を応援する個人や団体、教育機関が、
博覧会を応援する気持ちを込めたロゴマークを自由に使用できるというものです。
申し込みは2024年7月1日から始まり、全国の学校や地域で活用されています。
つまりトゥンクトゥンクは、単なるキャラクターではなく、
**“市民とともに育つ博覧会の仲間”**なのです。
子どもたちが描く未来の地球像や、地域の花づくり活動ともつながっていきます。
🌸 トゥンクトゥンクの活動とこれから
トゥンクトゥンクは、2024年の国際会議「TICAD 9 横浜歓迎レセプション」で初登場しました。
その後、GREEN×EXPO 2027の広報イベントやポスター、SNSに登場し、
横浜市の環境学習や学校プロジェクトでも活用されています。
今後は会場での案内キャラクター、グッズ展開、映像出演など、
“動くトゥンクトゥンク”としてさまざまな形で登場予定。
ぬいぐるみやキーホルダー、文房具などのグッズも企画されています。
また、大阪・関西万博(Expo 2025)のマスコット「ミャクミャク」と並び、
“日本の博覧会マスコット”として世界にも発信されています。
🌼 トゥンクトゥンクが伝えるメッセージ
トゥンクトゥンクは、ただのかわいいキャラクターではありません。
それは、地球の声を代弁する存在でもあります。
自然が元気なときは花を咲かせて踊り、
環境が傷つくと涙を流して静かになります。
この姿には、「自然と人のつながりを忘れないで」というメッセージが込められています。
トゥンクトゥンクは、花と人と地球の“感情をつなぐセンサー”。
私たちが自然を大切にすれば、トゥンクトゥンクも笑顔になり、
その笑顔がまた地球を元気にする――そんな循環を伝えているのです。
GREEN×EXPO 2027が描く“幸せな未来”とは、
人と自然が共に生き、心の鼓動(トゥンクトゥンク)でつながる世界。
花が咲き、風がめぐり、人が笑うその未来を、
トゥンクトゥンクは私たちと一緒に見つめています。
クイズ⑤
トゥンクトゥンク(Tunku Tunku)の特徴として、最も正しいものはどれでしょう?
- 建物をモチーフにしたロボットキャラクター
- 海の生き物をモデルにした動物キャラ
- 宇宙から来た精霊で、人と自然の心をつなぐ存在
正解は 3 です。
👉 トゥンクトゥンクは、宇宙の彼方から地球にやってきた精霊。
花や木、風や石の気持ちに共鳴し、自然と人の心をつなぐGREEN×EXPO 2027の象徴です。
国際園芸博覧会とは?世界と日本の花博の歴史
「国際園芸博覧会(International Horticultural Exposition)」とは、
花や緑、自然との共生をテーマに、世界各国が集まって展示や交流を行う国際的な博覧会のことです。
略して「国際花博(花の万博)」とも呼ばれます。
国際博覧会(万博)と同様に、**AIPH(国際園芸家協会)**という世界組織の承認を受けて開催され、
一定の基準を満たすことで **BIE(博覧会国際事務局)**の認定も得られます。
AIPHは1948年に設立された、世界中の園芸関係者による国際組織で、
花と緑を通して「よりよい社会」を築くことを目的に活動しています。
そのAIPHが承認する博覧会には、規模や内容によって A1・B・C・Dクラス という区分があります。
なかでも A1クラスは“最高格付け”にあたり、
国家レベルでの開催が求められ、準備期間も数年単位。
GREEN×EXPO 2027は、このA1クラスに認定された世界でも数少ない花博のひとつです。
🌏 世界の国際園芸博覧会
これまでA1クラスの国際園芸博覧会は、
オランダ・ドイツ・中国・トルコ・カタールなど、自然と文化の共生を重んじる国々で開かれてきました。
近年では、2023年にドーハ(カタール)で開催された花博が記憶に新しいです。
その博覧会では「乾いた土地に緑を取り戻す」というテーマのもと、
砂漠に巨大な花の庭園をつくり、世界中に環境再生のメッセージを発信しました。
国際園芸博覧会の周期はおおよそ数年ごとで、
世界各地が持ち回りで開催します。
GREEN×EXPO 2027は、ドーハに続く次の開催国として承認され、
アジアではおよそ20年ぶりのA1クラス花博となります。
その意味でも、日本の開催は世界的な園芸文化のリーダーシップを示す大きな一歩なのです。
🌸 日本での花博の歴史
日本で初めてA1クラスの国際園芸博覧会が開かれたのは、**1990年の大阪花の万博(EXPO’90)**です。
「自然と人間の共生」をテーマに、184日間にわたり開催され、
来場者は約2300万人を超える大成功を収めました。
この大阪花博は、Expo 2027にもつながる「自然と共に生きる社会」を提唱した先駆けでした。
その後も、2000年の淡路花博(兵庫県)、**2004年の浜名湖花博(静岡県)**など、
日本各地で花と緑をテーマにした博覧会が行われ、地域の発展や観光振興に貢献してきました。
これらの経験が、今回の横浜開催につながっています。
GREEN×EXPO 2027は、こうした花博の伝統を受け継ぎながらも、
「環境」や「幸福(well-being)」といった現代的テーマを重ねた“新しい形の博覧会”です。
花を飾るだけでなく、都市、科学、福祉、教育を結びつける総合的なイベントへと進化しているのです。
🌼 花博がもたらす意味
国際園芸博覧会は、単なる観光イベントではありません。
それは、人類が“自然とどう共に生きるか”を考える実験の場です。
どの国の花も、気候も、文化も違いますが、
その多様性を一堂に集め、互いに学び合うことこそが花博の本質。
そこに「平和・共生・幸福」という普遍的なメッセージが込められているのです。
クイズ⑥
国際園芸博覧会(花博)について正しい説明はどれでしょう?
- 国内の園芸団体が中心となって開催する地方イベントのこと
- AIPHとBIEの認定を受け、世界各国が参加する国際的な花と緑の博覧会
- 花を販売するための商業見本市で、参加国は限定されている
正解は 2 です。
👉 国際園芸博覧会は、AIPH(国際園芸家協会)が認定する国際的な花と緑の祭典。
GREEN×EXPO 2027はA1クラスに位置づけられ、日本では大阪花博以来の開催となります。
横浜博覧会 YES’89との違い|経済の時代から幸福と環境の時代へ

GREEN×EXPO 2027が開かれる横浜には、実はもう一つの“博覧会の記憶”があります。
それが、**1989年に開催された「横浜博覧会 YES’89」**です。
この博覧会は、横浜開港130周年と市制100周年を記念して開催され、
みなとみらい地区の開発を全国に発信するための一大イベントでした。
会場は現在の「横浜コスモワールド」や「ワールドポーターズ」周辺一帯。
当時はまだ再開発が始まったばかりの場所で、
YES’89はまさに**“みなとみらい誕生のきっかけ”**となりました。
期間は1989年3月から10月までの約7か月間、
来場者は約1,300万人にのぼり、地方博としては異例の成功を収めました。
シンボルとなったのは、高さ112.5メートルの観覧車「コスモクロック21」。
この観覧車は博覧会終了後に「コスモワールド」として残され、
今でも横浜のシンボルとして輝き続けています。
つまり、YES’89は**「経済と都市開発の象徴」**として、
横浜の新しい街の顔をつくり出した博覧会だったのです。
一方、GREEN×EXPO 2027は“まったく別の方向”を目指しています。
YES’89が経済成長と都市開発を掲げていたのに対し、
GREEN×EXPO 2027は「幸福」「環境」「共生」といった、人の心に根ざしたテーマに重きを置いています。
30年以上の時を経て、“豊かさの価値観”が大きく変化したのです。
YES’89の時代、日本はバブル経済の真っ只中。
“モノを増やすこと”が豊かさの象徴でした。
それに対し、GREEN×EXPO 2027が目指すのは、
“心の満足”や“自然との調和”を通して人々の幸福を育てること。
この違いは、まさに「経済の時代からwell-beingの時代へ」の転換と言えるでしょう。
また、展示の内容にも大きなちがいがあります。
YES’89では「横浜未来都市」「科学とテクノロジー」「海洋開発」など、
当時の最先端技術を見せる“ショー型展示”が中心でした。
Expo 2027では、花・緑・環境・人・教育・福祉など、
**社会課題に向き合いながら未来を共につくる“参加型展示”**に変わっています。
たとえば、世界各国のパビリオンでは「花と気候」「緑の再生」「地域の幸福度」などをテーマに、
来場者自身が考え、体験し、行動につなげる仕組みが導入される予定です。
「見る博覧会」から「共に考える博覧会」へ――それがGREEN×EXPO 2027の最大の特徴です。
もう一つの違いは、“レガシー(遺産)”への考え方です。
YES’89では、博覧会の後に街のインフラ(道路・港湾・観覧車など)が残り、
都市としての発展に寄与しました。
GREEN×EXPO 2027では、人の心や社会の仕組みを未来へ残すことが目的です。
花や緑の文化、環境教育、地域の協働など、
“人と自然のつながり”という見えないレガシーを次世代に引き継ぎます。
このように、同じ横浜で行われる二つの博覧会は、
目的もメッセージもまったく異なります。
それでも共通しているのは、「未来への希望を描く」という点です。
都市が変わり、人が変わり、社会が成熟していく中で、
博覧会という“まちの祭典”は、いつの時代も**「次の横浜」を映す鏡**なのです。
クイズ⑦
1989年の横浜博覧会(YES’89)とGREEN×EXPO 2027の違いとして、最も正しいものはどれでしょう?
- YES’89は環境、GREEN×EXPO 2027は経済をテーマにしている
- 両方とも同じ場所・同じテーマで行われる予定である
- YES’89は都市開発中心、GREEN×EXPO 2027は幸福・環境中心の博覧会である
正解は 3 です。
👉 YES’89はみなとみらい地区の都市開発を目的とした経済的な博覧会、
GREEN×EXPO 2027は「花と幸福」「人と自然の共生」をテーマにした環境・文化の博覧会です。
時代の変化とともに“豊かさの意味”が大きく変わっています。
GREEN×EXPO 2027の見どころ・体験エリア|子どもも家族も楽しめる博覧会
GREEN×EXPO 2027(横浜国際園芸博覧会)は、花と緑の祭典であると同時に、
世代を超えて“学び・遊び・つながる”ことができる体験型博覧会です。
「花を見る」だけでなく、「花から未来を考える」展示がたくさん用意されています。
会場は、横浜市瀬谷区・旭区の旧上瀬谷通信施設跡地に広がる広大な100ヘクタールの敷地。
その中に、いくつものテーマゾーンが設けられます。
たとえば、世界各国の花と文化を紹介する「国際パビリオンゾーン」、
横浜市や日本企業が最新の環境技術を紹介する「未来共創ゾーン」、
そして花とアートが融合した「ガーデンアートゾーン」などです。
まるでひとつの小さな“地球の縮図”を歩いているような感覚を味わえるでしょう。
中でも注目されているのが、**「子ども向けSTEAM・自然体験エリア」**です。
ここでは、植物の光合成を学んだり、
顕微鏡で花粉や葉脈の構造を観察したりできるブースが設置されます。
また、AIやドローンを使った植物モニタリングの体験など、
科学と自然が一体化した“学びの森”のような空間がつくられる予定です。
さらに、親子で楽しめる**「ファミリーゾーン」**も充実。
花の迷路、自然素材を使った工作教室、夜に光るライトアップガーデンなど、
“遊びながら学べる仕掛け”が盛りだくさんです。
季節ごとの特別イベントとして、春のチューリップフェスティバル、
夏のグリーンアート展、秋の収穫フェアなども企画されています。
GREEN×EXPO 2027は、花や植物を通して「地球の未来」を考えることを目指しています。
たとえば、展示の一部では再生可能エネルギーを活用して電力をまかなう取り組みが行われ、
来場者が歩く動線にも「循環型設計」や「CO₂削減設計」が導入されます。
こうした**“環境にやさしい博覧会”**という仕組みそのものが、学びの題材になるのです。
また、**「ボランティア参加」や「市民パートナー活動」**も見どころのひとつ。
高校生や大学生、市民団体などが案内・翻訳・運営サポートを行い、
「自分が博覧会の一員になる」体験ができます。
特に子ども向けには、「花と未来キッズ大使」や「みどり探偵団」など、
探究型プログラムの導入も検討されています。
来場者がただの観客ではなく、“共に作る側”になれるのがGREEN×EXPO 2027の特徴です。
もちろん、食や文化の楽しみも欠かせません。
地元横浜の食材を活かしたフードエリア、世界の花をテーマにしたスイーツ、
リユース容器を使ったエコカフェなど、
“食を通して環境を学ぶ”仕組みも整っています。
夜には光と音の演出によるナイトガーデンが登場し、
昼間とは違った幻想的な風景を楽しむことができます。
このように、GREEN×EXPO 2027は「見る・学ぶ・感じる・参加する」のすべてを満たす博覧会です。
子どもたちが未来を感じ、大人たちが自然の力を再発見し、
家族みんなで**「花と緑から生まれる幸せ」**を共有できる場所。
まさに“学びと感動のエコテーマパーク”なのです。
クイズ⑧
GREEN×EXPO 2027の体験エリアの特徴として、正しいものはどれでしょう?
- 花や自然と科学を組み合わせ、子どもから大人まで学べる体験型の展示がある
- 見るだけの展示が中心で、触ったり学んだりすることはできない
- 入場者は大人限定で、子どもは安全上の理由で入れない
正解は 1 です。
👉 GREEN×EXPO 2027では、花と緑をテーマにしたSTEAM教育・自然観察・環境体験が充実。
子どもや家族が“参加して学べる博覧会”として、世界でも注目されています。
GREEN×EXPO 2027とSDGs・well-being|“幸せな未来”をデザインする博覧会
GREEN×EXPO 2027(横浜国際園芸博覧会)は、花や緑の美しさを楽しむだけではなく、
地球と人の“よりよい未来”をデザインする博覧会です。
その中心にあるのが、国連が提唱する SDGs(持続可能な開発目標) と、
近年世界的に注目されている well-being(ウェルビーイング:幸福・心の健康) の考え方です。
🌏 SDGsとGREEN×EXPO 2027のつながり
SDGsは、2015年に国連で採択された17の国際目標で、
「貧困をなくす」「質の高い教育」「気候変動への対策」「平和と公正」など、
地球全体の持続可能な発展をめざすための指針です。
GREEN×EXPO 2027では、このSDGsを花と緑の視点から体験的に学べる仕組みが設けられています。
たとえば、目標11「住み続けられるまちづくりを」、
目標13「気候変動に具体的な対策を」、
目標15「陸の豊かさも守ろう」などをテーマにした展示が行われます。
会場内では、再生可能エネルギーの活用、雨水の再利用、
資源リサイクル、CO₂削減型の建築設計など、
“地球にやさしい運営”そのものが学びになる仕掛けが組み込まれています。
つまり、展示物を見るだけでなく、「博覧会全体がSDGsの実験室」なのです。
💚 well-beingと幸福のデザイン
もう一つの大きな柱が well-being(ウェルビーイング)。
これは単なる“幸せ”ではなく、心・体・社会・環境のすべてが調和して
「よりよく生きる」ことを意味します。
GREEN×EXPO 2027では、このwell-beingを「花と人の関係性」で表現します。
花を育てることで心が安らぐ、緑に囲まれてストレスが減る――
こうした“自然がもたらす幸福”を科学的に体験できるゾーンが設けられます。
たとえば、植物の香りで脳のリラックス反応を測定する実験展示や、
緑の中で体を動かして心拍数の変化を体感するワークショップなど、
**科学と感性を融合した「幸福の実験空間」**が展開される予定です。
さらに、花や植物を通して人と人がつながる体験も重視されています。
ボランティア活動、地域交流、福祉施設との連携展示などを通じて、
「誰もが社会の一員として貢献できる幸福」を感じられるよう設計されています。
GREEN×EXPO 2027が目指すのは、**“他者との共感から生まれる幸福”**です。
🌼 花がつなぐ未来へのメッセージ
GREEN×EXPO 2027のメインテーマ「幸せを創る明日の風景」は、
まさにこのSDGsとwell-beingの融合を象徴しています。
環境を守りながら、心豊かに生きる社会。
そのバランスをどう実現していくかを、花と緑の世界を通して考える。
それがGREEN×EXPO 2027が世界に伝えたいメッセージです。
花は、国境を越えて人の心をつなぎます。
自然と人間の調和を通じて、“地球と人が共に幸せになる”。
そんな新しい時代の価値観を、横浜から世界へ発信するのがGREEN×EXPO 2027なのです。
クイズ⑨
GREEN×EXPO 2027が重視している考え方として、最も正しいものはどれでしょう?
- 経済成長を最優先にして、人の幸福はあとから考える
- SDGsとwell-beingを結びつけ、環境と人の心の豊かさを両立させる
- 花の展示を中心にして、社会や環境の問題にはあまり触れない
正解は 2 です。
👉 GREEN×EXPO 2027は、花と緑を通じてSDGs(持続可能な開発)とwell-being(幸福)を結び、
「環境にも人にもやさしい未来」をデザインする国際博覧会です。
自由研究に使える!花と未来の探究テーマ
GREEN×EXPO 2027(横浜国際園芸博覧会)は、子どもたちの自由研究にぴったりのテーマがたくさんあります。
花や緑、環境、幸福、まちづくり――どの切り口からも「自分で調べ、考える力」を育てる絶好の素材です。
ここでは、学校の理科・社会・総合の時間でも使える探究テーマのアイデアを紹介します。
🌸 テーマ①:花と緑が人の気持ちに与える影響を調べよう
花を見ると、なぜ気持ちが明るくなるのでしょう?
心理学の研究では、植物や自然のある空間にいると、ストレスが減り、集中力が高まることが分かっています。
このテーマでは、「花のある部屋」と「花のない部屋」で感じ方を比べる実験をしてみましょう。
【調べ方の例】
- 花を飾った教室と、何もない教室で気分アンケートをとる
- 緑が多い公園とコンクリートの広場で、落ち着く時間を比べる
- 観葉植物の育ち方と自分の気持ちを日記に記録する
グラフにまとめたり、写真を使って発表したりすると、
「植物がもたらす幸福効果」を分かりやすく伝えられます。
🌿 テーマ②:都市の緑化と地球温暖化の関係を調べよう
都市では、アスファルトやビルが多く、熱がこもりやすくなります。
これをヒートアイランド現象といい、気温上昇の原因になります。
でも、木や芝生を植えることで、地面の温度が下がることが知られています。
【調べ方の例】
- 公園の地面とアスファルトの地面で温度を比較する
- 木の下と日なたの気温のちがいを測定する
- 緑の多い地域と少ない地域で、暑さの感じ方を比べる
このテーマは、SDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」とつながります。
「どうすればまちがもっと涼しく、住みやすくなるか?」を考える自由研究に発展させましょう。
🌺 テーマ③:世界の花博を比べてみよう
GREEN×EXPO 2027のような国際園芸博覧会は、世界中で開かれています。
このテーマでは、「日本以外の花博」と比べてみましょう。
【調べ方の例】
- 過去の開催地(オランダ、ドイツ、中国、カタールなど)を調べる
- テーマやデザイン、展示内容の違いをまとめる
- 各国が大切にしている「自然とのつき合い方」を比較する
地理や文化の学習にもつながり、
「国ごとの環境意識のちがい」を考える良いきっかけになります。
🌼 テーマ④:横浜の“みどりの場所”を調べてマップを作ろう
横浜は、都市でありながら緑が多いまちです。
上瀬谷地区のほかにも、三ツ沢公園や本牧山頂公園、こども植物園など、
花と自然にふれられる場所がたくさんあります。
【調べ方の例】
- 家や学校の周りにある「みどりの場所」をマップ化する
- 各公園で咲いている花や木の種類を写真で記録する
- 「緑が多いとまちはどう感じが変わるか」をまとめる
この研究を通して、身近な地域の良さや、
自然と人が共に生きることの意味に気づくことができるでしょう。
🌻 まとめポイント
どのテーマも、「見る・測る・感じる・考える」の4つを組み合わせると深い研究になります。
また、調べたことをポスターやスライドにまとめて発表すると、
「花と未来」「環境と幸福」というGREEN×EXPO 2027のテーマを、自分の言葉で伝える練習にもなります。
自由研究は、“答えを探す”よりも、“問いを見つける”ことが大切です。
あなたのまわりにも、花や緑、自然の中にたくさんの発見が隠れています。
小さな一歩から、未来を考える研究を始めてみましょう。
おさらいクイズ|Expo 2027と横浜の挑戦を復習!
これまで学んできたGREEN×EXPO 2027(横浜国際園芸博覧会)の内容を、クイズでおさらいしてみましょう!
花・緑・人・都市がつながる未来の博覧会について、あなたはいくつ覚えているかな?🌸
クイズ①
GREEN×EXPO 2027(横浜国際園芸博覧会)はどこで開催されるでしょう?
- 横浜市の上瀬谷通信施設跡地
- 東京の上野公園
- 大阪の夢洲地区
正解は 1 です。
👉 GREEN×EXPO 2027は、横浜市瀬谷区・旭区にある旧上瀬谷通信施設跡地を再開発して開催されます。
クイズ②
GREEN×EXPO 2027のメインテーマはどれでしょう?
- 経済とテクノロジーの発展
- 幸せを創る明日の風景
- 世界の花を競うコンテスト
正解は 2 です。
👉 花や緑、人、都市がつながる「幸せを創る明日の風景」がテーマ。
人と自然が調和した幸福な社会をめざしています。
クイズ③
1989年の横浜博覧会(YES’89)とGREEN×EXPO 2027の主な違いはどれでしょう?
- YES’89は経済中心、GREEN×EXPO 2027は幸福と環境中心の博覧会である
- 両方とも同じ会場・同じ目的で開催される
- YES’89は国際博覧会、GREEN×EXPO 2027は地域限定の展示である
正解は 1 です。
👉 YES’89は都市開発を目的とした経済型の博覧会、
GREEN×EXPO 2027は「幸福・環境・共生」をテーマとする新時代の花博です。
クイズ④
GREEN×EXPO 2027が重視している考え方として、正しいものはどれでしょう?
- 経済を最優先にして環境への配慮は少なめ
- SDGsとwell-beingを結びつけ、環境と人の幸福を両立させる
- 花の展示を中心にして社会課題には関わらない
正解は 2 です。
👉 GREEN×EXPO 2027は、花や緑を通じて「持続可能な社会」と「心の幸福(well-being)」を両立させることを目指しています。
クイズ⑤
横浜市がGREEN×EXPO 2027で特に力を入れている取り組みはどれでしょう?
- 市民参加やボランティア育成を通じた“共に創る博覧会”
- 海外の団体にすべて任せて市の関与をなくす
- イベントだけに集中して、博覧会後の活用は考えない
正解は 1 です。
👉 横浜市は約700億円規模の予算を投じ、市民ボランティアや教育連携など、
“未来の横浜づくり”につながる長期的なまちづくりを進めています。
💡 まとめチャレンジ!
5問すべて正解できた人は、もうGREEN×EXPO 2027マスター!
間違えたところがあっても大丈夫。
もう一度前の章を読み返して、花と緑の博覧会がめざす「未来の幸福」について考えてみましょう🌿
まとめ|花と未来でつながる都市・横浜から世界へ
GREEN×EXPO 2027(横浜国際園芸博覧会)は、単なる「花の祭典」ではありません。
それは、人と自然がどのように共に生き、幸せを築いていけるかを世界と考える場です。
かつての博覧会は、技術や経済の発展を見せるものでした。
しかし21世紀の今、私たちが求めるのは「便利さ」よりも「豊かに生きること」。
花や緑は、その原点を静かに思い出させてくれます。
GREEN×EXPO 2027が掲げるテーマ「幸せを創る明日の風景」は、
“成長の象徴”から“共生の象徴”へと変わった時代のメッセージなのです。
この博覧会の特徴は、「まちづくり」「教育」「環境」「文化」がすべてつながっていること。
上瀬谷通信施設跡地という、かつて閉ざされていた土地が、
いまは世界と未来をつなぐ“希望のフィールド”へと変わろうとしています。
そこでは、花が都市を彩り、人々の出会いが新しいアイデアを生み出し、
次の時代を生きる子どもたちが“未来の幸せ”を自分の手で描いていくのです。
GREEN×EXPO 2027の取り組みは、横浜市にとっても大きな挑戦です。
700億円を超える事業規模の中で、環境への配慮や防災・教育・観光・福祉など、
あらゆる分野を統合した**「持続可能なまちづくり」**が進められています。
博覧会が終わったあとも、上瀬谷地区は「上瀬谷公園」や環境学習の場として残り、
地域と世界をつなぐ“みどりのレガシー”となるでしょう。
GREEN×EXPO 2027の成功に欠かせないのは、市民一人ひとりの参加です。
ボランティア、学校連携、地元企業の協力、家庭での環境学習。
それぞれの小さな行動が集まって、博覧会を支える大きな力になります。
「花を植えること」「緑を守ること」「誰かを笑顔にすること」――
それらはすべて、GREEN×EXPO 2027のテーマに通じる“幸せを創る行動”なのです。
そしてこの博覧会は、横浜だけでなく、世界全体にメッセージを届けます。
“地球と人がともに幸せになれる未来を、私たちはデザインできる。”
それがExpo 2027の約束であり、横浜が次の世代に贈る希望です。
花と緑が咲き誇る未来都市――。
その景色を創るのは、誰でもない、いまを生きる私たち一人ひとりです。
この記事を書いた人
西田 俊章(MOANAVIスクールディレクター/STEAM教育デザイナー)
公立小学校で20年以上、先生として子どもたちを指導し、教科書の執筆も担当しました。
現在はMOANAVIを運営し、子どもたちが「科学・言語・人間・創造」をテーマに学ぶ場をデザインしています。