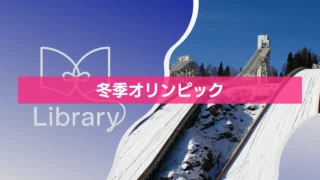チョーク&トークとは?
授業法の特徴と限界
個に寄り添う新しい学びへ
「チョーク&トーク」とは、教師が黒板に板書し、生徒がノートを写しながら授業を進める伝統的なスタイルです。効率的に知識を伝えられる一方で、受動的な学びになりやすく、現代の教育に求められる「個別最適化」や「主体的な学び」とのズレが指摘されています。
本記事ではチョーク&トークの特徴やメリット・デメリットを整理し、アクティブラーニングやICTとの違いを解説します。さらに、MOANAVIが実践する「個に寄り添った学び」との関係性についても紹介します。
チョーク&トークとは?授業法の定義
「チョーク&トーク(Chalk and Talk)」とは、教師が黒板に板書し、その内容を生徒がノートに写し取りながら授業を進めるスタイルを指します。日本の学校では長く主流となってきた授業形態であり、昭和から平成にかけて「授業=チョーク&トーク」といっても過言ではないほど一般的なものでした。
このスタイルでは、教師が教室の中心に立ち、知識を体系立てて効率的に伝達します。生徒は黒板に書かれた内容をノートにまとめ、教師の説明を聞きながら理解を深めていきます。
特徴とメリット
チョーク&トークには、以下のようなメリットがあります。
- 効率的な知識伝達:大人数の生徒に対して同じ内容を一斉に伝えられる。
- 板書による整理:教師が重要なポイントを板書することで、学習内容が体系的に理解できる。
- 準備が容易:教材やICT環境を整える必要がなく、チョークと黒板があれば授業が成立する。
- 反復と暗記に適している:板書を写す過程で内容を記憶しやすい。
これらの特徴は、知識の基礎を習得する段階では一定の効果を持っています。そのため、特に算数や理科など「手順を理解する必要がある教科」では、現在でも活用され続けています。
デメリットと限界
一方で、チョーク&トークにはいくつかの限界もあります。
- 受動的な学びになりやすい:生徒はノートを写すことが中心になり、自分で考える機会が少なくなる。
- 個々の理解度に対応しづらい:一斉授業で進むため、早く理解した子やつまずいている子に合わせるのが難しい。
- 主体性の育成が難しい:学習の方向性は常に教師主導となり、生徒が自ら問いを立てる学びに発展しにくい。
- 21世紀型スキルと相性が悪い:協働・創造・批判的思考などが求められる現代の学びには不十分。
このように、チョーク&トークは「効率的な知識伝達」という強みを持ちながらも、「個別最適化」「主体性」「協働」といった教育の新たな要請に十分応えられないという課題を抱えています。
アクティブラーニング・ICTとの違い
近年の教育改革では、アクティブラーニングやICT活用が重視されています。これらはチョーク&トークと対照的なアプローチです。
- アクティブラーニング
生徒同士の対話や協働を通じて学びを深める。知識を「受け取る」のではなく「活用する」力を育む。 - ICT活用
タブレットやオンライン教材を用いて、子ども一人ひとりの進度や理解度に合わせた学習が可能。
データに基づいたフィードバックも行いやすい。
チョーク&トークは「教師中心・一斉伝達型」、アクティブラーニングやICTは「学習者中心・個別最適化型」と整理できます。
つまり、現代の教育においては「チョーク&トークだけでは足りない」という認識が広がっており、一斉指導のメリットを活かしつつ、個別・協働学習をどう組み合わせるかが重要になっています。
個に寄り添った学びが求められる時代へ
教育現場では今、「個別最適化」と「協働的な学び」がキーワードになっています。子どもたちの学習スタイルや得意・不得意は一人ひとり異なるため、「全員に同じ方法で教える」だけでは十分ではありません。
- ノートを写すことが得意でない子
- 黒板を見ているだけでは集中が続かない子
- 逆に、板書を通じて理解を深める子
子どもの数だけ学び方があり、その多様性に対応する必要があるのです。
MOANAVIの実践:「個に寄り添う学び」
MOANAVIオルタナティブスクールでは、「チョーク&トーク」のような一斉伝達型ではなく、子どもが自分の学びを自分で選べる仕組みを取り入れています。
- STUDY POINTシステム
子ども自身が学ぶ量や内容を調整し、その行動をポイント化。達成感を得ながら主体的に学びを進める。 - STEAM教育・プロジェクト学習
実験や工作、地域活動を通して「やってみたい」気持ちから学びを広げる。 - 協働と社会参加
例えば「お祭りプロジェクト」では、子どもたちがゼロから企画し、地域や保護者とつながりながら活動を形にする。
こうした学びは、チョーク&トークの「一斉に同じ内容を伝える」スタイルとは対照的です。知識の伝達だけでなく、子どもが自分らしく学ぶことを大切にしている点がMOANAVIの強みです。
さらに、2026年4月には「モアナビ協創学園」が開校予定です。現在はMOANAVIオルタナティブスクールとして活動していますが、12月までは新規生徒の受け入れも行っています。来年度以降は、より本格的に「個に寄り添う教育」を実現する場として発展していきます。
まとめとこれからの教育
チョーク&トークは長年にわたり教育現場を支えてきた授業法であり、知識の定着には一定の効果があります。しかし、個々の子どもの多様性や21世紀型スキルが重視される現代においては、それだけに頼ることはできません。
これからは、チョーク&トークのメリットを生かしつつ、個に寄り添った学び・協働的な学び・ICTを活用した学びをどう組み合わせるかが重要です。
MOANAVIでは、子どもたちが「自分の学びを自分で選び、自分らしく成長できる」ように、さまざまな仕組みを実践しています。教育の未来を考えるとき、単なる授業法の比較にとどまらず、子どもの可能性を最大限に引き出す環境づくりが求められているのです。
記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)
STEAM教育デザイナー / MOANAVIスクールディレクター
理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。
📚 経歴・資格
✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者
✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)
✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)
✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演
✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説