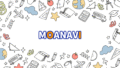小学生の不登校がもたらすリスクとは?
無理に学校に戻らない選択肢も考えよう
近年、不登校の小学生が増加しており、保護者としては「このままで大丈夫なのか?」と不安を抱えることも多いでしょう。不登校の状態が続くと、学習の遅れや社会とのつながりの減少など、さまざまなリスクが生じる可能性があります。
しかし、必ずしも「学校に戻ること」だけが解決策ではありません。本記事では、不登校がもたらすリスクを多角的に解説しつつ、無理に学校復帰を目指さない選択肢についても考えていきます。
不登校がもたらす主なリスク
1. 学習面の遅れと自己肯定感の低下
不登校になると、学校の授業を受けられないため、学習の遅れが生じることがあります。特に、読み書きや計算の基礎を学ぶ小学生の時期に学習機会が減ると、中学・高校になったときに「勉強についていけない」と感じることが増えるかもしれません。
また、「周りの子は勉強が進んでいるのに、自分は遅れている」という意識が生まれると、自己肯定感が低下し、「どうせ自分はダメだ」と思い込んでしまうこともあります。
【対策】
➡ 家庭学習やホームスクーリングを活用することで、学習の遅れを防ぐことができます。
➡ タブレット学習やオンライン教材を取り入れると、子どもが自分のペースで学習を進められます。
2. 社会とのつながりが減る
学校に行かないことで、友達や先生との関わりが減り、人とのコミュニケーションが少なくなります。特に小学生の時期は、友達と遊びながら社会性を学ぶ大切な時期です。その機会が減ると、将来的に対人関係に苦手意識を持ってしまうこともあります。
【対策】
➡ 公園や地域のイベントに参加することで、学校以外の友達を作ることができます。
➡ オンラインゲームやSNSを活用して、同じ興味を持つ子どもと交流するのも一つの方法です。
➡ オルタナティブスクールやフリースクールを活用すると、学校とは違う環境で社会的なつながりを持つことができます。
3. 昼夜逆転や生活習慣の乱れ
家にいる時間が長くなると、生活リズムが崩れやすくなります。特に、夜遅くまでゲームや動画を見て、昼夜逆転するケースもあります。生活習慣が乱れると、体調を崩しやすくなったり、気分が不安定になったりすることも。
【対策】
➡ 朝決まった時間に起きる習慣をつける(学校に行かなくてもOK)。
➡ 食事や運動のリズムを整える。特に、朝日を浴びると体内時計がリセットされやすくなります。
4. 家庭内のストレス増加
不登校が続くと、保護者も精神的な負担を感じやすくなります。「どうしたらいいの?」と悩み、親子関係がギクシャクしてしまうことも。親が焦ると、子どももプレッシャーを感じ、余計に家にこもってしまう悪循環に陥ることもあります。
【対策】
➡ 「無理に学校に行かせなくても大丈夫」と考え方を切り替える。
➡ 親自身もカウンセリングや不登校の親の会などで相談する。
無理に学校に戻らない選択肢
不登校の解決策は「学校復帰」だけではありません。子どもが安心して過ごせる環境を見つけることが大切です。
1. フリースクールやオルタナティブスクールを活用する
フリースクールやオルタナティブスクールは、学校以外の学びの場として注目されています。決められたカリキュラムではなく、子ども自身が興味を持ったことを学ぶスタイルが多く、「自分らしく学ぶ」ことができます。
🌟 おすすめポイント
✅ 学校より自由な環境で学べる
✅ 先生やスタッフが一人ひとりに寄り添ってくれる
✅ 同じような境遇の友達と出会える
2. ホームスクーリング(自宅学習)
家庭で学習を進める「ホームスクーリング」という方法もあります。最近では、オンライン教材や動画授業も充実しているため、学校に行かなくても学ぶ環境を整えることが可能です。
🌟 おすすめポイント
✅ 自分のペースで学べる
✅ 学校のストレスがない環境で学習できる
✅ 保護者と一緒に学ぶことで、安心感がある
3. 通信制・オンライン学習を活用する
小学生向けのオンラインスクールも増えており、パソコンやタブレットを使って学ぶことができます。学校の授業を補完する形で取り入れることで、学習面の遅れを防ぐことができます。
🌟 おすすめポイント
✅ 先生と直接やりとりしながら学べる
✅ 集団授業が苦手な子でも、自分のペースで進められる
✅ 学校の授業と並行して学ぶことも可能
まとめ:子どもに合った選択肢を見つけよう
不登校になると、「このままでいいのか」と不安になるかもしれません。しかし、大切なのは「子どもが安心して学び、成長できる環境」を見つけることです。
学校復帰だけが正解ではなく、フリースクール、オルタナティブスクール、ホームスクーリング、オンライン学習など、さまざまな選択肢があります。親子で話し合いながら、子どもに合った道を探していきましょう。
不登校は「問題」ではなく、「子どもに合った学びのスタイルを見つけるチャンス」かもしれません。焦らず、一歩ずつ前に進んでいきましょう。
MOANAVIのオルタナティブスクール

不登校の解決策として、オルタナティブスクールの活用は有効な選択肢の一つです。その中でも、MOANAVIは独自のカリキュラムと少人数制を採用し、子どもたち一人ひとりの学びを大切にしています。公立の小中学校と連携し、出席認定にも対応しているため、卒業資格の取得も可能です。
MOANAVIでは、STEAM教育を取り入れた学びを提供し、対話と体験を重視した環境で、子どもたちの創造性や問題解決能力を育成しています。また、近隣の図書館や美術館、動物園、博物館などの公共施設を積極的に活用し、豊かな学びを展開しています。
不登校でお悩みの保護者の方、そして新しい学びの場を探しているお子さまにとって、MOANAVIは安心して学べる環境を提供しています。まずはお気軽にご相談ください。
詳細はMOANAVIの公式サイトをご覧ください。
記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)
STEAM教育デザイナー / 株式会社MOANAVI代表取締役
理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。
📚 経歴・資格
✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者
✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)
✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)
✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演
✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説