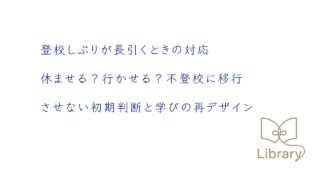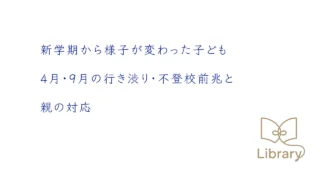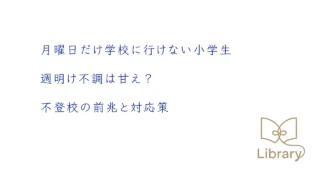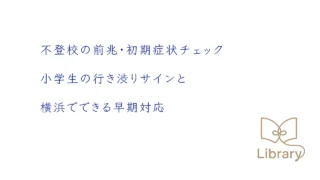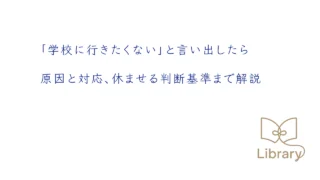二重符号化理論とは?
記憶の種類を活かした勉強法を具体例で解説
言葉+イメージで記憶力アップ!
「勉強したのにすぐ忘れてしまう…」
「暗記が苦手で覚えられない…」
そんな悩みを解決するカギが、二重符号化理論(Dual Coding Theory) と 記憶の種類の活用 です。
本記事では、心理学の知見をもとに「なぜ記憶に残るのか」を解説しながら、算数・国語・英語・理科・社会など教科別の具体的な勉強法、さらに家庭で取り入れられる工夫まで紹介します。
二重符号化理論とは?【基礎知識】
Dual Coding Theoryを提唱した心理学者ペイビオ
カナダの心理学者 アラン・ペイビオ(Allan Paivio) が提唱した「二重符号化理論」は、学習効果を高める心理学の理論として知られています。
言葉+イメージで記憶が強化される仕組み
人間の脳は情報を 言語的システム(言葉・文字)と 非言語的システム(図・映像・イメージ)の2つで処理しています。
この両方を組み合わせることで記憶が定着しやすくなります。
例:
- 英単語「apple」を文字だけでなく🍎のイラストと一緒に覚える
- 歴史の年号をただ暗記するのではなく、人物の似顔絵と一緒に覚える
➡ 言葉+イメージを活用することで「記憶の強化」が可能になります。
記憶の種類と学習への活用法
意味記憶
知識や概念を理解するための記憶。
例:九九、漢字の読み、歴史の用語。
エピソード記憶
体験やストーリーに基づく記憶。
例:実際の実験の体験、物語を読んだときの感情。
手続き記憶
体を使った動作で身につく記憶。
例:自転車の乗り方、計算のやり方、英語の音読。
➡ この3つの記憶を意識して学習に組み込むと、効率的に覚えられます。
二重符号化理論×記憶の種類で効果的に学ぶ方法【教科別】
算数・数学の勉強に活かすコツ
- 九九や公式はリズムや歌で繰り返す(手続き記憶)
- 文章題は図や絵に変換する(意味記憶+イメージ)
- 図形問題は折り紙で実際に形を作る(体験+エピソード記憶)
国語・読解力を伸ばす勉強法
- 漢字を絵やイメージと結びつける(意味記憶)
例:「森=木が3つ 🌳🌳🌳」 - 物語はイラスト化や人物相関図で整理する(エピソード記憶)
社会(歴史・地理)の暗記を楽しくする方法
- 歴史の出来事を漫画やストーリーで覚える(エピソード記憶)
- 地理は地図に名産品やイラストを描き込む(意味記憶+イメージ)
- 年表をイラスト入りで作る(例:織田信長🔥、坂本龍馬⚓️)
理科(実験・観察)で身につく学習法
- 実験の流れをイラストで描く(意味記憶+イメージ)
- 動植物の観察スケッチをする(エピソード記憶)
- 化学反応を動画で視覚的に確認(非言語的システム)
英語の単語・文法を定着させる方法
- 単語カードに絵を描いて覚える(意味記憶+イメージ)
- 動作をしながら単語を覚える(手続き記憶)
- 音読をリズムに合わせて行う(手続き記憶+二重符号化)
二重符号化理論を使った勉強法のメリット・デメリット
メリット
- 記憶の定着が早い
- 理解が深まり、応用が効く
- 勉強が「楽しい」と感じやすい
デメリット
- 言葉+イメージの工夫に時間がかかる
- 教材や親の工夫が必要になる場合がある
家庭でできる二重符号化学習の実践例
小学生の家庭学習に取り入れる方法
- 漢字練習にイラストを添える
- 算数文章題を絵にする
- 家庭科の料理を写真付きで記録
中高生の受験勉強に役立つ工夫
- 英単語帳にイラストを書き足す
- 歴史年表に人物イラストを入れる
- 理科の実験ノートに図を描く
保護者がサポートできるポイント
- 子どもが描いたイラストを「いいね」と承認する
- 暗記カードを一緒に作る
- 話しながら学習内容を整理する
まとめ|二重符号化理論で「覚えられない」を解決しよう
- 二重符号化理論=言葉+イメージで記憶を強化
- 記憶の種類(意味・エピソード・手続き)を意識する
- 教科ごとに適した方法で取り入れると効果大
この方法を取り入れることで、「覚えられない…」が「楽しく覚えられる!」に変わります。
ぜひ家庭学習や日々の勉強に取り入れてみてください。
記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)
STEAM教育デザイナー / MOANAVIスクールディレクター
理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。
📚 経歴・資格
✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者
✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)
✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)
✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演
✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説