
オルタナティブスクールとは?
選ばれ始めた「学校以外の学び場」とは何か
「オルタナティブスクールって何?」──そんな声が増えている一方で、検索数も徐々に伸びており、注目が高まりつつあります。この記事では、オルタナティブスクールの定義やフリースクールとの違い、近年注目されている理由、社会背景、そしてMOANAVIが実践する横浜でのオルタナティブ教育の具体例をご紹介します。「学校だけが学びの場ではない」と感じ始めた今、保護者や教育関係者にぜひ知っていただきたい内容です。
「オルタナティブスクールって何?」という声が増えている
最近、「オルタナティブスクール」という言葉を目にする機会が増えてきました。
学校に行けない・行かない子どもが増える中で、「学校以外の選択肢」を探す保護者が増えています。その中で注目されているのが、「オルタナティブスクール」です。
Google検索でも「オルタナティブスクール」というキーワードの検索数が増えており、関心が高まりつつあることが分かります。しかし、同時に「オルタナティブスクールって何?」「フリースクールとどう違うの?」という声も多く聞かれます。
この記事では、「オルタナティブスクールとは何か」を丁寧に解説するとともに、なぜ今この学び方が注目されているのか、そして横浜で活動するMOANAVIの取り組みについてもご紹介します。
オルタナティブスクールとは
「オルタナティブ(alternative)」とは、「もう一つの選択肢」という意味。つまり「オルタナティブスクール」とは、「従来の公立・私立学校とは異なる、もう一つの学びの場」を指します。
学校教育法などで厳密に定義されている言葉ではないため、運営形態や教育方針はスクールごとに異なりますが、次のような特徴を持つことが多いです。
オルタナティブスクールの主な特徴
- 一斉授業ではなく、個別や探究型の学び
- 子どもの主体性を重視
- 評価はテストではなく、ポートフォリオや対話
- 多学年・異年齢の交流がある
- カリキュラムは柔軟、興味関心に応じて設計される
フリースクールとの違いは?
「オルタナティブスクール」と似た言葉に「フリースクール」があります。どちらも学校外の学びの場ですが、以下のような違いがあります。
| フリースクール | オルタナティブスクール |
|---|---|
| 不登校支援を目的とすることが多い | 多様な学びの選択肢の一つとして提供される |
| 子どもの安心・居場所づくりが主軸 | 教育理念に基づいた独自カリキュラムを提供 |
| 教科学習は必須でないこともある | 学力と探究の両方を大切にするスクールもある |
実際には明確に線引きされているわけではなく、「フリースクールの中にオルタナティブ教育を取り入れている」など、グラデーションのあるケースも多いです。
なぜ今、「オルタナティブスクール」が注目されているのか
1. 不登校の増加
文部科学省の調査によれば、2023年度には不登校の小中学生が30万人を超え、過去最多となりました。
従来は「学校に行けない=困ったこと」とされてきましたが、今は「学校以外の選択肢を探す」動きが活発になっています。保護者も「うちの子にとって最適な学び方は何か」を真剣に考えるようになっています。
2. 多様性を尊重する社会の流れ
「同じ制服を着て、同じ時間割で、同じ内容を学ぶ」従来型の学校は、すべての子どもに合うわけではありません。
- HSC(敏感な子)
- 発達特性のある子
- 海外生活を経験した帰国子女
- 興味関心が明確な子
こうした子どもたちは、自由度の高い学びの方が本来の力を発揮できることもあります。社会全体として「多様な学びの形を認める」方向に進みつつあるのです。
3. メディア・SNSでの発信の影響
「オルタナティブ教育」や「サドベリースクール」「モンテッソーリ教育」などのワードがYouTubeやInstagram、noteなどで頻繁に取り上げられるようになっています。
実際に通っている子どもや保護者の体験談がバズることで、「こういう選択肢もあるのか!」と初めて知る人が増えてきています。
横浜で活動するMOANAVIのオルタナティブスクールとは
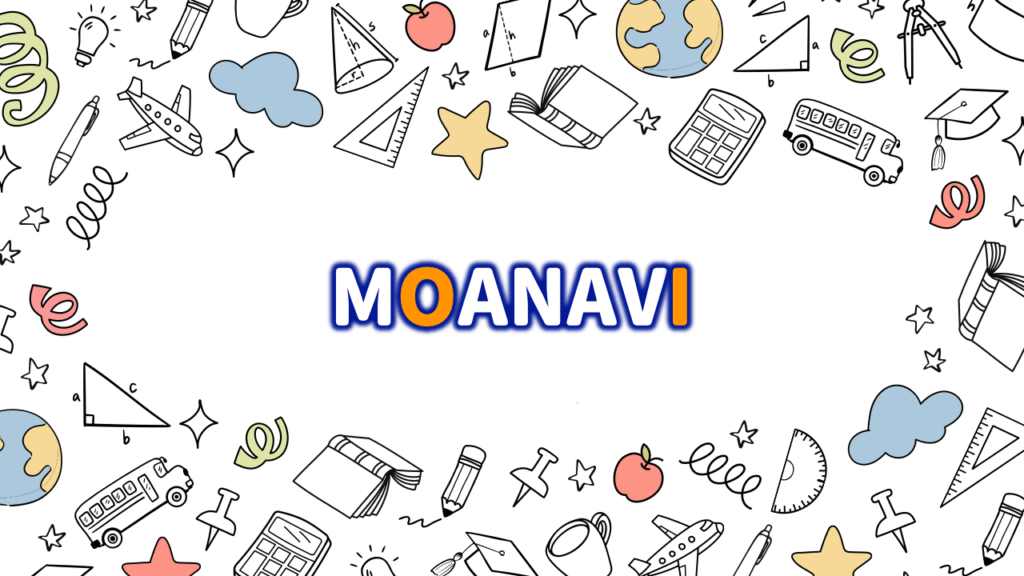
横浜市内で活動しているMOANAVIも、まさにこの「オルタナティブスクール」の一つです。
MOANAVIでは、不登校の子どもだけでなく、「自分らしい学びを求めるすべての子どもたち」にとっての居場所・学びの場を提供しています。
MOANAVIの特徴
- 自己調整学習を重視し、自分のペースで学ぶ
- 探究型のテーマ学習(科学・言語・人間・創造)
- 小人数制、異年齢での学び合い
- 学びの行動をポイント化する「STUDY POINTシステム」
子どもたちの声
「学校には行けなかったけど、MOANAVIなら行きたくなる」
「自分で決めて、自分で学ぶってこういうことなんだって初めて思った」
保護者の方からも、「子どもが笑顔を取り戻した」「勉強に対する抵抗感が減った」という声が寄せられています。
オルタナティブスクールという選択肢があることを、もっと多くの人に知ってほしい
オルタナティブスクールは、まだ一般的には広く知られているとは言えません。しかし、着実に認知は広がっており、特に「不登校」「多様な学び方」「自律的な子育て」をキーワードに関心を持つ人が増えています。
子どもが学校に合わないとき、「我慢して通う」か「休む」かの二択ではなく、「自分に合った別の学びの場がある」という第三の選択肢があることを知ってほしい──それが、MOANAVIの願いでもあります。
最後に:MOANAVIのオルタナティブスクールを見に来ませんか?
もしこの記事を読んで「ちょっと気になるな」と感じたら、ぜひ一度MOANAVIに見学に来てみてください。
無理に通わせる必要はありません。「こういう学び方もあるんだ」と感じるだけでも、きっと子育ての視野が広がるはずです。
記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)
STEAM教育デザイナー / 株式会社MOANAVI代表取締役
理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。
📚 経歴・資格
✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者
✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)
✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)
✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演
✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説







