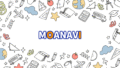共働き家庭の小学生
長期休暇の過ごし方30選
【夏休み・冬休み・春休み・GW】
「夏休み、子どもをどうする?」
共働き家庭にとって長期休暇は毎年の大きな課題です。学童に空きがない、在宅勤務と両立できない、家にいるとゲームや動画ばかりになる…。
この記事では、共働き家庭の小学生が安全に・充実して過ごせる長期休暇の工夫30選を紹介します。夏休みはもちろん、冬休み・春休み・GWにも使えるアイデアを網羅。預け先の確保から自宅での工夫、1日のスケジュール例、費用の考え方、横浜エリアで活用できる学びの場までまとめました。
共働き家庭の長期休暇「どうする?」最初に決めたい3つのこと
- 預け先の確保
学童や民間学童、短時間預かり、地域プログラムなどを検討して、安全に過ごせる環境を準備しましょう。 - 家庭での過ごし方の工夫
在宅勤務と両立するために「午前は学習・午後は遊び」というルールを決めるのが効果的です。 - 家族・地域の協力
祖父母に一部をお願いする、地域の学び場を活用する、友達同士でシェアするなど「組み合わせ」で柔軟に。
小学生が毎日を安全に過ごすための方法(共働き家庭の工夫)
- 防犯対策:留守番時はインターホンに出ない、SNSで不在を発信しない。
- 生活リズム:学校がある日と同じ起床・就寝時間を守り、乱れを防ぐ。
- オンライン安全:家庭で利用ルールを決め、タイマーやフィルタリングを導入する。
小学生の夏休みの過ごし方30選(共働き家庭向け)
自宅での工夫(10個)
- 読書(朝読書の習慣)
毎朝10分の読書を取り入れることで、生活リズムを崩さずに集中力を養えます。 - 工作・クラフト
紙や段ボール、身近な材料を使ったクラフトは、創造力や手先の器用さを育みます。 - パズル・知育ゲーム
楽しみながら思考力を刺激。静かに遊べるので在宅勤務中の親にも安心です。 - 家事シェア
料理や掃除を一緒に行うことで、生活力と責任感が身につきます。 - ミニ自由研究
植物の成長を観察したり簡単な実験を記録したり、探究心を伸ばすきっかけに。 - 日記を書く
日々の出来事を文章化することで、表現力と振り返りの力を高めます。 - クッキング体験
ホットケーキやサンドイッチなど簡単な料理に挑戦し、達成感を得られます。 - オンライン学習教材
短時間で学習を進められ、保護者が仕事中でも安心。 - 家庭でのミニ発表会
調べたことや自由研究の成果を家族に発表して、表現力を磨けます。 - 室内運動
雨の日でもできるヨガや体操で体力を維持。
外出での体験(10個)
- 図書館で調べ学習
本に囲まれた静かな環境で調べ物をすると、学びへの集中度が高まります。 - 科学館・博物館
実際に見たり触れたりすることで、知識がより実感を伴って定着します。 - 水族館・動物園
動物や魚を観察することで、自然や命への関心を深められます。 - 地域の夏祭り・ワークショップ
地域の人々との交流を通して、社会性やコミュニケーション力が育ちます。 - 公園で自然観察
虫取りや植物観察など、身近な自然から科学的な視点を学べます。 - プール・水遊び
夏ならではのアクティビティで体を動かし、リフレッシュにも最適。 - キャンプ・デイキャンプ
非日常的な体験を通じて、協調性やサバイバル力を培います。 - 地域のボランティア
清掃活動などを通じて、社会とのつながりや役割を実感できます。 - 映画館で映画鑑賞
物語を楽しみ、感想を話し合うことで思考力や表現力を高められます。 - スポーツ体験教室
新しい競技に挑戦してみることで、運動習慣とチャレンジ精神を育成。
学びにつながる活動(10個)
- 読書計画を立てる
「1日1冊」や「1日30分」など目標を決め、達成感を得る体験を重ねます。 - 基礎学習(計算・漢字)
短時間でも毎日継続することで、学力が確実に定着します。 - 英語の歌・絵本
遊び感覚で始められ、語学に自然に触れられます。 - 絵日記・イラスト日記
文章と絵を組み合わせて表現力を養い、思い出にも残ります。 - 調べ学習まとめ
テーマを決めて調べ、ノートにまとめることで探究心を育てます。 - 家庭内ミニ研究発表
人前で話す経験を積み、自信を育むチャンスに。 - 目標シート作成
学習や生活の目標を見える化し、計画性と自律心を養います。 - 学習アプリ活用
ゲーム要素のある学習アプリで、楽しく継続的に取り組めます。 - 学んだことを家族に発表
アウトプットによって理解が深まり、自信が育ちます。 - オンライン図鑑・教育動画
昆虫・宇宙・歴史など、興味のある分野を深掘りできます。
冬休み・春休み・GWにも使える工夫
- 短い休みでも「午前学習+午後遊び」のリズムを守る。
- 季節行事(クリスマス・お正月・春のイベント)を取り入れる。
- 読書計画や1日1枚のプリント学習で習慣を維持する。
学童だけに頼らない!過ごし方の組み合わせ方
- 学童+民間サービス:午前は学童、午後は習い事やイベント。
- 自宅+地域の場:午前は家庭学習、午後は地域スペース。
- 費用の目安:学童(月1〜2万円)、民間学童(数万円)、イベント(数百〜数千円)。
横浜・西区で活用できるMOANAVIの学び場
- まなびのあそび場:週1回無料開放。将棋やカードゲーム、紙コップタワー体験。
- ACADEMIA:放課後学習空間。小学生が自分のペースで学べる。体験申込も可能。
- イベント:スタンプワークショップやSTEAM体験など、長期休暇に親子で参加できる企画。
共働きの夏休みQ&A(どうする?に答える)
- Q. 学童に入れないときは?
午前は自宅学習+午後は地域イベントなどを組み合わせる。 - Q. 小学生の留守番は何年生から?
一般的には高学年から。ただし安全ルールを徹底すれば中学年前後から短時間も可能。 - Q. 在宅勤務と両立する工夫は?
子どもには午前学習・午後遊びのリズムを与え、親は集中時間を確保。
まとめ
共働き家庭にとって長期休暇は大きな負担ですが、
「預け先の確保」+「家庭の工夫」+「地域の活用」 の3本柱で解決が可能です。
MOANAVIの学びの場やイベントを取り入れることで、子どもにとっても保護者にとっても安心で有意義な休暇を実現しましょう。
記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)
STEAM教育デザイナー / MOANAVIスクールディレクター
理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。
📚 経歴・資格
✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者
✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)
✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)
✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演
✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説