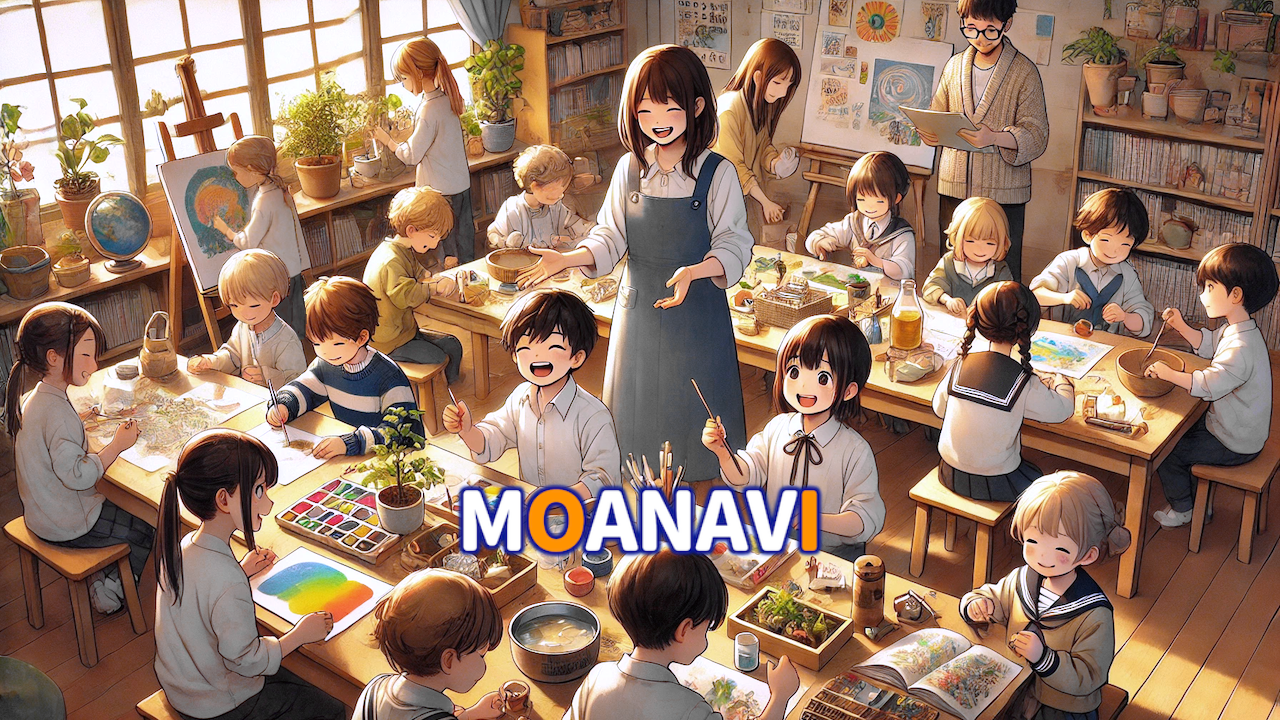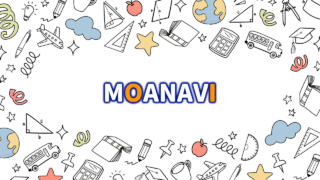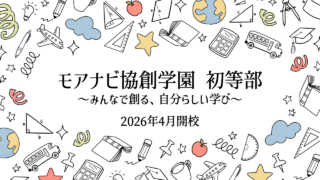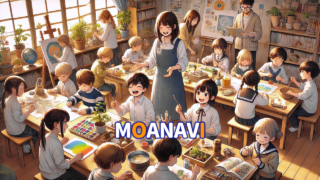通知表の評価が変わる?
現行の「観点別評価」と、次期指導要領の見直しについて解説します
2025年7月、文部科学省は次期学習指導要領で「主体的に学習に取り組む態度」を評定(通知表の成績)から外す方向で検討していることを発表しました。この記事では、保護者の方にはあまり知られていない現行の評価制度について整理し、改訂の背景や今後の教育のあり方について、MOANAVIの考えも交えてわかりやすく解説します。
現在の通知表は「3つの観点」で評価されています
小学校・中学校の通知表では、子どもたちの学びを以下の3つの観点から評価する仕組みが導入されています(2017年改訂の学習指導要領より):
- 知識・技能
→ 内容を覚えているか、基本的な技術を身につけているか - 思考・判断・表現
→ 理解を深め、自分の言葉で説明できるか、応用できるか - 主体的に学習に取り組む態度
→ 意欲、粘り強さ、自ら学ぼうとする姿勢、ふりかえりなど
この3つの観点をもとに、教科ごとにA・B・Cや5段階の評定が付けられています。
「主体的な態度」が成績から外れる?——見直しの背景
2025年7月、次期学習指導要領の議論の中で、「主体的に学習に取り組む態度」を成績(評定)の対象から除外する方向性が発表されました。
これは、以下のような理由によるものです:
- 評価が主観的になりやすい
- 教員が説明責任を果たすのが難しい
- 子どもによっては、「頑張っても伝わらない」と感じてしまう
- 教員の評価負担が重くなっている
つまり、「やる気があるかどうか」「学習に前向きかどうか」を数字で評価すること自体に限界があると判断されたのです。
今後はどうなる?——次期指導要領の方向性
2030年度以降を目処に予定されている次期学習指導要領では、
- 「知識・技能」
- 「思考・判断・表現」
この2つの観点のみで、通知表の評定(数値評価)がつけられる方向です。
「主体的に学習に取り組む態度」はどうなるかというと、コメント(所見欄)などの記述式で伝える形が検討されています。
MOANAVIの学びと、評価のこれから
MOANAVIでは、開校当初から「評価されることより、学びのプロセスそのものを大切にする」というスタンスで教育を行ってきました。
例えば:
- 自分で学習内容や量を調整できる「STUDY POINT」システム
- やり方や表現の仕方が自由なSTEAMプロジェクト
- 子ども自身が学習をふりかえる習慣づくり
こうした取り組みは、「数値化されにくい学びの価値」を大切にしたいという願いから始まりました。
今回の改訂案は、MOANAVIが大切にしてきた教育のあり方が、より多くの子どもたちにとって当たり前になる転機ともいえます。
保護者の皆さんへ
通知表の数字は一つの指標ですが、子どもたちの「学びたい」「できた」「わかった!」という気持ちを数字だけで測ることはできません。
MOANAVIでは、評価にとらわれず、自分らしく学び、挑戦できる環境づくりを続けていきます。
もし、お子さまの学びに不安や迷いがある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)
STEAM教育デザイナー / 株式会社MOANAVI代表取締役
理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。
📚 経歴・資格
✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者
✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)
✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)
✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演
✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説