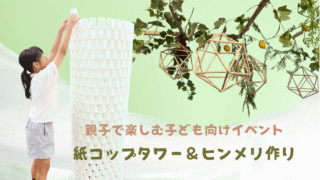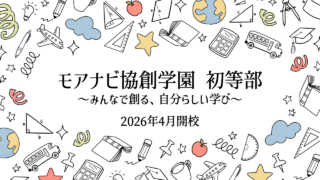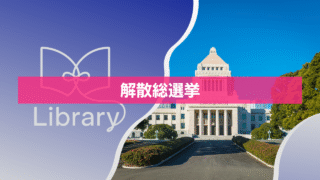2025年教育改革で「総合的な学習の時間」はどう変わる?
中教審WGの内容と家庭でできる探究サポート
子どもたちが「自分で課題を見つけ、考え、表現する力」を育てる――。
その中心にあるのが、「総合的な学習の時間」と「総合的な探究の時間」です。
いま文部科学省では、中教審(中央教育審議会)のワーキンググループを通して、
これらの学びを時代に合わせて見直す議論が始まっています。
AIの活用、教科をこえた探究、そして評価のあり方まで――
2025年の教育改革は、子どもの学び方を大きく変える節目になりそうです。
本記事では、中教審WGで議論されている内容をわかりやすく整理し、
保護者として知っておきたいポイントと、家庭でできる関わり方のヒントを紹介します。
学校の“総合的な学習”がどんな意味をもち、これからどう変わっていくのか。
子どもたちの学びの未来を、一緒に見つめていきましょう。
総合的な学習の時間とは?目的・内容・生活科との違いをやさしく解説
学校で行われる「総合的な学習の時間」とは、
子どもたちが自ら課題を見つけ、調べ、考え、表現する力を育てることを目的とした学びの時間です。
国語や算数のように教科書で知識を教わるのではなく、
自分の関心を出発点にして、社会や自然、身のまわりの問題に目を向け、
「なぜだろう」「どうすればよいのだろう」と問いを立てながら学びを深めていきます。
文部科学省では、この時間を通して「生きる力」を育てることを重視しています。
ここでいう“生きる力”とは、単なる知識ではなく、
情報を整理・活用し、自分の考えを持ち、他者と協働して行動する力のことです。
AIや情報化が進むこれからの社会では、
「与えられた問題を解く力」よりも「自分で問題を見つけ、考える力」が求められる――
そんな時代の変化に対応するための学びともいえます。
また、「総合的な学習の時間」は、小・中・高で目的が少しずつ異なります。
小学校では身近な生活や地域をテーマに“気づき”を大切にし、
中学校では社会課題への関心や自分なりの意見形成へと発展します。
高校になると、進路や将来の生き方と結びつけながら、
より専門的・実践的な「総合的な探究の時間」へと発展していきます。
こうして子どもの成長に合わせて、探究のレベルが段階的に深まる設計になっているのです。
低学年で行われる「生活科」との違いも、保護者の方がよく疑問に思う点です。
生活科は主に1・2年生が対象で、身近な人・自然・地域との関わりを通して
「発見する」「感じる」などの体験的な学びを中心にします。
そこから得た“興味や気づき”をさらに発展させ、
3年生以降でより論理的・探究的に取り組むのが「総合的な学習の時間」です。
つまり、生活科が“探究の入口”であり、総合的な学習の時間はその“発展編”といえます。
このように、「総合的な学習の時間」は単なる調べ学習ではなく、
子どもが自ら問いを立て、考え、表現することで
「自分の学びをつくる力」を育てる重要な時間です。
そして、その学び方の姿勢は、今後のAI時代の教育改革の中心テーマにもつながっています。
なぜ中教審が見直すの?2025年の教育改革で議論されている方向性
2025年に向けて、文部科学省は次の学習指導要領改訂に向けた議論を本格化させています。
その中心にあるのが、「生活」「総合的な学習」「総合的な探究の時間」をどう位置づけ直すかというテーマです。
この分野を専門に扱うために、中教審(中央教育審議会)の中に**「生活・総合的な学習・探究の時間ワーキンググループ(WG)」**が設置されました。
第1回の会合は2025年10月15日に予定されており、今後1年をかけて方針をまとめる見込みです。
このWGがつくられた理由は、総合的な学習が各学校で広がる一方で、
「どんな力を育てる時間なのか」「教科との関係をどう整理するのか」
といった課題が浮き彫りになってきたためです。
文科省は、社会の変化に対応し、より一貫性のある学びを実現するために、
**「探究・情報・教科横断」**の三本柱を中心に再設計を進めようとしています。
今回のWGで想定されている主な議論は、以下の4つに整理できます。
- 探究的な学びを中心に据えた教育課程の再構築
これまで「体験的な学び」や「自由研究」に見られがちだった総合的な学習を、
明確に「課題発見・解決型の探究プロセス」として再定義し、
すべての学校で一定の質を確保する方向が検討されています。
特に、「自分で課題を見つけ、考え、行動し、ふりかえる」という探究サイクルの定着が重視されています。 - 教科等横断的な資質・能力の整理
現行の学習指導要領でも「思考力・判断力・表現力」を共通資質として掲げていますが、
実際には教科ごとにバラバラに扱われているのが現状です。
今回のWGでは、これらを情報活用能力やAIリテラシーと結びつけて、
教科を超えて育てる新しい学力観の整理が検討されています。 - 評価とカリキュラム・マネジメントの見直し
探究活動の成果はテストで測りにくいため、
「どのように成長を見取るか」「どんな記録を残すか」が全国的な課題となっています。
WGでは、ポートフォリオや自己評価、ふりかえりシートなどを活用し、
教員間で共通理解をもって支援できるようにする仕組みが話し合われています。 - 教職員体制・地域連携・ICT活用の在り方
探究的な学びは、教員一人で完結できるものではありません。
複数教員によるチームティーチング、地域の専門家との協働、AIツールの活用など、
学校を「学びのチーム」として運営していくための体制づくりが求められています。
これらの改革は、単なる制度変更ではなく、子どもの学び方そのものを変える動きです。
国は今後、「生活科」から「総合的な探究の時間」までを一貫した流れとして捉え、
子どもが学年を上がるごとに、より自律的に考え、行動できるようになる仕組みを整えようとしています。
保護者にとっても、この改革は無関係ではありません。
「探究学習」や「AIの活用」が学校だけで完結しない時代、
家庭での問いかけや応援の仕方が、子どもの学びを大きく左右します。
このWGの議論は、まさに“家庭と学校の新しい関係づくり”の始まりといえるのです。
総合的な学習・探究の時間はどう変わる?新しい授業の姿
これからの「総合的な学習・探究の時間」は、これまでの“調べてまとめる”だけの活動から大きく変わろうとしています。
中教審WGでは、「知識を得ること」よりも「課題を発見して考える力」「情報を活用して表現する力」を育てることを中心に据えた再設計が進められています。
つまり、総合的な学習は単なる“自由研究”ではなく、探究のプロセスを通じて自分で学びをつくる時間へと進化していくのです。
授業の形も変わります。
たとえばこれまでの総合的な学習では、「地域を調べよう」「環境問題についてまとめよう」といった課題が多く見られました。
今後はそこに、データ分析・ICT活用・AIツールとの協働が加わります。
実際にWGでは、子どもがAIを活用して情報を整理・比較したり、グループで意見をまとめたりする事例が紹介されました。
「AIが出した答えをどう判断するか」「自分の考えとどう違うのか」を話し合う授業が、今後は一般的になっていくでしょう。
また、学習内容の幅も広がります。
国語や社会、理科などの教科で学んだ知識を“つなげて使う”ことが重視され、
学校の外――地域社会・企業・大学などと連携した教科横断型プロジェクト学習が拡大していく見込みです。
たとえば「地域の高齢化をどう支えるか」「気候変動に対して自分たちができることは何か」など、
正解のないテーマを自分たちなりに考え、発表・提案する機会が増えていきます。
これにより、子どもたちは“教科の枠を越えて学ぶ”経験を通して、
現実の社会課題と自分の学びがつながる感覚を持てるようになります。
評価の仕方も変わっていきます。
テストの点ではなく、「どう考えたか」「どんな工夫をしたか」「どんな視点でまとめたか」といったプロセスの見取りが重視される方向です。
中教審WGでも、ポートフォリオや発表型評価、ふりかえりシートなどを活用して、
子どもの“思考の変化”を見取る評価方法が議論されています。
これは、結果だけを競うのではなく、挑戦の過程を大切にする教育への転換でもあります。
このような変化によって、授業は一方的な「教える時間」から、
子どもと教師が共に考え、対話しながら進める「協働的な学び」へと変わります。
教室での活動に地域の人や専門家が関わったり、オンラインで外部とつながったりするケースも増えるでしょう。
こうした学びの変化は、単に授業のスタイルが変わるという話ではありません。
それは、子どもたちが社会の中で自分の意見をもち、行動できるようになるための準備です。
そして、保護者がこの変化を理解し、家庭で「今日どんなことを考えたの?」と対話を重ねることで、
学校での探究と家庭での学びが自然につながっていくのです。
家庭でできるサポート|探究学習を支える5つのヒント
探究的な学びは、学校だけで完結するものではありません。
子どもが「自分で考え、調べ、まとめる力」を身につけていくためには、
日常生活の中でもその力を発揮できる環境が大切です。
中教審WGでも、学校と家庭・地域が連携しながら「子どもを中心にした学びの場」をつくることが強調されています。
ここでは、家庭でできる5つのサポートのヒントを紹介します。
①「どうして?」と問いかける日常会話を増やす
探究の原点は「なぜ?」という好奇心です。
たとえば、ニュースや天気、身近な出来事に対して、
「どうしてそうなるんだろうね?」「それってほかの国ではどうなんだろう?」と問いかけてみましょう。
正しい答えを出すことよりも、考えるきっかけを共有することが目的です。
保護者が一緒に考えたり、「お母さんもわからないから調べてみよう」と言うことで、
“わからないことを調べる”姿勢が自然に育ちます。
② 家庭でもできる小さな探究・調べ学習を取り入れる
探究学習というと難しそうに感じるかもしれませんが、
家庭でも簡単に取り入れられる方法があります。
たとえば、「好きな動物について調べる」「食卓にある食材の原産地を地図で探す」など、
身近な話題から始めるだけでも立派な探究です。
大切なのは、調べて終わりではなく、気づいたことを話す・比べる・まとめるというプロセス。
家族の会話や夕食の時間を「学びの共有の場」にしていくと、
学校の総合学習とも自然につながります。
③ 調べ方・まとめ方・ふりかえりを一緒に考える
探究のプロセスには「情報を集める」「考えを整理する」「発表する」という段階があります。
このうち、家庭でサポートしやすいのは、まとめ方やふりかえり方です。
「どんな順番で話すと伝わるかな?」「似ている意見と違う意見を分けてみようか」など、
論理的な整理の仕方を一緒に考えるだけで、学びの質がぐんと上がります。
また、学びの最後に「どんなことがわかった?」「次に知りたいことは?」と聞くことで、
子どもが自分の学びを“続けたい”と感じるきっかけになります。
④ AI検索や生成ツールを“学びの道具”として扱う
中教審WGでは、AIの教育利用が明確に議題に上がっています。
AIは“答えを教える存在”ではなく、“考えるサポート役”として使うことが大切です。
家庭でも、ChatGPTや画像生成AIなどを使って、
「AIはこう答えたけど、あなたはどう思う?」「どこが正しくて、どこが違うと思う?」と対話することで、
子どもが情報を批判的に読み取る力を育てることができます。
これからの時代、「AIと一緒に考える力」は、家庭でこそ培われるスキルになるでしょう。
⑤ うまくいかなくても「考えた過程」を認めて励ます
探究学習では、うまくいかないことや途中で迷うことが当たり前です。
結果よりも、その過程にどんな工夫や努力があったかを見取ってあげましょう。
「たくさん考えたね」「そこに気づいたのはすごいね」という言葉が、
子どもにとって大きな自信になります。
中教審WGでも、「評価を“点数づけ”ではなく“成長の記録”としてとらえる」方向が示されています。
家庭でもこの考え方を取り入れることで、子どもは安心して試行錯誤できるようになります。
このように、保護者が“教える人”ではなく“考える仲間”として寄り添うことが、
探究学習を支える最大のサポートになります。
日常の何気ない会話の中にも、子どもの思考を育てるチャンスはたくさんあります。
「家庭が学びのパートナーになる」――まさにそれが、今の教育改革の方向性なのです。
テーマが見つからないときは?子どもの興味を広げるヒント
「探究のテーマを決めましょう」と言われても、子どもがなかなか思いつかない――
そんな姿を見て不安になる保護者の方も多いでしょう。
でも安心してください。
テーマをすぐに決められないのは、子どもがまだ“自分の問い”を見つける途中にいるからです。
これは、探究学習のごく自然なプロセスであり、焦る必要はありません。
中教審WGでも、「子ども自身が問いを立てる経験をどう支えるか」が大きな議題のひとつです。
知識や情報があふれる今の時代、教師や大人が課題を与えるのではなく、
子どもが自分の中から生まれた疑問を形にできることが、学びの出発点として重視されています。
この「課題設定力」は、将来の学び方や働き方にも直結する“生きる力”の核となるスキルです。
では、家庭ではどんな関わり方ができるでしょうか。
ポイントは、テーマ探しを「探す作業」ではなく「気づく過程」として見守ることです。
① 「好き」「困り」「不思議」から出発する
テーマを考えるときは、いきなり「社会問題」や「研究テーマ」を選ぶ必要はありません。
子どもが日常で感じる「これが好き」「ちょっと困る」「なんでだろう?」という気持ちが、
探究のスタート地点になります。
たとえば、「犬が好き」から動物の習性を調べる、
「朝が苦手」から生活リズムや睡眠の仕組みを探る、
「雨の日に外で遊べない」から気象や環境の問題を考える――。
こうした小さなきっかけが、立派な探究テーマに育っていきます。
② 家庭や地域の中に“学びの素材”を見つける
中教審WGでは、「地域と結びついた探究」を強化する方向も示されています。
家庭や地域の中にも、テーマのヒントはたくさんあります。
たとえば「商店街のゴミを減らすには?」「地元の特産品をもっと知ってもらうには?」など、
身近な課題に目を向けると、子どもが“社会とつながる学び”を体験できます。
親子で地域の行事やイベントに参加したり、地元の人に話を聞いたりすることも、
テーマ探しのヒントになります。
地域そのものが、子どもの探究の「教室」になるのです。
③ 親は“指導者”ではなく“伴走者”になる
探究学習では、子ども自身が考えることが何より大切です。
保護者が「こうしたほうがいい」「それはテーマにならないよ」と方向づけてしまうと、
せっかくの主体的な学びが失われてしまいます。
大切なのは、一緒に考える姿勢。
「そのテーマ、面白いね」「それを調べたら何がわかるかな?」と、
興味を共有するような声かけを意識しましょう。
家庭は“評価する場所”ではなく、“一緒に探す場所”です。
④ 失敗や迷いも“学びの一部”として扱う
探究学習には、正解がありません。
途中で行き詰まったり、テーマを変えたくなったりするのも自然なことです。
WGでも、「試行錯誤をどう支えるか」が今後の大きな課題とされています。
家庭では、うまくいかないときこそ「よく考えてるね」「別の視点も探してみよう」と、
失敗を前向きにとらえる言葉がけを意識しましょう。
そうすることで、子どもは“考えることをやめない”姿勢を身につけます。
テーマを決めるというのは、単に課題を選ぶ作業ではなく、
子どもが自分の興味・価値観・世界の見方を発見していくプロセスです。
保護者がその成長を焦らず見守ることで、
子どもは自分の「なぜ?」を形にできるようになっていきます。
総合的な学習の時間が育てようとしているのは、まさにこの“問いを生み出す力”。
その第一歩を支えるのが、家庭での温かい関わりなのです。
評価や成績はどう変わる?中教審でも議論される新しい見方・考え方
「探究学習では、どうやって成績をつけるの?」
この質問は、総合的な学習の時間が始まった当初から、保護者や先生の間でたびたび話題になってきました。
実際に中教審のワーキンググループ(WG)でも、**「探究的な学びをどう評価するか」**が重要な議題のひとつになっています。
これまでの学校教育では、テストの点数や提出物の出来栄えといった「結果」を中心に評価が行われてきました。
しかし、探究的な学びでは「考えるプロセス」や「気づき」「挑戦の仕方」が重視されるため、
従来の評価方法では十分に子どもの成長をとらえきれません。
WGでは、これを「結果主義からプロセス主義への転換」と呼び、
全国的に新しい評価観の導入を検討しています。
文部科学省は、次のような方向で整理を進めています。
- 観点別評価の見直し
現在の評価は「関心・意欲・態度」「思考・判断」「技能・表現」「知識・理解」といった観点で行われています。
今後はこれをよりシンプルに整理し、特に「思考・判断・表現」を中心とした一体的な見取りを重視する方向です。
これは、子どもの“考える力”を全教科・総合的学習で一貫して育てるための考え方です。 - ポートフォリオ(学びの記録)を活用した評価
ノートやレポート、発表スライド、ふりかえりシートなど、
子どもが自分の学びを可視化できる記録を蓄積していく方法です。
WGでは、こうしたポートフォリオを使って、教師が子どもの思考の変化や表現の成長を見取る仕組みが提案されています。
つまり、「この子がどんなふうに考えるようになったか」を評価の中心に置くのです。 - ふりかえり・自己評価の重視
探究的な学びでは、子どもが自分で「うまくいったこと」「課題に感じたこと」を整理することが大切です。
そのため、教師の評価だけでなく、子ども自身が自分を評価する力を育てる方向も議論されています。
自己評価を通じて、「次はこうしてみよう」と考える力が身につきます。 - 協働的評価とチームでの支援
総合的な学習では、複数の先生が関わるケースが多くなります。
WGでは、教員一人ではなく、複数の教員・地域の人・外部講師などが
“チームとして見守る評価”を導入できないかという議論も進められています。
この流れは、学校全体で子どもの成長を支える「カリキュラム・マネジメント」と深く関わっています。
こうした評価の変化は、成績表の見方にも影響します。
テストの点数が中心ではなく、子どもがどんな考えをもち、どう工夫して学んだかが記録として残るようになります。
そのため、保護者が「結果」だけを見て一喜一憂するのではなく、
「どんな発見があった?」「前と比べてどう変わった?」とプロセスを言葉で認めることが重要になります。
探究学習の評価は、“伸びしろを見つける評価”とも言えます。
子どもが自分の思考をふりかえり、「次はこうしたい」と前向きに考えられるようになることが、
評価の本来の目的です。
WGでも、成績づけよりも「成長を記録し、学びを支える評価」へと変えていく方向が明確に示されています。
つまり、これからの学校では「評価=点数」ではなく、
評価=子どもの学びを支えるフィードバックへと変わっていきます。
その考え方を家庭でも共有できれば、
学校と家庭が一緒に子どもの探究を見守り、応援できる時代がやってきます。
これからの教育はどう変わる?中教審WGが描く“学びの未来像”
今、日本の教育は大きな転換点を迎えています。
これまでの「一斉授業」「知識の定着」中心の教育から、
子ども一人ひとりが自分の興味や課題に応じて学ぶ“探究的で自律的な学び”へ――。
中教審の「生活・総合的な学習・探究の時間」ワーキンググループ(WG)は、まさにその未来を描こうとしています。
WGで議論されている大きなテーマのひとつが、
「個別最適な学び」と「協働的な学び」をどう両立させるかという課題です。
これまでは、「自分のペースで学ぶ個別学習」と「仲間と一緒に進めるグループ学習」が、
別々のものとして扱われがちでした。
しかし、子どもが自分の得意・関心をもとに学びを設計し、
必要に応じて他者と協力しながら課題を深める――そんな学び方がこれからの理想像です。
つまり、「一人で学ぶ」か「みんなで学ぶ」かではなく、
**“一人ひとりが自分を主語にして、他者とつながりながら学ぶ”**時代に入っていくのです。
もうひとつの大きなテーマが、AIとの共存と情報活用能力の育成です。
WGでは、「生成AIをどう教育現場に取り入れるか」も具体的に話し合われています。
AIが情報を整理したり、アイデアを出したりするのを手助けにしながら、
最終的に「自分の考えをもつ」「意見を伝える」ことを目指す方向が示されています。
つまり、AIが考えてくれるのではなく、AIと一緒に考える――
そんな“人間とAIの協働学習”を、次の学習指導要領では明確に位置づけていく可能性があります。
さらに、WGでは「学びのエージェンシー(agency)」という言葉も注目されています。
これは、子どもが自分の学びを自分で動かす力のこと。
自ら課題を見つけ、周りと協力しながら行動し、ふりかえる力です。
これまでの「先生に言われたことをこなす学び」から、
「自分で目的をもち、仲間と支え合いながら進める学び」へ。
総合的な学習の時間は、その“エージェンシー”を育てる中心的な場として再定義されています。
また、学校教育の枠を越えた学びも重視されています。
WGでは、「地域・家庭・社会とつながる共育(ともいく)」という考え方が示されています。
地域の企業や大学、行政と協働する授業や、家庭での調べ学習・対話など、
学校外での体験が子どもの学びを支える仕組みを整えていく方針です。
これにより、学校は「閉じた教室」から「開かれた学びの拠点」へと変わっていくでしょう。
このような教育の未来像は、単に授業の改革にとどまりません。
それは、子どもが自分で人生をデザインできる力を育てる教育への転換です。
どんな環境でも、自分で考え、選び、行動できる人を育てること――
それが、WGが描くこれからの教育のゴールです。
そしてこの変化の中で、保護者の役割も変わります。
子どもを管理する存在から、学びを共に考える「パートナー」へ。
家庭が学びを応援し、学校がそれをつなぐことで、
子どもの学びは学校だけでなく、社会全体へと広がっていきます。
それこそが、WGが示す“未来の学びのかたち”なのです。
まとめ|2025年の教育改革に向けて、家庭で意識したい3つのこと
2025年に向けた教育改革では、子どもが「自分で学びをつくる力」を育てることが重視されています。
総合的な学習の時間や探究学習は、その中心的な学びとして位置づけられています。
家庭でできることは、特別なことではありません。
日常の中で次の3つを意識するだけで、子どもの探究は確実に深まります。
- 「なぜ?」を一緒に考えて、興味の芽を伸ばす
- 調べて・まとめて・発表する体験を日常の中に取り入れる
- 結果ではなく、考えた過程や工夫を認める
こうした関わりが、これからの時代に求められる“自分で学び続ける力”につながっていきます。
MOANAVIでは、子どもたちが「自分の問いから学びを広げる」力を育てるために、
探究的な学びやSTEAM教育、自己調整学習の実践を行っています。
学校の授業と家庭の学びがつながるように、保護者向けの記事やセミナーも定期的に発信しています。
家庭での声かけひとつが、子どもの未来を変える大きなきっかけになります。
記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)
STEAM教育デザイナー / MOANAVIスクールディレクター
理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。
📚 経歴・資格
✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者
✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)
✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)
✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演
✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説