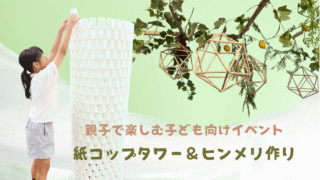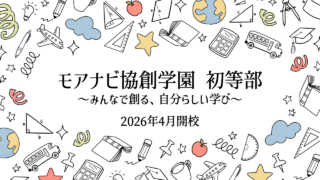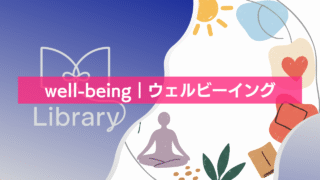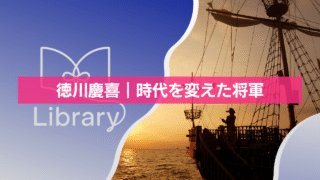不登校の新選択肢「学びの多様化学校」完全ガイド
横浜市の支援・フリースクールとの違いも解説
はじめに
「学校に行きたくない」と悩む子どもが増える中で、文部科学省が導入を進めているのが 「学びの多様化学校」 という新しい制度です。
フリースクールとも異なるこの仕組みは、今後の不登校支援に大きな役割を果たすと期待されています。
では、学びの多様化学校とは何なのか?横浜市では設置が進んでいるのか?そして、フリースクールとの違いはどこにあるのか?
本記事では、制度の概要から課題、横浜市の支援の現状までをわかりやすく解説します。
学びの多様化学校とは?【制度の基礎知識】
文部科学省が導入する新しい学びの場
学びの多様化学校とは、既存の小中学校に代わる新たな教育機関として構想されている仕組みです。
不登校の子どもや学校に馴染めない子どもが「安心して学び続けられる場」を確保するために、法制度上で位置づけられる予定です。
フリースクールとの違い
- フリースクール:民間団体やNPOが運営し、費用は自己負担。法制度上は「学校」ではないため、出席扱いになるかどうかは各学校判断。
- 学びの多様化学校:国や自治体が制度設計を進めており、将来的には 公的な学校と同等の学びの場 として整備される見込み。
メリット
- 子どもが安心できる新しい選択肢になる
- 公的制度として認められることで、就学上の扱いが明確になる
- 多様な教育スタイル(探究学習・プロジェクト型学習など)の導入が可能
デメリット・課題
- 財政面・制度設計がまだ十分に整っていない
- 教員確保や教育水準の担保が課題
- 保護者にとって「従来の学校」との違いがわかりにくい
横浜市の現状:学びの多様化学校は「まだない」
2025年現在、横浜市には公立の学びの多様化学校は設置されていません。
その代わりに、市は「不登校支援の拠点」として ハートフル(教育支援センター) を強化しています。
ハートフルの拡充
- 上大岡には大規模拠点が整備され、多くの子どもを受け入れられる環境が整いました。
- さらに市内の学校内にも「校内ハートフル」を増やす動きが進められており、身近な場所で支援を受けられる体制が広がりつつあります。
今後の可能性
全国では統廃合で空いた校舎を活用して「学びの多様化学校」への転用を検討する自治体もあります。
横浜市ではまだ正式な動きはありませんが、今後の政策によって設置される可能性があります。
学びの多様化学校とフリースクールの比較
| 特徴 | 学びの多様化学校 | フリースクール |
|---|---|---|
| 運営主体 | 公的(自治体・学校法人など) | 民間団体・NPO |
| 出席扱い | 原則認められる見込み | 学校長の判断による |
| 費用 | 公的支援あり(予定) | 自己負担(数万円〜) |
| 教育内容 | 個別最適化学習、探究学習 | 団体ごとに異なる(自由度が高い) |
| 社会的認知度 | 公的制度として拡大予定 | 認知度は高まっているが制度外 |
保護者が知っておきたい3つの視点
- 横浜市にはまだ設置されていない → 現状はフリースクールやハートフルの利用が中心
- 制度が整備されれば公的な支援が受けられる → 学費や出席扱いの不安が減る
- 今できることを大切にする → 子どもに合う「居場所」を一緒に探す
モアナビ協創学園が提供する選択肢
モアナビ協創学園(横浜市西区)は、不登校や学校に合わない子どもが安心して学べるオルタナティブスクールです。
「科学・言語・人間・創造」の4領域をベースにしたSTEAM教育やプロジェクト型学習を取り入れ、子どもが自分のペースで学び、自信を育てられる環境を整えています。
不登校支援の制度が変わりゆく中で、すでに実践を積み重ねてきたMOANAVIの取り組みは、子どもにとって「今すぐ利用できる安心の場」として価値を持っています。
まとめ
- 学びの多様化学校は、不登校の子どもにとって新しい学びの選択肢になる制度。
- 横浜市ではまだ設置されていないが、ハートフルの拡充が進んでいる。
- 保護者にとっては、「制度を待つ」だけでなく、今利用できる居場所(フリースクール・民間スクール)を知っておくことが大切。
子どもが「自分らしく学べる」未来のために、制度と民間の両面から選択肢を持っておきましょう。
記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)
STEAM教育デザイナー / MOANAVIスクールディレクター
理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。
📚 経歴・資格
✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者
✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)
✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)
✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演
✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説